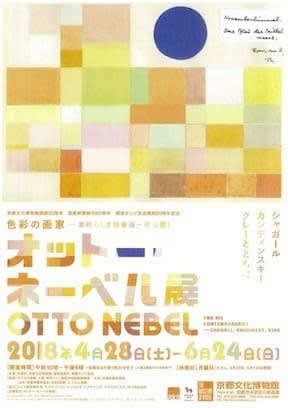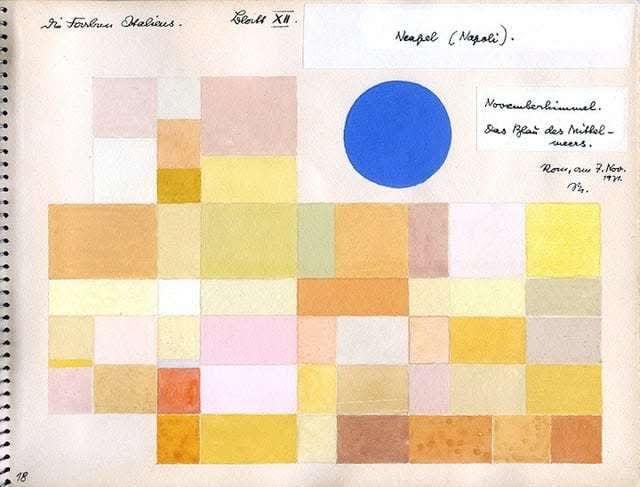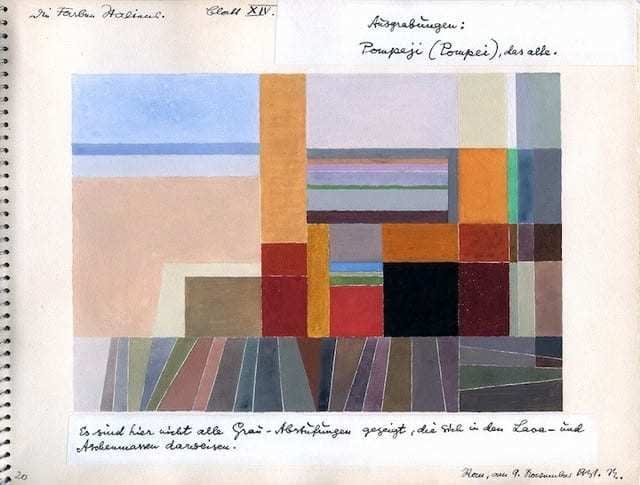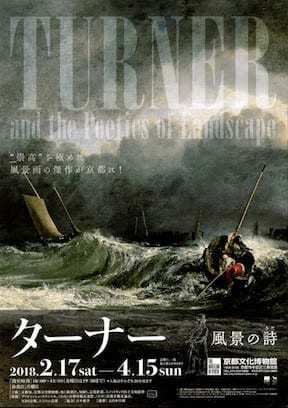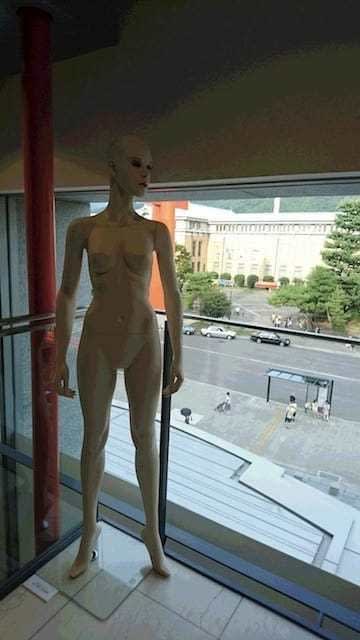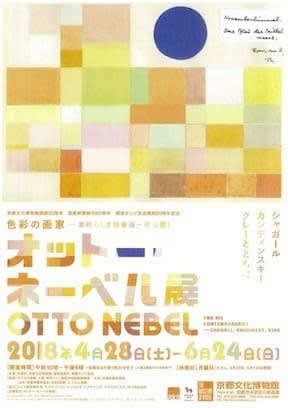
★色彩の画家 オットー・ネーベル展 シャガール、カンディンスキー、クレーとともに
京都文化博物館
オットー・ネーベルの絵を観に行きました。
《知られざる画家》との肩書ですが、
僕も名前は知りませんでした。
ポスターの絵を観る限り、
《クレーに近いなぁ》という印象。
●ネーベルの肖像写真 1937年 (オットー・ネーベル財団提供)

会場の中は、若い人が多いということには、驚きでした。
《前衛的》、《現代的》絵画思考ということでしょうか?
シャガール、カンディンスキー、クレーの作品に出会えるというのも魅力でしょうか?
若い頃は、建築家および舞台俳優を目指していたという。
彼の思考スタイルが作品によく現れています。
感情に流されず、構築的であり、表現的です。
バウハウスでとともに学んだということで、
クレーやカンディンスキーの作品との融和性がみられます。
時に、誰の作品かわからないという類似性がみられます。
しかし、オットー・ネーベルは自分の信念を強く持っていたこともよくわかります。
独自の作画スタイルを追求しています。
作家としての強さを最後まで持ち続けていたことが理解できます。
勇気づけられる展覧会でした。
●オットー・ネーベル『イタリアのカラーアトラス(色彩地図帳)』より、1931年、インク、グアッシュ・紙、 オットー・ネーベル財団
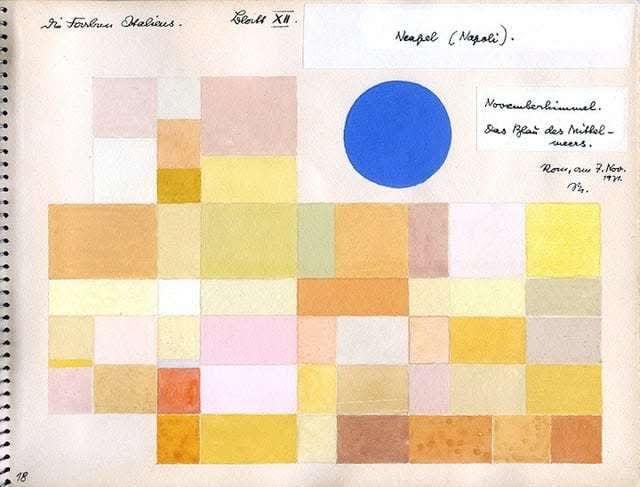
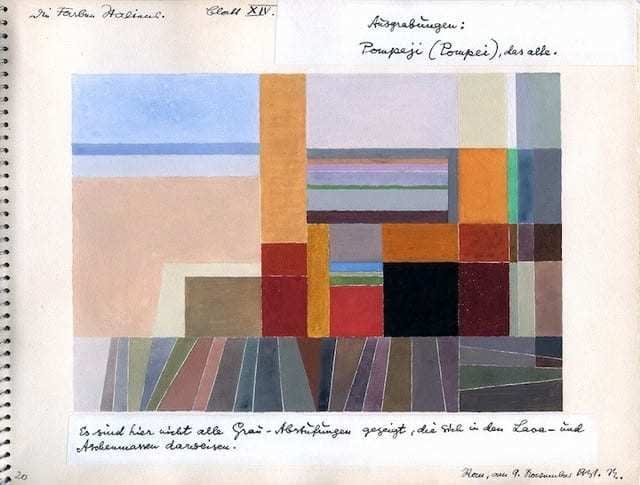
彼は、独自に色彩の追求をしています。
『イタリアのカラーアトラス(色彩地図帳)』は魅力的でした。
1931年にイタリアを旅した際に
都市や町の景観を、視覚感覚によって色や形で表現した色彩の実験帳です。
観る者は、解き放たれた感覚を味わいます。
学ぶ者には、多くの示唆を与えてくれます。
かつて、僕も同じようなことに挑戦していたことがあり、
とても興味深い展示でした。