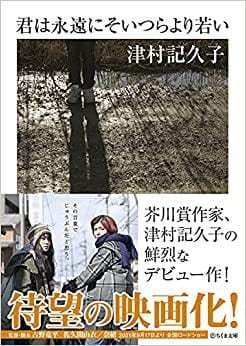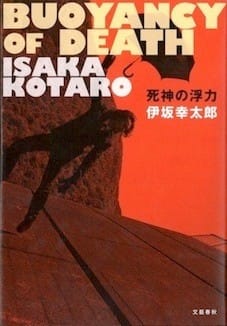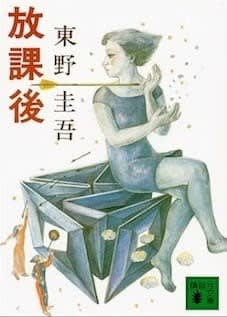★追懐のコヨーテ
森博嗣
講談社文庫 The cream of the notes
森博嗣さんの小説は数冊読んだが
このようなエッセイを読むのは初めて。
森さん自身はある程度定期的に出しているようです。
コロナ禍の時代、
森博嗣さんはどのように考えどのように生活しているのか。
興味があって購入。
まぁ、森さんらしいというか
孤独が好きなんだなと。
静かにお暮らしのようでした。
「仕事」というのは、つまり罰ゲームである。
「全力を尽くすな」が親父の教えの一つだった。
・・・・・
などなど、共感できる視点。
対人感覚、社会感覚は僕とよく似ているなぁ。
タイトルの付け方の上手い人だなぁとつくづく感心。