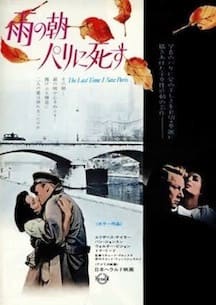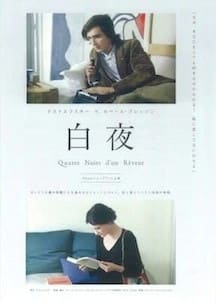★モンテーニュ通りのカフェ
監督: ダニエル・トンプソン
2006/フランス
洒落た映画ポスター。
こんなイラストデザインをチラシに使うなんて。
物語はパリが舞台。
サルトルの名前が出てきて、
ヴォーヴォワールが出てくると、
これはもう60年代ではないか。
音楽も60年代の懐かしいメロディ。
ユーロの現代話なのに、
半世紀前のフランスの雰囲気。
ブラック、そしてブランクーシの「接吻」も出てくる。
この映画は何も考えずに
素直に良き時代のパリを堪能しましょう。
ベル・エポック
過ぎゆく時間に身を委ねましょう。
という感じの映画でした。