瀬木比呂志 『絶望の裁判所』(講談社現代新書2250)2014、講談社

批判は個人、システム、集団に対する否定的な表明であるが、筋道の通った基準の存在が大事である。一方、悪口は得てして個人の行状に対する感情のこもった発言や文章が多い。感情がこもる分だけ、筋道がぼやける。掲書は、日本の裁判制度が、裁判官の出世主義や権力や上司への忖度思考のために、いかに劣化・腐敗しているかを著者の経験をもとに縷々述べたものである。
これによると、裁判所の伏魔殿は事務総局という司法の中枢のようである。ここの事務総局長が、代々とんでもない権力を持っており人事その他を仕切っている。ともかく、これを読むと、刑事事件はもとより民事事件でも裁判所(官)のお世話には、決してならないようにしたいと大抵の人は思うであろう。その意味で、この書は批判本であるが、二人の個人が名指しでやり玉にあがっている。すなわち悪口本でもある。
一人は矢口洪一第11代最高裁判所長官(1920-2006)である。矢口はWikipediaの記事では、比較的、物の分かった進歩的な裁判官のように書かれているが、本書では分類不能な怪物とされており、個人的な悪口としては以下のようなエピソードが紹介されている。
私(瀬木)は最高裁で行われたあるパーティーの席で一度長官と話したことがある。ふと気が付くと長身の長官が前に立っている。両脇の人々がさっと引いてしまったために、言葉を交わさざるを得なくなった。
(君は民事局の局付けだそうじゃないか)
(はい、そうです)
(そうか、しかし私からみれば局付けなんて何でもない)
(はあ、そうでしょうね)
ということで、幸い先方が向こうに行ってしまった。
最高裁判所長官が自分の部下にその役職の価値をこのように面と言うのは信じがたい。このたわいもないエピソードの後で、瀬木は矢口の事をビジョンや人間観に関してゆがんだ部分の大きい人物であると切り捨てている。矢口は2006年に亡くなっており、上記のようなエピソードが真実かどうかは確かめようもない。それに、生きていたとしても、多分憶えてはいないだろう。瀬木が古い話しを、わざわざ書いて読者に示す背景がきっとあるはずだ。多分、最高裁判所時代に、矢口に酷い目にあったのだろう。
悪口を言われたもう一人は、竹崎博允第17代最高裁判所長官 (1944~)である。彼については、その個人的言動については取り上げていないが、裁判員制度の導入者としてやり玉にあげている。竹崎の時代に、裁判所の統制が強化され上命下服、上意下達のどうしようもない司法組織が完成したように書かれている。
この傾向は、現代日本の政府、行政、司法、大学、企業、町内会などほとんどすべての組織に蔓延するジャパニーズ・シンドロームといえるのではないか。これを原因とする日本国のおぞましい劣化は、コロナ禍における政府や地方行政の無為・無策で見事に証明されつつある。もっとも、このような情けない人達は、漱石の『坊ちゃん』にも教頭の赤シャツ、太鼓持ちの野田として登場するので、明治時代にすでに発生していたようである。彼らは、言葉使いなどから、とても士族の出とは思えないので、どんな背景から教師になったのか、社会歴史的な研究が望ましい。













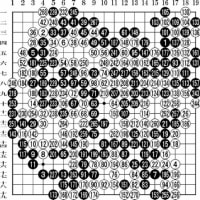












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます