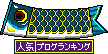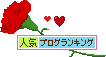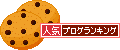5月6日(火)妻と二人で愛車プリウスに乗って比企郡の嵐山町と小川町へ「埼玉モダンたてもの」を見て歩きました。
最初に行ったのが「嵐山町立嵐山幼稚園」です。
この建物は日本赤十字社埼玉県支部旧社屋で、明治38年に埼玉県庁に隣接して建てられ、昭和58年に嵐山町立鎌形小学校の敷地内に移築保存されたものです。

埼玉を代表する明治期の建造物で、19世紀末のアメリカで流行したシンプルスタイルの影響を強く受けています。
赤瓦葺きの屋根に水色の壁面、建具の白と外観の色彩も明るく軽快なものです。
小学校校舎として使われた後に、現在は幼稚園として大切に使われています。

次に足を運んだのが、小川町の小川赤十字病院です。
裏手の高台に登っていくと、小さな正六角形の建物がありました。
これが「日向亭」(日本赤十字社埼玉県支部旧六角便殿)です。
実は上記の日本赤十字社埼玉県支部旧社屋の付属建物で、迎賓用の化粧室でした。
この正六角形の建物は形状等が周囲の緑多い環境によく調和することから、この場所に昭和57年に移築されました。

次に行ったのが「小川町和紙体験学習センター」(旧埼玉県製紙試験場)です。
スクラッチタイルを張った背の低い門柱が印象的。
和紙のまち小川に、昭和11年に埼玉県製紙試験場としてつくられました。
板張りの廊下、事務室、応接室には、昭和モダンの雰囲気が残っています。
現在は、和紙漉(す)き体験のできる施設として活用されています。

小川町の中心街に足を運ぶと数奇屋風の木造2階建でありながら洋風の窓や部屋に、レトロモダンな雰囲気が感じられる「割烹旅館 二葉」の本館が見えてきました。
「割烹旅館 二葉」は創業260年を数える料理旅館で本館は国指定登録有形文化財です。
「割烹旅館 二葉」の名物は「忠七めし」というご飯で、明治の偉傑・山岡鉄舟が名付親です。
「忠七めし」とは茶碗にごはんを盛り、薬味のさらしネギ・ワサビ・ゆずをのせ、その上から、どびんの熱い出汁をかけ、お茶漬けのようにサラサラといただく…のだそうです。
天皇陛下をはじめ、映画監督黒澤明、作家向田邦子など各界の方々から愛されたそうです。

「割烹旅館 二葉」から歩いて10分ほどのところにある造り酒屋「晴雲酒蔵」。
「晴雲酒蔵」の目印は、レンガ造りの大きな煙突です。
お米を蒸す熱源として木炭が使用されており、その当時使用されていた煙突です。

「晴雲酒蔵」では、蔵の2F(麹室)を資料館として見学することができます。
酒造りに使用される様々な道具類を見ることができます。
木造の大きな蔵の和小屋組は迫力満点です。