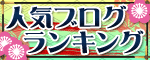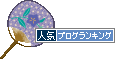9月27日(土)妻と二人で愛車プリウスに乗って飯能市・入間市・所沢市の「埼玉モダンたてもの」を見て歩きました。
西武池袋線の飯能駅ビル内にある旅行案内所で市内の地図をもらい、最初に「飯能織物協同組合事務所」に行きました。
この建物は、飯能が絹織物で栄えていた頃の大正11年に組合事務所として建てられました。
構造は木造総二階建て、寄せ棟、瓦葺きです。
外壁は下見板張り、窓は当初木製の上げ下げ窓でした。
この洋風な外観に対して、屋根には、両端に鯱が二尾据えられ、和風の桟瓦が葺かれています。
内部も違い棚を配した床の間を持つ十八畳の和室があり和風の雰囲気を残しています。

このあたりはレトロな街並みが楽しめますが、そのひとつが「吉川理容所」です。
飯能駅近くの「銀座通り」にあるこのお店は、石造風の看板建築が目印のレトロな床屋さんです。
昭和10年頃から営業しており、店内をよく見ると、当時から使っている特注の道具入れ外国製の鏡など、こだわりの逸品に出会えます。

「吉川理容所」の建つ「銀座通り」から「大通り」に出ると、黒漆喰の壁、下屋の屋根にうだつ、屋根の棟には大きな棟飾りがあがるなど贅の限りを尽くした建物が現れました。
「店蔵絹甚」(みせぐらきぬじん)です。
明治37年建築で、篠原甚蔵・長三親子によって建てられました。
篠原家は織物、生糸、繭、などの取引をしていました。

店蔵、居宅、土蔵の3棟があり、居宅と土蔵の間には中庭があります。
店蔵は商いのための空間で、客との商談などに利用され、居宅は家人の住まい、土蔵は商品等の保管庫になっていたと考えられます。
写真は座敷から見た店蔵扉です。
観音扉の金庫のような扉です。

飯能市のレトロな街並みをあとにして、名栗村の「旧平沼寛一郎邸」に向かいました。
「旧平沼寛一郎邸」は明治中期に建築された山あいの古民家です。
手入れの行き届いた落ち着いた色調の外観が、周囲の山や川などの自然と調和して良好な景観を生み出すとともに、自然と人々の生活が調和した山里の景観の核となっています。

田舎の民家でありながら、武家屋敷様式の書院造り、自然に朽ちた木の欄間、狆くぐり、襖絵、金唐和紙、丁寧に作られた建具など、当時の大工、職人の想いがこもります。

切妻屋根や、カラフルな色ガラス窓が名栗渓谷に溶け込み、美しい風景をつくり出しています。
また、座敷の窓から観音山や庭を眺めることができ、ゆったりとした気持ちになります。

次に行ったのが入間市の「旧石川組製糸西洋館」です。
実は今年の1月18日に入間市などの「モダンたてもの」を見て歩いたのですが、このたてものをうっかり見落としてしまったものですから、今回、訪問することにしました。
この西洋館は、石川組製糸の創始者石川幾太郎により、大正10年に迎賓館として上棟された和風工法による西洋風建造物です。
建物外観は、化粧煉瓦張りで、屋根窓を設けた変化のある屋根に特色があります。
残念なことに現在は期日を限って年に数回、春と秋に公開を行っているだけです。

本日の最後は所沢市の「クロスケの家」です。
場所は早稲田大学所沢キャンパスのすぐ近くなのですが、非常にわかりにくい所にありました。
「クロスケの家」は「トトロのふるさと基金」が森を守るための活動拠点として管理している古民家です。
母屋は約50年前に越生から移築された築百年を超える古民家で、縁側、囲炉裏や襖絵など昔ながら農家のたたずまいを色濃く残す貴重な文化財です。
明治10年代末から20年代初頭の築とされる蔵を伝統工法で補修し、左官職人によるトトロの家紋や蔵のあちらこちらにクロスケが隠れています。
リュックを背負った方はクロスケではなく私の妻です。(笑)