
1月14日(日)妻と二人で我が町・行田市が舞台になったTBS日曜劇場「陸王」のロケ地巡りをしてきました。

行田商工会議所では「観光情報館ぶらっと♪ぎょうだ」で「陸王」の劇中に使用された小道具の展示が行われていたので、最初にそちらに足を運びました。

実際にドラマの中で使用したミシンや宮沢紘一着用の「初代陸王」などの展示品が所狭しと並べられていました。
行田商工会議所はドラマでは埼玉中央銀行行田支店長室シーンで使われました。

商工会議所の裏手にあるのが、TBS「ぴったんこカン・カン」の「陸王埼玉御礼旅」で安住アナと竹内涼真たち陸王の出演者が行った「蕎麦 忠次郎蔵」です。
足袋蔵の中の一つであるこの店蔵は取り壊しの運命にさらされていましたが、平成16年にそば屋「忠次郎蔵」として生まれ変わったのです。
熱い肉汁に冷たいそばをつける、肉汁そばが人気だそうです。

ドラマのあちらこちらのシーンに登場するのが行田市のシンボル「忍城祉」です。
関東七名城に謳われた忍城は文明年間(1469~86年)の初め頃に築城され、上杉、北条氏との戦いにも落城せず、石田三成の水攻めにも耐え、戦国の世を生き抜いた名城です。
「陸王」以前にも、忍城が舞台となった作品は多数作られています。
三成の水攻めに耐えぬいた忍城の戦いを描いた「のぼうの城」も忍城が舞台です。

忍城から産業文化会館の前を歩き、市民プールに来ると、茂木がRⅡから4代目陸王に履き替える、あの感動的なシーンの階段があります。

市民プールから水城公園に向かう途中には行田市民駅伝シーンや「ぴったんこカン・カン」の「陸王埼玉御礼旅」で登場する「十万石ふくさや行田水城公園店」が見えてきました。

市内の国道125号沿いに本店を置き、県内外で38店舗を展開する十万石ふくさやは「陸王 十万石まんじゅう」を発売。
当初、日曜限定販売でしたが、注文が多いため11月から全店で毎日販売とのこと。

このあたりは行田の観光名所「水城公園」で、「陸王」のいろんなシーンに活躍でした。
「忍城」の外堀跡を利用して、中国江南地方の水郷式造園の手法を取り入れた水郷公園として整備されました。
園内には四季折々の草花が植えられていて、春になると地域有数の桜の名所となり、夏になると、葵の池がホテイアオイで埋め尽くされることでも知られています。

陸王のメイン舞台となる「こはぜ屋」を見に行きましょう。
行田八幡神社の裏手には「こはぜ屋」の外観として使われた「イサミコーポレーション」があります。
足袋のほか学生服や体育衣料などの製造を行っています。
大正時代を中心に建設された古い建物が残っており、行田市内に残る当時の大型足袋工場としては最古のものです。

向町の舞原被服工業(現在はマイハラ不動産)にある蒲鉾型屋根の工場。
この中が「こはぜ屋」の縫製作業室として、またシルクレイ開発室として撮影されたのです。

なお、舞原被服工業が昭和27年に建てた足袋の石蔵(舞原蔵)は戦後の行田を代表する均整のとれた石蔵として有名です。

宮沢(役所広司)と坂本(風間俊介)が、シカゴケミカルについて話をしていた喫茶店カフェコロラドです。
行田市駅近くの秩父線の踏切のそばにあります。

「横田酒造」付近では飯山(寺尾 聰)と村野(市川右團次)が屋台で話すシーンが撮影されました。
横田酒造は、文化2年(1805年)の創業。
江戸に下った近江商人・横田庄右衛門が良い水を求めてこの地で造り酒屋を開いたのが始まりです。

写真は「ぴったんこカン・カン」 2017年10月13日(金)放送で安住アナと役所広司と竹内涼真の3人が訪れた『足袋御殿』と呼ばれている和牛懐石「彩々亭」です。
足袋つづくりで財をなした荒井八郎氏の家だったところで、昭和天皇も訪れた場所です。
ここにはドラマにも使われているドイツ式八方つま縫いミシンが展示されているそうです。

陸王チームが飲んでいた「居酒屋そらまめ」は小針にある「活味」という居酒屋です。
行田市でも少し離れた場所にあるので愛車プリウスに乗って行きました。
ドラマに登場する「居酒屋そらまめ」では、メンチカツが名物メニューになっています。
「居酒屋そらまめ」のメンチカツが山崎製パンとのコラボ商品(肉王メンチカツ)になってコンビニやスーパーで売られているそうです。

「陸王ロケ地巡り」の最後は隣の鴻巣市にある「鴻巣市立競技場」です。
竹内涼真扮する茂木が練習するダイワ食品陸上競技場の撮影場所となりました。
2020年の東京オリンピック・パラリンピックのCMにも「鴻巣市立競技場」が使用されているようです。
また女子サッカーのなでしこリーグの試合会場になっているそうです。
実は私達夫婦も週に一度は買い物(ヤオコー免許センター前店)を兼ねて、この競技場の周囲をウォーキングしています。
ランキングに参加中です。クリックして応援お願いします。
↓↓↓


4月6日(木)我が家から歩いて10分ぐらいに位置する丸墓山古墳の桜を見に行って来ました。

丸墓山古墳は、埼玉県行田市にある古墳であり、直径105m、日本最大の円墳として有名です。
また、近年では昔地元の方が植えたソメイヨシノが成長し、桜の名所として親しまれています。

「丸墓山」という名の由来については、「麿墓」(まろはか)が訛って「丸墓」になった、あるいは丸い墳丘からその名が付いたなどの説がありますが、いずれにしても江戸時代の書物に「丸墓山」が登場することから、当時からすでにその名で知られていたことが確認できます。

その後、丸墓山古墳は思わぬ形で歴史の舞台となります。

豊臣秀吉が天下統一を進める1590年、家臣の石田三成は、秀吉の備中高松城水攻めにならい、忍(おし)城を水攻めにします。
その際、城がよくみえるこの古墳の上に陣を張ったのです。

現在駐車場から古墳へと続く道は、その際築かれた堤防の跡といわれています。
いわゆる「石田堤」です。

西国を制した豊臣秀吉は関東責めに入り、16万の大軍で小田原城を包囲します。
「この際 小田原方に味方するすべての城をつぶせ」と豊臣秀吉から命じられた石田三成は2万の軍を引きつれ、館林城、羽生城などを次々に制圧し、残るはこの地の忍城のみとなります。
三成の軍勢は2万、忍城方総大将城代成田長親(のぼう様)はわずか500の軍勢で壮絶な戦いが始まります。

成田長親は領民たちに木偶の坊から取った「のぼう様」などと呼ばれても泰然としている御仁。
従来の武将とはおよそ異なるが、なぜか領民の人心を掌握していました。
地の利と士気の高さから、緒戦は忍城側の圧勝でした。
三成は、近くを流れる利根川を利用した水攻めを行うことを決定します。
この水攻めに対する長親の策は、敵兵の前で田楽踊りを披露することでした。
三成軍が総攻撃を行おうとする矢先、小田原城が落城したとの知らせが成田勢にももたらされ、忍城も開城しました。
小田原城落城時までもちこたえた支城は忍城だけでした。
( 和田 竜 作“のぼうの城”より)
ランキングに参加中です。クリックして応援お願いします。
↓ ↓ ↓
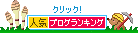

今日は妻と二人で行田市の「古代蓮の里」へ行ってきました。
土曜日にもかかわらず早朝からご覧のような人出です。








みなさん立派なカメラで本格的な人が多いようです。
私も一眼レフを買おうかなと思うこともあるのですが・・・
カメラも懲りだすとキリがないですからね・・・・(笑)
人気blogランキングへ



























