最初にこれまでの復習をざっとする。案外忘れていることが多いのに気づく。本題のケースではA社というアパレル業界でトップシェアの会社の問題を取り上げる。where(どこが問題か)とwhy(なぜそうなるのか)について考えるのが課題。イシューを特定し、分解の枠組みを決める。枠組みを決めるところまでが事前にメーリングリストで課題にされていた。私は夜中の12時頃と朝の7時頃にメールをアップした事もあるが、受講生のなかには朝の4時頃にアップする人もいた。みんな時間のやりくりには大変なんだ。データ分析できるようにExcelファイルが用意されているのは親切。ケースの記述と基本的な表から差や伸び率、構成比などを求めてみる。すると業界2位の会社は利益の伸びが突出している。市場環境のデータは記述部分とひとつの表だけ。市場環境は自明のこととして、これはベンチマーク分析がよいだろうと思った。しかし、授業ではきちんと3C分析から始めることが指摘された。当然と言えば当然かもしれない。5F、4P、3Cなどのフレームワークで考えた人もいたようだ。どういう場面でどういうフレームワークを使うか。これは経験を積み重ねるしか上達しないだろうが、いつも自分は何のために何を知りたいのかを考えるのが重要だろう。それにしてもグロービスのケースはうまく作られている。見かけの数字に引っ掛かってしまうところがあった。業界の特性を深く考えるのも重要だと気づく。この日の朝、食事をしているときにふと思いついてwhyのロジックツリーを2つ、手書きで作った。授業には全く使わなかったが、これでwhereとwhyの使い方の違いがつかめたように思う。授業ではinputとoutput、原因と結果を意識してoutputから考えるのが大切だという解説があった。ビジネスには誰もが納得する共通の正解はない。自分にとっての正解を求めるしかない。間違いを恐れず、考え、発言する。教室では現場と違って間違っても損失にはならない。むしろ間違った分だけ、実務で間違わなくなるメリットがある。学校はそれがよいところだ。授業ではふだんおかしいと思っているんだが、誰もおかしいと言わないことを先生に気づかされることが多い。今回はSWOT分析。このフレームワークはできれば使わない方がよいとのこと。私の場合SW(強みと弱み)はよく使うが、OT(機会と脅威)は使い方がわからず、使うことがなかった。使わない方がよい理由はFACTを評価するのではなく、このフレームワークだとすでに解釈が入ってしまうかららしい。
最新の画像[もっと見る]
-
 大学スポーツコンソーシアムKANSAI『大学スポーツの新展開』晃洋書房
5年前
大学スポーツコンソーシアムKANSAI『大学スポーツの新展開』晃洋書房
5年前
-
 ハラリ、ギャロウェイ、ガブリエル他『欲望の資本主義3 偽りの個人主義を越えて』東洋経済
5年前
ハラリ、ギャロウェイ、ガブリエル他『欲望の資本主義3 偽りの個人主義を越えて』東洋経済
5年前
-
 良品計画『無印良品の業務標準化委員会』誠文堂新光社
5年前
良品計画『無印良品の業務標準化委員会』誠文堂新光社
5年前
-
 河田剛『不合理だらけの日本スポーツ界』ディスカヴァー21
5年前
河田剛『不合理だらけの日本スポーツ界』ディスカヴァー21
5年前
-
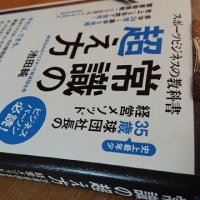 池田純『常識の超え方』文藝春秋
5年前
池田純『常識の超え方』文藝春秋
5年前
-
 丸山俊一『AI以後』NHK出版新書
5年前
丸山俊一『AI以後』NHK出版新書
5年前
-
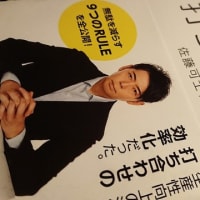 佐藤可士和『佐藤可士和の打ち合わせ』日経ビジネス人文庫
5年前
佐藤可士和『佐藤可士和の打ち合わせ』日経ビジネス人文庫
5年前
-
 倉田剛『日常世界を哲学する』光文社新書
5年前
倉田剛『日常世界を哲学する』光文社新書
5年前
-
 ジェラルド・ガーニー他『アメリカの大学スポーツ 腐敗の構図と改革への道』玉川大学出版部
5年前
ジェラルド・ガーニー他『アメリカの大学スポーツ 腐敗の構図と改革への道』玉川大学出版部
5年前
-
 村上春樹/安西水丸『夜のくもざる』新潮文庫
5年前
村上春樹/安西水丸『夜のくもざる』新潮文庫
5年前









