スウェーデンで生活をしていると、日々の買い物の至るところで環境に関するマーキングを見つける。

クラーヴ
スウェーデンでは最もメジャーなエコロジー認証。農薬や化学肥料を使わず、遺伝子組み換えも行っていない有機栽培の食品や繊維製品に付けられている。NPO「クラーヴ」が認証を行っている。Kravとはスウェーデン語で「要求する」という意味。つまり、生産者に厳しい基準をクリアするように要求している、ということだ。

スヴァーネン(白鳥)
原材料の調達から生産、そして廃棄に至るまでの商品のライフサイクル全体を考慮して付けられるエコロジー認証。質や性能も考慮されている。対象は、洗剤から家具やホテル運営に至るまで68の商品グループ。北欧5カ国の政府間協力機構である北欧閣僚委員会(Nordiska ministerrådet)のイニシアティブで始まり、スウェーデンでは政府から委託を受けた認証機関が審査を行う。


ブロー・ミリヨーヴァール(環境によい賢い選択)
原材料の採取から製品の完成までのプロセスを考慮して付けられるエコロジー認証。対象は、紙や洗剤など、生活雑貨が多い。スウェーデン最大の環境団体である自然保護協会(Naturskyddsföreningen)が認証を行っている。右上の写真にあるように、電車にも付けられている。

フェアトレード(スウェーデン語では、レットヴィーセマルクト)
国際的なNGOフェアトレードによる認証。彼らと直接貿易を行うことで中間での搾取をなくし、適切な賃金を彼らに払っている、という認証。一次産品などが多い。環境的な持続可能性ではなく、社会的な持続可能性を考慮したエコロジー認証だといえるだろう。
最近はこれらの商品に対する需要が高いために、スーパーなら大概どこでもこれらのマークが付いた商品を買うことができる。一般の消費者に対するアクセス性が高まるにつれ、需要が高まり、その結果、スーパーがさらに品揃えを充実させようという好循環が働いているのだと感じる。
また、公的機関や自治体の中には、グリーン購入ポリシーを掲げているところも多く、そこでの需要も高まっている。ヨーテボリ大学の経済学部が職員のために購入しているコーヒー豆やティーバッグ、砂糖なども最近は「クラーヴ・マーク」と「フェアトレード」の両方が付いている。

このほかにも「エングラマルク」などいくつかある。あと一つ、あえて挙げるとすればこんなのもある。

TCO(テーセーオー)・マーキング
これは、パソコンのキーボードやディスプレイ、ヘッドセットをはじめとするオフィス機器や椅子・机などオフィス家具に付けられた認証。人間工学を考慮した利便性や、電磁場の抑制、省エネ性、生産者が環境認証を取得しているか、生産過程で有害物質の放出が抑制されているか、などが考慮されている。
面白いのは、ホワイトカラーの労働組合TCOが設立した認証制度だという点だ。TCOの組合員はオフィスワーカーが多い。だから、彼らにとって利便性がよく、体への負担(肩こり、電磁気の影響etc)が少ない製品の購入を促進しようという、労働組合ならではの発想だ。また、職場からエコロジーを実現しようという取り組みと考えることもできる。

クラーヴ
スウェーデンでは最もメジャーなエコロジー認証。農薬や化学肥料を使わず、遺伝子組み換えも行っていない有機栽培の食品や繊維製品に付けられている。NPO「クラーヴ」が認証を行っている。Kravとはスウェーデン語で「要求する」という意味。つまり、生産者に厳しい基準をクリアするように要求している、ということだ。

スヴァーネン(白鳥)
原材料の調達から生産、そして廃棄に至るまでの商品のライフサイクル全体を考慮して付けられるエコロジー認証。質や性能も考慮されている。対象は、洗剤から家具やホテル運営に至るまで68の商品グループ。北欧5カ国の政府間協力機構である北欧閣僚委員会(Nordiska ministerrådet)のイニシアティブで始まり、スウェーデンでは政府から委託を受けた認証機関が審査を行う。


ブロー・ミリヨーヴァール(環境によい賢い選択)
原材料の採取から製品の完成までのプロセスを考慮して付けられるエコロジー認証。対象は、紙や洗剤など、生活雑貨が多い。スウェーデン最大の環境団体である自然保護協会(Naturskyddsföreningen)が認証を行っている。右上の写真にあるように、電車にも付けられている。

フェアトレード(スウェーデン語では、レットヴィーセマルクト)
国際的なNGOフェアトレードによる認証。彼らと直接貿易を行うことで中間での搾取をなくし、適切な賃金を彼らに払っている、という認証。一次産品などが多い。環境的な持続可能性ではなく、社会的な持続可能性を考慮したエコロジー認証だといえるだろう。
最近はこれらの商品に対する需要が高いために、スーパーなら大概どこでもこれらのマークが付いた商品を買うことができる。一般の消費者に対するアクセス性が高まるにつれ、需要が高まり、その結果、スーパーがさらに品揃えを充実させようという好循環が働いているのだと感じる。
また、公的機関や自治体の中には、グリーン購入ポリシーを掲げているところも多く、そこでの需要も高まっている。ヨーテボリ大学の経済学部が職員のために購入しているコーヒー豆やティーバッグ、砂糖なども最近は「クラーヴ・マーク」と「フェアトレード」の両方が付いている。

このほかにも「エングラマルク」などいくつかある。あと一つ、あえて挙げるとすればこんなのもある。

TCO(テーセーオー)・マーキング
これは、パソコンのキーボードやディスプレイ、ヘッドセットをはじめとするオフィス機器や椅子・机などオフィス家具に付けられた認証。人間工学を考慮した利便性や、電磁場の抑制、省エネ性、生産者が環境認証を取得しているか、生産過程で有害物質の放出が抑制されているか、などが考慮されている。
面白いのは、ホワイトカラーの労働組合TCOが設立した認証制度だという点だ。TCOの組合員はオフィスワーカーが多い。だから、彼らにとって利便性がよく、体への負担(肩こり、電磁気の影響etc)が少ない製品の購入を促進しようという、労働組合ならではの発想だ。また、職場からエコロジーを実現しようという取り組みと考えることもできる。










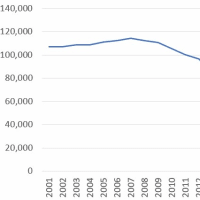
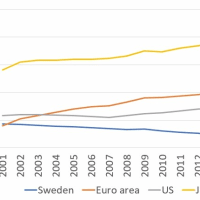
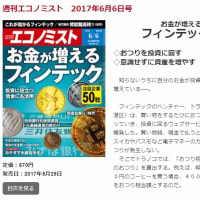
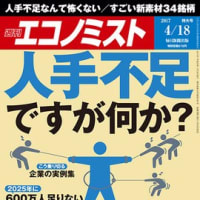






電車やホテルにもついているから、無理なく環境にいいものを選択できますよね。見つけるのも楽しかったな^^
それに比べて日本の有機JASマークはイマイチ信用できないんですよね。。遺伝子組換えもそうだけど、基準が甘いという話を聞きます。
日本にも省エネラベルはあるけど、労組ラベルはその上をいっていますね。
私事になりますが、現在私がTAを務めているウプサラ大学のmiljövård kursで丁度認証マークを採りあげたところで、個人的にもタイムリーな話題として記事を読ませていただきました。
先日行ったディスカッションでは学生さん達がエコロジー認証マークの林立がもたらす帰結について話合いました。主な意見として、2010年に導入が義務付けられるKRAVより基準が緩いEUマークは信頼性、基準への理解といった点で消費者を混乱させる可能性がある、森林認証制度FSCやPEECには互いの差別化が容易でないことや企業への審査が甘く生物学者の団体が指摘したように認証の信憑性に疑問がある、といったものが出されました。
ちなみに以下はコースで使用した参考サイトです。
1. EU の認証
sr.se/cgi-bin/ekot/tema/arkiv.asp?ProgramID=1630&Max=2007-01-10&Min=2003-11-21&PeriodStart=2006-12-18&Period=2&Artikel=1099952
2. Marine stewardship council
sv.msc.org/
3. Forest stewarship council (FSC) and PEFC
www.snf.se/verksamhet/skog/fsc-pefc.htm, www.pefc.se/, faltbiologerna.se/verksamhet/927/faeltbiologernas-fsc-sida och www.fsc-sverige.org
4. Trygg textil och ”rättvisa kläder” (衣類の認証マーク)
www.oeko-tex.com/OekoTex100_PUBLIC/index.asp?cls=02 och www.radron.se/templates/common____5544.asp
5. エコツーリズム
www.naturensbasta.se/ekoturism/index.asp och www.mycarbonfootprint.eu/
6. 様々なエコロジー認証マーク
www.fairtradecenter.se/, www.svanen.nu, www.tcodevelopment.com, www.environdec.com/, www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabname=@iso14000&menuItemID=139 och dagensmiljo.idg.se/2.1845/1.110962
Allmänna länkar: www.wwf.se, www.snf.se, www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=773, www.miljosverige.se/vgv/
多少商品が割高でも、世の中に少しでもよいと思ってフェアトレードの商品を購入している消費者にとってはとてもラベルへの信頼性をもゆるがす放送でした。製造者も企業のイメージアップと社会貢献への取り組みのためにフェアトレードを採用しているにも関わらず、認証後にそれがうまく機能しているか調べるのにまだまだ改善の余地がありそうでです。
自分の論文でバイオプラスチックの認証ラベルについて調べたときも日本とヨーロッパ、アメリカでずいぶん基準が違うのに驚きました。消費者が誤解をしないよに十分検討された上で導入されるといいのですが、日本の場合、認証にとてもお金がかかるので,中小企業はなかなかラベリングの制度についていけない、という問題もあります。そもそも日本の基準はヨーロッパと比べてかなり甘いと思いますが。
省エネルギー政策は世界的にみてもいい線いっていると思いますが、政策決定にスピード感のない日本において循環型社会の構築はまだまだ時間がかかりそうです。技術はどこよりも良いのに、おしい話です。
その通りに思います。CO2排出に関する新たな認証を巡る議論について、次に紹介しました。
多数のリンク、ありがとうございます。
参考資料をお探しの方のお役に立つのではないかと思います。
せっかくの認証も、それが消費者の信頼を勝ち取るためには、認証の理念が実際に実現されているのか、常に評価していかなければなりませんね。
ご指摘のようなメディアによるルポタージュも、そのために必要な「監視役」としての役割を果たしているのだと思います。