 やっぱり講演会をやるべきかなあと思います。
やっぱり講演会をやるべきかなあと思います。
皇室についての理解や質問などに出来るだけ答える形で。
またお茶会なども楽しいよね

今までは一方的な講演会でしたけど、今後はぜひ「質疑応答形式」を取り入れたいです。
とはいえ・・・・















さて、通りすがりさんの
「教育勅語の中身に異論はないですが、明治天皇を現人神として「間違いを犯すはずがなかった」とおっしゃるのには全く同意できません。明治の世であっても天皇はただの人だったはずです。今と本質的に変わりません。
ですので、教育勅語を「間違いを犯すはずのない人の教訓」であるとしてありがたがるのはおかしいと思います」
というご意見についてですが、戦前は天皇は「現人神」という立ち位置だったんです。
神は間違わないのです。そうでしょ?
今の私達からすれば天皇も皇族もただ人ですが、戦前は心でそう思っても口に出してはいえなかった。
というか、天皇に対して「天皇様だって間違う事はあるさ」などとは考えもしなかった時代であた・・・・
という事が言いたかったのです。
蓼科さまの
「すみません。わからないので教えて下さい。和服ではどうしてNGなんでしょうか?
私、手描き友禅職人の娘なので、和服って大事にしたい気持ちがあるんですけど、こういう場にそぐわないわけを教えて下さいませ」
に関していうと、和服がダメとかそういう事ではなく、皇室では明治以来、正装は「洋装」なんです。
明治維新後、先進国に追いつく為に「洋装令」が出され、今に至っているのです。
じゃあ、その前はどうだったか?
それは袿袴姿でした。
私、最近、つくづく研究したいなと思っている事に「古代の皇族のキラキラネーム」(これは何度もブログで述べてきましたし、講演会でも話しています)があるのですが、今は「奈良時代から平安時代への服装の転換」についてです。
服装というのはどの国も自然に変わって行くもので、奈良時代までの朝廷はほぼ中国と同じ服装でした。
冠、かんざし、耳飾り、指輪、腕輪など装飾品もあったのですが、平安時代になると、とたんにそれらが消えていきなりあの十二単ですよ。この間に自然な変化がなかったのかしら・・・・と。
で、この十二単の簡略版が江戸末期まで続くわけですが、髪型にしても服装にしても、丈の長さなど以外、形としてはそんなに変わっていないんですよね。
奈良と平安。遷都しただけでいきなり服装も変わるものなのかなあと。
それはおいておいて。
だから皇室にとって、正装は洋装。でなければ袿袴姿なのです。
いわゆる「着物」というのは武家と庶民の服装で、髪型も勿論そうです。こういうところで皇室と徳川をきっちりわけていたともいえますね。
和宮が江戸に来た時、天璋院との間で様々なもめごとがありましたが、貴族文化と武家文化の違いだったのでしょう。(廊下を足袋をはいて歩くのが大奥風で裸足は女官風とか)
皇后陛下は皇室に入った時から、喪服を洋装ではなく着物にしていました。
ご結婚後すぐに照宮様が亡くなられた時も、回りが洋装なのに一人で黒い喪服。代替わりの時はさすがにその勇気がなかったのかもしれませんけど、現在はどこでも黒の喪服です。
しかし、他の皇族は洋装を貫いています。だから変なのです。
なぜ皇后だけがそうも伝統を無視して着物に拘るのか。
そこに着物への愛ではなく「袿袴や十二単を持っていないからって何よ」的な恨みを感じるんですね。
それは皇族出身の香淳皇后への対抗意識だったのではないかと私は思います。
無論、明治以降に創設された宮家の妃はみな武家出身者が多く、彼女達にとって洋装は公家とか武家とか言わない共通の正装で便利だったんじゃないかと思いますけど。
そういえば皇后陛下は着物道楽で「手書き友禅」がお好きですよね。
でも紋は何を使っているのか・・・・菊?正田家?白樺?










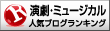


















時々拝見していただいています。
今回のお答えの中で
>今の私達からすれば天皇も皇族もただ人ですが、戦前は心でそう思っても口に出してはいえなかった。
とありますが、だから今の時代にこれを子供達に、洗脳させるように覚えさせるのは時代錯誤だと言われてるのではありませんか?
天皇や皇族の捉え方が違うわけですから。
私達ってことは、ふぶきさんも天皇、皇族をただの人だと思ってるのですよね?だからこそ、いつもかみつきまくってるわけでしょうし。
それなのに今の子供に天皇を現人神という立ち位置に考えさせるのはおかしいのではないですか?
批判しているわけではなく、矛盾しているように感じたので、私が間違っていたらお答えください。ふぶきさんがうっかりしていたのでしたら、お答えはけっこうです。
こちらのブログが、非常に詳しく、あちこちの情報を加えて教えてくださいました。
h
ttp://blog.livedoor.jp/remmikki/archives/4932934.html#comments
(安全なブログですが、あえて直接リンクにはしないでおきました)
ブログ的情報は、2012年の東日本大震災の震災慰霊式のときから、表立って始まります。
その式に、皇后が「黒無地五つ紋」をお召しになり、登場されたことが、一つの大きな出来事だったようです。
この間、宮内庁とのやりとりも出ています。
皇后が職人に注文→宮内庁から「とんでもないやめてほしい」というお断りが職人の方に入る→再び皇后から注文→注文が通る
といったような経緯だったようです。
宮内庁としては、庶民・武士に端を発した「黒無地五つ紋」というのは、「庶民」の象徴(少なくとも貴人ではない)であり、皇室では正式な場ではそぐわないと、拒否の姿勢だったそうですが、皇后がその意思を貫き通したとのこと。
何より宮内庁が驚愕したのは、その「黒無地五つ紋」のこの紋が、「菊」だったこと。
これこそ「わたくしは、庶民出生の皇后です!」との宣言にほからならなかったとか。
今、我々はエライ人を皇后にしているんだと、改めて背筋が寒くなってまいりました。(上記ブログ、さらに飛んでいろいろなブログを全てお読みになると、さらに意味がおわかりになるかと思います)
なぜにそちらには批判されないのですか?
民族衣装と言っても「振袖」等は武家で進化した衣装形態なので、皇族が着用するなら仰っているように「袿袴」でなければおかしいです。
都合のいいときだけ「素敵なお着物~!」ではブログ主の好き嫌いだけの意見ですね。
あなたが荒らしでないと仮定して1度だけお返事しますが、天皇を現人神と思うか、ただ人と思うかという事と教育勅語の内容は関係ありませんので。
何を洗脳させるようにしているのかわかりません。
森友の事なら、それはあちらの教育方針であって。私には答えかねます。
みぃ太郎さま
言いがかりですね。園遊会などに着物を取り入れたのは皇后ですし、積極的に着物を着ているのも皇后です。
しまきさま
ありがとうございます。そんな事が・・・・いやはや。
タオチャンさま
ナス子さんは今きっとブログより大事な事が出来たのではないかと思います。
「皇室の女性の正式な喪服は、昭和天皇の大喪の礼の際着用されていた黒のロ-ブモンタントになります。
今回のような一般人が着るような着物は、本来皇室のかたがお召しになることはありませんでした。
(これは、全ての着物に関してです)
明治時代に、「正装は洋装」との定めがあり、神事などの装束以外は洋装になりました。(女性の大礼服には桂袴がありましたが)
香淳皇后の時代に日本の世界に誇る和服をお召しいただきたいという動きがあり、皇后さまが着用されたところ、昭和天皇が「良宮は和服のほうが似合うよ」と言われた為 今まで皇族は『公に着用できなかった和服が着用されるようになったのです。』
今回皇后さまが初めて我々庶民と同じ喪服を着用されました。これはかつてない災害を国民と共に深く哀しんでおられる皇后さまのお気持ちではないでしょうか。」
(2012年当時のことです。そのためもあり、このコメンターの方は、皇后の喪服を好意的に解説しています)
この答えには質問があり、東日本大震災の慰霊式に実際ご参加なさった方からのものだったようです。
「皇室の方は、喪服はお召しにならないはずです。天皇陛下は洋装でいらっしゃいました。式典の初め、皇后陛下の喪服姿を見て、会場がざわついておりました。これは皇后陛下のお姿に対する違和感だったのではないでしょうか?
なお、紋は「菊」と見て取れました。」
とのことでした。
やはり、あのお姿は、見た人によっては衝撃だったようです。そして菊のご紋であること、直接見た方の証言により、はっきりしたように思います。
宮廷文化の視点から言えば、袴無しとは下着姿と同じということ。
そもそも、出歩いたり仕事をする必要性から平安衣装がどんどん簡略化され、いわゆる着物が誕生したのです。
したがって着物が正式ではない、というのは間違いないのです。
皇族には伝統保護の観点から、現代の和装も御召しになって頂きたいですが、喪服等は洋装令に従ってほしいものです。
少し省略して記述します
「我が国民は忠義と孝養を尽くし、全国民が心を一つにして立派な行いを長年行ってきたことは、我が国の優れたところであり、教育の根源もそこにあります。
国民は、父母に孝養し、兄弟仲良くし、夫婦仲睦まじく、友達とは互いに信じ合い、行動は慎み深く、他人に博愛の手を差し伸べ、学問を修め、仕事を習い、それによって知能をさらに開き起こし、徳と才能を磨き上げ、進んで公共の利益や世間の務めに尽力し、憲法を重んじ、法律に従いなさい。
もし緊急の事態が生じたら、正義心から勇気をもって公のために奉仕し、永遠に続く皇室の運命を助けるように。
このような道は、わが皇室の祖先が残された教訓であり、その子孫と国民がともに守っていかねばならないことで、昔も今も変わらず、国の内外をも問わず、間違いのない道理です。
私はあなた方国民とともにこの教えを胸中に銘記して守り、皆一致して立派な行いをしていくことを切に願っています。」
明治23年10月30日
明治天皇御名御璽
※文中の「私」は明治天皇です。
読んでいて、今の日本人にとって、失われつつある、立派な心得です。
年金からのお小遣いをくれないからといって、孫が祖父を殺したり、知的障害者の入居者を十何人も殺したり、いじめによる自殺が相次いだりする現代の人たちにこそ、読ませたい言葉だと私は個人的に思うのです。
森友学園は、私は今となると、「神道」について、どこまで深く理解していたのか疑問符です。単なるそれを手段とした商売人のような気がしてならない。
理事長の発言を生で聞いて、心の底から嫌な気持ちになりました。
なお、この「教育勅語」が最も当てはまらないのが、皮肉なことに、アレラの方たちです。
やはり民間からの興しいれは
非常に危険を伴うものだということです。
その中で紀子妃殿下は大変
素晴らしい方で、必ずしも
皇族で泣ければいけないとは
言えないのですが、例外的な
存在ではないかと思います。
皇后陛下にしても、皇太子妃にしても、民間からの嫁入りが、実に
時限爆弾的存在に成りうることを
如実に示していると感じ、空恐ろしい気持ちです。
その気になれば、反天連のような
思想を持った勢力がいとも簡単に内部から皇室を破壊するための
策謀をめぐらし実行に移せるのだ・・・ということを我々国民の側も
肝に銘じておくべきではないかと
思います。
結局、着物云々にしても、
着物が駄目という訳ではなく、
「伝統」に従わない心根の部分が
問題なのだと解釈しています。
皇室こそ伝統を重んじることを
最優先すべきなのではないかと思います。
平安時代もそれなりの長さがあるので、平安初期からあの十二単が完成していたわけではなかったと思われます。
菅原道真が遣唐使を廃止して、唐にかぶれた文化が廃れ、国風文化が花咲いていく中での十二単です。
ですから、平安初期の竹取物語のかぐや姫は絵本の中では十二単ですが、本来は奈良時代の服装に近いものだったと思われます。