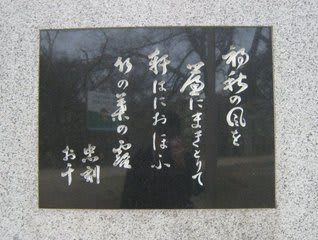ようやく春らしい天気にめぐまれた日曜日
お世話をしているウォーキング倶楽部の月例会で
神戸・垂水海岸から大蔵海岸を歩いた
JR垂水駅(神戸市垂水区)に9時半集合
今日の担当はめったさん、地元生まれでおなじみの場所
資料の準備は万全、こちらは付いていくだけの安心コース
珍しく女性群が全員欠席でおじさんたちだけのウォークになった
(あー、静かでいいとは誰も言わなかったが・・・?)
ほんとうはケンカ相手がいなくてさびしい
スタートしてすぐ播磨三大社の一つ、海神社へ
いつものように安全祈願のお参りをして
すぐ近くの商業施設マリンピア神戸の外周を海岸にそって歩く

目の前に淡路島がゆったりと見える
世界最長吊り橋の明石海峡大橋(3911メートル)が
そびえるように迫ってくる

海岸では釣りをする人、ウォーキングしてる人
親子連れで家族している人、写生大会の子供たち
キャンバスに大橋を描いている人

のんびりと久しぶりの春の陽を浴びて
海峡の日曜日を楽むように大勢が来ていた
公園の一角ではフリーマーケットも開かれていた
大橋の手前に1915年築で現存する日本最古コンクリートブロック
造建造物で国の重要文化財に指定されている孫文記念館があり
最新の大橋と最古の記念館とのコントラストが妙にマッチしていた

橋の下を大型船から小型の釣り船まで、大小さまざまな船が
ひっきりなしに海峡を行き来する
ここは瀬戸内海の交通の要衝、ながめているだけでも楽しい

瀬戸内で育った自分にとって海といえばこの景色が最高
淡路島と和歌山の間を流れる紀淡海峡もみえる
はるか関西空港のゲートタワーも見える

大蔵海岸を目指して2号線を歩いていると
明石藩舞子砲台場跡の碑が目に付いた
勝燐太郎(海舟)指導のもと明石藩が築造したものだ

文久3年(1863)外国船侵攻にそなえ幕府の命だった
数年前まで長く開催をされていた明石海峡ウォークラリーの
おなじみのスタート地点・明石市大蔵海岸にやってきた
海岸の公園には堀江健一さんのマーメイド号が展示してあり
実にのどかな海岸風景だが
ここの歩道橋には悲しい事故があった

2001年7月21日の明石市民夏まつりの花火会場へ向かう人が
群衆なだれにより命を失った11人を偲ぶ「想」という像が
安置されている、そっと手を合わせて冥福を祈った

今日は福知山線列車事故5周年の日でもある
それを悼むウォークも開催されているが
例会と重なって参加できなかった
コースはJRの歩道橋を渡って山側へ移っていき
しばらくアップダウンの続く住宅街のコースをすすみ
昼食地点の大蔵山遺跡公園についた。
ここからの海峡の眺めもすばらしい、明石海峡大橋を本土側の
こんなに高い位置から眺めるのは初めて
この遺跡から2万年前の石器や弥生時代の竪穴式住居の焼け跡が発見されている

昼食、多忙で久しぶりに参加したよっしーさんの近況報告から話題は
よっしーさんはわが倶楽部でメタボ解消の指定強化選手のひとりだが、
すいぶんスリムになって参加してくれたその苦労談も披露
午後のコースも住宅街を右に左にアップダウンしながらすすむ
自分以外は53歳のリーダー、あとは40代の男働き盛り
自分とは体力に格段の差がある彼らと歩けることはうれしい
引き締まった後ろ姿、きれいに伸びる一歩一歩
やっぱり若い人(彼らも組織内では若くはない)と行動を
共にすることは多くの刺激と自分の見直しに大事な時間
さらにアップダウンの続く市街地を小刻みに左右にすすみ
五色塚古墳へ着いたのが14時17分
淡路島が右前方に望める台地に築かれたこの古墳

前方後円墳で全長194メートル、兵庫県で一番大きな古墳で
三段に築かれた墳丘は珍しくて、向かい側にもきれいに整備された
小壺古墳があり、何組かのウォーキンググループも訪れていた


山の手の住宅街からJR、山陽電鉄を越え東垂水展望公園へ
このあたりはかって砂地の海岸で担当のめったさんやリーダーのちゅうさんは
子供のころの遊び場、泳いでいたなつかしいところだった

コースは国道2号線にそってスタートしたJR垂水駅へ15時45分
約18キロ、日陰がほしい陽気の中でコース設定もすばらしく
大空のもとに潮の香の漂う垂水と明石の海岸ウォークは楽しかった
ゴールして倶楽部のリーダーをしてくれているちゅうさんの激励会
自分に続いて先月、熊野古道を完歩した彼が次の29日に
いよいよ四国霊場88ケ所めぐりにスタートすることになったので
急遽、激励会をすることにして駅下のみんみんでビールと餃子で激励
大手企業のビジネスマン、10年連続六甲縦走達成、53歳の男盛り
早ければ2年、5年をめどに歩くと力強く言ってくれた
帰り際、駅で久しぶり参加のよっしーさんがささやいてくれた
萎えたとき、自分のブログで元気づけられているという
一人だけダントツ年長の自分の役割はそれだけだから
そこからしぼりとれるものがあるなら取ってほしい
その分、自分の仕入業務を怠ってはならない
お役にたてる限りまだまだ引っこんではならないと思った。