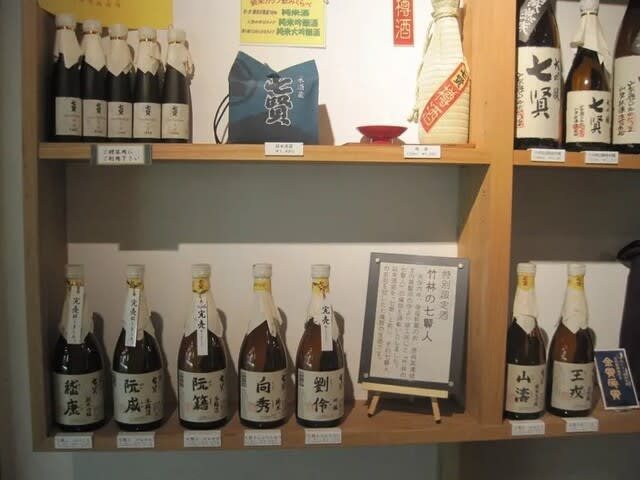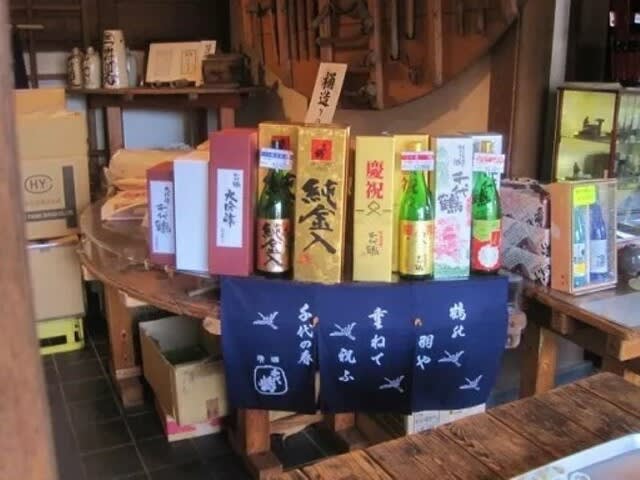最近の日本では世界中のワインが輸入され気楽に飲めるようになった。しかし以前は輸入ワインが非常に貴重であった。1969年、ドイツに住んだ時は「貴重な」という先入観もあってワインを良く飲んだ。ローテンブルグという中世の田舎町でのことである。
ガストフという古い食堂に入る。木目が美しい内装で、中は暗い。すぐに帽子、コートを脱ぎ、入り口近くの帽子掛けに掛ける。「グリュ-スゴット!」(神のお加護を!)と
主人へ声を掛けて座る。日本の学校ではグリュ-スゴット!などという挨拶は習ったことが無い。南ドイツの方言である。奥の左手のテーブルは男だけの地元常連客のテーブルであり、座ってはいけない。
田舎の店ではコートの脱ぎ方、挨拶の仕方、その後の仕草を地元の人々がジーッと見ている。作法通りにしないと露骨に嫌な顔をする。アメリカ人観光客は地元の作法に無頓着。どうしても嫌われてしまう。
ワインを注文する。渋みの効いた地元のワインを注文する。行く度に注文の銘柄を変え味を比較する。次第にドイツワインの深みが分かるようになる。ドイツワインだけを飲んでいるとフランスワインは不味いと感じるようになる。
あるとき2週間の全国旅行へ出た。フンボルト財団の主催した団体旅行で色々な国の人々15人位であった。旅行中の全ての宿は伝統的な民宿。地下室にケーラーというワインの貯蔵倉を持っている。夕食時には必ず年代物のワインの栓を2,3本抜く。栓を抜くのは民宿のご主人。重々しい顔でラベルの年代を読み、コルクを抜く。始めに一杯だけグラスに注ぎ、団員が交代で務める「主客」が一口飲む。しばし考えて、「美味い。少しドライだがそこはかとない葡萄の甘味もあり結構じゃないですか」などと誉める。主人が満足げに全員のワイングラスに注いで飲み始める。ワインに使った葡萄の品種やその年の天候などが主人から説明がある。それが終われば儀式が終わる。この部分はあくまでも伝統的な作法であり、間違っても少し味が良くないなどと言ってはいけない。始めの頃、決まった作法と知らない日本人が自分の好みの味ではないと言ったために主人と大激論になった。その後、交代で、自分が主客になったときは「美味い!深い味だ!」などと言うようになった。儀式が終われば、味の批判や評価をしても良い。南ドイツではワインの飲み方にも伝統的な儀式が出てくる。
ヨーロッパ諸国、中国、韓国などの色々な国々には種々のお酒がある。そしてお酒の飲み方にも違った作法がある。
郷に入れば郷に従うように飲み方もその地方の方法を遵守した方が良い。礼儀の基本である。
しかし要注意。中国では宴会のとき乾杯の応酬が何度もあり、「飲み干すのが礼儀」という。よく聞いてみると、それは始めの一杯だけのことらしい。乾杯の応酬の仕草だけで良いそうである。これを間違ってフラフラになっている日本人をよく見かけた。
でも老境にいる私にとっては酒を多量に飲んでいた時代ももう遠い昔になった。
懐かしく思うのは南ドイツでも面倒なワインの飲み方の儀式である。あれから50年近くになる。