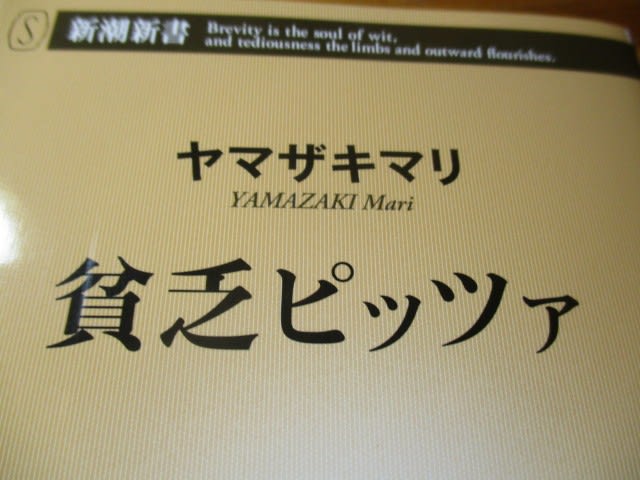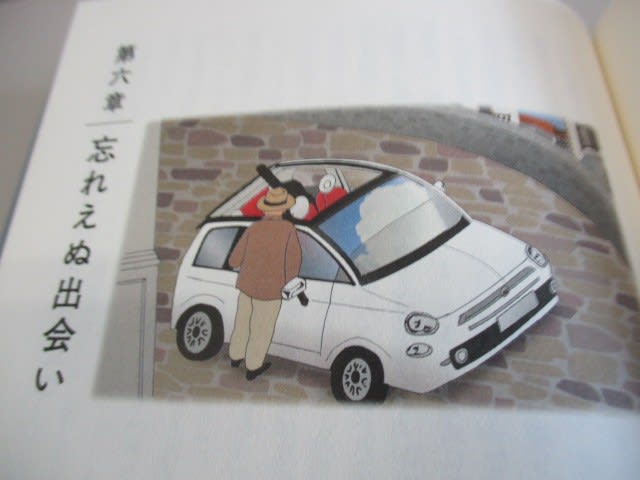人的資本経営、ISO30141、健康経営・・・経営資源「ヒト」にスポットライトが当たっています。
今までは、財務諸表に人材についての開示は不要でしたが、株主やステークホルダーが欲しいのは、最大の経営資源である会社組織が囲いこんでいる「人財」。
2023年3月期から、有価証券報告書での開示がはじまりました。
米国では2020年から開示義務が課せられているため、3年以上遅れてのディスクロージャーになります。
今週号の日経ビジネス誌2023.10.30の特集記事は「丸井・エーザイ・味の素に学べ 人的資本開示の心得」。
旬のテーマです。

Contents
Part1 人的資本の見える化は世界的な潮流 横並びの日本企業 開示を起点に変革を起こせ
Part2 成長力の源泉、こう見せる 独自指標に価値
Part3 経営開示に焦点 KPI示し克服の道筋示す
Part4 上場企業だけじゃない 「見える化」「透明性」であなたの職場を快適に
人的資本開示アワードは、日経ビジネス誌が始めた専門家による賞。
人的資本投資、企業価値、経営戦略、ダイバーシティ、エンゲージメントなどの視点から審査を行ったということです。
全体表彰
金賞 丸井グループ・・・挑戦と失敗の価値 数字で明確に示す 店舗より人への投資効率高い
銀賞 エーザイ・・・豊富なデータで人財の投資効率示す 定量的に開示
銅賞 味の素・・・施策の成果を「働きがい」で可視化 エンゲージメントと業績の相関関係
開示された情報が納得を得るためには、客観性、定量化、数字、ファクト、ロジックが必要です。
受賞した各社ともに、その要件を満たしており、社員に対してもストーリーを持って語れる内容になっています。
その際、その会社らしさは、KPIに出ています。
「LTV(ライフタイムバリュー)」、「オフィス年間平均出社率(伊藤忠)」、「依願退職率(東京ガス)」「健康年齢(小野薬品)」、「奈良県GDP(南都銀行)」、「成長対話満足度(三菱商事)」「中核人材のグループ他社経験比率(東洋製缶)」・・・。
面白いですね。
女性エンパワーメント部門では、双日、丸井グループ。
デジタル部門では、リコーと帝人。
育成部門では、日清食品、ディスコ。
サクセッション部門では、三井化学と味の素。
インパクト部門では、エーザイとオムロンがそれぞれ受賞しています。

まだ義務化はされていないものの、中堅企業、中小企業でも人的資本開示を活用すれば、メリットを享受することが出来ると思います。
コミットメント、モチベーションの向上、リテンション対策、そして何よりも学生求職者へのアピールです。
単に女性管理職比率や離職率といった定番メニューだけではなく、自社独自の指標を作っても面白いと思います。
新人から一人前になるまでの平均年数
年間の研修時間
管理職に昇進するまでの平均年数
イクメン休職率
年次有給休暇取得率・・・
今まで、BS(貸借対照表)、PL(損益計算書)、CS(キャッシュフロー計算書)などの財務諸表には出てこなかった人財。
上場企業では、会社組織が抱え込んでいる人財を有価証券報告書に記載しなければならない時代になりました。
これを機に、ニッポンの会社に再びイノベーションを起こすチャンスにしていかなければならないと思います。