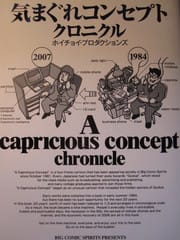今年は、戦後80年。
ヒトラーが率いたドイツ第三帝国崩壊80年に当たります。
ヨゼフ・ゲッベルス(1897年~1945年)
ヒトラーの片腕としてプロパガンダ、宣伝の魔術を駆使したナチス(ドイツ労働者党)の宣伝大臣を務めた男です。
最近、映画「ゲッベルス ヒトラーをプロデュースした男」が静かな人気のようです。
書店にも、ゲッベルス本がチラホラ見えるようになってきました。

ゲッベルス 悪の真相
ダイアマガジン ダイアプレス刊 1300円
同書は、ゲッベルスの生涯を一冊にまとめたムック本。
カラーページ入りの迫力ある一冊です。
 目次
目次序章 ナチス・ドイツとゲッベルス
第1章 ゲッベルスの抱いたコンプレックス
第2章 ナチ党の躍進とヒトラーの登場
第3章 ナチ党の総選挙とプロパガンダ
第4章 国民啓蒙・宣伝大臣ゲッベルス
第5章 第二次世界大戦とゲッベルス
第6章 ナチスの落日とゲッベルスの最後
ゲッベルス宣伝大臣は、新聞、ラジオ、映画、音楽、芸術、ポスター、デザインなどを意図的に創り出し、ドイツ国民を魅了し、ヒトラー独裁政権を演出しました。
現代で言えば、広告プロデューサー、クリエイティブディレクター、コピーライターの仕事を兼ね備えた政治家。
国民を洗脳し、ナチス党の目指す事を実現するための仕組み、仕掛けを造り上げました。
日本の戦前の「大本営発表」や「勝った、勝った」も同じ匂いがします。
治安維持法や隣組、特高警察などの仕組みを作り、日本国民を悲劇的な絶望的な戦争に巻き込んでいきます。
抵抗する者は、非国民として逮捕され、収監され、殺されました。
大衆操作(マス・マニュピレーション)の恐ろしさです。
 半島や大陸の国のマスゲームのようです。
半島や大陸の国のマスゲームのようです。オリンピックさえ、プロパガンダ、宣伝のための道具にしました。

ゲッベルスは、幼少の頃、足に障がいを持ち、これが生涯にわたるコンプレックスになったと言われています。
身長の低い小さく、痩せた男でした。
愛国心溢れる彼は、第一次世界大戦の兵役検査にも落ち落胆。
しかしながら、学業は超優秀で大学に進学、博士の学位も取得します。
文学博士・・・ドイツの浪漫文学が専門です。
が、ドイツの第一次世界大戦の敗戦のため職業につくことが出来ず、苦悩は続きます。
就職できないのはユダヤ人のせいと思い込んでいたようです。
そんな中、ナチス(ドイツ労働者党)と出会い、そしてアドルフ・ヒトラーに惹かれていきます。
最初は左派と右派でヒトラーと考えを異にしていたそうです。
演説力にも高い才能のあったゲッベルスは、ヒトラーが獄中で書いた「わが闘争」に賛同。
反ユダヤ主義、反スラブ主義、反共産主義に染まっていきます。
そして、国民啓蒙・宣伝大臣ゲッベルスが誕生することになります。
ラジオ、新聞、映画、音楽、ポスター、オリンピックなどを自らプロデュースし、ドイツ国民を戦争に巻き込んでいきます。
1945年、ナチス・ドイツの敗戦。
ゲッベルスはヒトラーに続き、ベルリン地下壕で家族とともに自死することになります。
享年48。

ゲッベルスについては、大学時代に興味を持ち、東京・神田神保町の古書店で何冊か本を買って研究していた時期があります。
ゲッベルスの存在は、自分の人生にも大きな影響をあたえました。
宣伝の力で世の中をよりよく出来るかもしれない・・・。
卒業後は、電波媒体(ラジオ、テレビ)に強い大手広告代理店に入社することになります。
今回の映画やムック本で、更にゲッベルス研究を進めることが出来たと思います。

彼の残したプロパガンダ、宣伝のテクニックは、現代の政治宣伝、広告宣伝にも大きな影響を与えていると思います。
二度あることは三度あります。
 いつまでも変わらない人間の性。
いつまでも変わらない人間の性。油断すると、体制に迎合して突っ走るリスクを抱えています。
現代では、インターネットやSNSもあり、大衆操作や政治や選挙に利用されるリスクも多々あります。
当時よりも危険な状況とも言えます。
フェイクに流されず、自ら学び、考え、行動する人間が求められていると思います。
スティーブ・ジョブさんの言葉を思い出します。
Think Different!