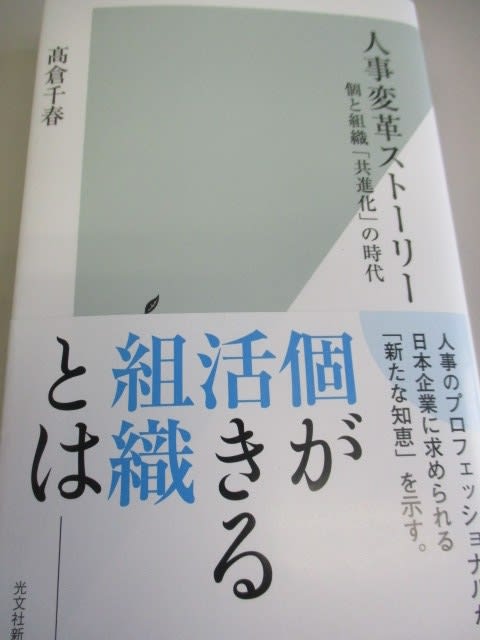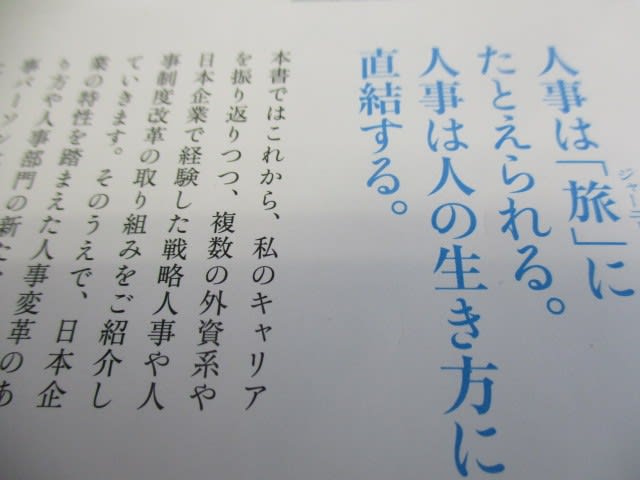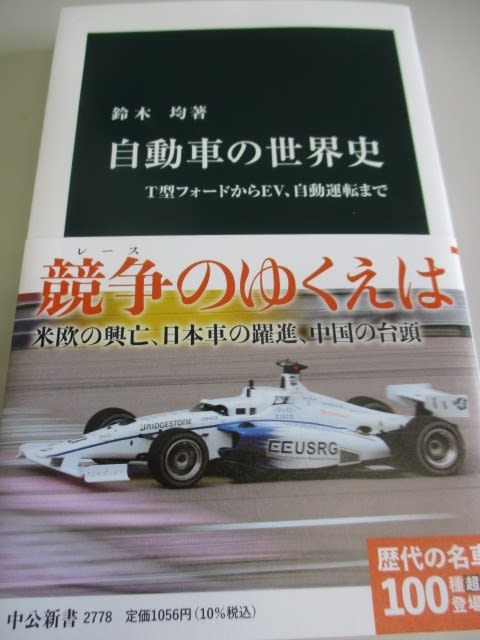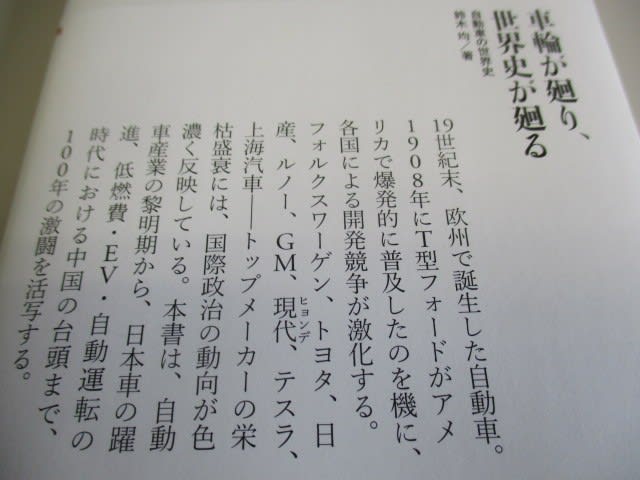外車ディーラーの営業の方が言っていました。
「この一年で欧州から輸入するクルマの運送費が爆上がりしていて困っています」
そういえば、地政学上の問題で、スエズ運河が使用できず、アフリカ喜望峰を回ってアジアへというルートになっています。
喜望峰を回ると21日間が余計にかかり、運賃は5倍に跳ね上がるとのこと。

日経ビジネス誌2024.3.11号の特集は、「物流経営の時代 陸海空クライシスを乗り切れ」。
物流、ロジスティクスというと経営の機能の中でも地味な感じがします。
でも、物流、ロジスティクスは、企業や組織の生死を決します。
歴史を見ても、ナポレオン、ナチスドイツ、旧日本軍の敗北は、ロジスティクスの軽視によるものとされています。
Contents
Part1 経営力で供給網改革 2024年問題の突破口
Part2 海の大動脈、目詰まり 北海道でパスタ不足
Part3 「運送拒否」に現実味 待遇改善、荷主の責任
Part4 物流危機、経営の出番 拠点再編に共同配送
国内の運送業界では、トラックドライバーの残業規制で、2024年で14%、2030年で34%のトラック輸送力が不足すると予測されています。
今までは、トラック運転手の長時間労働で支えられていた国内物流が、年間時間外労働960時間までという規制によって機能しなくなります。
6年後には、3分の1の荷物が運ばれなくなる・・・国内で混乱が起こると思います。
物流業界の人出不足は、本当に深刻になると思います。
ロボットやドローンなどりハイテクを入れていかなければ、経済が回らなくなります。
さらには、地政学の中で、大動脈であるスエズ運河、パナマ運河が通行できなくなるという国際的な問題も発生しています。
イエメン沖や台湾海峡についても、リスク大です。

これからの時代、物流、ロジスティクスに強い経営者が求められてくると思います。
アップルCEOのテッム・クックさん、ゼロックスの元CEOのウルスラ・バーンズさんなどは物流部門で実績を上げた経営者です。
最近は、情報系のCIO、財務系のCFOが脚光を浴びていますが、これからはCLO(チーフ・ロジスティクス・オフィサー/物流担当役員)の存在が重要になってくると思います。
物流、ロジスティクスを学べる大学や大学院は少数派・・・これからの専門性、キャリアを切り拓くチャンスです。