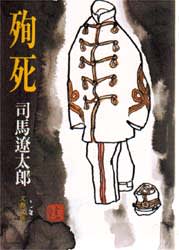イタリアの優勝で幕を閉じたワールドカップ。やはり鉄壁の守備は健在で、“歴史のあるチーム”の強さが印象的でした。
先にご紹介した、『 君主論 』のマキャベリに関する著作や、全15巻の『ローマ人の物語』 など、魅力的な著作がたくさんある、塩野七生氏もサッカーファンだとは知りませんでした。本書は通常の氏の本とは、かなり趣が異なるつくりです。
私も知らずにネットで購入したのですが、B5サイズの大型です。美しい風景、迫力のある歴代の英雄などの写真などがふんだんに使われ、すぐにでもローマに行きたくなるような魅力的な本です。人によっては、ローマ人の物語15巻分をぐっと凝縮した本、と形容しています。
古代ギリシアの模倣といわれたローマ帝国が、模倣だけで1000年も続くのかという、10代のころの疑問を、半世紀たった今でも追い続けていると、塩野氏は語っています。
なぜローマ、特にローマの男たちにそれほど惹かれるのか、それを思うままに語った本です。歴史書というより、歴史やローマの魅力をわかりやすく解説した本です。私のような歴史を知らない人間にはうってつけの入門書ではないでしょうか。
そしてローマ史から見た今の日本を語ります。偉大な作家や歴史家が語る現在というのはいつも洞察に富み、新しい視点を与えてくれます。歴史から学べとよく言われますが、本書では随所にそういうエッセー風の記述があり、本書の魅力の一つです。
最後には、ギリシア・ローマの英雄たちで、サッカーのドリームチームまで作って“遊んで”います。イタリアにいれば嫌でもサッカー通になるのだそうです。
塩野監督の攻撃型チームのツートップは、破壊力抜群のハンニバルとアレクサンダー大王、守備方チームでは司令塔にカエサル、ツートップはアントニウスとダキアだそうです(笑)。
旅行ガイドブックのような構成で、勉強にもなり、大変楽しませてくれる一冊です。
http://tokkun.net/jump.htm
 | 痛快!ローマ学集英社インターナショナル詳 細 |
『痛快!ローマ学』塩野七生
集英社インターナショナル:219P:1785円
■■ 記事にご賛同いただけましたら、ご協力ください ■■
 5位まで来ましたが、さすがに、ここからは一歩一歩です。
5位まで来ましたが、さすがに、ここからは一歩一歩です。 静的リンクって?
静的リンクって?読書小説書籍・雑誌ニュースbookおすすめサイト家族旅行趣味ローマイタリアドイツフランス