脳外傷や脳血管障害の後遺症としての高次脳機能障害(記憶障害、注意障害、遂行機能障害)に対するリハビリテーションとして間違いようの無い構造化された(シンプルでわかりやすい)環境をつくる、明確な手順を決めるというのがある。カレンダーを貼って予定を明記したり、手順を張り紙で明示したり、記憶障害の人にメモリーノート(手帳)書いて確認する習慣を定着させたり、日常生活に最低限必要な一連の行動を手続き記憶として覚えこませたりする(行動強化)。就職や復職に当たっては専任のジョブコーチをつけ、その人のできること、できないこと、得意なこと、苦手なことを把握した上で、できる仕事を職場の中で探したり、職場と交渉したりする。
そういうことをやっているのに、そもそもにわれわれの職場はこんなに構造化されていないんだろう。手順もきっちり標準化されておらず分かりにくいのか。それぞれの予定もわかりにくいのか?何故こんなにいろんなことを同時にやらなくてはいけないようになっているのか?担当者がいないとどうして何もかもわからないような状態なのか?各人の能力や役割に応じた仕事の分配になっていないのか?人を育てようとせず、人を人数あわせのコマのようにしかかんがえていないのか?何度言ってもクーラーは壊れたままで汗をだらだらかきながら仕事をしなくてはならないのか?危険で気が散る環境なのか?
あちこちバリアだらけでまったくユニバーサルデザインからは程遠い。安全やプライバシーへの配慮が無い。「見える化」「カイゼン」などの工業のQC,TQMなどの手法、コーチングなどのビジネスの手法を病院で上からも下からもどうしてもっと積極的に導入しないのか?といい加減、イライラしてきた。これまで特定の個人の能力だけに頼ってカイゼンされぬまま仕事をしてきたつけが噴出してきている。⇒ナビゲート
まずは5Sからだろう。
1.整理 2.整頓 3.清掃 4.清潔 5.躾(習慣化)
鍵は Simplification と Standardization にあると思われる。まずはマニュアル作りと改善から・・・。
そういうことをやっているのに、そもそもにわれわれの職場はこんなに構造化されていないんだろう。手順もきっちり標準化されておらず分かりにくいのか。それぞれの予定もわかりにくいのか?何故こんなにいろんなことを同時にやらなくてはいけないようになっているのか?担当者がいないとどうして何もかもわからないような状態なのか?各人の能力や役割に応じた仕事の分配になっていないのか?人を育てようとせず、人を人数あわせのコマのようにしかかんがえていないのか?何度言ってもクーラーは壊れたままで汗をだらだらかきながら仕事をしなくてはならないのか?危険で気が散る環境なのか?
あちこちバリアだらけでまったくユニバーサルデザインからは程遠い。安全やプライバシーへの配慮が無い。「見える化」「カイゼン」などの工業のQC,TQMなどの手法、コーチングなどのビジネスの手法を病院で上からも下からもどうしてもっと積極的に導入しないのか?といい加減、イライラしてきた。これまで特定の個人の能力だけに頼ってカイゼンされぬまま仕事をしてきたつけが噴出してきている。⇒ナビゲート
まずは5Sからだろう。
1.整理 2.整頓 3.清掃 4.清潔 5.躾(習慣化)
鍵は Simplification と Standardization にあると思われる。まずはマニュアル作りと改善から・・・。










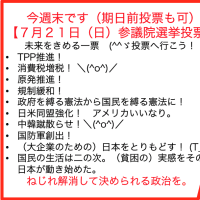
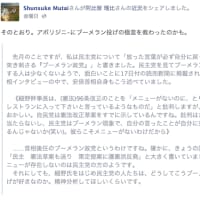




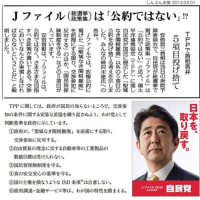

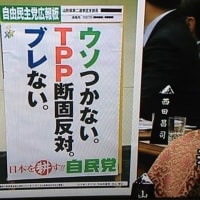

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます