壊れゆくブレイン(18)
「この前のことだけど、結果はどうなったの?」ぼくは、何日か経ってまた若者の日常にあこがれ、まゆみに訊いてみる。
「せっかち」
「それは、違うだろ。ぼくらより、流れている時間は君らのほうが早いと思うよ」
「きちんと彼女に伝えた。もう、それでおしまい。あとは本人に気があれば、直接、連絡するって」
「それで?」
「だから、それで終わり」
「うまく行きそう?」
「さあ、悩んでたけど、そういうのって自分が決めるものでしょう」
「そうだね」
「人を介するのもどうかと思うよ。先ずは、会って自分から謝るとか・・・」
「それが出来ないし、反省しているから苦労しているんだろう、まもるも」
「でもね、誰かの言葉を通すと、話が逆に混乱しない?」まゆみは、正論を語る。でも、それも大雑把にいえば正しい意見だった。
「まゆみちゃんは、どうなの? 前に彼氏がいたとか言ってたね」
「終わりは終わり。わたしは切り替えが早いの」
「若いときに、誰かにおぼれるほど好意をもった経験って、何にも代え難いほどの思い出になるよ」
「多分、そうだろうね。でも、苦しむでしょう」
「ここに見本がいる」ぼくは、自分の指で自分の胸を突いた。「でも、それすらも愛着のある思い出」
「わたしも、いつかする」
「そして、泣いたり喚いたりする」
「するタイプに思える?」彼女はちょっと不機嫌な顔を作る。でも、自分がこれからどう振舞うかなどは、根本的にしらないものだ。
ぼくらはこうして広美の勉強の面倒を終えた彼女をおくる道中に、さまざまなことを話した。過去のこともあれば、現在のこともあった。これから訪れるであろう未来のことも話した。彼女は両親のことを話題として提供し、ぼくは妻との生活を話した。そこに、裕紀が表れることは稀だったが、ぼくのこころにはいつもその存在があった。消すことのできない記憶。たまには甘美な思い出にもなり、ときには痛みを伴うかさぶたのようなものにもなった。
「じゃあ、また水曜」と言って、次回の予約を確認するようにぼくはある地点に来るとまゆみを見送る。それから、またひとりでいま来た道を歩く。その間にテーブルの上は片付いている。娘は風呂にはいったり、先程まで習っていた勉強を復讐したりした。雪代は会社の経費をノートにつけたりしている。ぼくは、そのことを思いながら歩いている。自分には、予定通りといえないまでも家族ができ、戻るところがあった。
「ただいま」
扉を開けると、コーヒーの匂いがした。それは雪代がやることが待っているという合図でもあった。
「コーヒー、入れたけど飲む?」
「うん。なにかの計算?」
「仕入れたり、支払ったりの点検。いつものこと」
「お疲れさま」と言って、ぼくは彼女をひとりにするため、コーヒーのカップを持ち、自分の部屋に消えた。ぼくはテーブルのライトを着け、引き出しから日記を取り出した。それは、ぼくのものではない。裕紀が書き残したものだ。ぼくは最初のうちは見る気もまったくしなかった。だが、自分は安定した生活を手に入れ、あの日々を振り返る余裕がでてきた。そして、彼女がどのような気持ちで毎日を送っていたのか、もちろん、毎日の正確な記録が残っているわけでもないが、大体は把握できた。それを数ページ毎に読み返し、添削するように、ぼくは別のノートにその感想をつづった。ある気持ちに対してのリアクションがあり、彼女に出せない手紙をぼくは書いているようなものだった。これが、雪代の裏切りでない証拠に、ぼくはこうして自分というものが、その日々の追憶を通してまた生きているということを説明し納得してもらっていた。読みたければ、君も読んでいいよとも雪代に言った。彼女が、どうしているのか分からない。もう死んでしまっている女性に嫉妬などもたない。もともと、あまり嫉妬とかの感情を有していない彼女だった。
それを20分ほどして、ぼくは止めた。コーヒーも空になり、リビングに戻った。雪代も自分のすることを終えたようだった。ぼくらは、向かい合って座り、生活のことを語り、仕事の話をして、娘のことを相談した。
「まゆみちゃんと、こそこそ、何を秘密のように話していたの?」
「男同士の秘密だったけど、もう、いいよ。まもる君は前の女性に未練をもっていた」
「それが、まゆみちゃん?」
「違う。だけど、まゆみちゃんの友だち」
「縒りを戻したいとか?」
「その通り」
「それを手伝ってもらっている・・・うまく、いったの?」
「あとは、本人同士だって。意図だけは伝えたから、と言われた」
「わたしたちも、むかし、別れた」
「ぼくは、東京に行く前に、映画館で君と島本さんの姿を見た。とても、傷ついたよ」
「あなたも女性といたけど」
「あれは、何でもない同僚。引継ぎのお礼。そういえば、あいつ、どうしてるんだろう?」
ぼくは、何年も前のことを昨日のように思い出している。自分の思い出のストックが増え、たまにその重みで頭の重心が耐えられなくなりそうになる。ぼくはシャワーを流し頭を洗い外的な要因からそれを拭おうとしたが、もちろんそのようなことは無理だった。
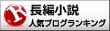
「この前のことだけど、結果はどうなったの?」ぼくは、何日か経ってまた若者の日常にあこがれ、まゆみに訊いてみる。
「せっかち」
「それは、違うだろ。ぼくらより、流れている時間は君らのほうが早いと思うよ」
「きちんと彼女に伝えた。もう、それでおしまい。あとは本人に気があれば、直接、連絡するって」
「それで?」
「だから、それで終わり」
「うまく行きそう?」
「さあ、悩んでたけど、そういうのって自分が決めるものでしょう」
「そうだね」
「人を介するのもどうかと思うよ。先ずは、会って自分から謝るとか・・・」
「それが出来ないし、反省しているから苦労しているんだろう、まもるも」
「でもね、誰かの言葉を通すと、話が逆に混乱しない?」まゆみは、正論を語る。でも、それも大雑把にいえば正しい意見だった。
「まゆみちゃんは、どうなの? 前に彼氏がいたとか言ってたね」
「終わりは終わり。わたしは切り替えが早いの」
「若いときに、誰かにおぼれるほど好意をもった経験って、何にも代え難いほどの思い出になるよ」
「多分、そうだろうね。でも、苦しむでしょう」
「ここに見本がいる」ぼくは、自分の指で自分の胸を突いた。「でも、それすらも愛着のある思い出」
「わたしも、いつかする」
「そして、泣いたり喚いたりする」
「するタイプに思える?」彼女はちょっと不機嫌な顔を作る。でも、自分がこれからどう振舞うかなどは、根本的にしらないものだ。
ぼくらはこうして広美の勉強の面倒を終えた彼女をおくる道中に、さまざまなことを話した。過去のこともあれば、現在のこともあった。これから訪れるであろう未来のことも話した。彼女は両親のことを話題として提供し、ぼくは妻との生活を話した。そこに、裕紀が表れることは稀だったが、ぼくのこころにはいつもその存在があった。消すことのできない記憶。たまには甘美な思い出にもなり、ときには痛みを伴うかさぶたのようなものにもなった。
「じゃあ、また水曜」と言って、次回の予約を確認するようにぼくはある地点に来るとまゆみを見送る。それから、またひとりでいま来た道を歩く。その間にテーブルの上は片付いている。娘は風呂にはいったり、先程まで習っていた勉強を復讐したりした。雪代は会社の経費をノートにつけたりしている。ぼくは、そのことを思いながら歩いている。自分には、予定通りといえないまでも家族ができ、戻るところがあった。
「ただいま」
扉を開けると、コーヒーの匂いがした。それは雪代がやることが待っているという合図でもあった。
「コーヒー、入れたけど飲む?」
「うん。なにかの計算?」
「仕入れたり、支払ったりの点検。いつものこと」
「お疲れさま」と言って、ぼくは彼女をひとりにするため、コーヒーのカップを持ち、自分の部屋に消えた。ぼくはテーブルのライトを着け、引き出しから日記を取り出した。それは、ぼくのものではない。裕紀が書き残したものだ。ぼくは最初のうちは見る気もまったくしなかった。だが、自分は安定した生活を手に入れ、あの日々を振り返る余裕がでてきた。そして、彼女がどのような気持ちで毎日を送っていたのか、もちろん、毎日の正確な記録が残っているわけでもないが、大体は把握できた。それを数ページ毎に読み返し、添削するように、ぼくは別のノートにその感想をつづった。ある気持ちに対してのリアクションがあり、彼女に出せない手紙をぼくは書いているようなものだった。これが、雪代の裏切りでない証拠に、ぼくはこうして自分というものが、その日々の追憶を通してまた生きているということを説明し納得してもらっていた。読みたければ、君も読んでいいよとも雪代に言った。彼女が、どうしているのか分からない。もう死んでしまっている女性に嫉妬などもたない。もともと、あまり嫉妬とかの感情を有していない彼女だった。
それを20分ほどして、ぼくは止めた。コーヒーも空になり、リビングに戻った。雪代も自分のすることを終えたようだった。ぼくらは、向かい合って座り、生活のことを語り、仕事の話をして、娘のことを相談した。
「まゆみちゃんと、こそこそ、何を秘密のように話していたの?」
「男同士の秘密だったけど、もう、いいよ。まもる君は前の女性に未練をもっていた」
「それが、まゆみちゃん?」
「違う。だけど、まゆみちゃんの友だち」
「縒りを戻したいとか?」
「その通り」
「それを手伝ってもらっている・・・うまく、いったの?」
「あとは、本人同士だって。意図だけは伝えたから、と言われた」
「わたしたちも、むかし、別れた」
「ぼくは、東京に行く前に、映画館で君と島本さんの姿を見た。とても、傷ついたよ」
「あなたも女性といたけど」
「あれは、何でもない同僚。引継ぎのお礼。そういえば、あいつ、どうしてるんだろう?」
ぼくは、何年も前のことを昨日のように思い出している。自分の思い出のストックが増え、たまにその重みで頭の重心が耐えられなくなりそうになる。ぼくはシャワーを流し頭を洗い外的な要因からそれを拭おうとしたが、もちろんそのようなことは無理だった。












