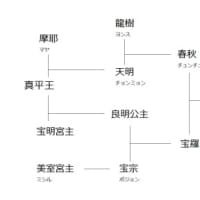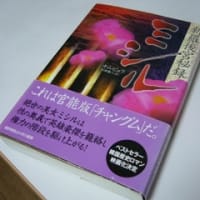暦(こよみ)の話が出たついでに。
まだカレンダーというものが無かった時代に、人々がどのようにして季節の推移を計っていたかというと、その基準(ものさし)となるのは間違いなく太陽と月である。
お月様が30日ごと(正確には29.5日ごと)に丸くなったり欠けたりするというのはすぐわかることで、だからその周期をひとつの単位としたのが太陰暦である。一月(ひとつき)の「月」はやはりmoonなのであってこれはわかりやすい。
一年という単位については太陽である。もっとも昼の長い日(夏至)と短い日(冬至)をどうやって認識するかが一番重要なのだが、その方法としては夏至・冬至の日に太陽が昇る(あるいは沈む)方向に目印があればよい。
たとえば、付近の山々のうちで山頂がとがっているなどわかりやすいものを選んで、夏至や冬至の日にその山頂に太陽が昇る(あるいは沈む)観測地点を見つければよいのである。
こういったことはすでに縄文時代から行われていることで、縄文時代の遺跡・遺構を調べてみると近くに特徴的な山があり、夏至の日や冬至の日の観測地点であることが多い。
東京都内にストーンサークルがあるということを知る人はあまりいないのではないかと思うが、かなり小規模のものながら実在する。
田端環状積石遺構
小田急京王相模原線の多摩境駅から歩いてわずかのところ。写真は2004年当時のものだが、現在は埋め戻して公園として整備されているようだ。
そしてこの場所からは冬至の日、丹沢山系の中でもその容姿が一番目立つ蛭が岳の山頂に沈む夕陽が観測できるのである。
田端環状積石遺構からの日没
まだカレンダーというものが無かった時代に、人々がどのようにして季節の推移を計っていたかというと、その基準(ものさし)となるのは間違いなく太陽と月である。
お月様が30日ごと(正確には29.5日ごと)に丸くなったり欠けたりするというのはすぐわかることで、だからその周期をひとつの単位としたのが太陰暦である。一月(ひとつき)の「月」はやはりmoonなのであってこれはわかりやすい。
一年という単位については太陽である。もっとも昼の長い日(夏至)と短い日(冬至)をどうやって認識するかが一番重要なのだが、その方法としては夏至・冬至の日に太陽が昇る(あるいは沈む)方向に目印があればよい。
たとえば、付近の山々のうちで山頂がとがっているなどわかりやすいものを選んで、夏至や冬至の日にその山頂に太陽が昇る(あるいは沈む)観測地点を見つければよいのである。
こういったことはすでに縄文時代から行われていることで、縄文時代の遺跡・遺構を調べてみると近くに特徴的な山があり、夏至の日や冬至の日の観測地点であることが多い。
東京都内にストーンサークルがあるということを知る人はあまりいないのではないかと思うが、かなり小規模のものながら実在する。
田端環状積石遺構
小田急京王相模原線の多摩境駅から歩いてわずかのところ。写真は2004年当時のものだが、現在は埋め戻して公園として整備されているようだ。
そしてこの場所からは冬至の日、丹沢山系の中でもその容姿が一番目立つ蛭が岳の山頂に沈む夕陽が観測できるのである。
田端環状積石遺構からの日没