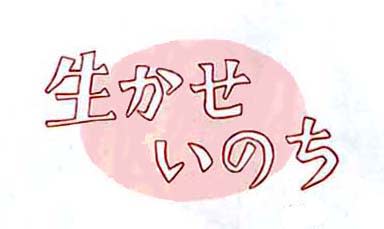▽筆者は大分県中津市の 弘法寺 住職 吉武 隆善
皆さんは高野山へお参りされたことがありますか。高野山は宗旨、宗派にかかわらず誰もがお参りできる、とてもすばらしいところです。私は先日、駐在布教のため久しぶりに高野山へのぼらせていただきました。駐在布教とは、大師教会において十善の戒をお授けすることと、金剛峯寺の新別殿において、お参りさ
れた方に本山を代表してご挨拶させていただきお話をさせていただくことです。 そこでいつも感じるのは、高野山にお参りされる方々が種々様々であることです。年齢も赤ちゃんから高齢の方までおられますし、日本のみならず外国からもたくさんの方々がお参りされます。
私は金剛峯寺にお参りされた若い男の子や女の子たちに、どうしてお参りに来たのか訪ねてみました。答えは決まって「ただ何となく」です。私が「弘法大師って知ってる?」と開くと、「教科書で見たことがあるけど、あまりよくは知らない」と言います。しかし、そのあと必ず言うのが、「知らないけど何か高野山っていいところやね。来てよかった」という言葉です。そこで私は、「こうしてお参りできるのは、高野山やお大師さまにご縁があったということよ。そのご縁を大切にしてね」と言います。
高野山は今から約千二百年前の八一六年、弘法大師によって開かれたところです。最初お大師さまは京都の東寺にいらっしゃり、たくさんのお弟子さんたちを見ておられました。しかし、京都は多くの人で賑わい、弟子たちがついきれいな女の人に気がいってしまい修行に専念できないので、どこか修行に適した場所はないかと考えたのでした。そしてお大師さまは、昔登ったことがある山のことを思い出されたのです。その山は深山幽谷の地で、その形はまるで仏さまの座布団のような蓮の形をしています。そこに国家と修行者のための道場を開こすと思いました。そして何より、お大師さまは高野山をご入定の地としてお選びになったのです。
お大師さまはご入定なされる前に、このようなお言葉を残されています。「虚空尽き、衆生尽き、捏磐尽きなば、我が願いも尽きなん」ー1この世がある限り、この世で迷い苦しむ人がいる限り、私は最後の一人まで救いますよ、とおっしゃっておられます。まさに気の遠くなるような月日です。
またお大師さまは、ご入定される前にすべてのお弟子さまをお集めになられ、このようなお言葉も述べられています。「これからは、このようにみんなと会うこともなくなるでしょう。そのときには絵に描かれた私の姿、石や木に刻まれた姿を私だと思って、私の名前を呼んでください。そのときには体を幾千万にでも分けてその方の傍に行き、その方たちをお救いしますよ」
何十人、救いを求止の身を幾イお救いすり慈悲のお心でしょう。そんなお大師さまが今もいらっしゃる高野山だからこそ、みんなは何かしら引き付けられ、ご縁をもらってお参りできるのです。
参与770001-4228(本多碩峯)