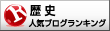水戸黄門では、8時40分くらいになると、角さん、助さんが敵?をバッタバッタと斬り倒している。
あれだけの敵を相手にしては、峰打ちも難しそうだし、一体彼らは一週間に何人殺すのだろう?
しかも、相手は、「それ行け!」と悪代官に命令されただけの罪のない侍たちである。
時代劇のチャンバラが架空であるということはよく言われている。
日本刀では、そんなに何人も斬れないとか、日本刀の性能面から見て言われる。
ハードはともかく、江戸時代の武士の意識はどうだったのだろう?
第二次世界大戦中、日本軍の精神的スローガンにされてしまった「葉隠」の冒頭の一説、
「武士道とは死ぬことと見つけたり」
は、あまりにも有名だ。
「葉隠」は江戸中期(享保元年頃)、肥前佐賀藩士山本常朝が著した書である。
この一説を読み、
「やはり、武士というのは主君や、理あるところには命をなげうって殉職も厭わない人たちだったのだろう」
と思うのは早計かも知れない。
戦国時代や乱世の余韻の治まりきらなかった江戸初期はともかく、江戸時代も中期以降になってくると、泰平の空気が武士にも伝わり、武士は戦闘員としての性格を弱めていく。
さきほどの「葉隠」の中にも、敵に向かったとき、目の前がまっくらになるが、少し心をしずめるとおぼろ月夜くらいの明るさをとりもどす、
ということを述べている箇所がある。
池波正太郎も、自著の中で曾祖母から聞いた話をユーモアを交えて紹介している。
時代劇の剣戟シーンになると、
「ちがう。ちがう」
つぶやきながら、しきりにくびを振った。
「塚原朴伝のような名人ならともかく、ふつうの侍の切り合いは、あんなものじゃない。よくおぼえておおき」
曾祖母は、松平家に奉公をしていたとき、実際に、侍の切り合いを見ている。
維新戦争で、上野の山に彰義隊がたてこもり、新政府軍がこれを攻めたとき、
「私たちは、みんな長刀を掻い込み、鉢巻をしめて、殿さまをおまもりしたのだよ」
と、曾祖母は、カビが生えた梅干みたいな顔に血をのぼらせて、
「そのとき、彰義隊が一人、御屋敷の御庭に逃げ込んで来た。官軍が一人、これを追いかけて来てね、御庭の築山のところで、一騎打ちがはじまった」
それを、目撃したのである。
二人は刀を構え、長い間、睨みあったまま、動かなくなってしまったという。
それは気が遠くなるほどに長い、長い時間だったそうな。
そのうちに、二人が、ちょっと動いたとおもったら、官軍のほうが、
「大きな口を開けたかとおもったら・・・・」
うつぶせに倒れてしまった。
曾祖母のはなし半分にしても、おそらく、
そんなものだったろう。
以下②へ・・・
葉隠 教育社 松永義弘訳
江戸切絵図散歩 池波正太郎 新潮社
あれだけの敵を相手にしては、峰打ちも難しそうだし、一体彼らは一週間に何人殺すのだろう?
しかも、相手は、「それ行け!」と悪代官に命令されただけの罪のない侍たちである。
時代劇のチャンバラが架空であるということはよく言われている。
日本刀では、そんなに何人も斬れないとか、日本刀の性能面から見て言われる。
ハードはともかく、江戸時代の武士の意識はどうだったのだろう?
第二次世界大戦中、日本軍の精神的スローガンにされてしまった「葉隠」の冒頭の一説、
「武士道とは死ぬことと見つけたり」
は、あまりにも有名だ。
「葉隠」は江戸中期(享保元年頃)、肥前佐賀藩士山本常朝が著した書である。
この一説を読み、
「やはり、武士というのは主君や、理あるところには命をなげうって殉職も厭わない人たちだったのだろう」
と思うのは早計かも知れない。
戦国時代や乱世の余韻の治まりきらなかった江戸初期はともかく、江戸時代も中期以降になってくると、泰平の空気が武士にも伝わり、武士は戦闘員としての性格を弱めていく。
さきほどの「葉隠」の中にも、敵に向かったとき、目の前がまっくらになるが、少し心をしずめるとおぼろ月夜くらいの明るさをとりもどす、
ということを述べている箇所がある。
池波正太郎も、自著の中で曾祖母から聞いた話をユーモアを交えて紹介している。
時代劇の剣戟シーンになると、
「ちがう。ちがう」
つぶやきながら、しきりにくびを振った。
「塚原朴伝のような名人ならともかく、ふつうの侍の切り合いは、あんなものじゃない。よくおぼえておおき」
曾祖母は、松平家に奉公をしていたとき、実際に、侍の切り合いを見ている。
維新戦争で、上野の山に彰義隊がたてこもり、新政府軍がこれを攻めたとき、
「私たちは、みんな長刀を掻い込み、鉢巻をしめて、殿さまをおまもりしたのだよ」
と、曾祖母は、カビが生えた梅干みたいな顔に血をのぼらせて、
「そのとき、彰義隊が一人、御屋敷の御庭に逃げ込んで来た。官軍が一人、これを追いかけて来てね、御庭の築山のところで、一騎打ちがはじまった」
それを、目撃したのである。
二人は刀を構え、長い間、睨みあったまま、動かなくなってしまったという。
それは気が遠くなるほどに長い、長い時間だったそうな。
そのうちに、二人が、ちょっと動いたとおもったら、官軍のほうが、
「大きな口を開けたかとおもったら・・・・」
うつぶせに倒れてしまった。
曾祖母のはなし半分にしても、おそらく、
そんなものだったろう。
以下②へ・・・
葉隠 教育社 松永義弘訳
江戸切絵図散歩 池波正太郎 新潮社