先週、両国から吉原まで歩いてみた。
両国から浅草までは川沿いを歩き、浅草寺を通って待乳山聖天宮を経て、山谷堀、日本堤、吉原大門という道程である。
歩いてみて印象的だったのは浅草寺の賑わい。
外国の人を含め、進むのも困難なくらいの混雑振りであった。
隅田川沿いは歩道が整備され、歩きやすい。
ちらほらと観光目的で歩いている人も見かける。
両国から浅草にかけての見所としては、国技館、安田庭園、首尾の松、といったところ。
首尾の松は隅田川沿いに張り出す見事な枝振りで、江戸時代、舟通いの客にとってもっとも目立つ存在であった。吉原の帰りに客が「首尾はどうだった」と確認を行う場所とも言われたのが、首尾の松の語源とされる。
実際に見に行くと、隅田川からは少しだけ離れた場所にある。この位置だと、安藤広重の絵のように隅田川まで張り出すのは難しいと思える。場所が移ったのだろか。
それに、いかにも小振りである。
現地にあった説明文を読むと、この松は昭和37年に植えた7代目だそうだ。
初代は、江戸初期に植えられたが、安永年間に風害で倒れ、代わりに植えられた二代目も安政年間に枯れたとされる。
松が百年の間にどれだけ大きくなるのか知らないが、少なくとも、安政年間には目印になるほど大きな松の木はなかったことになる。
安政以後はたびたび木は枯れ、明治には「湖畔の蒼松」に改名したというが、重厚すぎるネーミングである。
「首尾の松」の由来にも3種類あるらしいが、吉原通いの客が首尾を確認したという案が一番しっくり来る。
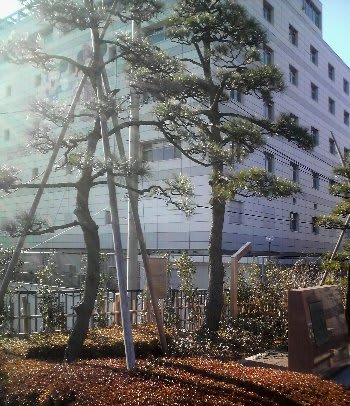
↓ よろしかったら、クリックお願いいたします。

両国から浅草までは川沿いを歩き、浅草寺を通って待乳山聖天宮を経て、山谷堀、日本堤、吉原大門という道程である。
歩いてみて印象的だったのは浅草寺の賑わい。
外国の人を含め、進むのも困難なくらいの混雑振りであった。
隅田川沿いは歩道が整備され、歩きやすい。
ちらほらと観光目的で歩いている人も見かける。
両国から浅草にかけての見所としては、国技館、安田庭園、首尾の松、といったところ。
首尾の松は隅田川沿いに張り出す見事な枝振りで、江戸時代、舟通いの客にとってもっとも目立つ存在であった。吉原の帰りに客が「首尾はどうだった」と確認を行う場所とも言われたのが、首尾の松の語源とされる。
実際に見に行くと、隅田川からは少しだけ離れた場所にある。この位置だと、安藤広重の絵のように隅田川まで張り出すのは難しいと思える。場所が移ったのだろか。
それに、いかにも小振りである。
現地にあった説明文を読むと、この松は昭和37年に植えた7代目だそうだ。
初代は、江戸初期に植えられたが、安永年間に風害で倒れ、代わりに植えられた二代目も安政年間に枯れたとされる。
松が百年の間にどれだけ大きくなるのか知らないが、少なくとも、安政年間には目印になるほど大きな松の木はなかったことになる。
安政以後はたびたび木は枯れ、明治には「湖畔の蒼松」に改名したというが、重厚すぎるネーミングである。
「首尾の松」の由来にも3種類あるらしいが、吉原通いの客が首尾を確認したという案が一番しっくり来る。
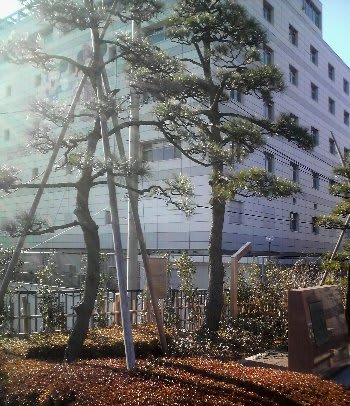
↓ よろしかったら、クリックお願いいたします。



















 洲崎神社
洲崎神社