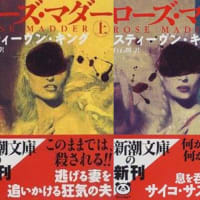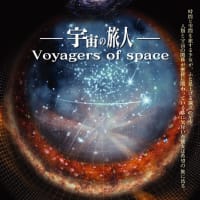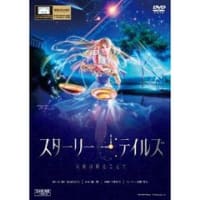著者:吉村昭 新潮文庫刊
初版刊行:昭和61年12月20日
49刷刊:平成21年 6月 5日(入手版)
前編では。
本書の主人公である、佐久間清太郎の人生を眺めることで。
人が、その人の一度きりの人生を生きるということが、どのような
意味を持つものなのか、ということを考えさせられる書である、
という、いわば本書の縦軸に関する感想を述べた。
この、後編では。
第二次世界大戦をはさんだ、日本の監獄史という横軸を俯瞰しながら
本書を紐解いていくこととしたい。
驚愕の事実が。
そこには、あった。
あの、日本中が食うや食わずやの状況に喘いでいた時期。
さぞかし、刑務所における囚人の処遇も悪かったのだろうと思い込んで
いたのであるが。
実際には、囚人には当時の平均的な日本人よりも、よほど良質なレベルの
食事が配給されていたらしい。
それは。
日々を監獄の中で暮らす囚人達にとって、喜びといえば食事くらいしか無く、
その品質を下げることは暴動等を引き起こす呼び水に、容易になり得たと
いうことが、主要因らしい。
もちろん、それも状況により変化はある。
実際、戦争末期には栄養不足により、全国の刑務所で死亡率が急上昇して
いったという記載もあるが。
戦前は、規則正しい生活と十全な食事がもたらした恩恵のため、死亡率は
むしろ市井の住民よりも刑務所内のほうが低かったようである。
それが。
開戦と同時に刑務所内の囚人の死亡率は急上昇し。
ついには、一般国民と比べて2倍弱にまで高まったというのであるから
尋常ではない。
しかも、それは。
「米、麦を主とした主食の摂取量が一般国民の二倍以上」という刑務所
において起こっている事態なのである。
如何に、食事というものがバランスよく様々な栄養素を摂取する必要が
あるか、よく分かるというものである。
それでも。
少なくとも、刑務所内に農場を開墾することができた網走刑務所などは。
相当にレベルの高い食事を、最後まで提供できていたようである。
そして。
刑務所内の農場で取れた生産物は、基本的には全て囚人に割り当てられる
ものと決まっていた。
その結果。
網走刑務所においては、恐るべき逆転が生じることとなる。
つまり。
看守に代表される一般国民よりも、囚人の方がはるかに良質の食事を摂取
しているという事態が生じていたのである。
この事態を前に。
看守に、やる気を出せという方が、余程酷な話ではないだろうか。
むしろ。
その規律を最後まで守り通した、刑務所内の刑務ラインの指揮系統の
統率の素晴らしさに、僕は驚嘆せざるを得ない。
普通。
そうなれば。
看守の立場を利用して、食材を横流しし。
それで一儲けしようとまで行かなくとも、本人や家族の糊口を凌ぐ術と
しようと考える方が、余程自然ではないか。
何といっても。
収監されているのは、罪人なのである。
それに比べて、自分たちはお国の役人なのである。
その役人が、家族ぐるみでひもじい思いをしているのに。
その統制化に置かれている罪人たる囚人達が、のうのうとご馳走を食べて
いることは。
とりわけ、老親や乳飲み子、病人等を家族に抱えた看守にとっては、
耐え難いことだったのは、想像に難くない。
そのような、状況下にあっても。
殆どの彼らは。
その職責に殉じ、粛々と職務を遂行していった。
何よりも、そのことに。
素直に僕は驚嘆し。尊敬の念を抱いてしまう。
もちろん。
中には、様々な不正もあったのかも知れない。
それでも、少なくとも、あの綿密な調査でもって知られる吉村氏が
調べた限りにおいて、そうした事実が掴めなかったということは。
しかも、それが。
正規の職員による一部の能吏に限定された訳でもないのだ。
末期には、人手不足から様々なレベルの職員が雇用されたという。
それでなくとも、壮健な年代層は徴兵されていっている状況だ。
その中で、残っていた人々も。
軍需工場に勤務すれば、食料の配給の面でも優遇されるのだ。
にも、関わらず。
看守職には、そうした特典も無い。
しかも、相手は荒くれた囚人達である。
そうした状況下で、どうやって彼らの矜持を維持し、統率することが
出来たのか。
吉村氏は、例によってその乾いた筆致で、淡々と歴史を追っていく。
そこには、劇的なドラマがある訳でも無く。
ただ。
看守という職責に、その身を殉じていった男たちの物語のごく一部が
語られるのみである。
確かに、佐久間に対する処遇には、厳し過ぎる側面も多々あった。
逃亡を恐れるあまり、後ろ手に回して嵌められた手錠等が、その最たる
ものである。
その手錠をされている間。
手も使えずに、佐久間は更に顔を突っ込ませ、犬のように食事をする
ことを、余儀なくされたという。
だが。
そうした処遇も、あの時代の状況下においては、仕方なかった側面も
あったのだろう。
何せ、佐久間に脱走されることは。
看守をはじめとする、関連するライン全てに叱責が及ぶことでも有り。
ただでさえ困窮する生活に、更に拍車をかける結果ともなったのだから。
それでも。
そのような状況下において。
あるものは、厳しく。
また、あるものは、人道的に。
佐久間に接していった。
その、どちらも。
職務に対する矜持を、胸に掲げて。
そのことが。
そうした時代が存在したことが。
僕は、無常に嬉しいのだ。
翻って、現代。
そこまでの誇りを胸に、自分は仕事に従事しているか?
苦い、問いだ。
(この稿、了)
初版刊行:昭和61年12月20日
49刷刊:平成21年 6月 5日(入手版)
前編では。
本書の主人公である、佐久間清太郎の人生を眺めることで。
人が、その人の一度きりの人生を生きるということが、どのような
意味を持つものなのか、ということを考えさせられる書である、
という、いわば本書の縦軸に関する感想を述べた。
この、後編では。
第二次世界大戦をはさんだ、日本の監獄史という横軸を俯瞰しながら
本書を紐解いていくこととしたい。
驚愕の事実が。
そこには、あった。
あの、日本中が食うや食わずやの状況に喘いでいた時期。
さぞかし、刑務所における囚人の処遇も悪かったのだろうと思い込んで
いたのであるが。
実際には、囚人には当時の平均的な日本人よりも、よほど良質なレベルの
食事が配給されていたらしい。
それは。
日々を監獄の中で暮らす囚人達にとって、喜びといえば食事くらいしか無く、
その品質を下げることは暴動等を引き起こす呼び水に、容易になり得たと
いうことが、主要因らしい。
もちろん、それも状況により変化はある。
実際、戦争末期には栄養不足により、全国の刑務所で死亡率が急上昇して
いったという記載もあるが。
戦前は、規則正しい生活と十全な食事がもたらした恩恵のため、死亡率は
むしろ市井の住民よりも刑務所内のほうが低かったようである。
それが。
開戦と同時に刑務所内の囚人の死亡率は急上昇し。
ついには、一般国民と比べて2倍弱にまで高まったというのであるから
尋常ではない。
しかも、それは。
「米、麦を主とした主食の摂取量が一般国民の二倍以上」という刑務所
において起こっている事態なのである。
如何に、食事というものがバランスよく様々な栄養素を摂取する必要が
あるか、よく分かるというものである。
それでも。
少なくとも、刑務所内に農場を開墾することができた網走刑務所などは。
相当にレベルの高い食事を、最後まで提供できていたようである。
そして。
刑務所内の農場で取れた生産物は、基本的には全て囚人に割り当てられる
ものと決まっていた。
その結果。
網走刑務所においては、恐るべき逆転が生じることとなる。
つまり。
看守に代表される一般国民よりも、囚人の方がはるかに良質の食事を摂取
しているという事態が生じていたのである。
この事態を前に。
看守に、やる気を出せという方が、余程酷な話ではないだろうか。
むしろ。
その規律を最後まで守り通した、刑務所内の刑務ラインの指揮系統の
統率の素晴らしさに、僕は驚嘆せざるを得ない。
普通。
そうなれば。
看守の立場を利用して、食材を横流しし。
それで一儲けしようとまで行かなくとも、本人や家族の糊口を凌ぐ術と
しようと考える方が、余程自然ではないか。
何といっても。
収監されているのは、罪人なのである。
それに比べて、自分たちはお国の役人なのである。
その役人が、家族ぐるみでひもじい思いをしているのに。
その統制化に置かれている罪人たる囚人達が、のうのうとご馳走を食べて
いることは。
とりわけ、老親や乳飲み子、病人等を家族に抱えた看守にとっては、
耐え難いことだったのは、想像に難くない。
そのような、状況下にあっても。
殆どの彼らは。
その職責に殉じ、粛々と職務を遂行していった。
何よりも、そのことに。
素直に僕は驚嘆し。尊敬の念を抱いてしまう。
もちろん。
中には、様々な不正もあったのかも知れない。
それでも、少なくとも、あの綿密な調査でもって知られる吉村氏が
調べた限りにおいて、そうした事実が掴めなかったということは。
しかも、それが。
正規の職員による一部の能吏に限定された訳でもないのだ。
末期には、人手不足から様々なレベルの職員が雇用されたという。
それでなくとも、壮健な年代層は徴兵されていっている状況だ。
その中で、残っていた人々も。
軍需工場に勤務すれば、食料の配給の面でも優遇されるのだ。
にも、関わらず。
看守職には、そうした特典も無い。
しかも、相手は荒くれた囚人達である。
そうした状況下で、どうやって彼らの矜持を維持し、統率することが
出来たのか。
吉村氏は、例によってその乾いた筆致で、淡々と歴史を追っていく。
そこには、劇的なドラマがある訳でも無く。
ただ。
看守という職責に、その身を殉じていった男たちの物語のごく一部が
語られるのみである。
確かに、佐久間に対する処遇には、厳し過ぎる側面も多々あった。
逃亡を恐れるあまり、後ろ手に回して嵌められた手錠等が、その最たる
ものである。
その手錠をされている間。
手も使えずに、佐久間は更に顔を突っ込ませ、犬のように食事をする
ことを、余儀なくされたという。
だが。
そうした処遇も、あの時代の状況下においては、仕方なかった側面も
あったのだろう。
何せ、佐久間に脱走されることは。
看守をはじめとする、関連するライン全てに叱責が及ぶことでも有り。
ただでさえ困窮する生活に、更に拍車をかける結果ともなったのだから。
それでも。
そのような状況下において。
あるものは、厳しく。
また、あるものは、人道的に。
佐久間に接していった。
その、どちらも。
職務に対する矜持を、胸に掲げて。
そのことが。
そうした時代が存在したことが。
僕は、無常に嬉しいのだ。
翻って、現代。
そこまでの誇りを胸に、自分は仕事に従事しているか?
苦い、問いだ。
(この稿、了)
 | 破獄 (新潮文庫)吉村 昭新潮社このアイテムの詳細を見る |
 | 破獄 [DVD]東北新社このアイテムの詳細を見る |
 | パピヨン-製作30周年記念特別版- [DVD]キングレコードこのアイテムの詳細を見る |