
(つづき)
3月のダイヤ改正で新設された「46-1番」。
博多ふ頭を出て天神に向かう場面では、冒頭の画像のような行先表示だった。
これに特に違和感を感じないという人も一定数居るようだが、

個人的には、こういう順番でルートを辿るというふうに感じ取ってしまうため、それに従うと
「キャナル→宮竹小→天神→博多駅→雑餉隈営業所」
という、ものすごいルートになってしまう。
このような、順番を無視した表示は他にもあるし、丸数字で示した順番も、「この順番で停車するバスが多い」というだけであり「必ずこの順番にしないといけない」わけでもないため、この「46-1番」の表示が誤りだとは言い切れない部分がある。
…といっても、やはり違和感はある。

現在の体裁を維持して修正するとすればこういう感じだろうか。
ただ、「宮竹小」という情報は、都心部ではそこまで重要ではなく、宮竹小を通るか否かを知りたい人には、「46-1」という数字で既に情報が提供されているという考え方もできると思う。

体裁にこだわらなければこうとか、

「都心部での利用者」をより強く意識するならこういう表示でもよいのかも。
(つづく)
3月のダイヤ改正で新設された「46-1番」。
博多ふ頭を出て天神に向かう場面では、冒頭の画像のような行先表示だった。
これに特に違和感を感じないという人も一定数居るようだが、

個人的には、こういう順番でルートを辿るというふうに感じ取ってしまうため、それに従うと
「キャナル→宮竹小→天神→博多駅→雑餉隈営業所」
という、ものすごいルートになってしまう。
このような、順番を無視した表示は他にもあるし、丸数字で示した順番も、「この順番で停車するバスが多い」というだけであり「必ずこの順番にしないといけない」わけでもないため、この「46-1番」の表示が誤りだとは言い切れない部分がある。
…といっても、やはり違和感はある。

現在の体裁を維持して修正するとすればこういう感じだろうか。
ただ、「宮竹小」という情報は、都心部ではそこまで重要ではなく、宮竹小を通るか否かを知りたい人には、「46-1」という数字で既に情報が提供されているという考え方もできると思う。

体裁にこだわらなければこうとか、

「都心部での利用者」をより強く意識するならこういう表示でもよいのかも。
(つづく)










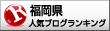





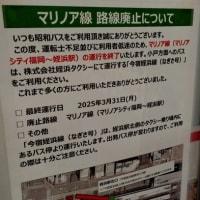















































・行先は雑餉隈営
・天神・博多駅を通る
・特筆すべき経由地はキャナル・宮竹小
と一目でわかりはするのですが、慣れないとこれではいくらなんでもわかりにくいですね。
経由地として最も強く主張したいのがどこなのかによって表示は変わると思いますが、46‐1の特徴はやはり竹下、井尻、宮竹小を経由するところでしょうから、そこを強調するのが最も利用者にわかりやすい、ということになります。
ただ宮竹小については番号ですでに示されている、というのはおっしゃる通りと思いますので、思い切って削って、下二つのどちらかが望ましいのかなと思います。この路線は終点より経由地重視型でしょうから。
話は外れますが、最近運転手さんに「○○には停まりますか?」と尋ねる人(特におばさん)が増えているような感じを個人的には受けます。LEDになってわかりにくくなったのか、路線再編が多くなって以前の感覚が染みついた人が、とりあえず来たバスに乗ってしまうのか、それはわかりませんが、行先表示の問題も少し関わっているのかなと考えてみたりもします。
「違和感がある」のは、自ずと「記載順=停車順」という法則が脳内にできあがっていて、そのフィルターで見ているからだと思われます。心配しないでください、私もそうです(笑)。
[46]のころから思っていたことですが、この路線の難しさはいくつかあって、(1)始発地を出発してすぐに天神・博多駅という二大拠点を通る、(2)その二大拠点の「間に」(←これ大事)重要経由地であるキャナルシティがある、というのがあります。幕式時代でも、天神・キャナルシティ・博多駅、いずれもマゼンタ色だったぐらいです(もっとも、正確に言えばキャナルシティのみ赤文字)。
それに加えて、この[46][46-1]系統は郊外向きという“下り”路線といえますが、天神・キャナルシティ・博多駅から郊外方面への輸送という目的の他路線とは違い、(3)始発地が海の玄関口ゆえに天神・キャナルシティ・博多駅で下車する乗客も想定しなければならない、ということがあげられます。おまけに、行先表示の決まりで、終点は分かりやすく表示しなさい、というのがあったかと思います(拡大表示しろ、とかのビジュアル的要素ではなく)。
そういった制約の中で表示を決めなければならず、かなり頭を悩ませる路線であることは間違いなさそうです。
LEDとなって幕式と比べて掲載情報量が限られると、乗客の立場になって考えれば、自分の行きたい方面に行くか行かないかを瞬時に判断しなければ乗り遅れてしまう(?)ため、前面は“とりあえず経由地を目立つように記載すればいい”とし、正確な停車順についてはあえて側面に任せているのかもしれません。
私が掲げる改善例は、最後から2番目の画像ですね。本当は「竹下駅」「井尻駅」として[46]とな区別を図りたいところですが、「竹下駅」というバス停はないし(近似値では別の場所になっちゃう)、他県からの方から見れば、どっちがJRでどっちが西鉄、という別の問題が出てきそうなので、思いとどまりました(笑)。
>経由地として最も強く主張したいのがどこなのかによって表示は変わると思いますが、46‐1の特徴はやはり竹下、井尻、宮竹小を経由するところでしょうから、そこを強調するのが最も利用者にわかりやすい、ということになります。
下りかつ都心部の、しかも、天神or博多駅の手前に関しては、「竹下、井尻、宮竹小」すら要らない、という考え方もあると思います(私自身は、それを積極的に支持しているわけではないですが)。
52番や13番などは、天神の手前では、行先部分の上段に大文字で天神、下段に小文字で桧原営、とかですし、天神の先の経由地については全く重要視されていません。
一方で61番などは、天神の手前でも屋形原とか今立とかちゃんと表示していたりして、そういうちぐはぐさもありますよね。
>「違和感がある」のは、自ずと「記載順=停車順」という法則が脳内にできあがっていて、そのフィルターで見ているからだと思われます。
そうなんですよね。
そのフィルターがある人とない人は、どっちが多数派なんでしょうかね?
フィルターがない人が多数派なら、私も素直に従いたいと思います(笑)。
前面は雑誌の表紙のようなもので、側面が目次だと、割り切らないといけないのかもしれませんね。