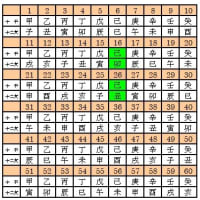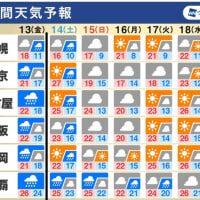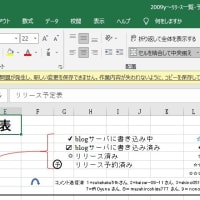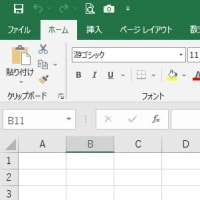私がパソコンを手にするようになったのは、1985年(昭和60年)4月からです。個人所有ではなく、会社で導入したデスクトップPCです。OSはMS-DOS、データの記録には8インチ・フロッピーディスクを使用していました。
この頃から、つい2、3年前まで、PC内蔵の記憶装置は専らHDD(ハードディスクドライブ)でしたが、最近ではHDDではなく、SSD(Solid State Drive)を内蔵記憶装置とするPCが普及し始めているようです。
多くのPCメーカーからSSDモバイルPCが販売されています。一頃はHDD搭載の従来型に比べ、10万円以上も高価でしたが、今年は概ね4~5万円程度の価格差となっており、購入し易くなった感があります。
堅牢性やeco性を考えれば、次に買い替えるときにはSSDモバイルPCにしようと思います。
ご存知の事とは思いますが、SSDとは、記憶媒体としてNAND型フラッシュメモリを用いるドライブ装置です。ATAなどHDDと同じ接続インタフェースを備え、HDDの代替として利用できる装置です。
<NAND型フラッシュメモリ>
メモリカードメディアに広く応用されており、コンパクトフラッシュ、スマートメディア、SDメモリーカードなどの記憶素子として利用されています。
“NAND”の学問的・技術的説明は省略させていただきます。
HDDは金属製の円盤(ディスク)をモーターで高速回転させ、ディスク上に浮上してデータの書き込みや読み取りをするヘッドを高速で移動させています。
このため、どうしても回転音や振動、発熱などが発生するし、電撃や衝撃でディスクとヘッドが接触する、所謂ディスククラッシュが発生してしまいます。最近のHDDはかなり堅牢にはなっていますが、構造的にクラッシュは避けることができないようです。
SSDはHDDのようにディスクを持たない半導体素子でできているため、シークタイム(ヘッドをディスク上で移動させる時間)やサーチタイム(目的のデータがヘッド位置まで回転してくるまでの待ち時間)がなく、高速で読み書きができます。更に、機械的に駆動する部品が無いため衝撃に強いほか、モーターが無いことから消費電力が少なく、発熱が大幅に抑制されます。
このように、いい事づくしのようなSSDにも欠点があります。それは、書き換え回数に上限があるという点です。
フラッシュメモリにはSLC(Single Level Cell)とMLC(Multi Level Cell)の2種類あります。SLCは10万回程度、MLCは1万回程度と書き換え回数に上限があるとされています。
しかし、NAND型フラッシュメモリは上書き動作が行えないため、自動的に別の空きブロックに書き込み、更新前のデータを削除して空きブロックとするようにし、結果として書き換え回数に限界があるという欠点をカバーしています。PCの平均的使用期間である5年程度の使用では問題ないようになっているようです。