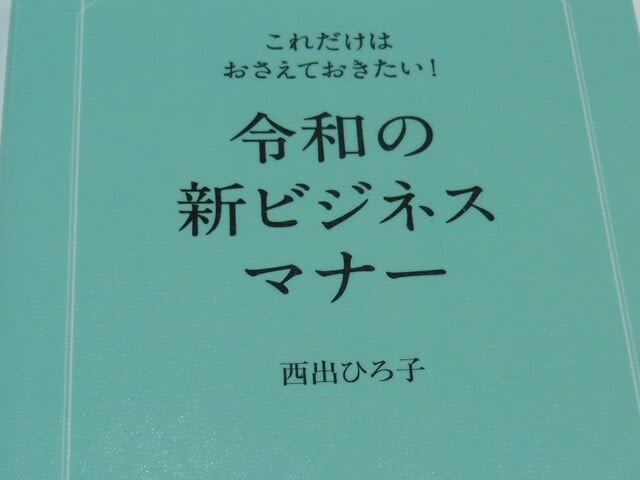ビジネスマナーについて解説した本。
「令和の新ビジネスマナー」と銘打っていることから、ビジネスマナーの変化を強調し、グローバルスタンダードへの移行(15ページ)などということも書かれています。近年は時間をかけることは相手の時間を奪うことと捉える人が多くなったのでコミュニケーションは最小限にする、苦情に対して手土産を持ってお詫びに行くと訪問されるのは迷惑だと言われかねないなどの指摘がなされています(12ページ)が、そうは言っても皆が皆そう考えるわけでもなく、実際どうすべきかは簡単ではないように思えます。ビジネスマナーの正解は1つだけではない、「型」どおりに行うのがマナーではない、相手を思いやることが最も大切だとしつつも、とはいえ多くの人は「型」を見てジャッジしているから、型を知り実践できることも大切だ、基本の「型」を身につけてこそくずすことができると述べ(16~17ページ)、まずは「型」を身につけろと言うのです。
近年の変化に応じて、結局はどうすればいいのか、思い悩んでしまいます。基本の型を身につけずにそういうことを言うのは10年早いということかもしれませんが。

西出ひろ子 秀和システム 2023年3月15日発行
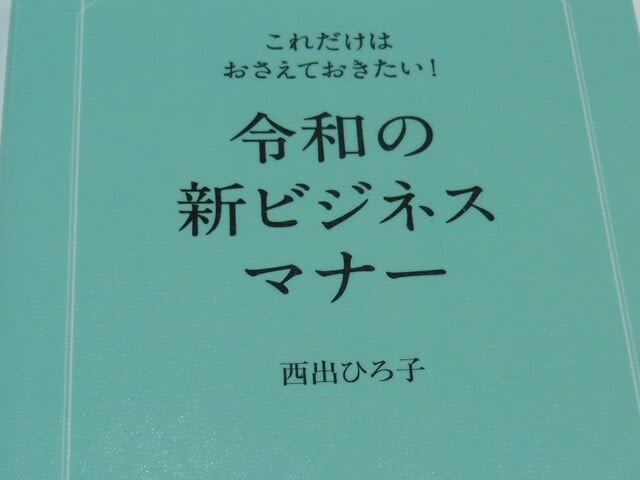
「令和の新ビジネスマナー」と銘打っていることから、ビジネスマナーの変化を強調し、グローバルスタンダードへの移行(15ページ)などということも書かれています。近年は時間をかけることは相手の時間を奪うことと捉える人が多くなったのでコミュニケーションは最小限にする、苦情に対して手土産を持ってお詫びに行くと訪問されるのは迷惑だと言われかねないなどの指摘がなされています(12ページ)が、そうは言っても皆が皆そう考えるわけでもなく、実際どうすべきかは簡単ではないように思えます。ビジネスマナーの正解は1つだけではない、「型」どおりに行うのがマナーではない、相手を思いやることが最も大切だとしつつも、とはいえ多くの人は「型」を見てジャッジしているから、型を知り実践できることも大切だ、基本の「型」を身につけてこそくずすことができると述べ(16~17ページ)、まずは「型」を身につけろと言うのです。
近年の変化に応じて、結局はどうすればいいのか、思い悩んでしまいます。基本の型を身につけずにそういうことを言うのは10年早いということかもしれませんが。

西出ひろ子 秀和システム 2023年3月15日発行