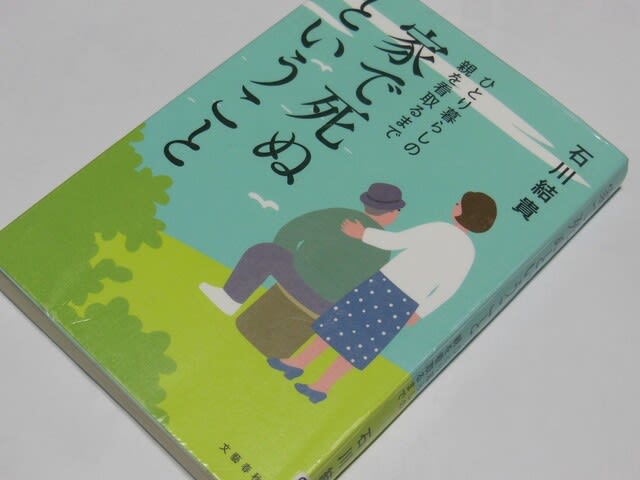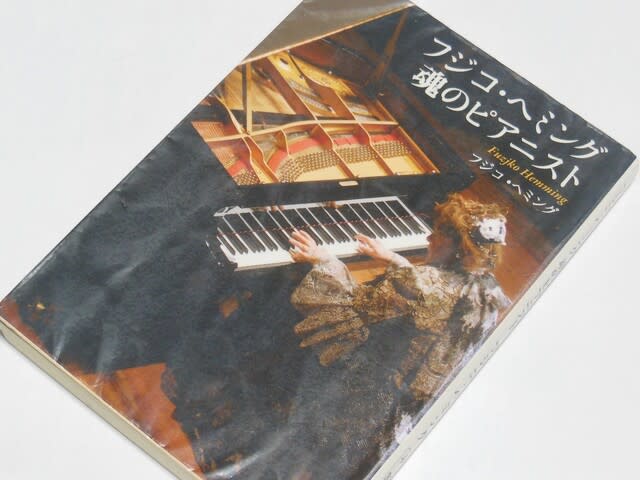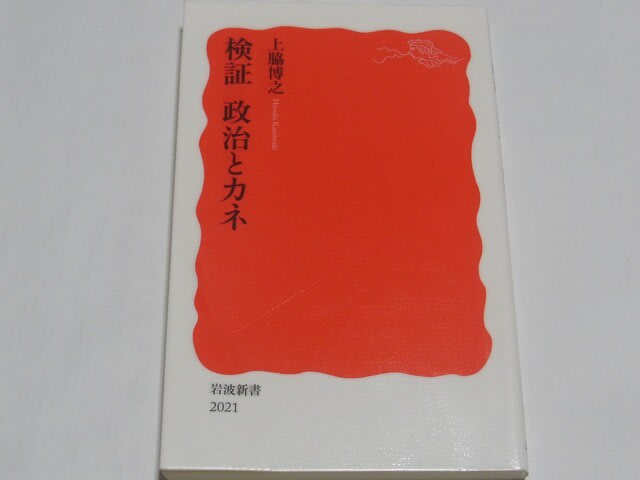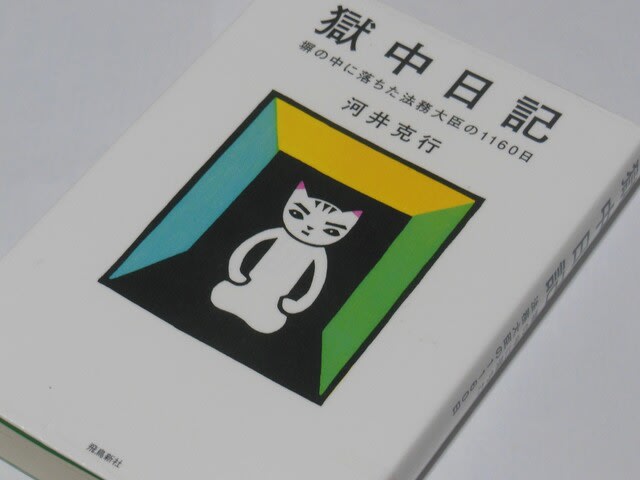ゴミの収集・運搬、中間処理、最終処分の実情等について説明した本。
自らゴミ収集等の作業に従事し、清掃労働者の過重労働や危険、通行人の反応とそれに対する清掃労働者の対応と心情を自らあるいは身近に感じながらレポートする姿勢は、労働者側の弁護士の私の目からは好感します。
ただ、そういった立場で清掃労働者と接している著者が、ゴミをきちんと分別せず、さらには飲み残しやタバコの吸い殻などを入れたペットボトルなどを投棄するような不心得な一般人や差別的言動を行う者に怒りを持つのは理解できますが、そのような一般人を悪者にして、(清掃労働者への理解を求め、また敬意を表することはいいのですが)自治体や中間処理事業者などの関係事業者を礼賛するばかりでいいのか、事業者の実態や産業廃棄物処理施設や処分場に問題はないのかという疑問も、私には残りました。著者としては、まずもって一般人が自覚してもらうことが先、それだけでもかなりよくなるという意識と、取材先を悪く書けない/書きたくないという事情があるのかも知れませんが。

藤井誠一郎 ちくま新書 2024年10月10日発行
東洋経済オンライン連載

自らゴミ収集等の作業に従事し、清掃労働者の過重労働や危険、通行人の反応とそれに対する清掃労働者の対応と心情を自らあるいは身近に感じながらレポートする姿勢は、労働者側の弁護士の私の目からは好感します。
ただ、そういった立場で清掃労働者と接している著者が、ゴミをきちんと分別せず、さらには飲み残しやタバコの吸い殻などを入れたペットボトルなどを投棄するような不心得な一般人や差別的言動を行う者に怒りを持つのは理解できますが、そのような一般人を悪者にして、(清掃労働者への理解を求め、また敬意を表することはいいのですが)自治体や中間処理事業者などの関係事業者を礼賛するばかりでいいのか、事業者の実態や産業廃棄物処理施設や処分場に問題はないのかという疑問も、私には残りました。著者としては、まずもって一般人が自覚してもらうことが先、それだけでもかなりよくなるという意識と、取材先を悪く書けない/書きたくないという事情があるのかも知れませんが。

藤井誠一郎 ちくま新書 2024年10月10日発行
東洋経済オンライン連載