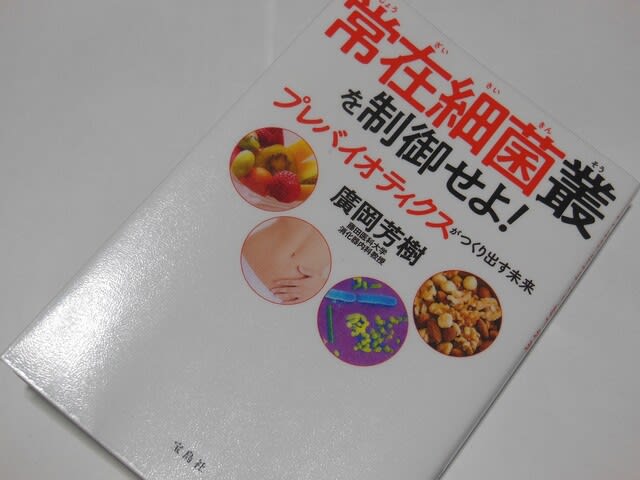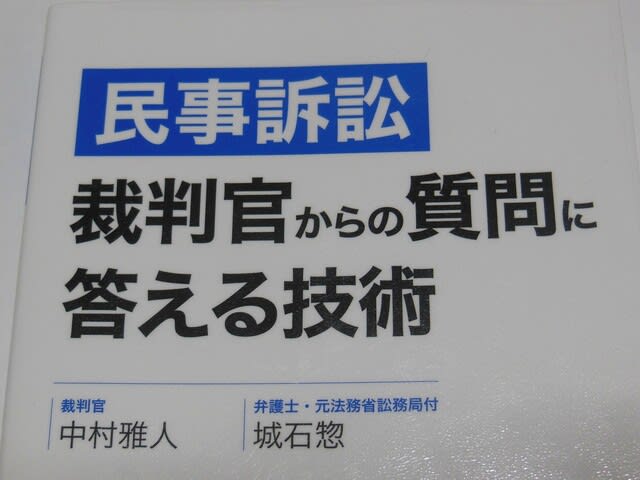月例給与と賞与からの源泉徴収・社会保険料控除、年末調整等の給与計算の実務について解説した本。
多数の図表を用いて、順番に説明されているので理解しやすいのですが、例えば社会保険料は月例給与では給与対象月(在籍・就労月)末日の資格の存否で発生し(その結果、月末締め当月払いの場合は支払月末日基準だが、翌月払いのことが多いのでその場合)支払前月末資格の扱いとなるのに賞与は支払月当月末日の資格基準で徴収の有無が分かれる、かつ資格喪失は退職日の翌日(末日退職なら翌月も保険料発生)とか、年齢(介護保険料は40歳到達月から65歳到達月まで徴収)は誕生日前日基準(前日の24時)(1日誕生日で40歳になった人は前月分から介護保険料徴収開始)とか、ちゃんと図示されていてさえ頭が混乱します。給与の変動による標準報酬月額の変更届の要件とか、保険料率変更時のどの月から計算を変えるかとかの実務上迷いそうな話、賞与は源泉徴収さえも面倒そうな様子など、会計や社会保険労務士の仕事ってたいへんだなぁと思わせてくれます。
給与計算の段取り・作業がイメージできるとともに、なんか面倒そうだなぁというイメージも持ってしまいました。

竹内早苗 労務行政 2025年2月1日発行(初版は2018年2月18日)

多数の図表を用いて、順番に説明されているので理解しやすいのですが、例えば社会保険料は月例給与では給与対象月(在籍・就労月)末日の資格の存否で発生し(その結果、月末締め当月払いの場合は支払月末日基準だが、翌月払いのことが多いのでその場合)支払前月末資格の扱いとなるのに賞与は支払月当月末日の資格基準で徴収の有無が分かれる、かつ資格喪失は退職日の翌日(末日退職なら翌月も保険料発生)とか、年齢(介護保険料は40歳到達月から65歳到達月まで徴収)は誕生日前日基準(前日の24時)(1日誕生日で40歳になった人は前月分から介護保険料徴収開始)とか、ちゃんと図示されていてさえ頭が混乱します。給与の変動による標準報酬月額の変更届の要件とか、保険料率変更時のどの月から計算を変えるかとかの実務上迷いそうな話、賞与は源泉徴収さえも面倒そうな様子など、会計や社会保険労務士の仕事ってたいへんだなぁと思わせてくれます。
給与計算の段取り・作業がイメージできるとともに、なんか面倒そうだなぁというイメージも持ってしまいました。

竹内早苗 労務行政 2025年2月1日発行(初版は2018年2月18日)