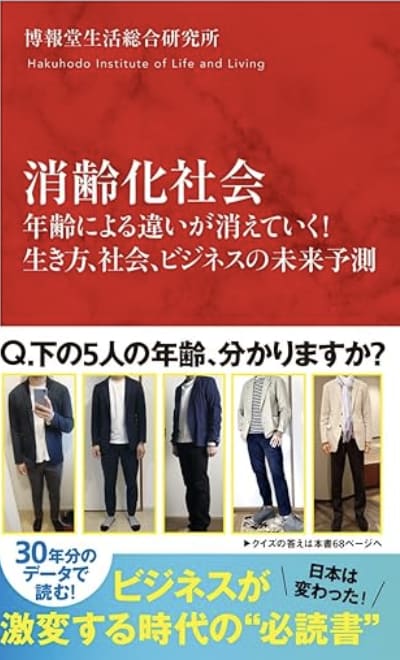@「日本は少子化問題で崩壊する」と予言している事に驚愕するが頷ける。それは本書にある人口動態での重要ポイント「経済力」「民族性」「社会的エゴイズム」があり、日本の現状は経済の低迷路線の選択と単独民族(単独民族の継承・移民不可)を継続していることだ。「崩壊」の主の理由である少子化問題は既に危険レベルにあり、幾ら労働者不足を科学技術で補おうと、また女性の地位と待遇改善を図ろうと手遅れに近いという。政治政策がこのままでは、日本の経済は成長が不可能で、若い夫婦が労働しても賃金的にも時間的にも子供を育てる環境がさらに失くなっていくと言うことだ。それは国家が増税と新税を繰り返しても、高齢者負担(医療・年金・保険)は若い層とは既に大差があり追いつけない、と言うことだ。日本の若い層は真剣に無策で自己主義的な国政を改善していかない限り日本の将来は明るくならないどころか、真っ暗闇に突然覆われるかもしれない。あるいは、外国移住した方が災難(極重税)に遭わずに済むかもしれない。更に気になるのは、国内の「米」の現状。政府の減反に次ぐ減反政策で農業人口の減少と老齢化など「米」不足と高騰化は政府とJAの思惑通りだが、国民にとって愚策でしかない。
『人口は未来を語る』ポール・モーランド
「概要」40億、121、79000―国家の命運は人口が握る! 気鋭の人口学者による大胆な未来予測。超大国になるか発展途上のままか、経済的に豊かになるか貧困にあえぐか。
ー都市で暮らす人々は小家族を選択し、出生率が低下、社会が高齢化し、人口が減少、移民流入と民族構成の変化となる
ー3つの色の変化
・増加するグリーン:人口増加の減速による環境回復の可能性=より効率的により少ない資源で食料を確保できる可能性
・増加するグレー:世界人口全体の高齢化と、多くの国の超高齢化の可能性
・減少するホワイト:民族的変化、すなわちアフリカの人口増とヨーロッパ系人口の減少
ー人口変化
・世界人口に占めるアフリカの割合は1950年に14人に1人だったが、2100年には3人に1人
・今世紀末の世界人口は150億人を超えるのかアフリカの出生率次第
・2064年に100億人弱を迎え2100年には90億人を切ると研究機関ランセットは予測
・平均出生率は1950年デンマークの2倍、現在は1.1倍、平均寿命も3分の2が僅か10%未満
ー急速な都市化
・第一次世界大戦前やには百万人都市は10数箇所、現在中国だけでも121箇所もある
・農耕民の3分の1が都市住民になり世界人口の半分を超えた(2100年には7割超)
・都市化の後退はパンデミック、財政破綻で起こ理、災害では食料水不足を招く
・イノベーションにより都市は消費エネルギーが減り、大気汚染も減り、交通渋滞も減る
・国策にもよるが都市と農村との格差は小さくなる(教育・暮らし)
・都市での少子化は進みキャリアアップと少ない投資で少子化が実現
・結婚・出産が減退、性生活も減退(日本の40歳未満は4人に1人は異性交渉がない)
日本は先進国の中でも最も幸福度が低く、子供を育てる時間と金銭的余裕がない
ー高齢化社会
・若い人口国は革命を起こしやすい(ロシア・ソ連時代)
・日本は100歳以上が7万9千人(90%が女性で、65歳以上が28%)
・日本に次いで高齢化社会国になるのはイタリヤ、ドイツ、中国、米国となる
・高齢化社会は長期停滞経済、低金利(過去30年で成長率が2%を超えなかったのは2回だけ)
・高齢化で高騰する医療費、年金へはゼロ金利、赤字国債発行、増税となる(自転車操業となる)
・公的年金を増やす工夫は移民労働者を増やす、年金支給年齢を上げる
ー犠牲となる選択(経済力・民族性・社会的エゴイズム)
・日本は経済力(経済低迷)を犠牲に民族性(移民を認めない)、家事と介護を女性に押し付け、結婚や子育てより自立(仕事で賃金を得る)を優先させる
・英国は移民を受け入れ、労働力を上げ、経済(税収を増やし)を活性化させるが、民族構成に変化し始めた(外国籍生まれが20%以上)
・イスラエルは経済と民族を優先し、出産率も伸ばしている だが移住も増えている
ー人口動態が重要
・気候変動、パンデミック、AI、地政学など以上に人口動態が重要な位置を占めていく
・日本の現状:少子化による崩壊が起きる最も早い国
母親としても働き手としても満たされない女性が多くいる
科学技術で補おうとしているがそれだけでは解決しない(出生率1.3低下が早い)