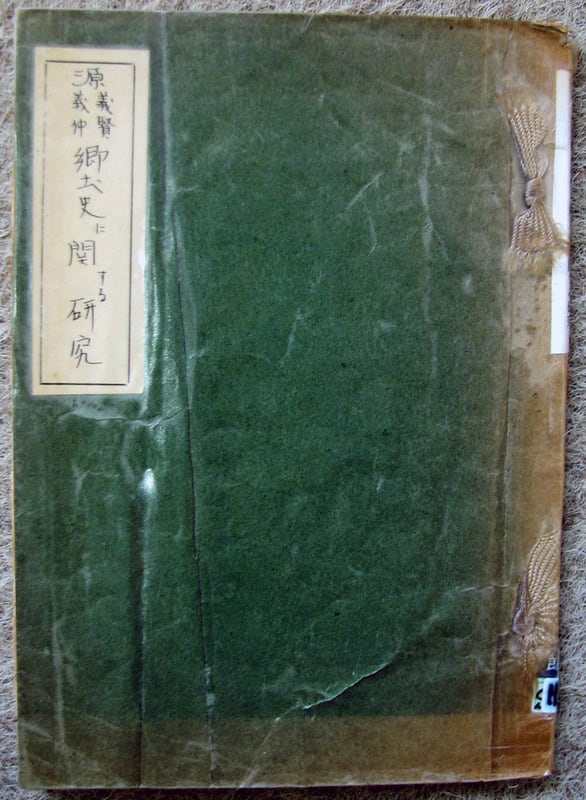当時大里郡岡部の住人で岡部ノ六弥太忠澄と称する武士がいたがこの岡部氏との所領争に加えて、義朝が京都にあって源氏の棟梁として重視されているのも、東国の武士団がその支配下にあるからであって、その地盤において、ともに源氏の正統を伝える弟の義賢の武名が日増しに高くなることは、義朝にとっては耐えられない苦痛であったろうと想像される。その心中は甚だ穏やかでなく、東国の棟梁の地位をめぐる内訌的なものではあるまいかと思われる。
時に駒王丸二歳の嬰児であったが、義平は郎党の大里郡畠山の住人畠山重能に探し出して必ず殺すように命じたが情ある重能に助けられて、長井ノ庄(大里郡妻沼町)の住人斉藤別当実盛に託せられた。
重能から駒王丸を託された実盛は、駒王丸の乳母の夫、信濃国(長野県)木曽ノ庄司中三権守中原兼遠に預けることにして、駒王丸を懐に抱きながらはるばる木曽に落ちていった。母は涙ながらに中原兼遠に幼児の保護を哀願したことであろうと思われる。
実盛の母の頼みを聞いた兼遠は、源平盛衰記によると、此の子共は正しく源氏の正統で、今は親を討たれて心細い孤児の境遇にあるが兼遠は何としてでも養育して、天下の檜舞台へ晴ればれしく乗り出させましょうといったと伝えている。
義仲は宮菊(菊姫)と称する妹がいたが、義賢討死の折、夫人の小枝御前は妹の満寿に、宮菊を養女として託したが詳らかない。
義仲討死当時の宮菊は美濃国(岐阜県)に住していたらしく、吾妻鏡元暦二年(1185)二月三日の項に左馬守義仲朝臣に妹公あり……その女が美濃国から京都に出て来てとある。
又五月一日の項に故伊予守義仲朝臣妹公宮菊と云。京都より参上。これ武衞招引せしめ給ふの故なりとあり、更に御台所ことに憐み給ふ……即ち美濃国遠山庄内の一村を賜ふ所也とある。
頼朝より与えられた美濃国の一村の領地として、頼朝の家人小諸太郎光兼の世話で安穏な生活を送ったと思われる菊姫のその後の消息は残念ながら不明である。
駒王丸は、その後成長して高祖義家の故事を襲ぎ、仁安元年(にんなん、にんあん)(1166)京都石清水(いわしみず)八幡宮において元服をなし、木曽二郎義仲と称した。
時に義仲十三歳のときである。
治承四年(1180)九月七日義仲二十七歳の秋、驕る平家を打ち世を平和にかえさんと北陸道より皇都に攻め上り、平家を西海に追いおとした当時の義仲の心中はいかばかりであったろうか。
僅二歳にして父を討たれ日陰の身を木曽山中に育った義仲が、三十歳の若き源氏の武将として入京した寿永二年(1183)七月二十七日と後白河法皇から平家追討の院宣を賜った二十八日の両日は義仲の生涯にとって最良の日であり幸福な日ではなかったかと思われる。
寿永二年八月十日平家討伐の論功行賞として従五位下左馬守兼越後守となり、六日後の十六日には伊予守に任ぜられ翌三年正月六日には、従四位下に昇進し、武門最高の栄誉たる征夷大将軍に任じられて、粟津ヶ原において、相模の三浦一族石田次郎為久に討ち取られる迄、旭将軍と称された薄倖の人木曽義仲は史上余りにも有名である。
義仲の墓は、大津市馬場之町の義仲寺に存し、その背後には義仲をこよなく愛惜したといわれる俳聖松尾芭蕉の墓がある。元禄四年(1691)八月義仲寺を訪れた芭蕉は観月の宴を催した折、
木曽殿と背中あはせの寒さかな*
と詠み、短命の英雄を愛して自分もこの英雄の瞑る義仲寺に葬られることを願ったといわれる。
帯刀先生義賢の墓は鎌倉街道の東面、新藤義治の庭に存する五輪の塔がそれであり、大正十三年(1924)三月三十一日埼玉県指定の史蹟として保存されている。(昭和31年10月20日稿) 菅谷村文化財保護委員・日本歴史研究会理事
『菅谷村報道』170号 1966年(昭和41)12月15日
*「木曽殿と背中あはせの寒さかな」は、伊勢の俳人島崎又玄の元禄五年(1692)の句。
参照:ブログ『現身日和(うつせみびより)』の記事「義仲と芭蕉が眠る義仲寺は静かに訪れる人を待つ <大津巡り18回>」。