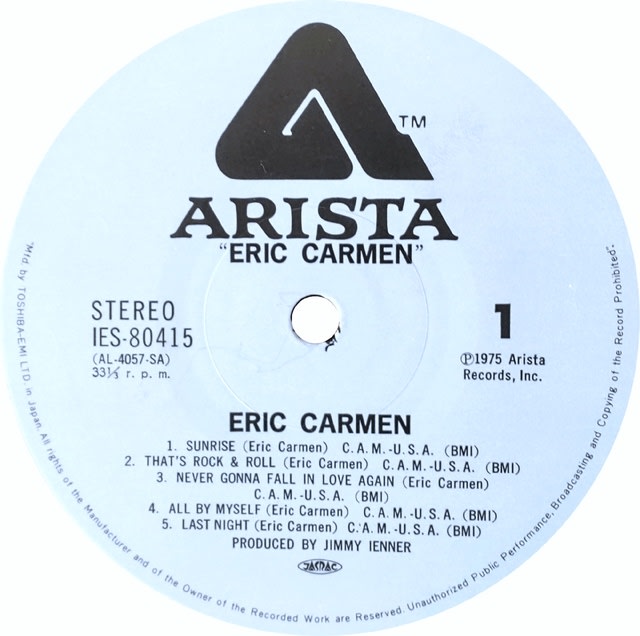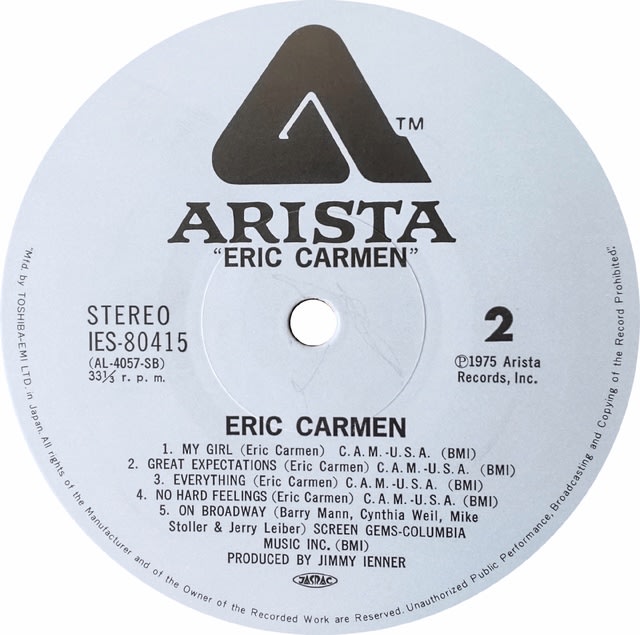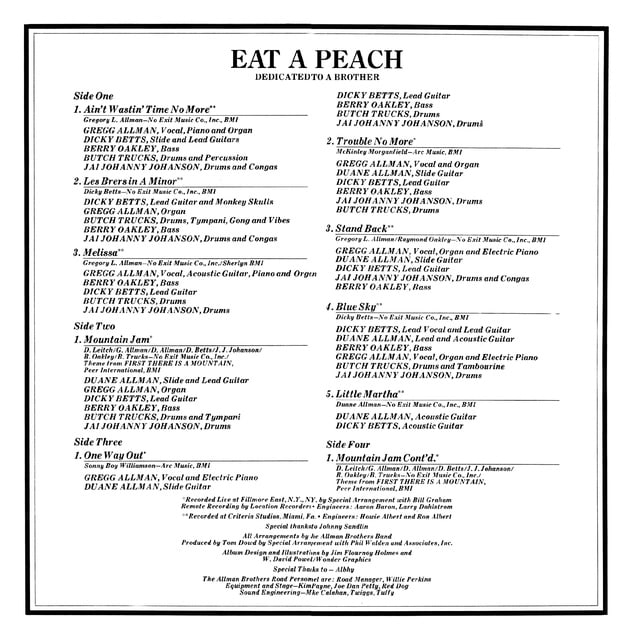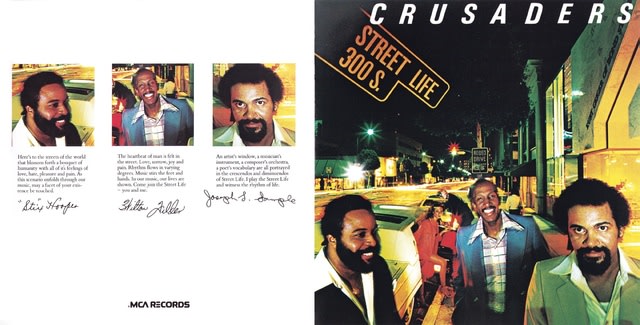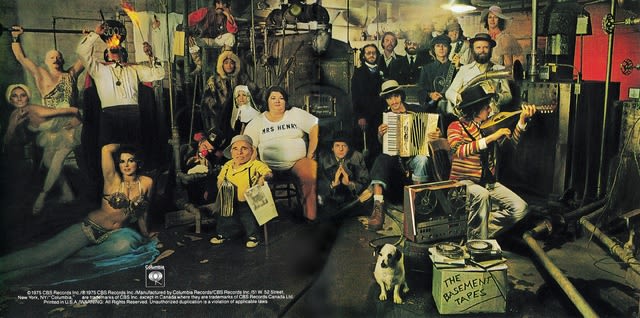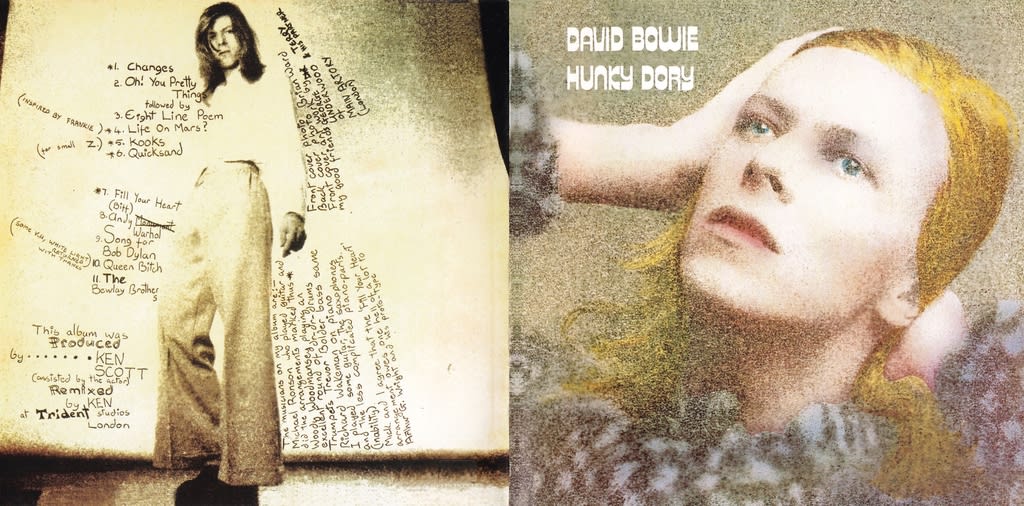昭和30年代頃から、Made In Japanといえば安かろう悪かろうのパチモンなるイメージだった。
しかし、先人の絶え間ない努力の結果、いつの間にか最高品質の代名詞と呼ばれる様になった。
本日はディープ・パープルの1972年のライブ・アルバム、Made In Japanでも。

(1998年に出た25周年記念盤、2枚組のCDセットで、2枚目のCDにはオリジナルに付いてこなかったアンコール曲が収められた優れモノ)
このアルバムは当初ライブ録音の許可をパープル・サイドは出さなかったのだが、最終的に日本の機材で録音した音源をパープル・サイドがチェックした上で日本限定で商品化するかどうか判断すると言う完全にワン・サイドの契約となった。
しかしライブ音源の出来が非常によくLive In Japanとして日本での発売の許可がもたらされ、その後日本から逆輸入されたレコードが海外で評判を呼び、結局海外でもMade In Japanとして発売される事に。
スピードに乗ったHighway Starは爽快だし、スローテンポなChild In Timeもブルージーな割にねちっこさがないボーカル、更にインプロビゼーションのパートではアップ・テンポになりリッチーが軽快にソロ・ギターを刻んでゆく。そこからSmoke On The Water、ドラム・ソロのあるMule、Strange Kind Of Womanに Lazyと中弛みなしに快調に飛ばしていき、20分余りの長尺曲Space Truckin’に傾れ込み大団円を迎える完璧なライブ・アルバム。
このアルバム、アメリカでプラチナ・アルバムを獲得するなど売れに売れたし、この後他の著名アーティストも日本でライブ録音をするのが流行りに…
さすが、Made In Japan。
品質最高、間違いなし!