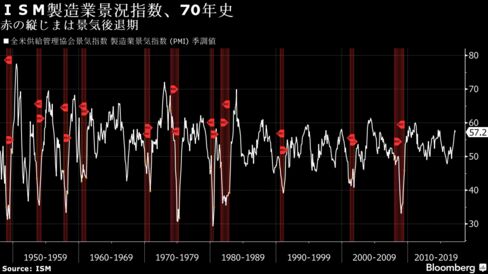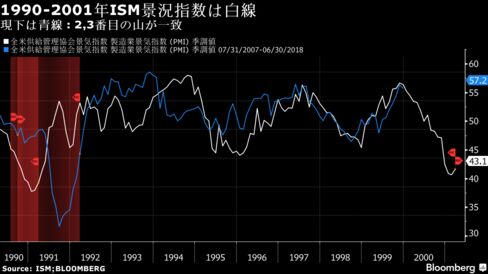<iframe class="hatena-bookmark-button-frame" title="%E6%9D%91%E4%B8%8A%E4%B8%96%E5%BD%B0%E6%B0%8F%E3%81%8C%E3%81%84%E3%81%BE%E4%B8%96%E3%81%AB%E5%87%BA%E3%81%A6%E3%80%81%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%97%E3%81%A6%E3%82%82%E8%A8%B4%E3%81%88%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%20%E5%A8%98%E3%81%AE%E3%80%8C%E6%AD%BB%E7%94%A3%E3%80%8D%E3%82%92%E8%B6%8A%E3%81%88%E3%81%A6" frameborder="0" scrolling="no" width="115" height="20"></iframe>
旧通産省(現経産省)の官僚から投資ファンド「村上ファンド」の代表へ転じ、2006年にインサイダー取引の疑いで逮捕された村上世彰氏。逮捕以降はシンガポールに拠点を置きながらマスコミに一切登場しなかったが、去る6月21日、自身の半生を描いた『生涯投資家』を文藝春秋社から出版した。
村上氏はコーポレート・ガバナンス(企業統治)改革による日本経済の活性化をライフワークにしてきた。2011年に最高裁での執行猶予付きの有罪判決を受け、一時は事実上の隠居生活に入ったのかと思われていたものの、同書ではガバナンス改革については今も並々ならぬ情熱を持っていることを明らかにしている。
私は日本経済新聞時代も独立後もジャーナリストとして村上氏への取材を重ねてきた。マスコミが「村上バッシング」一色になっているなか、拙著『不思議の国のM&A』などで村上氏のようなアクティビスト(物言う株主)が果たす社会的役割に意識的に光を当ててきた。そんなこともあり、村上氏にはかねて自伝を書くよう促してきたし、同氏からインタビュアーの打診を受けた際には喜んで引き受けた。
村上氏は自伝出版をきっかけにアクティビストとしての活動を本格的に再開するのか。インタビューでは「コーポレート・ガバナンスを根付かせることに自分なりの意地がある」と語るなどアクティビストらしさを見せる一方で、目立ち過ぎに伴う負の側面に言及するなど複雑な心境ものぞかせた(なお、<>内はインタビュアーである私の補足説明 / 撮影:西﨑進也)
。
きっかけは強制調査
――こういう形で村上さんを取材するのは本当に久しぶりです。
村上: 2006年6月5日の朝、逮捕直前に牧野さんに電話しましたよね。もう10年以上も前になります。何が起きていたのかフェアに書いてくれたのは牧野さんぐらいでした。
――当時、村上さんを直接取材していた記者は日経社内では私ぐらいでした。でも、逮捕当日はまったく出番がありませんでした。村上さんを取材したこともない記者が書いた記事で翌日の1面が埋まっていました。
村上: 残念でしたね。牧野さんには感謝しています。
<フジテレビジョンに経営改革を迫るなどしていた村上氏は大手メディア経営陣から敵視され、「拝金主義者」「ハゲタカ」のレッテルを貼られていた。系列のテレビ東京株を村上ファンドに取得されていた日経も例外ではなく、編集局内では「村上ファンドの宣伝になるような記事は書かないように」という暗黙の合意ができていた。今風に言えば「忖度」である。
当時、日経に編集委員として在籍していた私は、国内では携帯電話で村上氏を自由に取材できる唯一の記者だった(海外ではニューヨーク駐在の同僚記者が同氏とパイプを持っていた)。実際、誰も知らないネタもいくつか仕入れていた。村上ファンド側を取材するのは至難の業であっただけに、それなりの記事を書く自信はあった。
だが、「村上バッシング」にくみしなかったから社内では煙たがられていたのか、ほとんど何も書けず、逮捕当日にも出番を与えてもらなかった。>
――ただ、独立を機に『不思議の国のM&A』を出版し、そこで村上ファンドについて書けなかったことを書きました。改めてお聞きしますが、今回、どうして本を書く気になったのですか。
村上: 2015年11月に証券取引等監視委員会の強制調査を受けたことが大きいですね。最初の1週間は(相場操縦など違法行為があったと決めつけるような)一方的な情報が流されて、その後は強制調査がどうなっているのか何も情報が出てこなくなくなりました。そして今までずっと待っている状態です。
強制調査の結論が出るまで待ち続けてもいいのだけれども、僕はそれでいいとしても、家族のことも考えなくちゃいけない。やっぱり自分からも発信すべきではないのか、結局悪者扱いされるかもしれないけれども何も発信しないよりはマシではないか――こんな思いが家族にあった。そこで「父親の責任として、自分のやってきたことをきちんと書こう」と思い至りました。
――本の中でも最後に触れていますが、娘さん(長女の村上絢氏)は強制調査のストレスで死産をしてしまった。これも本を書く大きなきっかけになったのでは?
村上: それが一番大きなきっかけです。世の中にはやってはいけないことがある。法解釈だけの問題じゃない。娘は相場操縦の嫌疑がかかった時期、第一子の出産直前でまったく出社していなかったのだから無関係なはず。事前に調べれば妊婦かどうかくらいはすぐに分かる。
にもかかわらず、証券監視委は、強制調査時に第二子を妊娠していた娘を何日間にもわたって苦しめるようなことをやった。そして娘は妊娠7ヵ月で死産してしまった。本人に対する謝罪も行われていない。
一方的な報道は最初の1週間だけ
――強制調査については当初、相場操縦の疑いで刑事告発間違いなしといった「推定有罪報道」でマスコミは横並びでした。だから逮捕の観測まで出ました。疑われる側にしてみれば相当なストレスになりますよね。まさにデジャブ。11年前に検察が村上ファンドに対して強制捜査に入った際にもマスコミは横並びで推定有罪報道でした。
村上: 当日、強制調査を特報したNHKには不当に情報が流されたようです。週刊誌にもそのように読める記事が出ていましたね(週刊新潮2016年2月4日号の記事「東京地検がフタ!『企画調査課長』とNHK記者の不倫」のこと)。
ありがたかったのは、今回は一方的な情報が続いたのは最初の1週間だけで、その後は情報が流れなくなったということ。ニッポン放送株や阪神電鉄株を買い集めていた10数年前には、最後まで徹底的にたたかれて、「お前なんか退場しろ」というメッセージばかり耳にしていました。
もちろん今も同じかもかもしれない。今回も「お前なんか退場しろ」というメッセージが出てくるのであれば、それはそれで仕方がない。
<証券監視委が2015年11月25日に相場操縦の疑いで村上氏の事務所や家族の自宅などを対象に強制調査に入ると、新聞やテレビは一斉に推定有罪報道に傾いた。村上氏側に一切取材していないにもかかわらず、「関係者によると」と出所をあいまいにして「村上氏=犯罪人」というイメージを作っていった(現代ビジネスのコラム「村上世彰氏『相場操縦』報道に見るメディアのリーク依存体質」参照)。
主な新聞見出しをひろってみると、「監視委、刑事告発も視野」(産経)「村上元代表、安値で大量売りなど」(日経)「村上氏、相場操縦の疑い」(朝日)「相場操縦、空売りでも利益か」(読売)などだ。
調査の行き過ぎを懸念する声は皆無だった。強制調査に入る情報を事前に入手していたNHKは現場でテレビカメラを回し、監視委係官が大量の段ボール箱を運び出すシーンを流していた。
強制調査からすでに1年8ヵ月が経過しようとしている。だが、村上氏もインタビューの中で語っているように、監視委による調査がその後続いているのか、それとも中断しているのか、外部からはさっぱり分からない。このまま何もなしで終わるのだとしたら、強制調査時のマスコミ報道はいったい何だったのか。村上氏の長女に対する調査の意味も改めて問われるのではないか。>
星野監督と対談してもいい
――本は自分1人で全部書いたのですか?
村上: はい。とても時間がかかりました。ただ、過去の記録を引き出したり、最新の経済データを入手したりする作業については、2人のスタッフに手伝ってもらえた。時間にすれば合計でざっと3千時間。僕が千時間、2人のスタッフがそれぞれ千時間ずつという感じです。担当編集者の方にも感謝しています。
――本が出て本当に良かったと思います。これまでは村上さんを悪者に見せたい検察側の話が一方的にたれ流されていました。この本が出たことで「捜査する側」だけでなく「捜査される側」からの景色も初めて見えるようになり、全体像をとらえやすくなったわけですからね。対立していた両者からの話が初めて出揃ったのです。
村上: 今から思うと対立していたわけではないような気がしますね。僕は株主として物申していただけだった。それを対立と捉えたのは、相手の経営陣であったように思います。
僕は、ありのままを『生涯投資家』に書いたつもりでいます。だから、この本を読んで怒っておられる方々もいるかもしれない。そうした方々と、もし対談の機会があれば、もう一度きちんと、僕が目指していたことについて話をしたい。そうすることで、本当は何が起きていたのかが正しく世の中に伝わると思います。(フジテレビ会長だった)日枝さんや星野監督など、いかがでしょうか。(笑)。
――大企業の経営者と対談して話がかみ合うかどうか。個人的にはとても興味があります。
村上: 牧野さんがアレンジしてくれれば、僕は出ますよ(笑)。
<星野監督とは、プロ野球の阪神タイガースでシニアディレクターを務めていた星野仙一氏のこと。村上ファンドが阪神電鉄株を買い集め、阪神タイガースの上場も提案していた2006年当時、村上氏について聞かれて「いずれ天罰が下る」とコメントしたのである。実はその半年ほど前に星野氏は村上氏と都内で対談し、意気投合していたにもかかわらず、である。
これには対して村上氏は大きなショックを受けた。当時、私の取材に応じた際にも「自分の子どもがいじめに遭わないか心配」「さすがにこの発言は駄目でしょう」などと言い、見るからに落ち込んでいた。
鉄道事業の再編に情熱を傾けているというのに、それについてはまともな議論ができず、感情的バッシングを受けているだけ――こんな思いをにじませていた。『生涯投資家』でも「天罰」発言に触れ、「とても悲しい出来事」と振り返っている。>
アジアへの不動産投資
――でも時代の雰囲気が変わってきましたよね。日本版スチュワードシップコード(機関投資家の行動原則)が策定されるなど、この10年ほどで村上さんが主張してきたガバナンス論がようやく世の中で認められ始めた。
村上さんは早く登場し過ぎたんじゃないですかね。ついでに言えば私も少し早過ぎたのかもしれません。日経社内で「市場原理主義者」と呼ばれて、村上さんについてなかなか書かせてもらえなかった(笑)。
時代が村上さんにようやく追い付いてきたということであれば、本格的にアクティビスト活動を再開してもいいのではないですか。他人の資金を預かるのではなく、自分の資金を運用する形になりますけれども。
村上: どうしてもコーポレート・ガバナンスを日本に根付かせたいという想いがあり、意地になってやっているところがあります。でも再び批判されるかもしれないし、やらなきゃいけないわけでもない。仕組みづくりは今後の日本のさらなる発展に重要だと思っていますが、僕に求められるものがなければそれまでの話です。
その点で、アジアへの投資についてはリターンが出るかどうかだけを純粋に考えればよく、やりやすいです。土地を買って、いろんなものを建てています。日本的要素を入れながら建てて現地で売る、というのは楽しい。一方で日本では、コーポレート・ガバナンスの浸透をミッションに投資をしていても、なかなかそれが伝わらず、いろんなことを言われてやりにくいことが多いですね。
――不動産にも大きな関心を持っていることは以前から知っていましたが、『生涯投資家』を読んでその理由がよく分かりました。やっと腑に落ちました。
村上: 若い頃から父親にいろいろ見せられましたからね。
――どのぐらいの資金を不動産で運用しているのか公にできますか?
村上: 結構増えましたが、内緒にさせてください(笑)。自分のお金だけで運用しています。
――ずっと昔にお父さんと一緒に世界各地を回ったように、現在は自分1人で世界各地を回っている?
村上: 好きな所だけですけどね。面白いと思えば行くし、思わなければ行かない。
――特にどこが面白いですか?
村上: 最近はフィリピンに注目していますね。なかなかいいパートナーが見つからないのですけれども、もう少し投資を大きくしようかと思っています。
なにがいいのかと言うと、フィリピンの場合は10%以上の人が外国で働いているんです。主にハウスキーパーと船員。この人たちの給与が相当上がっていて、仕送り額が増えています。フィリピン国内の産業は成長していないけれども、お金が国内に流れ始めている。だから景気がいい。
フィリピン以外ではベトナム、カンボジア、バングラデシュも魅力的ですね。
アクティビストの株主提案
――村上さんは定年がないから元気な限りは続けるつもりですか?
村上: 不動産投資に関しては、自分が楽しいと思えなくなったらやめます。不動産投資には自分のミッションがない。純粋に投資としての魅力がなくなったらやめるかもしれない。
――確かに海外での不動産投資にはミッションは見いだしにくいかもしれませんね。でも株式投資にはガバナンスというミッションがある。だからここは今後も続けると考えていいですか?
村上: そうですね。例えば黒田電気では文書ねつ造事件がありました。会社が従業員の同意を得ずに、勝手に文章を捏造し開示いたしました。日本においてまだまだコーポレート・ガバナンスが行き届いていないことを痛感しました。となると、エネルギーが出てきます。
――村上さんは2006年に阪神電鉄株を買い集め、散々たたかれながらも初志貫徹で同社の経営権取得を確実にしました。ところが、その瞬間に逮捕され、鉄道再編の夢を打ち砕かれました。
村上: 本でも書いているように、当時は阪神と京阪電鉄の統合をきっかけとした鉄道会社の大再編を考えていたし、「上場企業」の在り方に布石を打てると思っていたから大変残念でした。
あれからもう10年以上ですが、今は黒田電気の株主総会が近づいている。コーポレート・ガバナンスの筋を通したいが、目立つことに対する漠然とした不安は感じます。
<インタビューが行われたのは6月23日で、6日後の同月29日に黒田電気の株主総会が予定されていた。村上氏は自身の関連会社の一つである投資会社レノを通じて独自の社外取締役候補を選任するよう株主提案しており、勝算ありと読んでいた。だから、阪神電鉄の経営権取得目前に逮捕された当時との連想が働き、「漠然とした不安」と語ったのである。
村上氏の行動が「漠然とした不安」を裏付けている。同氏が10年以上前の逮捕後に長い間にわたって対外的に何も発信せず、本を書くのもためらっていたのは、「目立ちすぎると適当な理由をでっち上げられてまた逮捕されるかもしれない」という不安を常に抱えていたからだ。
黒田電気の株主総会は予想通りに村上氏側の提案が通り、同氏と同じ旧通産省出身の安延申氏が社外取締役として選任された。アクティビストの株主提案が可決されるのは日本では極めて珍しい。>
《⇒後編につづく》
村上世彰(むらかみ・よしあき)
1959年大阪府生まれ。1983年から通産省などにおいて16年強、国家公務員として務める。1999年から2006年までM&Aコンサルティングを核とする「村上ファンド」を運営。現在、シンガポール在住の投資家。今年の6月には『生涯投資家』(文藝春秋)を出版。










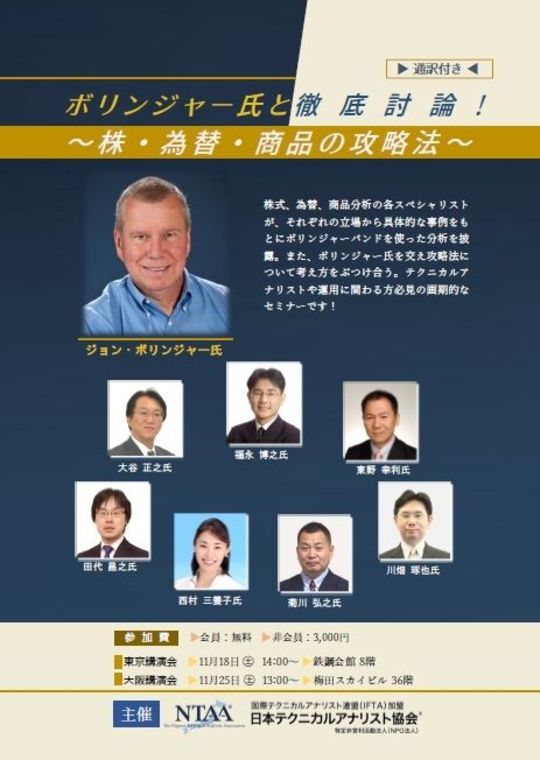

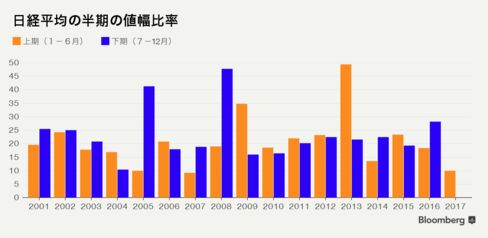









 「お金儲けは悪いことですか?」“村上ファンド”を率いて日本に旋風を巻き起こした男が、その実像と思いを自ら書き上げた最初で最後の告白
「お金儲けは悪いことですか?」“村上ファンド”を率いて日本に旋風を巻き起こした男が、その実像と思いを自ら書き上げた最初で最後の告白