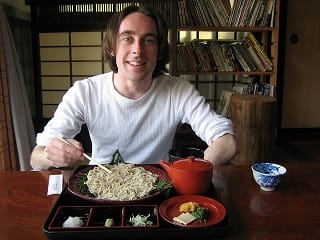能登町の神和住の真念寺で「いしかわ自治体問題研究所」の夏季セミナーに参加しました。
講師は春日俊雄さん。新潟県高柳町では「じょんのびの里」を作り上げた観光カリスマです。
農村滞在型交流観光を学ぼうという奥能登の経営者・職人・役人たちが研究会メンバーと共に集いました。

春日先生の進めてきた地域づくりを要約すると・・・
まず住民自身が地域の場に刻まれ時に溶け込んでいる「人」「歴史・文化」「風土」「風景」を深く知り、
自然と折り合いをつけた暮らしをローカル性(都市に無いもの)として語り、外部の共感を得ること。
住民それぞれがその価値に気づき自己表現としての暮らし方を再認識し、住民が実践する事業推進で
役割を担う(参加する)こと。
行政は民意総体の前向きのエネルギーの芯がどこにあるのかをつかみその支援に徹すること。

春日先生のお話にはいくつか印象深いエピソードやキーワードがありました。
・自分の年の刻み方が大切。できるできない、成した成さないよりも。
・生きた証として和紙を作る人がいる。生き方としてパンを作る人がいる。
・ズバ抜けた個人の元気さが都会人・著名人の共感を得、交流が続く。
・スウェーデンの過疎対策はそこにいる個人が生きられるための家業支援に向けられる。
・20年ずっと地域を見てきた行政マンが合併でいなくなった。ゆえに地域自治組織が求められる。
・実践活動の中で気づく。当事者を現地に連れていくと本人のスイッチがパチンと入る。
・ローカル性(都市にないもの)とは積み上がった時間&自然と折り合った暮らしのこと。

こういう空間(お寺の中)で研修会が行われることも、私は地域価値のひとつだとと思います。
もうお一方、金沢大学の安嶋是晴先生からは輪島に伝わる「御当組(おとうぐみ)制度」について
お話がありました。初めて聞いたビックリするような話でした。またの機会にお伝えします。
地域の有名な担い手の皆さんともお会いすることができ、たいへんよい機会になりました。

さあ、自分には何ができるか?何をするのか!