SGLT2阻害薬で治療している患者では、極端な炭水化物制限を行っていると、血糖値が正常に近くてもケトアシドーシスを生じる「正常血糖糖尿病ケトアシドーシス」(eDKA)が引き起こされるおれそがあることが明らかになった。
しかし、炭水化物比率を40%に制限すると、比率が55%だった場合に比べて、同薬の使用により血中のケトン体が有意に上昇することも判明した。これにより、極端な炭水化物制限を行うと「正常血糖糖尿病ケトアシドーシス」(eDKA)を引き起こす可能性があることが示唆された。GLT2阻害薬の適切な使用にあたっては、患者が日常的に摂取する食事の内容や量を把握することが重要であることが示された。
「糖尿病ケトアシドーシス」は、多くは急性の高血糖がきっかけで発症する。血糖値を下げるインスリンが不足すると、血糖をエネルギー源として利用できなくなり、体はエネルギー不足になる。そのため、かわりに脂肪がエネルギー源として分解されて、使われてしまう事態だ。
ケトアシドーシスになると、脂肪の分解によってケトン体という物質が血液中に増え、血液が酸性に傾き(アシドーシス)、脱水状態になる。この症状が起きた場合、すぐに医療機関へ連絡し。一刻も早く治療する必要がある。
Recommendationでは、インスリン分泌能が低下している症例へのSGLT2阻害薬の投与では、ケトアシドーシスの発現に厳重な注意が必要として、「全身倦怠・悪心嘔吐・体重減少などを伴う場合には、血糖値が正常に近くてもケトアシドーシスの可能性があるので、血中ケトン体を確認すること」と記載されている。
2型糖尿病患者23人を対象に、炭水化物比率とGIが異なる3群に割り付けた。(1)炭水化物比率55%+高GI、(2)炭水化物比率55%+低GI、(3)炭水化物比率40%+高GI――に無作為に割り付け、同じ内容の食事を2週間継続してもらった。対象患者には、後半の1週間にはルセオグリフロジンを服用してもらい、同薬の服用前後に持続血糖測定(CGM)を行った。
その結果、3群すべてにおいて、炭水化物比率やGIによらず、ルセオグリフロジンを服用するとCGMによる血糖の平均値および曲線下面積が有意に改善していた。
以上から、日本人2型糖尿病患者でらは、日常的に摂取する食事の炭水化物比率が40~55%であれば、炭水化物比率やGIによらず、SGLT2阻害薬が、安全かつ有効性に使用できることが分かった。一方で、血中ケトン体は、炭水化物比率が40%だった群では、比率を55%とした2群に比べて、同薬を使用すると有意に上昇することも分かった。
以上から、厳格な炭水化物制限を行う患者ではSGLT2阻害薬の使用により、正常血糖糖尿病ケトアシドーシスを生じるおそれがあることが示唆された。
ketoacidosis
ケトン体の蓄積により体液のpHが酸性に傾いた状態。ケトン体(アセトン、アセト酢酸、β-ヒドロキシ酪酸)は脂肪の分解により肝臓で作られ、血液中に放出される。体内にケトン体が増加する状態をケトーシス(ケトン症; ketosis)といい、特にアセト酢酸、β-ヒドロキシ酪酸は比較的強い酸であるためケトアシドーシスとも呼ぶ。
ケトアシドーシスは、かぜやインフルエンザなどの感染症にかかっている時や、強いストレス下にある時など、血液が体組織よりももっと酸性に傾いている時に急激に発症する。糖尿病性ケトアシドーシスは、主に1型糖尿病患者に起こる。インスリンが不足した状態では、グルコース(ブドウ糖)の代りに脂肪の代謝が亢進し、ケトン体が作られる。1型糖尿病患者で、インスリンを十分に補わないと、血糖値が上がり続け、ケトン体が血液中に蓄積しケトアシドーシスをきたす。この状態では細胞が損傷を受け、さらに脱水が加わると意識障害(ケトアシドーシス昏睡)を起こす。
最近、清涼飲料水をたくさん飲むうちに、糖尿病性ケトアシドーシスに陥るという深刻な問題がおきている。大容量のペットボトルで清涼飲料水を飲んでいたことから、ペットボトル症候群(清涼飲料水ケトーシス)と名付けられている。(2005.12.15 掲載) (2009.1.16 改訂)

ジャヌビア錠(一般名:シダグリプチンリン酸塩水和物)は2009年から発売されている糖尿病の治療薬になります。糖尿病の治療薬の中でも「DPP4阻害薬」という種類に属します。
ジャヌビアはインスリンの分泌量を増やすことで血糖値を下げるお薬になります。しかし古い糖尿病治療薬と異なり、インスリンを過剰に分泌させない工夫がされており、これにより低血糖のリスクがほとんどない安全性に優れるお薬になります。

また更新します。皆様もご自愛ください。










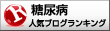

















いつも更新楽しみに読ませて頂いてます!
SGLT-2阻害薬のジャディアンス処方されて飲んでます(´・ω・`)
一緒にDPP-4阻害薬+ピグアナイト錠配合のエクメットも飲んでます(´・ω・`)
こんな私ですが、仕事復帰に伴いゆるゆる糖質制限解除して普通にご飯食べてたのですが
何気にこの判断は正解だったのですねorz
糖質制限続けてなくてよかったーー! と今回の記事を読んでほっと胸を撫で下ろしている所です
これからも更新楽しみにしてますー
無理の無い範囲で色々頑張ってください(´・ω・`)