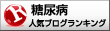下肢閉塞性動脈硬化症は、動脈硬化が原因となり下肢の動脈が細くなる(狭窄する)、あるいは詰まる(閉塞する)病気だ。少し歩くと太ももの裏やふくらはぎが痛くなり、休むと再び歩くことができるという症状(間欠性跛行)が特徴的だ。さらに重症化すると足の冷感が強くなり、安静にしていても足が痛くなる。あるいは足に潰瘍や壊疽ができても治らなくなる。早急な治療を行わなければ、足を切断しなくてはならないこともある。
下肢閉塞性動脈硬化症の治療法として目覚ましい成果を出しているのが「カテーテル治療」だ。血管内手術の技術の発達により、体の負担が少なく十分な治療効果を得られるようになってきた。適切な治療を受ければ、劇的な症状の改善が望めるという。
カテーテル治療は、細い管(カテーテル)を血管の中に通し、バルーン(風船)をふくらませて血管を広げ、血管の詰まりなどを取り除く治療法のこと。間歇性跛行の症状では、歩行距離が伸び、安静時痛のある症例では、痛みの改善、また壊死の危険を回避できる。
カテーテル治療は低侵襲治療で、身体への負担が少ない。血流が回復することで、治療後すぐに足がポカポカするなどの大きな改善を期待できる。血流改善で足の痛みがなくなり、身体が動かしやすくなり、糖尿病の血糖コントロールに欠かせない運動を生活に取り入れるチャンスが広がる。

国立循環器病研究センター血管科医長の河原田修身氏らの研究チームはこのほど、動脈硬化で足に潰瘍や壊疽を来した患者へのカテーテル治療がもたらす血流改善効果を明らかにした。
これまで提唱されてきた膝下動脈の血流分布(アンギオサム)理論に従わなくても同等の血流改善効果が得られることが、皮膚潅流圧(SPP)の測定で裏付けられたという。
アンギオサム理論は、各動脈が支配する皮膚や筋肉、骨などの3次元的な領域を示し治療に活用するという考え方で、特に形成外科の分野で用いられてきた。近年は動脈硬化による足の潰瘍や壊疽の場合でも、皮膚上の2次元的な地図として導入されている。
膝下には主に3本の動脈が走っており、2次元的な同理論に従えば足背側に傷がある場合は前脛骨動脈を、足底側に傷がある場合は後脛骨動脈を治癒する必要があるが、その有用性は実臨床の場では一定の見解が得られていなかった。
そこで研究チームは、足の潰瘍や壊疽の患者に、治療前後にレーザードプラー血流計で測定していた足背と足底の皮膚潅流圧(SPP)の変化を後ろ向きに検討した。
すると理論通りの変化を示したのは半数程度で、残りは前脛骨動脈であれ後脛骨動脈であれ、脛骨動脈のカテーテル治療によって足背と足底ともに同等な血流改善を認められた。
「実臨床では必ずしも理論上の2次元アンギオサムに従っていない」との見解を示し、その理由の1つに「足の潰瘍や壊疽の患者では各動脈を結ぶネットワークがあり、多くの場合は脛骨動脈1本の治療だけでも足全体の血流が改善する」と、河原田氏は説明している。
「足の潰瘍や壊疽の患者に対するカテーテル治療では、アンギオサムに固執せず、まずは技術的に安全確実に治療可能と考えられる動脈を治療し、少なくとも1本の血管で血流改善を確立することが重要となる。また、それでも不十分な場合には追加のカテーテル治療を段階的に考慮することが望ましい」とまとめた。

足病変の重症化で毎年1万人以上が下肢切断
現在、糖尿病や維持透析などの原因による足病変の重症化で、下肢切断となる人は年間1万人以上と言われています。これは、膝下、膝上、あるいは股関節から下を切る大切断の人数ですので、足の指だけといった小切断数は入っていません。足を切断する人は毎年どんどん増えているのです。
なかでも糖尿病の足壊疽(えそ)による大切断は、非外傷性の切断原因の第1位で、年間約3千人が足をなくしています。足を切断してしまうと寝たきりになる人が多く、1年生存率は透析患者で52%。5年になると約80%以上が死亡、透析を受けていない人でも5年で約6割が死亡するという報告もあります。
透析治療は、糖尿病腎症の重症化が原疾患の第1位(38%)で、次に慢性糸球体腎炎透析患者さん(32%)。男性の方が女性の3倍多く、50代から増えはじめ、60代~80代が多くを占めます(平均年齢67歳)。10年以上透析を行っている人は全体の約3割ですが、国の高齢化が進めばますます増加していく可能性があります。現在透析治療を受けている患者さんは31万4千人(平成26年現在)で、毎年4万人近くが新規で透析導入しています。透析患者さんも足病変リスクが高く、透析歴が長くなると全身の動脈が石灰化して動脈の壁が石管のように硬くなってきます。詰まると血行再建は難しく、足の切断に至ってしまうケースが多いのです。
しかし、足病変が起こらないよう正しい知識をもって日頃から足をケアしていれば、必要以上に恐れることはありません。動脈硬化も早期発見できれば、足の血管を拡張する治療法などによって、切断を回避することが可能になります。
国立循環器病研究センターより抜粋
(´;ω;`)ウッ…「治るなら、治してみたい、糖尿病」
僕のブログの書き方編。
「記事を見つける」→「ブログにコピペする」→「順に読んでいく」→「ビビる」
全国1050万人の糖尿病性神経障害合併症の患者さん、お元気ですか? 足ちょんぱの季節です(´;ω;`)
希望切断箇所を選んでね。①「指のみ」 ②「足首」 ③「膝下から」 ④「太腿からばっさりと」
※訂正します。糖尿病の主治医に聞いてね(´;ω;`)切断箇所、、、、

今朝の血糖値です。106(mg/dl)です。(`・ω・´)ふっ、どや! 薬物治療の成果は!どやっ!
「おい!おまい!報道ステーションばっか見てるだろう!」 (゚д゚)!ドキッ!ナゼワカル?
AM10:30から市民病院での定期検査です。逝ってまいります(`・ω・´)ゞ
必ず帰還します(`・ω・´)ゞ
生きて帰って・・・
また更新します。皆様もご自愛ください。