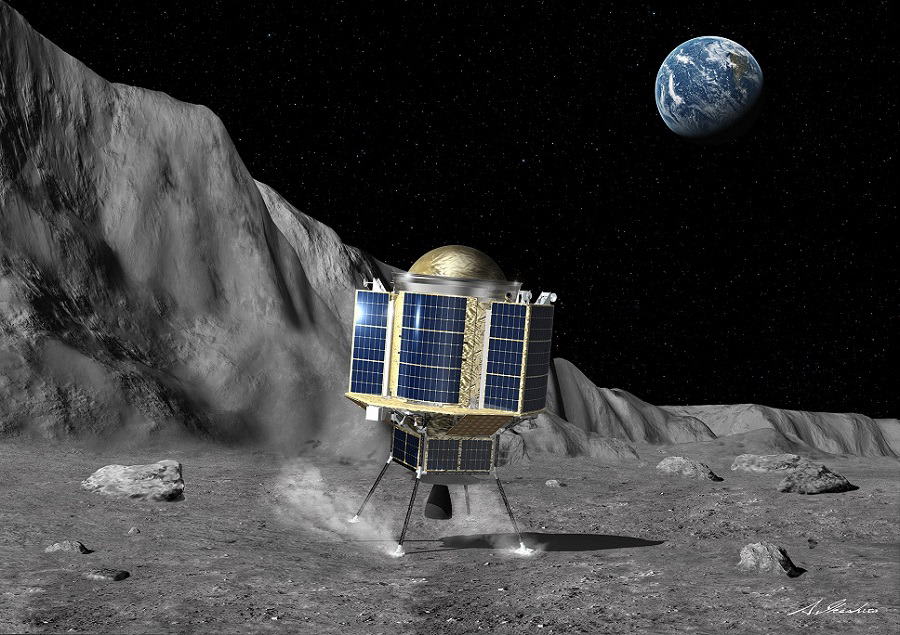月が形成される起源については、いくつかの仮説が提唱されてきました。
有力なのは、地球に火星くらいの大きさの天体テイアが斜めに衝突し、
バラバラになったテイアと地球の一部がまとまって月になった。
というジャイアント・インパクトという説です。
でも、1970年代にアポロ計画で採取された月のサンプルを再分析してみると、
その衝撃波は、これまでの仮説よりもはるかに強大だったことが分かってきます。
さらに、地球の一部とテイアから形成されたはずの月が、
地球と成分が似すぎているのも問題でした。
そう、「テイアだけでなく地球もほとんどが蒸発するほどだった」という可能性が、
高まってきたんですねー
今回発表された論文によると、
テイアが地球にぶつかる衝撃は「スイカをスレッジハンマーで叩くようなもの」だそうです。
過去のサンプルを新技術で再分析
これまでジャイアント・インパクト説が支持されてきたのは、
月の大きさや軌道上の位置について、すんなり説明できたからです。
でも21世紀に入ってから、
アポロ計画で採取された月の石の組成を新しい技術で再分析してみると、
これまでの説では説明できないことが出てくることに…
最近進歩した技術で、1970年代のアポロ計画によるサンプルを再分析すると、
以前よりはるかに小さな違いを測定することができます。
1970年代には気付かなかった多くのことを発見するのですが、
古いモデルでは、この新たな分析結果を説明できません。
40年前の仮説が正しければ、
月を形成する物質の半分以上はテイアに由来するもののはず。
でも月の石を分析すると、地球の石と非常に似通っているんですねー
月の石と地球の石
月の形成時の状況を推定するためには、カリウムの同位体の分析が有効とされています。
そこで今回の研究では、カリウムの同位体をこれまでの10倍の精度で分析できる手法を開発し、
月の石と地球の石の違いを見出そうとしています。
その結果、たしかに違いはあったのですが、
むしろ月と地球の緊密な関係を、さらに裏付けるものとなります。
その違いとは、月の石にはカリウム41というカリウムの中でも重い同位体が、
地球の石より0.4パーミル多く含まれていること。 パーミルは1000分の1。
その状態を作り出すには、
これまでの仮説で考えられるより、はるかに高温な状態が必要とされ、
説明するには「地球とテイアが正面から激しくぶつかり合った」と考えるのが、
適切というわけです。
このモデルでは、
極端な高温と強い衝撃によってテイアも地球の大半も蒸発することになります。
そして、蒸発したものが地球の500倍のサイズまで広がった後に、
それらが冷えて凝縮した結果が「月」だということです。
今回の研究結果から、月の形成にははるかに大きな衝撃が必要だと分かりました。
これまでのジャイアント・インパクトのエネルギーでは足元にも及ばない、
極度のジャイアント・インパクトがあったようです。
こちらの記事もどうぞ ⇒ 月の誕生に新説
有力なのは、地球に火星くらいの大きさの天体テイアが斜めに衝突し、
バラバラになったテイアと地球の一部がまとまって月になった。
というジャイアント・インパクトという説です。
でも、1970年代にアポロ計画で採取された月のサンプルを再分析してみると、
その衝撃波は、これまでの仮説よりもはるかに強大だったことが分かってきます。
さらに、地球の一部とテイアから形成されたはずの月が、
地球と成分が似すぎているのも問題でした。
そう、「テイアだけでなく地球もほとんどが蒸発するほどだった」という可能性が、
高まってきたんですねー
今回発表された論文によると、
テイアが地球にぶつかる衝撃は「スイカをスレッジハンマーで叩くようなもの」だそうです。
 |
| 地球とテイアが正面から激しくぶつかり合い、 極端な高温と強い衝撃によってテイアも地球の大半も蒸発、 そして凝縮することで月が形成された。 |
過去のサンプルを新技術で再分析
これまでジャイアント・インパクト説が支持されてきたのは、
月の大きさや軌道上の位置について、すんなり説明できたからです。
でも21世紀に入ってから、
アポロ計画で採取された月の石の組成を新しい技術で再分析してみると、
これまでの説では説明できないことが出てくることに…
最近進歩した技術で、1970年代のアポロ計画によるサンプルを再分析すると、
以前よりはるかに小さな違いを測定することができます。
1970年代には気付かなかった多くのことを発見するのですが、
古いモデルでは、この新たな分析結果を説明できません。
40年前の仮説が正しければ、
月を形成する物質の半分以上はテイアに由来するもののはず。
でも月の石を分析すると、地球の石と非常に似通っているんですねー
月の石と地球の石
月の形成時の状況を推定するためには、カリウムの同位体の分析が有効とされています。
そこで今回の研究では、カリウムの同位体をこれまでの10倍の精度で分析できる手法を開発し、
月の石と地球の石の違いを見出そうとしています。
その結果、たしかに違いはあったのですが、
むしろ月と地球の緊密な関係を、さらに裏付けるものとなります。
その違いとは、月の石にはカリウム41というカリウムの中でも重い同位体が、
地球の石より0.4パーミル多く含まれていること。 パーミルは1000分の1。
その状態を作り出すには、
これまでの仮説で考えられるより、はるかに高温な状態が必要とされ、
説明するには「地球とテイアが正面から激しくぶつかり合った」と考えるのが、
適切というわけです。
このモデルでは、
極端な高温と強い衝撃によってテイアも地球の大半も蒸発することになります。
そして、蒸発したものが地球の500倍のサイズまで広がった後に、
それらが冷えて凝縮した結果が「月」だということです。
今回の研究結果から、月の形成にははるかに大きな衝撃が必要だと分かりました。
これまでのジャイアント・インパクトのエネルギーでは足元にも及ばない、
極度のジャイアント・インパクトがあったようです。
こちらの記事もどうぞ ⇒ 月の誕生に新説