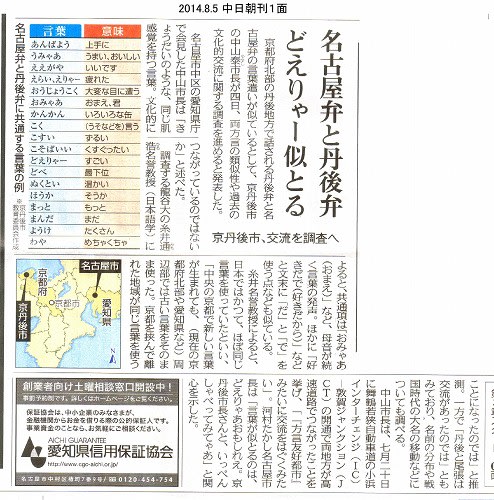私、御存知の方は御存知だと思いますけど、足首の関節の炎症、そしてその後の経過が上手くいっていなく、未だに杖携行の身です。無しでも歩けない事はないですが、バランスが保たれない上に、捻りが出来ず危険なので、「転ばぬ先の杖」ではないですが、使用しています。
なので歩行速度が大変遅く、しかも静止状態から動き始めも超ゆっくり。いうならば加速度ののろい昔の新幹線のよう。
こんな状態なので、エレベータに乗ると、親切なことに大抵一人くらいは操作盤の「開」ボタンを押していただけて「先にどうぞ」と譲られます。とても親切で、それは心から嬉しいです。でも本音を言うと、「どうぞ先に降りてください」ですし、実際にそう言っています。
というのは、エレベータでも車椅子対応のエレベータには大抵、車椅子搭乗ならではの機能がついているんです。乗り場に呼び出しボタンがありますね。「上方向」と「下方向」の組み合わせの下部に、車椅子記号と共に「上方向」と「下方向」のボタンがあります。
これは単に車椅子に座っている方だから低い位置に、なのではなく、車椅子ボタンを押すと扉の開く時間が多少長くなるんです。
エレベータのかご内部の階数ボタンも同じ。扉脇に上下に並んだ階数ボタンの他に、内部の側面低い位置に、車椅子用に横方向に並んだ階数ボタンがありますね。これも低い位置の操作性だけではなく、このボタンを操作することで、ボタンが押されたあった階に停止すると、そこでは若干開き時間が長くなります。
私は乗降に時間がかかるので、今では呼び出しボタンも、先客が押されていても、必ず呼び出しボタンまで行って、車椅子用ボタンを押しています。
そんなわけで、どうか皆さん、先に降りて下さい。実は先に降りてほしい理由はもう一つ。私は歩行速度が遅いです。しかし開ボタンを押していただいた方は大抵速いです。少なくとも今の私よりは速いです。そのため、エレベータを降りても追い越されるわけで、その階に人がいなければいいですが、待ち人が並んでいると私を追い越せないわけで。
※ ※ ※
ここまでは「どうかお願い」でしたけど、この先は「やってはいけません」のお話。上に書いた理由で車椅子用のボタンを押すと、着床の際にスムーズに制御する機能もあるエレベータがあります。スムーズになる分、到達時間はかかります。
また複数のエレベータがあるところでは、ロケーション制御(位置のコントロール)で車椅子ボタンを押されると、その階に優先的に配車というか籠を準備する機能の所もあります。そういうエレベータのところで車椅子用ボタンを押すと、他のエレベータ制御にも影響が出て、全体で待ち時間が長くなったりする場合もあります。
なので車椅子、或いは私のような乗降に時間がかかる方以外は、車椅子用ボタンは押してはならないのです。なかなか知られていませんが、手近だからの理由で車椅子ボタンは押してはいけません。