ジャズとビーチ・ボーイズとレッチリの<聖・三角形>の周りを、グルグルしている日々です。
ビーチ・ボーイズはいろんな方々のビーチ・ボーイズ愛を感じさせられるコメントを頂いて盛り上がりました。
そしてさらにsugarmountainさんのところで、至福の曲を聴かせてもらったり、嬉しい記事を読ませて頂いたりで、もー俄然盛り上がりリスニング中。
ジャズもまた、色々なコメントを頂いたり、嬉しいフィードバックがあったりで、こちらも絶賛リスニング中。
レッチリは、これはもう日々の活力と安定の源。アンソニーの声の癒し成分により、ざわざわする心も落ち着くっていうか。
なんか脈略ない三角形だなぁ、と思ってたんですけど、ふと2つの要素にからんでくるアーティストのことが思い浮かびました。
彼の名はバーニー・ケッセル。ジャズ・ギタリスト。
彼、『Pet Sounds』のセッションにも参加してるんですよね。私は全くそのことを知らず両者を聴いていたのですが、『Pet Sounds Sessions Box』が発売された際、オマケの詳細なブックレットを見て、その事実を知り、ちょっとビックリしました。
『Pet Sounds』に、いや、もうそれより随分前からのビーチ・ボーイズ作品にカリフォルニアの名うてのセッション・プレイヤー(主にスペクター人脈ですね)が参加していることは知っていたのですが、ウェスト・コーストのジャズ・プレイヤー達も割に参加していたようで、TVや映画の音楽に参加するのと同様、生活の糧のためだったのかなぁ、なーんて、複雑な気持ちにもなってしまいそうですが、出来上がった作品、それに当の本人たちのコメントを読む限り、そんな素人のヤボな邪推はどこかへ吹き飛んで、実に清々しい気分になります。
バーニー・ケッセル曰く

「ブライアンはスタジオに入ってくると、僕らにコード表を渡す。それで充分だったんだよ。
ブライアンは当時、非常に商業的に成功していたね。それに一緒に働く相手としては素晴らしかったよ」
ブライアン・ウィルソン曰く

「彼はまるでダイナマイトさ。本当に素晴らしいギター・プレイヤーなんだ。ホント、ダイナマイトだったんだ。“素敵じゃないか“のイントロをプレイしたのも彼なんだ。ジャズでも何でも、弾いてほしいギターは何でも弾く事が出来たんだ」
以上『Pet Sounds Sessions Box』より
なぬ!「素敵じゃないか」のイントロとな!
あの♪トンテトンテ♪言うてるやつですか!
「素敵じゃないか」には並々ならぬ想いがありますよ。しかもあのイントロが、あの曲の重要な決め手じゃないですかー!いや、ビーチ・ボーイズ史上、最も重要なイントロかも!それを弾いてるの?!(コレは今回気づきました!)
しかもブックレットの邦訳には「彼が書いた」となっていますよー!!およよ。
英文は
He Played the Introduction on “Wouldn't Be Nice“. Whew!
となっています。Whew!
Playってこの場合、イントロも「書いた」のか、ただ「演奏した」のか、どっちの意味ですか?
Whew!なんて驚いちゃってるし、別段むずかしい演奏でもないし、ケッセルは他の曲にもたくさん参加して演奏をしているし、んー、これはバーニー・ケッセルが「書いた」ってことなのですかねぇ・・・!?
今頃、一人で興奮してますけども!
ちなみにバーニー・ケッセルがクレジットされているペット・サウンズ曲は
“You Still Believe in Me“、“Let's Go Away For Awhile“、“I Know There's An Answer“、“I Just Wasn't Made For These Times“、“Caroline, No“です。あ、“Trombone Dixie“もだ。
* * * * * *
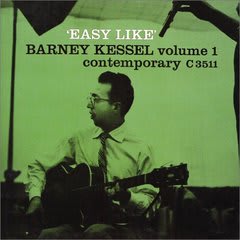
そんな訳で、“素敵じゃないか“のイントロを書いた(であろう)、バーニー・ケッセル。
ジャケがカッコイイ(であろう)、『Easy Like』。
53年発表の10インチに曲を足して56年にアルバムとして発表され直しました。ミドリがステキ。
私はこの人はこのアルバム1枚しか持っていないんですけど、よく聴いたアルバムで、とても心に残っています。
めちゃんこ聴き易いっていうのもあるし、コロコロ転がるようなギターの音色、流暢なコードワークは聴く場所や時間を選ばず、きっと聴く人に心地よい空間を演出してくれるに違いありません。
イチオシはM-8“That's All“。バディ・コレットのフルートが奏でるスィートなメロディと音色にコロッと。こんな優しい曲、参るってーの!
M-2“Tenderly“のギターがスゴい。渓谷に流れる川の水が様々な地形に関係なく流れる様に、ギターも流れています。当たり前の如く、ゆっくりとゆらゆらしながらしっかりと。そこに何ら間違いは見受けられず。
自作のM-1“Easy Like“、“Bernado“、“North of The Border“もケッセルのギターの魅力溢れる、活き活きとポップで面白いイイ曲です。
今日、久々に聴きましたが、初夏の夕暮れ時なんかには持ってこいのアルバムですね。
最近日も長くなって19時くらいまで明るいのも、妙にウキウキすることですし。
ビーチ・ボーイズはいろんな方々のビーチ・ボーイズ愛を感じさせられるコメントを頂いて盛り上がりました。
そしてさらにsugarmountainさんのところで、至福の曲を聴かせてもらったり、嬉しい記事を読ませて頂いたりで、もー俄然盛り上がりリスニング中。
ジャズもまた、色々なコメントを頂いたり、嬉しいフィードバックがあったりで、こちらも絶賛リスニング中。
レッチリは、これはもう日々の活力と安定の源。アンソニーの声の癒し成分により、ざわざわする心も落ち着くっていうか。
なんか脈略ない三角形だなぁ、と思ってたんですけど、ふと2つの要素にからんでくるアーティストのことが思い浮かびました。
彼の名はバーニー・ケッセル。ジャズ・ギタリスト。
彼、『Pet Sounds』のセッションにも参加してるんですよね。私は全くそのことを知らず両者を聴いていたのですが、『Pet Sounds Sessions Box』が発売された際、オマケの詳細なブックレットを見て、その事実を知り、ちょっとビックリしました。
『Pet Sounds』に、いや、もうそれより随分前からのビーチ・ボーイズ作品にカリフォルニアの名うてのセッション・プレイヤー(主にスペクター人脈ですね)が参加していることは知っていたのですが、ウェスト・コーストのジャズ・プレイヤー達も割に参加していたようで、TVや映画の音楽に参加するのと同様、生活の糧のためだったのかなぁ、なーんて、複雑な気持ちにもなってしまいそうですが、出来上がった作品、それに当の本人たちのコメントを読む限り、そんな素人のヤボな邪推はどこかへ吹き飛んで、実に清々しい気分になります。
バーニー・ケッセル曰く

「ブライアンはスタジオに入ってくると、僕らにコード表を渡す。それで充分だったんだよ。
ブライアンは当時、非常に商業的に成功していたね。それに一緒に働く相手としては素晴らしかったよ」
ブライアン・ウィルソン曰く

「彼はまるでダイナマイトさ。本当に素晴らしいギター・プレイヤーなんだ。ホント、ダイナマイトだったんだ。“素敵じゃないか“のイントロをプレイしたのも彼なんだ。ジャズでも何でも、弾いてほしいギターは何でも弾く事が出来たんだ」
以上『Pet Sounds Sessions Box』より
なぬ!「素敵じゃないか」のイントロとな!
あの♪トンテトンテ♪言うてるやつですか!
「素敵じゃないか」には並々ならぬ想いがありますよ。しかもあのイントロが、あの曲の重要な決め手じゃないですかー!いや、ビーチ・ボーイズ史上、最も重要なイントロかも!それを弾いてるの?!(コレは今回気づきました!)
しかもブックレットの邦訳には「彼が書いた」となっていますよー!!およよ。
英文は
He Played the Introduction on “Wouldn't Be Nice“. Whew!
となっています。Whew!
Playってこの場合、イントロも「書いた」のか、ただ「演奏した」のか、どっちの意味ですか?
Whew!なんて驚いちゃってるし、別段むずかしい演奏でもないし、ケッセルは他の曲にもたくさん参加して演奏をしているし、んー、これはバーニー・ケッセルが「書いた」ってことなのですかねぇ・・・!?
今頃、一人で興奮してますけども!
ちなみにバーニー・ケッセルがクレジットされているペット・サウンズ曲は
“You Still Believe in Me“、“Let's Go Away For Awhile“、“I Know There's An Answer“、“I Just Wasn't Made For These Times“、“Caroline, No“です。あ、“Trombone Dixie“もだ。
* * * * * *
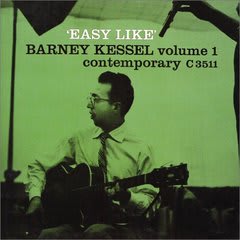
そんな訳で、“素敵じゃないか“のイントロを書いた(であろう)、バーニー・ケッセル。
ジャケがカッコイイ(であろう)、『Easy Like』。
53年発表の10インチに曲を足して56年にアルバムとして発表され直しました。ミドリがステキ。
私はこの人はこのアルバム1枚しか持っていないんですけど、よく聴いたアルバムで、とても心に残っています。
めちゃんこ聴き易いっていうのもあるし、コロコロ転がるようなギターの音色、流暢なコードワークは聴く場所や時間を選ばず、きっと聴く人に心地よい空間を演出してくれるに違いありません。
イチオシはM-8“That's All“。バディ・コレットのフルートが奏でるスィートなメロディと音色にコロッと。こんな優しい曲、参るってーの!
M-2“Tenderly“のギターがスゴい。渓谷に流れる川の水が様々な地形に関係なく流れる様に、ギターも流れています。当たり前の如く、ゆっくりとゆらゆらしながらしっかりと。そこに何ら間違いは見受けられず。
自作のM-1“Easy Like“、“Bernado“、“North of The Border“もケッセルのギターの魅力溢れる、活き活きとポップで面白いイイ曲です。
今日、久々に聴きましたが、初夏の夕暮れ時なんかには持ってこいのアルバムですね。
最近日も長くなって19時くらいまで明るいのも、妙にウキウキすることですし。


























































