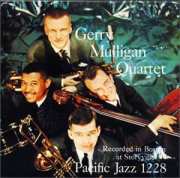今宵はバド・パウエル。私の20歳前後の第一次ジャズ・ブーム時代に買った、懐かしいアルバム。
私の持っているコレは『コンプリート・アメイジング・バド・パウエル』って20曲入りの日本盤CDなんですけど、全然コンプリートじゃないのですよね。第1集は網羅してありますけど、第2集からは4曲だけ。あとは『ファビュラス・ファッツ・ナヴァロ』の第1集、第2集からピックアップされていて、1949年の8/8(or 8/9)と1951年の5/1の録音を全部録音順(つまり『アメイジング~』の第1集のコンプリートという意味なのですね)に収録しているんだとか。このCDの悪評読んだことあるな。無粋だって。私もそう思うのでiTunesで普通の第1集、第2集の収録順に並び替えて聴いております。オリジナル通りがいいですよ、やっぱ。でもホントのオリジナルということになると、アルバムの元になった10inch盤の曲順通りに組まなきゃってことになるらしいですけど、ま、そこまでは、いいや(笑)
しかし、バド・パウエル。わかんなかったっすねー。当時。ホントにジャズ聴きたての頃に「名盤!」のうたい文句につられて買ってはみたものの、ロックやポップス漬けの耳には最初「?」だらけで。だから、もうわかるまでずーっと何回も何回もトライして聴き続けておりました。だから曲自体は耳に残っております。
最初、バド・パウエルの何が怖かったって、曲の間中「アァァ~~~☆●△※」と聴こえてくる訳の分からないうめき声。そんなの商品化されているモノから聴こえてくるのが初めての体験だったので、聴いてはイケナイものを聴いてしまったんだ(幽霊系)、私は・・・と思って、ドキーーッ!としてしまいました。とにかく実際はバドがピアノを弾きながらうめいていたわけで。今は逆にこの彼の「バックコーラス」がないと物足りなく感じます(笑)
そして今でもわかるかわかんないか、そこんとこ全然わかんないのだけど、ようやくいいと思えるようになったのはここ最近。
でも、昔からそんな感じで売られもせずに、ずっとウチにいらっしゃるので、勝手に戦友扱いしてます、アメイジング・バドさん。
さらに、最近の第2次ジャズ・ブームの時にバドがサイドメンで入ってるアルバムもいくつか購入して聴いてたり、ということもあって、長い年月をかけて、だんだんバドとの距離感が近づいていっているのでした。サイドで、というのはチャーリー・パーカーの『ジャズ・アット・マッセイ・ホール』やデクスター・ゴードンの『アワ・マン・イン・パリ』などのアルバム。リーダー作は未だにこれしか持っていません。
で、またちょっと聴いてみようと思ったキッカケは、なぜか今ハマりにハマっているマンガ『ワイルドマウンテン』(レコスケの本秀康さんの連載もの。マジ最高です!)。

淵野辺 銀造(銀ちゃん!私のiPod!)も右下に!
このマンガ、やたらジャズ、しかもブルーノートのオリジナル盤とかホントよく出てきて、そこも私はめちゃウレシイんですが、このマンガの4巻に、主人公のロマンスが始まるキッカケの重要な小道具としてこの『アメイジング・バド・パウエル』の第2集収録の ”Over The Rainbow” が使われているんですよねー。なんともニクイ使われ方で。あとね、バド自身もそのマンガに出てくるんですよね。逸話のシーンでね。
それで、一気にもうぐっと近くなっちゃったんです。バド・パウエルとの距離が。
で、思わず聴きたくなってiTunesに入れた次第なのです。
今の耳で聴くと、結構わかりやすいというか、聴きやすさすら感じて。
少し前までジャズばっか聴いてましたからね。ブルーノートものに集中していたし。
”ウン・ポコ・ロコ”の3連チャンだって怖くない。むしろ楽しい(笑)
アルバム全体に漂っているビバップの香りがオツなんです。
で、一番聴きたかった ”Over The Rainbow” 。"虹の彼方に"。3分弱でアッサリ終わっちゃう小品なんですけど、ぐっとくるのはマンガの余韻のせいでしょうか。なんかバドがぐーっと迫ってくるような迫力と、それでいて切なさも感じてしまう。これ、不思議だなぁ。
だからこそ、何回も聴いて、ずいぶん年月が経った後でも、また同じように何回も聴いて、引き込まれてしまうのでしょうね。
全盛期のバド・パウエルの姿。テンション最高に冴えまくってて、かっこいい。怖いくらい、スゴイ。
"虹の彼方に” はピアノソロなんですが、そんなソロとかピアノトリオで演奏している曲に、やっぱり耳も心も持っていかれがちです。ピアノをじっくり聴くことが出来る曲。”オーニソロジー” とか "パリジャン・ソローフェア" とか "イット・クッド・ハプン・トゥ・ユー" など。
そういうのは、当時尖りに尖っていた、ということは裏ではドラッグと精神面での不安で苦しんでいた、ヤバイ、バド・パウエルの姿を想像しながら聴くんです。
ピアノ弾いている時だけは、この世の誰よりも真っ当で、そして誰よりも美しい人だったんじゃないかなー、なんて思いながら。
うん、バド、もっと聴いてみよう。
まずは『アメイジング~』の第2集のちゃんとしたヤツが欲しいなぁ。
私の持っているコレは『コンプリート・アメイジング・バド・パウエル』って20曲入りの日本盤CDなんですけど、全然コンプリートじゃないのですよね。第1集は網羅してありますけど、第2集からは4曲だけ。あとは『ファビュラス・ファッツ・ナヴァロ』の第1集、第2集からピックアップされていて、1949年の8/8(or 8/9)と1951年の5/1の録音を全部録音順(つまり『アメイジング~』の第1集のコンプリートという意味なのですね)に収録しているんだとか。このCDの悪評読んだことあるな。無粋だって。私もそう思うのでiTunesで普通の第1集、第2集の収録順に並び替えて聴いております。オリジナル通りがいいですよ、やっぱ。でもホントのオリジナルということになると、アルバムの元になった10inch盤の曲順通りに組まなきゃってことになるらしいですけど、ま、そこまでは、いいや(笑)
しかし、バド・パウエル。わかんなかったっすねー。当時。ホントにジャズ聴きたての頃に「名盤!」のうたい文句につられて買ってはみたものの、ロックやポップス漬けの耳には最初「?」だらけで。だから、もうわかるまでずーっと何回も何回もトライして聴き続けておりました。だから曲自体は耳に残っております。
最初、バド・パウエルの何が怖かったって、曲の間中「アァァ~~~☆●△※」と聴こえてくる訳の分からないうめき声。そんなの商品化されているモノから聴こえてくるのが初めての体験だったので、聴いてはイケナイものを聴いてしまったんだ(幽霊系)、私は・・・と思って、ドキーーッ!としてしまいました。とにかく実際はバドがピアノを弾きながらうめいていたわけで。今は逆にこの彼の「バックコーラス」がないと物足りなく感じます(笑)
そして今でもわかるかわかんないか、そこんとこ全然わかんないのだけど、ようやくいいと思えるようになったのはここ最近。
でも、昔からそんな感じで売られもせずに、ずっとウチにいらっしゃるので、勝手に戦友扱いしてます、アメイジング・バドさん。
さらに、最近の第2次ジャズ・ブームの時にバドがサイドメンで入ってるアルバムもいくつか購入して聴いてたり、ということもあって、長い年月をかけて、だんだんバドとの距離感が近づいていっているのでした。サイドで、というのはチャーリー・パーカーの『ジャズ・アット・マッセイ・ホール』やデクスター・ゴードンの『アワ・マン・イン・パリ』などのアルバム。リーダー作は未だにこれしか持っていません。
で、またちょっと聴いてみようと思ったキッカケは、なぜか今ハマりにハマっているマンガ『ワイルドマウンテン』(レコスケの本秀康さんの連載もの。マジ最高です!)。

淵野辺 銀造(銀ちゃん!私のiPod!)も右下に!
このマンガ、やたらジャズ、しかもブルーノートのオリジナル盤とかホントよく出てきて、そこも私はめちゃウレシイんですが、このマンガの4巻に、主人公のロマンスが始まるキッカケの重要な小道具としてこの『アメイジング・バド・パウエル』の第2集収録の ”Over The Rainbow” が使われているんですよねー。なんともニクイ使われ方で。あとね、バド自身もそのマンガに出てくるんですよね。逸話のシーンでね。
それで、一気にもうぐっと近くなっちゃったんです。バド・パウエルとの距離が。
で、思わず聴きたくなってiTunesに入れた次第なのです。
今の耳で聴くと、結構わかりやすいというか、聴きやすさすら感じて。
少し前までジャズばっか聴いてましたからね。ブルーノートものに集中していたし。
”ウン・ポコ・ロコ”の3連チャンだって怖くない。むしろ楽しい(笑)
アルバム全体に漂っているビバップの香りがオツなんです。
で、一番聴きたかった ”Over The Rainbow” 。"虹の彼方に"。3分弱でアッサリ終わっちゃう小品なんですけど、ぐっとくるのはマンガの余韻のせいでしょうか。なんかバドがぐーっと迫ってくるような迫力と、それでいて切なさも感じてしまう。これ、不思議だなぁ。
だからこそ、何回も聴いて、ずいぶん年月が経った後でも、また同じように何回も聴いて、引き込まれてしまうのでしょうね。
全盛期のバド・パウエルの姿。テンション最高に冴えまくってて、かっこいい。怖いくらい、スゴイ。
"虹の彼方に” はピアノソロなんですが、そんなソロとかピアノトリオで演奏している曲に、やっぱり耳も心も持っていかれがちです。ピアノをじっくり聴くことが出来る曲。”オーニソロジー” とか "パリジャン・ソローフェア" とか "イット・クッド・ハプン・トゥ・ユー" など。
そういうのは、当時尖りに尖っていた、ということは裏ではドラッグと精神面での不安で苦しんでいた、ヤバイ、バド・パウエルの姿を想像しながら聴くんです。
ピアノ弾いている時だけは、この世の誰よりも真っ当で、そして誰よりも美しい人だったんじゃないかなー、なんて思いながら。
うん、バド、もっと聴いてみよう。
まずは『アメイジング~』の第2集のちゃんとしたヤツが欲しいなぁ。