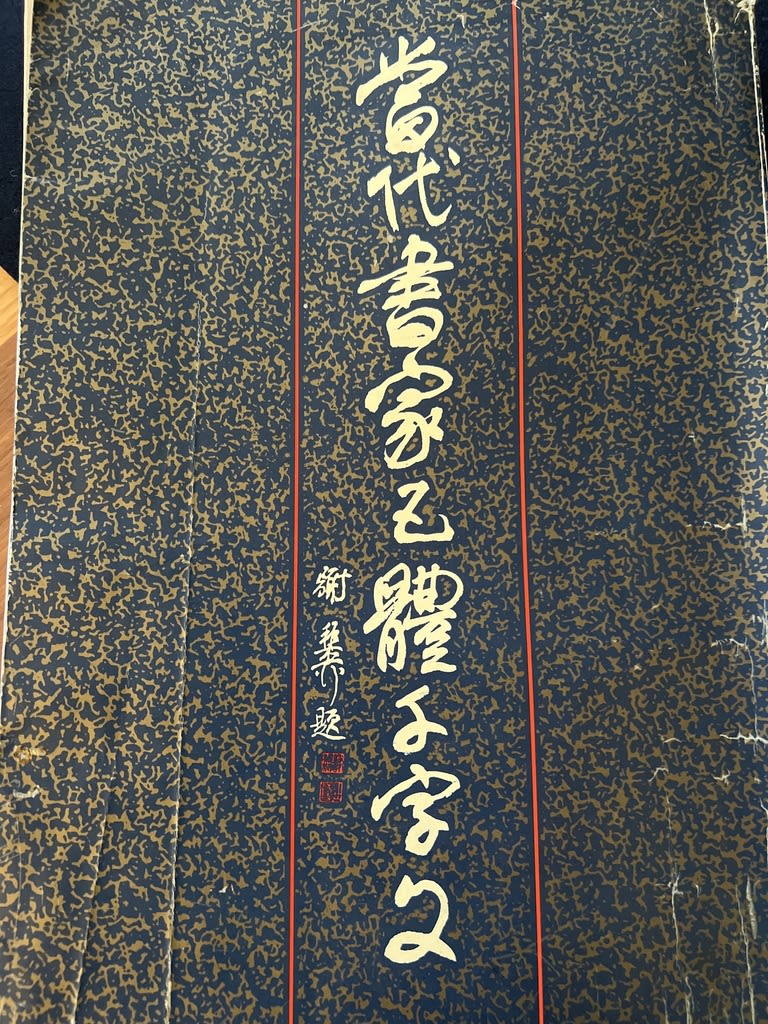これまで、gooブログでは、写真をスマホで撮影し、その中でブログへ掲載するものをその写真群から抜き出して、こちらの投稿用の欄に移行させていました。そのあと、ブログを書きはじめ、ある程度文章が書き上がったら、パソコンにその下書きを張り付けます。パソコンで作業した方が操作性を理解しているのでブログとしての体裁が取りやすいからですね。
ところが、gooブログが廃止となるのが明らかになり、ブログのデータをはてなブログへ移行したものの、今度は新規のブログ作成がわかりにくくなりました。文章だけで書くブログならなんとかなるのですが、スマホで撮影した写真をブログへ張り付けて、新規の掲載をするその方法が難解なのです。
相手は今までと全く違うブログの建て付けであります。用語も違うしブログ作成へのシステムが全く異なるのですから厄介な事この上無いのです。
当面文章のみのブログで、はてなブログのシステムを学びながら色々学習しようと思います。
それまでは、この4月19日の記事に、引っ越し先の「はてなブログのリンク」が張り付けしてますので、どうぞそちらからよろしくお願いします。
https://matyu711.hatenablog.com/