
新作もの(およびそれに近い、いわゆる”現代の”)オペラがはっきり言って苦手です。
2006-7年シーズンに、疑心暗鬼で観に行った『始皇帝』で痛い目にあい、
ますますその思いを強くしたので、昨シーズンのフィリップ・グラス作曲による
『サティヤグラーハ Satyagraha』に至っては、完全シカトの素通り状態で、
一度も公演も観に行きませんでした。
オペラに行くことは、拷問や苦行じゃないんですから、自分の見たいものだけを見ればよい、
フィリップ・グラスを聴かなきゃ死んでしまう、というわけでもあるまいし、と。
その基準からすると、今年の『ドクター・アトミック』は、素通り演目の候補にあがっていたのですが、
今週土曜日のサブスクリプションの演目に入ってしまっているうえ、
エクスチェンジ(他の公演にチケットを交換してもらうこと)などの面倒くさいことが苦手な私なので、
図らずも鑑賞すべき演目に入ってしまったのです。
新作オペラは映像や音源が限られていて、予習がしにくく、
舞台を一回いきなり観ただけでは、いろいろなことが吸収しにくいタイプでもある私は、
それも新作オペラを避けたい理由の一つになっているのですが、
ありがたいことに、この『ドクター・アトミック』は、おそらく2007年と思われる、
アムステルダムでの公演がDVD化されています。
この作品は、2005年にSFO(サン・フランシスコ・オペラ)で初演されましたが、
その公演を観たメトのゲルプ支配人が、音楽には惚れたものの、演出が気に食わない、という理由で、
オリジナルのピーター・セラーズに変え、メトではペニー・ウルコックの演出で
焼きなおされることになりました。
わざわざ、このような演出家の変更を行ってまで持ってきたメト初演もの、ということで、
ゲルプ氏が今年力を入れている演目の一つで、ライブ・イン・HD(ライブ・ビューイング)
の演目にも含まれているので、日本で映像をご覧になる機会のある方もいらっしゃるかもしれません。
この『ドクター・アトミック』はSFOが最初に作品依頼の声をかけた作曲家のジョン・アダムズと共に、
いや、もしかするとそれ以上に演出家のピーター・セラーズが
コンセプトやアイディアの形成に深く関わっていたこともあり、
セラーズをメトでの演出から外したことに対する疑念の声が、批評家筋の一部から上がっていました。
先にふれたアムステルダムの公演のDVDを見るうち、いろいろ作品についても思うことがあったので、
それも簡単に後ほど触れるつもりですが、
作品よりもむしろ、付録で付いてきた映像の方が面白く、中でも、
ピーター・セラーズのインタビューは、大変興味深いものがあり、
中には、『ドクター・アトミック』のライブ・イン・HDを
観に行く、という物好き(失礼!)な方もいらっしゃるかも知れないので、
その内容をご紹介したいと思います。
ちなみに、この『ドクター・アトミック』は、”原爆の父”と呼ばれる、
J・ロバート・オッペンハイマーを中心に、原爆開発のための”マンハッタン計画”
にたずさわった人々の、実験を経て原爆投下に至るまでの心の葛藤を描いた物語です。
テーマがテーマなので、日本人にとっては興味がひかれる作品ではあります。
このセラーズという人は、独特の照れがあるのか、リハーサルのシーンなどを見ると、
まるで頭のてっぺんからお花が生えているような”たりらりらーん”系のお方に見えますが、
このインタビューを聞くと、実に誠実な姿勢でこの難しいテーマに挑んでいることがわかります。
バイオを見ると、日本を含むアジアの国で勉強をした時期もあるようで、そのせいもあるのか、
被爆した日本側への思いも深く、インタビューの間で感極まって涙を浮かべる瞬間もありました。
アメリカ人で、このように原爆や軍事の問題を見ている人もいる、という点も非常に興味深く、
急ぎ足のディクテーションなので、細かいニュアンスを訳し切れていない部分もあるとは思い、
あくまで意訳として掲載させていただきます。
また、なじみのない詩人の名前など、聞き取りづらく、私の判断で割愛させて頂いている部分もあります。
インタビューの中で触れられている事実に関しての真偽等については、
私の方では裏づけを取っておりませんので、その点はご了承ください。
 ピーター・セラーズへのインタビュー
ピーター・セラーズへのインタビュー 
Q.(第二次大戦の実際の映像をモニターで眺めているセラーズに向かって)
ピーター、どうしてこの映像をご覧になっているんですか?
A.『ドクター・アトミック』の舞台で念頭にあったのは、第二次世界大戦末の空気とか雰囲気を想起させることでした。ハリウッドでも何度もこういう試みはありましたが、しかしハリウッドが作ったものは、事実とはかけ離れていました。オペラを作る一つの理由は、歴史というものを提示するとき、それが観客側の想像を許容するメディアだからで、実際の映像や画像、特にプロパガンダものを越えたところにもっていけるからでした。プロパガンダはプロパガンダであるがゆえに、故意に何を見せているか、また何をあえて見せていないか、という問題が常にありますので。音楽とか詩というものは、センサーシップ(検閲)が届かないところのものを表現できるし、自由な連想というものを可能にします。
しかし、観客には、こういった自由な連想の中で、もっとリアルなものとして、実際の戦闘の激しさを感じてほしいという気持ちもありました。そして、あの戦争が各人の葛藤であったことを思えば、今の時代は、もっともこのような題材に適した時期なのではないかと思うのです。世界のほとんどの地域でなんらかの戦争・紛争が繰り広げられているし、ボタン一つで空戦が始まる、今はそんな自動化された戦争の時代だからです。
こういった戦争のスタイルは、第二次世界大戦の、日本への空爆をきっかけに生まれたものでした。いってみれば、PCから何かを印刷するかのような破壊の方法です。若き日のロバート・マクミランにより想起され、やがてベトナム戦争で完成を見るこの方法は、戦争を大きな数学的問題に置き換えてしまいました。実戦経験のない人間が、全く空中から戦争をコントロールするというやり方です。
このシステマティックな爆撃スタイルによって行われた東京大空襲は、第二次世界大戦の末期に位置する空襲ですが、この空襲こそは、いわゆる近代的な“絨毯爆撃(カーペット・ボミング)”のスタイルがとられた世界初の例といってもよく、この完全な“空中からの無敵の力”というスタイルは、今でもアメリカが取り続け、そして自らを超大国せしめている理由となっているわけですが、しかし、奇妙な点は、アメリカは、完全には日本との戦争に勝ちはしなかった、ということでした。原子爆弾のせいで、勝って気持ちのいい戦争でも、また、勝ったことが正しいと思える戦争でもなかった。また原子爆弾が結果としてもたらした、世界における軍事国としての優位な立場にもかかわらず、朝鮮においても、ベトナムにおいても、また、キューバ、エルサルバドル、ニカラグアにおいても、そして、今ならイラクやアフガニスタンもこの中に入るのでしょうが、何か奇妙な感覚が戦争から生まれるようになったのです。このように原爆によって無敵の力を持つということは、正しいあり方でも、正しい生き方でも、自分がこうありたい、という理想像とも違う、という感覚、また、戦争が、数字とか統計とか、何人が犠牲になったか、といったことによって戦われるようになり、もはや人が人としてでなく、ただの数字としてしか考えられなくなった、という事実に対する疑問が、今のアメリカが関わっている戦争の根本にあるのです。それなのに、私達は過去からは何一つ学んでいないかのようにも思われます。このことから、一旦、人々をこの第二次世界大戦末期という時代に引き戻してみることは有益ではないかと考えたのです。
第一次世界大戦では、犠牲者の80%が兵士でした。そして、20%が女性や子供たち。しかし、20世紀の終わりまでにこの数字は逆転してしまいました。現代の戦争では、そして、それは、まさにこの第二次世界大戦末を出発地点としているわけですが、亡くなった人の80%が武力を持たない女性や子供といった民間人です。そして、14%が兵士なのです。この数字は心に留めておく必要があります。 “空中からの力”によって、これほどまで多くの、自分の命を守る術をもたない民間人の命を奪う戦争があってもいいのか?ということです。
Q.なぜ、『ドクター・アトミック』なのでしょう?なぜ、今、原爆なのでしょう?
A.原爆こそは、究極の破壊の例であり、また、戦争こそは、人間を神とみなす究極の例ではないでしょうか?また、原爆の存在はアメリカの世界での位置づけを決める一因となったわけで、その延長線上に私達もいるわけです。そこで、ジョン・アダムズと私が思い立ったのは、このオペラを作ることでアメリカの歴史を描き、また同時に、大きなサイクルの中で、今、アメリカはどういう場所に立っているのか、ということを模索することでした。また、どのような豊かな専門性、知識、優秀さを備えた人々がアメリカという国を作っていったか、移民、難民、独裁政治を逃れてきた人々たちがどのようにしてアメリカ人となっていったか、そして彼らがどのようにしてアメリカという国を世界有数の科学大国にしていったか、、、このような、アメリカは“単なるアメリカ”なのではなく、自国では生活し続けることができなかった人たちをはじめとする“他の人たち”こそがアメリカであるということ、これらのことを今のアメリカ人がもう一度見直すというのは非常に大事なことだと思うのです。そして、現在、9/11テロが引き金となって導入された国土安全保障の考えの下、多くの科学の道を目指す外国人たちが、アメリカの大学で学んだり研究することを拒否されています。その結果、アメリカの主要大学の化学、物理、エンジニアリングといった学部は、大変な危機にさらされています。それは、アメリカが学生を受け入れず、世界をシャットアウトしてしまっているからです。外国からの優れた化学者たち、ルーマニアやハンガリーをはじめとする、当時は政治が落ち着かなかった小国から、独裁政治を逃れてやって来た人たちが、アメリカが成し遂げた業績に貢献したわけです。もちろん、ユダヤ人たちも。ホロコーストを逃れ、肉親たちが収容所に囚われながら。
こういったことは、今でも古くなるどころかますます鮮やかな像として、私達を捕らえています。何百万という難民たち、かつてないほど多くの難民たちが、今地球上には存在しているからです。大変な数の人たちが自国で生活し続けられない状況に瀕しているのです。
もう一点、『ドクター・アトミック』について言うなら、登場人物に奥行きがあり、ある意味、神話的でもある点でしょうか。科学者たちのある種の英雄的な部分には驚くほどです。自らの意識下にある良心と闘いながら、同時に、この世の神秘を解き明かす科学者としての任務を遂行し、チームとして協力しあいながら並々ならぬ献身を重ね、限界に挑戦し続ける姿勢、また、科学や物理学というものが、真にヒロイックで、世のために役立つものであり続けられるはずで、世の中にある謎には科学こそが答えを提供できるのだ、という信念は、ほとんど信仰の域ですらあります。しかし、21世紀の初頭は、科学には答えられないことがたくさんある、ということに私達が気付き始めた時期でもあります。中には、社会的な、または、文化的なアプローチでのぞまなければならない事柄があるのだということに気付いたわけです。
そこに至るまでには、あらゆる学問が、“科学”であるフリをしている時代がありました。社会学、政治学、、、。何もかもが科学であるかのようにふるまいたがっていたのです。しかし、今は、科学的手法にも限界があることを、私達は段々と理解するようになりました。そして、人間が関わる事柄には、他の側面も大切であることを痛感するようになったのです。バランスこそが大事である、ということに。
科学がなしえた勝利は非常にパワフルでしたが、しかしその科学の強大な力を引き出したのは、詩やダンスや音楽、といったもので、オッペンハイマーも極めて文化的な人物でした。よく本を読んだし、ボードレールの詩などを引用したりもしています。彼は6つの言語を操ることが出来ましたし、アメリカ南西部の砂漠を歩きながら、外国語で書かれた書物を原語で読むこともしばしばでした。またインディアンへの興味も深く、研究所で働いていたインディアンの用務員やメイドをきちんと一人一人名前で呼んでいたといいます。科学者たちにとって、インディアンたちの文化にふれることは非常にエキサイティングなことであったので、実験室では高度なプルトニウム実験を行いながら、インディアン文化では神聖とされるシンボルをかたどったターコイズを銀に埋め込んだバックルを使用するほどでした。巨大な核融合実験を行うために、こういうわけで、ロス・アラモスという場所をオッペンハイマーは選択したのでした。
この作品で使われているテーマは、非常に良い題材であることは私も認めますが、限界もあります。結局のところ、広島で実際に起こったことを舞台上で再現することは不可能なのですから。長崎も。芸術には、科学と同様、おのずと限界というものがあるからです。
私がアーティストとして成し遂げられる何物も、実際に広島で起こった出来事に太刀打ちすることはできないし、あの言葉にならない20世紀最大の悲劇を完全に表現することも不可能です。
なので、ジョンと私は、最初の原子爆弾が投下されるまでの実質24時間という、小さな枠にフォーカスすることにしました。観客は、その後、広島でどんな事が起こるのか、ということを知っているわけで、その意味ではとてもギリシャ悲劇に似ています。観客誰もが知っている神話的な題材を扱うのは助かりますね、観客誰もがその後で何が起こるかということを知っている、という点において。その、誰もが知っている結果に至るまでの経緯を見せることは、大変興味深いプロセスだと思います。しかし、経緯を再現してみせ、自分たちに問いかけを行う、ということは、特殊効果映像を使用したハリウッド映画やプロパガンダ映像では普通おこらず、芸術によってこそ可能なことです。ハリウッド映画では、一分間にいくつも爆発が起こるのに対し、このオペラでは一晩中見ていても、からっきし爆発はおこらない。私達は、アメリカ人はもうすでに十分すぎるほど爆発を見ているのでは、と考えました。むしろ、ギリシャ悲劇では、目をかきだすところだとか、かき出された目がどんなのか、といったことを描くことではなく、“なぜ”この登場人物は目をかきだすのか、というところに焦点が置かれています。なので、私達の場合も、事実を再現していく間に提起される問題は、“なぜ、何が、これほどまでに才能に溢れる人たちを人類の歴史で最大の破壊兵器を生み出すことにかりたてたのか”ということなのです。
Q.その“なぜ”への答えは?
A.オペラにおいてだけでなく、人生において大事な問題のひとつは、私達が大きな歴史の力のなかに生きている、ということです。一人の人間には抗えない力。最もすぐれたオペラにもたびたび登場するのは、この“歴史の瞬間”とでもいうものの、空気とか雰囲気ではないでしょうか。登場人物は、全力で抗いますが、より大きな力にからめとられて抜けられなくなる。ロバート・オッペンハイマーも、どこかの時点で、“この原爆プロジェクトを脱けさせてください。”とも言えたはずです。しかし、そこにはあまりに大きすぎてもはや止められない何か、があった。同じことは1930年代のドイツについても言えますね。当時、個人の力ではとても止められないことのように感じられた。
そして、同じことを、今のアメリカ人も自国について感じているのです。歴史上の大きな出来事といっていい中東情勢が世界中を半ば麻痺させているのに、誰も何をどうしていいのかわからない。誰もが何かがおかしいと感じながら、誰もそれを止めることができない。何て不思議なことでしょうか。この作品で描かれている原爆にまつわる事柄には、これらすべての感覚が盛り込まれています。この原爆のプロジェクトには、ドイツとの競争、という英雄的な側面があったわけです。そしてドイツが1945年5月に降伏し、蓋をあけてみれば、ドイツ側には原爆プロジェクトなんてなかったことがはっきりした。丁度その時、日本はなんとかその足で踏ん張っている状態でした。足というよりはもうすでに膝が地面に落ちている、と形容してもいいほどでしたが。日本はすでにとても傷つき、荒廃していました。そして、多くの科学者たちはちょっと待てよ、と思ったのです。一体我々は何をしているのか?と。原爆が引き起こす結果は、それがナチスに対する闘いであれば、まだ人々を救う、という意味からも、罪悪感が薄くてすみますし、科学者自身もずっと自分にそう言い聞かせてきた。しかし、突然、すでに弱りきっている日本を原爆で攻撃するということは間違いではないのか?という疑問が頭をもたげてきたのです。そして、これは新しい軍力競争の時代を、冷戦時代をもたらすことになるのではないか?と。科学者たちはこれらの問いを自分たちに投げかけるようになった。それこそが、このオペラが、ドイツ降伏を起点に始まる理由です。1945年6月、原爆の最終段階のテストを急がされ、しかし、科学者の心には、これでいいのか?という思いが広がりはじめた時期でした。そしてそれに続いてあったのは、投下対象の選定とか、日本に原爆投下の予告を与えないこと、などの決定で、特に投下対象地の選定には、あえて、多くの労働者が住宅地としている場所を選んだのです。そして、原爆実験の日がやってきます。1945年7月16日、その夜の天気はひどいものでした。ずっと大きな嵐が来ると予想されていて、事実、その通りになったのです。しかし、その朝、トルーマン大統領は、ポツダムでスターリンとチャーチルとの会談に参加しなければならなかった。その会談に結果が間に合うよう、実験はその夜にどうしても行わなければならなかったのです。トルーマンは何が何でも、二人に、原爆実験の成功を発表しなければならなかった。トルーマンが知らなかったのは、ロス・アラモスにいるロシアのスパイのおかげで、スターリンには情報が筒抜けで、彼がトルーマンよりも原爆についてずっと多くのことをすでに知っていた、という事実でした。
というわけで、オペラの中では大嵐の中での実験の様子が描かれます。宇宙学、高等物理学の科学者たち、そして、雨の中で踊りを繰り広げるインディアンたち、、。色んな立場の、様々な“神”や“信条”をもつ人間がニュー・メキシコの同じ夜空の下にいて、人々の疑念や心配、勝利の感覚と敗北感の間に、あるビジョンが見えてきます。女性もこのビジョンに深く関わっています。このシーンのリブレットは、10年ほど前に一般公開されるようになった当時の機密文書の抜粋からなっています。なのでここでみなさんが舞台で見るものは、実際に語られた言葉です。そのことが、言葉の一つ一つに独特の重みを与えています。そして、歌う歌手にはそれに応じた責任というものが生まれました。その言葉にぴったり合った歌を歌い、演じるという責任です。
そして、多くの芸術家たちも色々な作品を生み出してきましたので、リブレットの残りの部分の大部分は彼らの詩によって構成されています。ボードレール、ヴァッドギーター、聖書、、それから女性詩人たちの詩。
ここに至るまでのことを振り返り、これでよかったのだろうか?という疑問を提示する意味で、キティ・オッペンハイマー役のためにジョン・アダムズが、アムステルダムの公演でこのような詩を付け加えました。
“We are hopes. You should have hoped us. We are dreams. You should have dreamed us.”
(私達は希望そのもの。だから、私たちの中に希望を見出すべきだったのに。
私達は夢そのもの。だから、私たちの中に夢を託すべきだったのに。)
私達がいま生きている時代は、再び、国の指導者たちが、戦争をすることしか知らない時代です。そして、それですら、あまり上手にできていない。多くの人が希望すら失ってしまいましたが、それでも、しかし、人間性は、まだ私達を待っているのです。
私達は希望そのもの。だから、私たちの中に希望を見出すべき,
私達は夢そのもの。だから、私たちの中に夢を託すべき,
“Calling our names, calling our names”
(私達の名前を呼んでいる、私達の名前を、、。)
2007年現在、冷戦の終わりに訪れたあの平和の感覚はどうなったのでしょう?夢や希望はまだずっと待ち続けています。このオペラを上演する最大の目的は、人々に、ここ十年ほどですっかりなりをひそめてしまった感のある、核兵器への自覚をもう一度目覚めさせることにあります。
ゴルバチョフと核完全撤廃を決意したときから、これは、イランの、パキスタンの、という問題ではなく、たった一つの核兵器ですら許さない、ということを意味したはずです。たった一つの兵器が、偶発的に、もしくは故意的に発射される可能性がある限り、世界のすべてにとって、それはもはや危機であるのです。全ての核兵器は撤廃されなければならず、私達にはその技術があるだけでなく、再度核兵器が製造されたなら、それをすぐに認知できる技術すらあるのです。どんな動きもすぐに探知できるのです。
今、世界は一つとなって、勇気とビジョンと正直さを持って決断を下し、何十億ドルという財源を、軍力ではなく、教育、医療、地域生活のためと平和活動に向けなおし、社会を繁栄させていかなければならないのです。そして、富める国から見れば驚くほどの貧困状態にあえいでいる、世界の3/4を占めている地域のための復興計画も大切です。この優先順位の再見直しこそ、最も重要です。
なので、もう一度原爆というトピックを持ち出し、人々の心に提示し、この誰も原爆の話などせず、幸せにショッピングに走って、問題を見て見ないふりをしている時代に、何を優先していくのか、ということを見直し、願わくは、希望や夢を、あらゆる世代に復活させること、、、
Q. が使命、ということですね。
A.(その通り、という風に微笑する。)
<予習編②に続く>
2006-7年シーズンに、疑心暗鬼で観に行った『始皇帝』で痛い目にあい、
ますますその思いを強くしたので、昨シーズンのフィリップ・グラス作曲による
『サティヤグラーハ Satyagraha』に至っては、完全シカトの素通り状態で、
一度も公演も観に行きませんでした。
オペラに行くことは、拷問や苦行じゃないんですから、自分の見たいものだけを見ればよい、
フィリップ・グラスを聴かなきゃ死んでしまう、というわけでもあるまいし、と。
その基準からすると、今年の『ドクター・アトミック』は、素通り演目の候補にあがっていたのですが、
今週土曜日のサブスクリプションの演目に入ってしまっているうえ、
エクスチェンジ(他の公演にチケットを交換してもらうこと)などの面倒くさいことが苦手な私なので、
図らずも鑑賞すべき演目に入ってしまったのです。
新作オペラは映像や音源が限られていて、予習がしにくく、
舞台を一回いきなり観ただけでは、いろいろなことが吸収しにくいタイプでもある私は、
それも新作オペラを避けたい理由の一つになっているのですが、
ありがたいことに、この『ドクター・アトミック』は、おそらく2007年と思われる、
アムステルダムでの公演がDVD化されています。
この作品は、2005年にSFO(サン・フランシスコ・オペラ)で初演されましたが、
その公演を観たメトのゲルプ支配人が、音楽には惚れたものの、演出が気に食わない、という理由で、
オリジナルのピーター・セラーズに変え、メトではペニー・ウルコックの演出で
焼きなおされることになりました。
わざわざ、このような演出家の変更を行ってまで持ってきたメト初演もの、ということで、
ゲルプ氏が今年力を入れている演目の一つで、ライブ・イン・HD(ライブ・ビューイング)
の演目にも含まれているので、日本で映像をご覧になる機会のある方もいらっしゃるかもしれません。
この『ドクター・アトミック』はSFOが最初に作品依頼の声をかけた作曲家のジョン・アダムズと共に、
いや、もしかするとそれ以上に演出家のピーター・セラーズが
コンセプトやアイディアの形成に深く関わっていたこともあり、
セラーズをメトでの演出から外したことに対する疑念の声が、批評家筋の一部から上がっていました。
先にふれたアムステルダムの公演のDVDを見るうち、いろいろ作品についても思うことがあったので、
それも簡単に後ほど触れるつもりですが、
作品よりもむしろ、付録で付いてきた映像の方が面白く、中でも、
ピーター・セラーズのインタビューは、大変興味深いものがあり、
中には、『ドクター・アトミック』のライブ・イン・HDを
観に行く、という物好き(失礼!)な方もいらっしゃるかも知れないので、
その内容をご紹介したいと思います。
ちなみに、この『ドクター・アトミック』は、”原爆の父”と呼ばれる、
J・ロバート・オッペンハイマーを中心に、原爆開発のための”マンハッタン計画”
にたずさわった人々の、実験を経て原爆投下に至るまでの心の葛藤を描いた物語です。
テーマがテーマなので、日本人にとっては興味がひかれる作品ではあります。
このセラーズという人は、独特の照れがあるのか、リハーサルのシーンなどを見ると、
まるで頭のてっぺんからお花が生えているような”たりらりらーん”系のお方に見えますが、
このインタビューを聞くと、実に誠実な姿勢でこの難しいテーマに挑んでいることがわかります。
バイオを見ると、日本を含むアジアの国で勉強をした時期もあるようで、そのせいもあるのか、
被爆した日本側への思いも深く、インタビューの間で感極まって涙を浮かべる瞬間もありました。
アメリカ人で、このように原爆や軍事の問題を見ている人もいる、という点も非常に興味深く、
急ぎ足のディクテーションなので、細かいニュアンスを訳し切れていない部分もあるとは思い、
あくまで意訳として掲載させていただきます。
また、なじみのない詩人の名前など、聞き取りづらく、私の判断で割愛させて頂いている部分もあります。
インタビューの中で触れられている事実に関しての真偽等については、
私の方では裏づけを取っておりませんので、その点はご了承ください。
 ピーター・セラーズへのインタビュー
ピーター・セラーズへのインタビュー 
Q.(第二次大戦の実際の映像をモニターで眺めているセラーズに向かって)
ピーター、どうしてこの映像をご覧になっているんですか?
A.『ドクター・アトミック』の舞台で念頭にあったのは、第二次世界大戦末の空気とか雰囲気を想起させることでした。ハリウッドでも何度もこういう試みはありましたが、しかしハリウッドが作ったものは、事実とはかけ離れていました。オペラを作る一つの理由は、歴史というものを提示するとき、それが観客側の想像を許容するメディアだからで、実際の映像や画像、特にプロパガンダものを越えたところにもっていけるからでした。プロパガンダはプロパガンダであるがゆえに、故意に何を見せているか、また何をあえて見せていないか、という問題が常にありますので。音楽とか詩というものは、センサーシップ(検閲)が届かないところのものを表現できるし、自由な連想というものを可能にします。
しかし、観客には、こういった自由な連想の中で、もっとリアルなものとして、実際の戦闘の激しさを感じてほしいという気持ちもありました。そして、あの戦争が各人の葛藤であったことを思えば、今の時代は、もっともこのような題材に適した時期なのではないかと思うのです。世界のほとんどの地域でなんらかの戦争・紛争が繰り広げられているし、ボタン一つで空戦が始まる、今はそんな自動化された戦争の時代だからです。
こういった戦争のスタイルは、第二次世界大戦の、日本への空爆をきっかけに生まれたものでした。いってみれば、PCから何かを印刷するかのような破壊の方法です。若き日のロバート・マクミランにより想起され、やがてベトナム戦争で完成を見るこの方法は、戦争を大きな数学的問題に置き換えてしまいました。実戦経験のない人間が、全く空中から戦争をコントロールするというやり方です。
このシステマティックな爆撃スタイルによって行われた東京大空襲は、第二次世界大戦の末期に位置する空襲ですが、この空襲こそは、いわゆる近代的な“絨毯爆撃(カーペット・ボミング)”のスタイルがとられた世界初の例といってもよく、この完全な“空中からの無敵の力”というスタイルは、今でもアメリカが取り続け、そして自らを超大国せしめている理由となっているわけですが、しかし、奇妙な点は、アメリカは、完全には日本との戦争に勝ちはしなかった、ということでした。原子爆弾のせいで、勝って気持ちのいい戦争でも、また、勝ったことが正しいと思える戦争でもなかった。また原子爆弾が結果としてもたらした、世界における軍事国としての優位な立場にもかかわらず、朝鮮においても、ベトナムにおいても、また、キューバ、エルサルバドル、ニカラグアにおいても、そして、今ならイラクやアフガニスタンもこの中に入るのでしょうが、何か奇妙な感覚が戦争から生まれるようになったのです。このように原爆によって無敵の力を持つということは、正しいあり方でも、正しい生き方でも、自分がこうありたい、という理想像とも違う、という感覚、また、戦争が、数字とか統計とか、何人が犠牲になったか、といったことによって戦われるようになり、もはや人が人としてでなく、ただの数字としてしか考えられなくなった、という事実に対する疑問が、今のアメリカが関わっている戦争の根本にあるのです。それなのに、私達は過去からは何一つ学んでいないかのようにも思われます。このことから、一旦、人々をこの第二次世界大戦末期という時代に引き戻してみることは有益ではないかと考えたのです。
第一次世界大戦では、犠牲者の80%が兵士でした。そして、20%が女性や子供たち。しかし、20世紀の終わりまでにこの数字は逆転してしまいました。現代の戦争では、そして、それは、まさにこの第二次世界大戦末を出発地点としているわけですが、亡くなった人の80%が武力を持たない女性や子供といった民間人です。そして、14%が兵士なのです。この数字は心に留めておく必要があります。 “空中からの力”によって、これほどまで多くの、自分の命を守る術をもたない民間人の命を奪う戦争があってもいいのか?ということです。
Q.なぜ、『ドクター・アトミック』なのでしょう?なぜ、今、原爆なのでしょう?
A.原爆こそは、究極の破壊の例であり、また、戦争こそは、人間を神とみなす究極の例ではないでしょうか?また、原爆の存在はアメリカの世界での位置づけを決める一因となったわけで、その延長線上に私達もいるわけです。そこで、ジョン・アダムズと私が思い立ったのは、このオペラを作ることでアメリカの歴史を描き、また同時に、大きなサイクルの中で、今、アメリカはどういう場所に立っているのか、ということを模索することでした。また、どのような豊かな専門性、知識、優秀さを備えた人々がアメリカという国を作っていったか、移民、難民、独裁政治を逃れてきた人々たちがどのようにしてアメリカ人となっていったか、そして彼らがどのようにしてアメリカという国を世界有数の科学大国にしていったか、、、このような、アメリカは“単なるアメリカ”なのではなく、自国では生活し続けることができなかった人たちをはじめとする“他の人たち”こそがアメリカであるということ、これらのことを今のアメリカ人がもう一度見直すというのは非常に大事なことだと思うのです。そして、現在、9/11テロが引き金となって導入された国土安全保障の考えの下、多くの科学の道を目指す外国人たちが、アメリカの大学で学んだり研究することを拒否されています。その結果、アメリカの主要大学の化学、物理、エンジニアリングといった学部は、大変な危機にさらされています。それは、アメリカが学生を受け入れず、世界をシャットアウトしてしまっているからです。外国からの優れた化学者たち、ルーマニアやハンガリーをはじめとする、当時は政治が落ち着かなかった小国から、独裁政治を逃れてやって来た人たちが、アメリカが成し遂げた業績に貢献したわけです。もちろん、ユダヤ人たちも。ホロコーストを逃れ、肉親たちが収容所に囚われながら。
こういったことは、今でも古くなるどころかますます鮮やかな像として、私達を捕らえています。何百万という難民たち、かつてないほど多くの難民たちが、今地球上には存在しているからです。大変な数の人たちが自国で生活し続けられない状況に瀕しているのです。
もう一点、『ドクター・アトミック』について言うなら、登場人物に奥行きがあり、ある意味、神話的でもある点でしょうか。科学者たちのある種の英雄的な部分には驚くほどです。自らの意識下にある良心と闘いながら、同時に、この世の神秘を解き明かす科学者としての任務を遂行し、チームとして協力しあいながら並々ならぬ献身を重ね、限界に挑戦し続ける姿勢、また、科学や物理学というものが、真にヒロイックで、世のために役立つものであり続けられるはずで、世の中にある謎には科学こそが答えを提供できるのだ、という信念は、ほとんど信仰の域ですらあります。しかし、21世紀の初頭は、科学には答えられないことがたくさんある、ということに私達が気付き始めた時期でもあります。中には、社会的な、または、文化的なアプローチでのぞまなければならない事柄があるのだということに気付いたわけです。
そこに至るまでには、あらゆる学問が、“科学”であるフリをしている時代がありました。社会学、政治学、、、。何もかもが科学であるかのようにふるまいたがっていたのです。しかし、今は、科学的手法にも限界があることを、私達は段々と理解するようになりました。そして、人間が関わる事柄には、他の側面も大切であることを痛感するようになったのです。バランスこそが大事である、ということに。
科学がなしえた勝利は非常にパワフルでしたが、しかしその科学の強大な力を引き出したのは、詩やダンスや音楽、といったもので、オッペンハイマーも極めて文化的な人物でした。よく本を読んだし、ボードレールの詩などを引用したりもしています。彼は6つの言語を操ることが出来ましたし、アメリカ南西部の砂漠を歩きながら、外国語で書かれた書物を原語で読むこともしばしばでした。またインディアンへの興味も深く、研究所で働いていたインディアンの用務員やメイドをきちんと一人一人名前で呼んでいたといいます。科学者たちにとって、インディアンたちの文化にふれることは非常にエキサイティングなことであったので、実験室では高度なプルトニウム実験を行いながら、インディアン文化では神聖とされるシンボルをかたどったターコイズを銀に埋め込んだバックルを使用するほどでした。巨大な核融合実験を行うために、こういうわけで、ロス・アラモスという場所をオッペンハイマーは選択したのでした。
この作品で使われているテーマは、非常に良い題材であることは私も認めますが、限界もあります。結局のところ、広島で実際に起こったことを舞台上で再現することは不可能なのですから。長崎も。芸術には、科学と同様、おのずと限界というものがあるからです。
私がアーティストとして成し遂げられる何物も、実際に広島で起こった出来事に太刀打ちすることはできないし、あの言葉にならない20世紀最大の悲劇を完全に表現することも不可能です。
なので、ジョンと私は、最初の原子爆弾が投下されるまでの実質24時間という、小さな枠にフォーカスすることにしました。観客は、その後、広島でどんな事が起こるのか、ということを知っているわけで、その意味ではとてもギリシャ悲劇に似ています。観客誰もが知っている神話的な題材を扱うのは助かりますね、観客誰もがその後で何が起こるかということを知っている、という点において。その、誰もが知っている結果に至るまでの経緯を見せることは、大変興味深いプロセスだと思います。しかし、経緯を再現してみせ、自分たちに問いかけを行う、ということは、特殊効果映像を使用したハリウッド映画やプロパガンダ映像では普通おこらず、芸術によってこそ可能なことです。ハリウッド映画では、一分間にいくつも爆発が起こるのに対し、このオペラでは一晩中見ていても、からっきし爆発はおこらない。私達は、アメリカ人はもうすでに十分すぎるほど爆発を見ているのでは、と考えました。むしろ、ギリシャ悲劇では、目をかきだすところだとか、かき出された目がどんなのか、といったことを描くことではなく、“なぜ”この登場人物は目をかきだすのか、というところに焦点が置かれています。なので、私達の場合も、事実を再現していく間に提起される問題は、“なぜ、何が、これほどまでに才能に溢れる人たちを人類の歴史で最大の破壊兵器を生み出すことにかりたてたのか”ということなのです。
Q.その“なぜ”への答えは?
A.オペラにおいてだけでなく、人生において大事な問題のひとつは、私達が大きな歴史の力のなかに生きている、ということです。一人の人間には抗えない力。最もすぐれたオペラにもたびたび登場するのは、この“歴史の瞬間”とでもいうものの、空気とか雰囲気ではないでしょうか。登場人物は、全力で抗いますが、より大きな力にからめとられて抜けられなくなる。ロバート・オッペンハイマーも、どこかの時点で、“この原爆プロジェクトを脱けさせてください。”とも言えたはずです。しかし、そこにはあまりに大きすぎてもはや止められない何か、があった。同じことは1930年代のドイツについても言えますね。当時、個人の力ではとても止められないことのように感じられた。
そして、同じことを、今のアメリカ人も自国について感じているのです。歴史上の大きな出来事といっていい中東情勢が世界中を半ば麻痺させているのに、誰も何をどうしていいのかわからない。誰もが何かがおかしいと感じながら、誰もそれを止めることができない。何て不思議なことでしょうか。この作品で描かれている原爆にまつわる事柄には、これらすべての感覚が盛り込まれています。この原爆のプロジェクトには、ドイツとの競争、という英雄的な側面があったわけです。そしてドイツが1945年5月に降伏し、蓋をあけてみれば、ドイツ側には原爆プロジェクトなんてなかったことがはっきりした。丁度その時、日本はなんとかその足で踏ん張っている状態でした。足というよりはもうすでに膝が地面に落ちている、と形容してもいいほどでしたが。日本はすでにとても傷つき、荒廃していました。そして、多くの科学者たちはちょっと待てよ、と思ったのです。一体我々は何をしているのか?と。原爆が引き起こす結果は、それがナチスに対する闘いであれば、まだ人々を救う、という意味からも、罪悪感が薄くてすみますし、科学者自身もずっと自分にそう言い聞かせてきた。しかし、突然、すでに弱りきっている日本を原爆で攻撃するということは間違いではないのか?という疑問が頭をもたげてきたのです。そして、これは新しい軍力競争の時代を、冷戦時代をもたらすことになるのではないか?と。科学者たちはこれらの問いを自分たちに投げかけるようになった。それこそが、このオペラが、ドイツ降伏を起点に始まる理由です。1945年6月、原爆の最終段階のテストを急がされ、しかし、科学者の心には、これでいいのか?という思いが広がりはじめた時期でした。そしてそれに続いてあったのは、投下対象の選定とか、日本に原爆投下の予告を与えないこと、などの決定で、特に投下対象地の選定には、あえて、多くの労働者が住宅地としている場所を選んだのです。そして、原爆実験の日がやってきます。1945年7月16日、その夜の天気はひどいものでした。ずっと大きな嵐が来ると予想されていて、事実、その通りになったのです。しかし、その朝、トルーマン大統領は、ポツダムでスターリンとチャーチルとの会談に参加しなければならなかった。その会談に結果が間に合うよう、実験はその夜にどうしても行わなければならなかったのです。トルーマンは何が何でも、二人に、原爆実験の成功を発表しなければならなかった。トルーマンが知らなかったのは、ロス・アラモスにいるロシアのスパイのおかげで、スターリンには情報が筒抜けで、彼がトルーマンよりも原爆についてずっと多くのことをすでに知っていた、という事実でした。
というわけで、オペラの中では大嵐の中での実験の様子が描かれます。宇宙学、高等物理学の科学者たち、そして、雨の中で踊りを繰り広げるインディアンたち、、。色んな立場の、様々な“神”や“信条”をもつ人間がニュー・メキシコの同じ夜空の下にいて、人々の疑念や心配、勝利の感覚と敗北感の間に、あるビジョンが見えてきます。女性もこのビジョンに深く関わっています。このシーンのリブレットは、10年ほど前に一般公開されるようになった当時の機密文書の抜粋からなっています。なのでここでみなさんが舞台で見るものは、実際に語られた言葉です。そのことが、言葉の一つ一つに独特の重みを与えています。そして、歌う歌手にはそれに応じた責任というものが生まれました。その言葉にぴったり合った歌を歌い、演じるという責任です。
そして、多くの芸術家たちも色々な作品を生み出してきましたので、リブレットの残りの部分の大部分は彼らの詩によって構成されています。ボードレール、ヴァッドギーター、聖書、、それから女性詩人たちの詩。
ここに至るまでのことを振り返り、これでよかったのだろうか?という疑問を提示する意味で、キティ・オッペンハイマー役のためにジョン・アダムズが、アムステルダムの公演でこのような詩を付け加えました。
“We are hopes. You should have hoped us. We are dreams. You should have dreamed us.”
(私達は希望そのもの。だから、私たちの中に希望を見出すべきだったのに。
私達は夢そのもの。だから、私たちの中に夢を託すべきだったのに。)
私達がいま生きている時代は、再び、国の指導者たちが、戦争をすることしか知らない時代です。そして、それですら、あまり上手にできていない。多くの人が希望すら失ってしまいましたが、それでも、しかし、人間性は、まだ私達を待っているのです。
私達は希望そのもの。だから、私たちの中に希望を見出すべき,
私達は夢そのもの。だから、私たちの中に夢を託すべき,
“Calling our names, calling our names”
(私達の名前を呼んでいる、私達の名前を、、。)
2007年現在、冷戦の終わりに訪れたあの平和の感覚はどうなったのでしょう?夢や希望はまだずっと待ち続けています。このオペラを上演する最大の目的は、人々に、ここ十年ほどですっかりなりをひそめてしまった感のある、核兵器への自覚をもう一度目覚めさせることにあります。
ゴルバチョフと核完全撤廃を決意したときから、これは、イランの、パキスタンの、という問題ではなく、たった一つの核兵器ですら許さない、ということを意味したはずです。たった一つの兵器が、偶発的に、もしくは故意的に発射される可能性がある限り、世界のすべてにとって、それはもはや危機であるのです。全ての核兵器は撤廃されなければならず、私達にはその技術があるだけでなく、再度核兵器が製造されたなら、それをすぐに認知できる技術すらあるのです。どんな動きもすぐに探知できるのです。
今、世界は一つとなって、勇気とビジョンと正直さを持って決断を下し、何十億ドルという財源を、軍力ではなく、教育、医療、地域生活のためと平和活動に向けなおし、社会を繁栄させていかなければならないのです。そして、富める国から見れば驚くほどの貧困状態にあえいでいる、世界の3/4を占めている地域のための復興計画も大切です。この優先順位の再見直しこそ、最も重要です。
なので、もう一度原爆というトピックを持ち出し、人々の心に提示し、この誰も原爆の話などせず、幸せにショッピングに走って、問題を見て見ないふりをしている時代に、何を優先していくのか、ということを見直し、願わくは、希望や夢を、あらゆる世代に復活させること、、、
Q. が使命、ということですね。
A.(その通り、という風に微笑する。)
<予習編②に続く>



















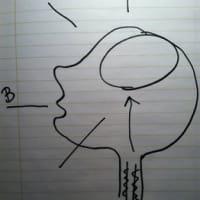
はい!私は見に行きます!
実はとても興味あるんです。
おお!娑羅さんがご覧になるとはまさに灯台もと暗しでした!
実は、『蝶々夫人』と同じメカニズムで、
この題材ゆえに、日本人の中には”あまり見たくない、、”という方もいらっしゃるのではないか、と危惧しています。
実演で観た感想はさきほどあげました。
ご覧になる方によって、作品への感想はいろいろだと思います。
純粋な音楽の演奏としては、非常にパワフルで聴きごたえがあったと思います。
何より、やはり、作品が、どんなに的外れ、的当たりであっても、
やはり、原爆を唯一経験したことのある国の人間として、
アメリカがこの問題をどのように見ているか、ということに無関心であるべきではないと思いますし、
コンテが若干苦手である私も、今は観てよかった、と思っています。
色んな意味で、”問題作”だと思います。
私の意見に対して、”いや、そうじゃない!”という意見も聴きたく、
多くの人に見ていただきたい気持ちはあるのですが、
果たしてライブ・ビューイングの稼働率はどうでしょうか?
娑羅さんのご感想をとっても楽しみにしています。