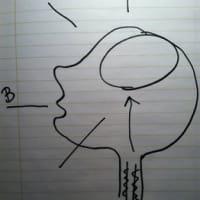すべてのフレーズ、いえ、すべての音が見所、聴き所ですが、字数に合わせて泣く泣く厳選。
第一幕
 いきなりスタート
いきなりスタート
序曲も前奏曲もなく、短い序奏のみですぐに結婚/借家斡旋屋ゴローとピンカートンの会話へ。
プッチーニの作品は、前奏曲序曲なしのいきなりスタート系が多い。
トゥーランドットしかり、ラ・ボエームしかり、トスカしかり。
オケには、その二人の会話に入るために序奏のテンポが落ちるその前の全ての音に
迫り来る悲劇を予感させるような緊迫感を込めてほしい。
ここがのっぺらぼうだったり、べたーんとした音だと、
”今日の公演を観に来た私ははずしてしまったのかもしれない”と、
不安になる一瞬でもあります。
 人はいいけど無力な男、シャープレスの登場
人はいいけど無力な男、シャープレスの登場
~ ピンカートンのアリア ”世界中どこでも Dovunque al mondo"
ピンカートンと蝶々さんの結婚式に参加するため、息をきらせながら、
ピンカートンが二束三文でお買い上げになった長崎港を望む丘の上の家に登ってくる駐長崎領事のシャープレス。
このシャープレス登場の部分の言葉とそれについているメロディーだけで、
結構なおじさんに違いないシャープレスがぜえぜえ言いながら大儀そうに丘を登ってくる様子が
目に浮かぶようです。
この作品でのプッチーニは、登場人物の性格描写はもちろん、
その心の動き、時間の変化、ある出来事が起こる瞬間、など、
何もかもを音で表現し尽くしていて本当に素晴らしい。
さて、ピンカートンは考えの至らぬ軽薄男ではあっても、完全な悪人ではない。
ここはポイントです。
彼は蝶々さんを意識的に苦しめようとしたわけではない。
無邪気さゆえの残酷さ。
これこそが蝶々さんを死においやる一要因です。(もう一つの要因については後ほど。)
ピンカートン役のテノールのキャラクターと歌には、
”悪気がないのに、それゆえに怖いその無邪気さ”が醸し出されていることが絶対条件。
思慮深い紳士であるところのシャープレスがやんわり非難するのをものともせず、
今度結婚する少女は現地妻に過ぎないこと、アメリカに帰ったら正妻(もちろんアメリカ人の)を
娶るつもりであることを屈託なく語るピンカートン。
その悪気なさが本当に怖いんだってば!ピンカートン!!!
悪気なさを炸裂させながら、世界中どこでも僕らさすらいのヤンキーは享楽に身をゆだねて好き勝手するのさ!
と歌う”世界中どこでも Dovunque al mondo"。
このあたりのピンカートンには多面性は必要なし。とにかく、無邪気に、
しかし、声楽的には、朗々とかつリリカルにその勘違いを歌い上げてほしい。
このピンカートン役、前編でも触れたとおり、CDなんかでは、名テノールが歌っていますが、
実演では、意外とビッグ・ネームが歌わない役です。
それには、彼がひどい男であるばかりか、そのひどさが、無邪気さ、間抜けさ、思慮のなさによっているという、
歌う側にとっては、はっきり言って非常に格好悪い役柄であるうえ、決め球となるようなスーパー・アリアもなし。
極端に言ってしまうと、蝶々夫人を支える準主役であり、決して主役ではありません。
またそのために、出番があまり多くなく(ほとんど一幕のみに集中)、雇うオペラハウス側からしても、
ビッグ・ネームのギャラを払うには、わりに合わない役柄である、という認識があるようです。
同じひどい男でも、パートはバリトンになってしまいますが、
『トスカ』のスカルピアや、『オテロ』のイヤーゴみたいな役だと、
悪の美学があるので、やりがいもあるというものでしょうが、
ピンカートンに、そんなこじゃれたものは一切ありません。ただ、格好悪さがあるのみ。
ゴローは、その歌う内容から、ネズミ男的なキャラクター(せこくてこすっからい男)として演じられ、
声も見た目もそんな風な人が担当することが多いのですが、
今シーズンのメトでのゴローに、私は目からうろこでした。
いなせなゴロー。これがなかなか良いのです。
今後のトレンドとして、いなせ路線のゴローが増えていくのか、
やっぱりネズミ男路線が定番として生き続けるのか、興味深いところです。
 蝶々さん、霞の向こうからあらわる! ”ああ、なんてきれいな空、素晴らしい海 Ah! Ah! quanto cielo! quanto mar! ”
蝶々さん、霞の向こうからあらわる! ”ああ、なんてきれいな空、素晴らしい海 Ah! Ah! quanto cielo! quanto mar! ”
ここはこのオペラの中でもっとも美しい場面の一つで、素晴らしい公演だと、
まるで霞の中から蝶々さんが現れるような、この世のものと思えぬ幻想的な音楽が聴けます。
なので、どんな形の演出をするにせよ、絶対にその美しさを邪魔してほしくない箇所でもあります。
まず、蝶々夫人に付き添ってきた親類縁者(ただし、女声のみの合唱)の声が聴こえ、
それにのるようにして、蝶々夫人の最初の言葉、Ancora un passo or via. Aspetta
(もう一息だわ。ちょっと待ってよ、待って。)
が聴こえてきます。ここからGiuと言って、みんなでお辞儀をするところまでは、
私はいつも息をひそめて舞台を見つめてしまう。
蝶々さんが歌う旋律は、登場してすぐに、割と高いレンジの音を、
しかも、柔らかい響きを込めつつ歌わなければならないということで、
さきほど、さらりと”素晴らしい公演だと、、”などと言いましたが、本当に難関。
さらに難易度を上げるために、最後の音をヴァリエーションでDesの音に上げるソプラノもいますが、
よほど高音に自信がない限り、上げても甲高い響きが出てしまって、
せっかくの挑戦が台無しになってしまうという、恐ろしい賭けの場所でもあります。
ちなみに、メトで昨シーズン(2006-7年)にこの蝶々さん役を歌ったドマスも、
今シーズン(2007-8年)歌ったラセットも、上げずにオリジナルの音で歌っていました。
 日本のメロと1、2、3!
日本のメロと1、2、3!
『蝶々夫人』では、作曲者プッチーニの取材力が炸裂、
越後獅子、さくらさくら、お江戸日本橋、宮さん宮さん、
かっぽれ、豊年節など、数々の日本の曲の断片が現れます。
そして、最もわかりやすいのが君が代のメロディー。
この作品では、”君が代”の旋律が日本を、”星条旗よ永遠なれ”の旋律が
アメリカを表現するのに繰り返し現われるので、
日本の国歌を”君が代”から他の曲に変えようという議論があるそうですが、
このオペラが存在し続ける限り、私としては、ありえない話です。
その、日本の旋律ですが、蝶々さんを歌うソプラノによって、微妙な違いがあるのも面白いところ。
日本の旋律の独特さを見事に歌いだしているソプラノは、この後に続く場の出来が楽しみになってきます。
蝶々さんの役が、至難の役と言われる理由は、
基本的にリリコ・スピントといわれる、叙情的でありながら力強い、という特定のカラーが声に必要とされること、
またとにかく最初から最後まで出ずっぱりで、とんでもないスタミナが必要であるということなどが挙げられますが、
私が一番大変だと思うのは、一幕、ニ幕、三幕と幕がすすむにつれ、
蝶々夫人が成長を遂げていき、それに応じてその変化を歌いわけられなければいけない、という点です。
特に、一幕で必要とされる、15歳の、まだ少女らしさを残した性格は、
リリコ・スピントの声質とやや相容れないので、歌い演じるのが難しい箇所であり、
ソプラノの歌唱センスと技術がおおいに試される幕でもあります。
その歌唱センスは、どのようにこの15歳の蝶々さんを演じようとしているか、ということに大きく左右されると思うのですが、
それが断片的に伺い知れるのが、”1、2、3、みんなでお辞儀をしましょう”の、
1、2、3の数え方。
まるで舌足らずの子供のように歌われる蝶々さん、
すでに芯の強さが伺えるようなしっかりした蝶々さん、いろいろです。
 ボンゾの奇襲攻撃~日本で一人ぼっちになった蝶々さん
ボンゾの奇襲攻撃~日本で一人ぼっちになった蝶々さん
こっそりと、自分の家の宗教(神道と思われる)を捨て、
ピンカートンのためにキリスト教に改宗していた蝶々さん。
この事実だけでも、彼女の思い込んだら一直線、な性格が伺いしれます。
いきなり結婚式の場にのりこんできたボンゾ(坊主)は全親類縁者の前でその事実を暴露、
怒った親類縁者は彼女を許さず、ピンカートンの元に彼女を置き去りにして、
去っていきます。
ここは、ドラマ上、非常に大事なシーン。
蝶々さんは、ここで、日本という国から拒絶され、アメリカ(物理的にではなく、
精神のよりどころとしてのアメリカ)に
自分の居場所を求めざるを得なくなるわけです。
観客は、すでにピンカートンが決して彼女に本当にアメリカという居場所を与えられる存在ではない、
というかそのつもりもないことを知っているだけに、胸がしめつけられますが、
もちろん、蝶々さんは、ピンカートンを信じきっています。
ボンゾが大暴れした後から、いきなり蝶々夫人の女中スズキが唱える祈りの言葉を経て愛の二重唱に流れ込んでいくまでの、あまりにもスムーズな音楽の流れは、本当に素晴らしい。
この巧みさにはいつもため息がでます。
 イタリア・オペラで最もロマンティックかつエロティックな愛の二重唱 ”もう夜も更けた Viene la sera ”
イタリア・オペラで最もロマンティックかつエロティックな愛の二重唱 ”もう夜も更けた Viene la sera ”
イタリア・オペラ一ロマンティックかつエロティックな、というこのタイトルに文句をつける輩には、
この私が飛び蹴りを食らわせます。
蝶々さんが婚礼衣装の帯を解いて夜着に着替えるという具体的な描写まであるこの二重唱。
今の映画のラブ・シーンのはしりといっても過言ではない。
そのうえに、こちらが赤面してしまいそうな、二人の睦言まで歌詞で歌われるのですから、
こわいものなしです。
しかし、そんなロマ&エロな見かけとは裏腹に、
ここ(特に二重唱の中盤以降)はオケがバックで大音量で鳴っているため、
蝶々さんとピンカートンは次々と畳み掛けるように現われる重量級の旋律を歌いこなさなければならず、
本当に大変。
この大変さが勝ってしまって、このシーンの本質が失われてしまっている二重唱を何度聴いたことか。。
ここで、”おお、なんとロマンチックな!”とか”なんとエロティックな!”と思わされる歌唱が
舞台から聴こえて来たら、歌っている歌手の二人に大感謝してください。
ここでも、星が瞬く音の描写とか、プッチーニの筆が炸裂していますし、
最後に大爆発するオケと二人の歌声は本当にエクスタティック。
ヴェルディの『オテロ』の二重唱と、第一位のタイトルを巡って激しく競い合っておりますが、
プッチーニの曲には、理屈でなく、五感に直接ふれてくるような生々しさがあるのが特徴ではないかと思います。
(逆にそれが、ヴェルディの洗練されたそれとは違って苦手、という人がいるのもある程度、わかります。)

第二幕
”駒鳥が次に巣をつくるころには(一年したら)”
という約束も虚しく、もう三年間、ピンカートンはアメリカに帰国したまま、日本に戻ってきていない。
 信じ続けて帰りを待つ蝶々さん~”ある晴れた日に Un bel di ”
信じ続けて帰りを待つ蝶々さん~”ある晴れた日に Un bel di ”
すでにピンカートンが残した金も底をつき、極貧生活に陥りはじめている蝶々さんとスズキ。
年の功と冷静な性格ゆえに、すでにピンカートンがもう蝶々さんの元には戻ってこない、
ということを薄々感じ始めているスズキが、泣き崩れる中、”馬鹿ね、彼は絶対帰ってくるんだから!”
と蝶々さんが歌う”ある晴れた日に”はあまりに有名なアリア。
歌詞で歌われる、ピンカートンが日本に戻ってくるときの模様をひたすら描写した
”水平線に煙がたなびいて、白い船があらわれ、
祝砲が打たれて、、”云々という箇所は、
幕の後半で、実際にピンカートンの船が長崎港に入港するときの様子と巧みに対応しており、
このオペラのリピーターは、思わずこの後に訪れるシーンに思いを馳せ、倍の量の涙を流すのです。
また、真ん中の、”すぐにピンカートンを迎えにはいかないで、じっとじらすの”という歌詞とあわせて、
このピンカートンが長崎に戻ってくる光景を、何度となく頭の中で繰り返したであろう蝶々さんのいじらしさが泣けます。
そんな蝶々さんのもとを、シャープレスとゴローが訪問。
すわ!良い知らせか?と浮き足だつ蝶々さん。
しかし、シャープレスがやってきたのは、ピンカートンからの手紙の内容を蝶々さんに伝えるため。
辛い内容であることを予感しているシャープレスがなかなか手紙の件を切り出せないでいるなか、
蝶々さんを新しくヤマドリという男性(ヤマドリ氏、自らがすでに数々の女性と関係があるため、
蝶々さんの過去は気にならないらしい。)と引き合わせようとするゴロー。
しかし、そんなヤマドリを蝶々さんは冷たくあしらいます。
まさにピンカートンもそんな無関心さ、冷たさで蝶々さんを見ているであろうとは思いもしないように。
蝶々さんの視点では、ゴローはひどい男であるし、
確かに、これでまた手数料を一稼ぎ、という腹がゴローにもないわけではないのですが、
しかし、彼は一方で、アメリカ人ピンカートンに捨てられた蝶々さんに対し、
同じ日本人として憐れみを感じており、むしろその気持ちこそ、
このヤマドリ斡旋の直接かつ最大の動機であると私は思っています。
いや、ヤマドリもそんな事情を知りながら、この話にのってくれているわけで、
この場面を見るたびに、ついこの二人の日本人男性と、そして、シャープレスの
蝶々さんへの思いやりが心に染みる。
しかし、もちろん蝶々さんは、そんな彼らの思いやりが理解できるほど大人な女性ではないのであって、
悲劇への道をまっしぐらに進んで行くのです。
 とばっちりを受けるシャープレス~ピンカートンからの手紙
とばっちりを受けるシャープレス~ピンカートンからの手紙
ついに手紙の件を切り出すきっかけを得たシャープレス。
ごく静かなオケの伴奏にのせて始まる、手紙の二重唱("
Legger con me volete questa lettera")は、涙腺崩壊必至の場面。
ここで注目は、この手紙におよんでなお、ピンカートンの野郎は、
直接に蝶々さんに話しかけるのではなく、あくまで、シャープレスに宛てた手紙になっている点です。
いやー、この台本、本当にうまいです。
この設定だけで、あいかわらずピンカートンが、自分で引き起こしたことの顛末すら、
自分で責任を持って片付けることのできない、赤ん坊のような男であることを十分伝えきっているのですから。
そして、とばっちりを受けるシャープレス。アンラッキーな人です。
この二重唱、シャープレスが手紙を読み上げ、蝶々さんが合いの手を入れる形になっているのですが、
実にせつない。
特に、”もう蝶々さんは、私のことなど覚えていないかもしれないが”という手紙の一節に、
蝶々さんが、”覚えていないですって?スズキ、お前からも言ってちょうだい!
もう僕のことを覚えていないかもしれない、だなんて!”
と答え、つい今まで抑えていた思いのたけがあふれ出してしまう箇所は、
旋律の美しさとあいまって、我々観客もつい胸が痛くなるような場面です。
手紙の中で、自分が再度長崎に入港することを伝えるピンカートン。
あまりの嬉しさに、蝶々さんは、この後に続く、シャープレスへの
”あなたから、適切なご配慮を頂き、彼女に心の準備をさせてほしいのです”
という言葉の真意を理解できません。
しかし、シャープレスは、さすがに大人ですから、いち早くその意味を理解し、
蝶々さんに、”もしこのまま彼がずっとあなたのもとに帰ってこなかったら、どうしますか?”という言葉で、
その手紙の本意を彼女に伝えようとします。
ここで初めて、蝶々さんは、今までゆるぎのなかった自分の心に、
黒い雲が垂れ込めてくるのを感じるわけです。オケがすでにそんな彼女の心の動きを描写していて見事ですが、
もちろん蝶々さん役のソプラノも、歌で彼女が感じたその不安を表現せねばなりません。
ついに”ヤマドリのプロポーズを受けては?”と駄目押しするシャープレス。
自尊心を傷つけられ、”帰ってください!”と言い放つ蝶々さんの様子に、
いかに彼女の気持ちを傷つけたかを悟って、愚かなことを言いました、と詫びるシャープレス。
この後の蝶々さんの、
Oh, mi fate tanto male, tanto male, tanto, tanto!
(ああ、あなたは本当にひどいことをされました。とても、とても!)
という言葉は、今やシャープレスという、ピンカートンおよびアメリカという世界への、
架け橋も今や失おうとしているのでは?という蝶々さんの不安と、
その向こうにある、ピンカートンを失うということ、および自らの死への予感が凝縮されている大事なフレーズです。
(一枚目の写真はレナータ・テバルディ、二枚目はマリア・カラス)
<後編 その2に続く>
第一幕
 いきなりスタート
いきなりスタート序曲も前奏曲もなく、短い序奏のみですぐに結婚/借家斡旋屋ゴローとピンカートンの会話へ。
プッチーニの作品は、前奏曲序曲なしのいきなりスタート系が多い。
トゥーランドットしかり、ラ・ボエームしかり、トスカしかり。
オケには、その二人の会話に入るために序奏のテンポが落ちるその前の全ての音に
迫り来る悲劇を予感させるような緊迫感を込めてほしい。
ここがのっぺらぼうだったり、べたーんとした音だと、
”今日の公演を観に来た私ははずしてしまったのかもしれない”と、
不安になる一瞬でもあります。
 人はいいけど無力な男、シャープレスの登場
人はいいけど無力な男、シャープレスの登場 ~ ピンカートンのアリア ”世界中どこでも Dovunque al mondo"
ピンカートンと蝶々さんの結婚式に参加するため、息をきらせながら、
ピンカートンが二束三文でお買い上げになった長崎港を望む丘の上の家に登ってくる駐長崎領事のシャープレス。
このシャープレス登場の部分の言葉とそれについているメロディーだけで、
結構なおじさんに違いないシャープレスがぜえぜえ言いながら大儀そうに丘を登ってくる様子が
目に浮かぶようです。
この作品でのプッチーニは、登場人物の性格描写はもちろん、
その心の動き、時間の変化、ある出来事が起こる瞬間、など、
何もかもを音で表現し尽くしていて本当に素晴らしい。
さて、ピンカートンは考えの至らぬ軽薄男ではあっても、完全な悪人ではない。
ここはポイントです。
彼は蝶々さんを意識的に苦しめようとしたわけではない。
無邪気さゆえの残酷さ。
これこそが蝶々さんを死においやる一要因です。(もう一つの要因については後ほど。)
ピンカートン役のテノールのキャラクターと歌には、
”悪気がないのに、それゆえに怖いその無邪気さ”が醸し出されていることが絶対条件。
思慮深い紳士であるところのシャープレスがやんわり非難するのをものともせず、
今度結婚する少女は現地妻に過ぎないこと、アメリカに帰ったら正妻(もちろんアメリカ人の)を
娶るつもりであることを屈託なく語るピンカートン。
その悪気なさが本当に怖いんだってば!ピンカートン!!!
悪気なさを炸裂させながら、世界中どこでも僕らさすらいのヤンキーは享楽に身をゆだねて好き勝手するのさ!
と歌う”世界中どこでも Dovunque al mondo"。
このあたりのピンカートンには多面性は必要なし。とにかく、無邪気に、
しかし、声楽的には、朗々とかつリリカルにその勘違いを歌い上げてほしい。
このピンカートン役、前編でも触れたとおり、CDなんかでは、名テノールが歌っていますが、
実演では、意外とビッグ・ネームが歌わない役です。
それには、彼がひどい男であるばかりか、そのひどさが、無邪気さ、間抜けさ、思慮のなさによっているという、
歌う側にとっては、はっきり言って非常に格好悪い役柄であるうえ、決め球となるようなスーパー・アリアもなし。
極端に言ってしまうと、蝶々夫人を支える準主役であり、決して主役ではありません。
またそのために、出番があまり多くなく(ほとんど一幕のみに集中)、雇うオペラハウス側からしても、
ビッグ・ネームのギャラを払うには、わりに合わない役柄である、という認識があるようです。
同じひどい男でも、パートはバリトンになってしまいますが、
『トスカ』のスカルピアや、『オテロ』のイヤーゴみたいな役だと、
悪の美学があるので、やりがいもあるというものでしょうが、
ピンカートンに、そんなこじゃれたものは一切ありません。ただ、格好悪さがあるのみ。
ゴローは、その歌う内容から、ネズミ男的なキャラクター(せこくてこすっからい男)として演じられ、
声も見た目もそんな風な人が担当することが多いのですが、
今シーズンのメトでのゴローに、私は目からうろこでした。
いなせなゴロー。これがなかなか良いのです。
今後のトレンドとして、いなせ路線のゴローが増えていくのか、
やっぱりネズミ男路線が定番として生き続けるのか、興味深いところです。
 蝶々さん、霞の向こうからあらわる! ”ああ、なんてきれいな空、素晴らしい海 Ah! Ah! quanto cielo! quanto mar! ”
蝶々さん、霞の向こうからあらわる! ”ああ、なんてきれいな空、素晴らしい海 Ah! Ah! quanto cielo! quanto mar! ”ここはこのオペラの中でもっとも美しい場面の一つで、素晴らしい公演だと、
まるで霞の中から蝶々さんが現れるような、この世のものと思えぬ幻想的な音楽が聴けます。
なので、どんな形の演出をするにせよ、絶対にその美しさを邪魔してほしくない箇所でもあります。
まず、蝶々夫人に付き添ってきた親類縁者(ただし、女声のみの合唱)の声が聴こえ、
それにのるようにして、蝶々夫人の最初の言葉、Ancora un passo or via. Aspetta
(もう一息だわ。ちょっと待ってよ、待って。)
が聴こえてきます。ここからGiuと言って、みんなでお辞儀をするところまでは、
私はいつも息をひそめて舞台を見つめてしまう。
蝶々さんが歌う旋律は、登場してすぐに、割と高いレンジの音を、
しかも、柔らかい響きを込めつつ歌わなければならないということで、
さきほど、さらりと”素晴らしい公演だと、、”などと言いましたが、本当に難関。
さらに難易度を上げるために、最後の音をヴァリエーションでDesの音に上げるソプラノもいますが、
よほど高音に自信がない限り、上げても甲高い響きが出てしまって、
せっかくの挑戦が台無しになってしまうという、恐ろしい賭けの場所でもあります。
ちなみに、メトで昨シーズン(2006-7年)にこの蝶々さん役を歌ったドマスも、
今シーズン(2007-8年)歌ったラセットも、上げずにオリジナルの音で歌っていました。
 日本のメロと1、2、3!
日本のメロと1、2、3!『蝶々夫人』では、作曲者プッチーニの取材力が炸裂、
越後獅子、さくらさくら、お江戸日本橋、宮さん宮さん、
かっぽれ、豊年節など、数々の日本の曲の断片が現れます。
そして、最もわかりやすいのが君が代のメロディー。
この作品では、”君が代”の旋律が日本を、”星条旗よ永遠なれ”の旋律が
アメリカを表現するのに繰り返し現われるので、
日本の国歌を”君が代”から他の曲に変えようという議論があるそうですが、
このオペラが存在し続ける限り、私としては、ありえない話です。
その、日本の旋律ですが、蝶々さんを歌うソプラノによって、微妙な違いがあるのも面白いところ。
日本の旋律の独特さを見事に歌いだしているソプラノは、この後に続く場の出来が楽しみになってきます。
蝶々さんの役が、至難の役と言われる理由は、
基本的にリリコ・スピントといわれる、叙情的でありながら力強い、という特定のカラーが声に必要とされること、
またとにかく最初から最後まで出ずっぱりで、とんでもないスタミナが必要であるということなどが挙げられますが、
私が一番大変だと思うのは、一幕、ニ幕、三幕と幕がすすむにつれ、
蝶々夫人が成長を遂げていき、それに応じてその変化を歌いわけられなければいけない、という点です。
特に、一幕で必要とされる、15歳の、まだ少女らしさを残した性格は、
リリコ・スピントの声質とやや相容れないので、歌い演じるのが難しい箇所であり、
ソプラノの歌唱センスと技術がおおいに試される幕でもあります。
その歌唱センスは、どのようにこの15歳の蝶々さんを演じようとしているか、ということに大きく左右されると思うのですが、
それが断片的に伺い知れるのが、”1、2、3、みんなでお辞儀をしましょう”の、
1、2、3の数え方。
まるで舌足らずの子供のように歌われる蝶々さん、
すでに芯の強さが伺えるようなしっかりした蝶々さん、いろいろです。
 ボンゾの奇襲攻撃~日本で一人ぼっちになった蝶々さん
ボンゾの奇襲攻撃~日本で一人ぼっちになった蝶々さんこっそりと、自分の家の宗教(神道と思われる)を捨て、
ピンカートンのためにキリスト教に改宗していた蝶々さん。
この事実だけでも、彼女の思い込んだら一直線、な性格が伺いしれます。
いきなり結婚式の場にのりこんできたボンゾ(坊主)は全親類縁者の前でその事実を暴露、
怒った親類縁者は彼女を許さず、ピンカートンの元に彼女を置き去りにして、
去っていきます。
ここは、ドラマ上、非常に大事なシーン。
蝶々さんは、ここで、日本という国から拒絶され、アメリカ(物理的にではなく、
精神のよりどころとしてのアメリカ)に
自分の居場所を求めざるを得なくなるわけです。
観客は、すでにピンカートンが決して彼女に本当にアメリカという居場所を与えられる存在ではない、
というかそのつもりもないことを知っているだけに、胸がしめつけられますが、
もちろん、蝶々さんは、ピンカートンを信じきっています。
ボンゾが大暴れした後から、いきなり蝶々夫人の女中スズキが唱える祈りの言葉を経て愛の二重唱に流れ込んでいくまでの、あまりにもスムーズな音楽の流れは、本当に素晴らしい。
この巧みさにはいつもため息がでます。
 イタリア・オペラで最もロマンティックかつエロティックな愛の二重唱 ”もう夜も更けた Viene la sera ”
イタリア・オペラで最もロマンティックかつエロティックな愛の二重唱 ”もう夜も更けた Viene la sera ”イタリア・オペラ一ロマンティックかつエロティックな、というこのタイトルに文句をつける輩には、
この私が飛び蹴りを食らわせます。
蝶々さんが婚礼衣装の帯を解いて夜着に着替えるという具体的な描写まであるこの二重唱。
今の映画のラブ・シーンのはしりといっても過言ではない。
そのうえに、こちらが赤面してしまいそうな、二人の睦言まで歌詞で歌われるのですから、
こわいものなしです。
しかし、そんなロマ&エロな見かけとは裏腹に、
ここ(特に二重唱の中盤以降)はオケがバックで大音量で鳴っているため、
蝶々さんとピンカートンは次々と畳み掛けるように現われる重量級の旋律を歌いこなさなければならず、
本当に大変。
この大変さが勝ってしまって、このシーンの本質が失われてしまっている二重唱を何度聴いたことか。。
ここで、”おお、なんとロマンチックな!”とか”なんとエロティックな!”と思わされる歌唱が
舞台から聴こえて来たら、歌っている歌手の二人に大感謝してください。
ここでも、星が瞬く音の描写とか、プッチーニの筆が炸裂していますし、
最後に大爆発するオケと二人の歌声は本当にエクスタティック。
ヴェルディの『オテロ』の二重唱と、第一位のタイトルを巡って激しく競い合っておりますが、
プッチーニの曲には、理屈でなく、五感に直接ふれてくるような生々しさがあるのが特徴ではないかと思います。
(逆にそれが、ヴェルディの洗練されたそれとは違って苦手、という人がいるのもある程度、わかります。)

第二幕
”駒鳥が次に巣をつくるころには(一年したら)”
という約束も虚しく、もう三年間、ピンカートンはアメリカに帰国したまま、日本に戻ってきていない。
 信じ続けて帰りを待つ蝶々さん~”ある晴れた日に Un bel di ”
信じ続けて帰りを待つ蝶々さん~”ある晴れた日に Un bel di ”すでにピンカートンが残した金も底をつき、極貧生活に陥りはじめている蝶々さんとスズキ。
年の功と冷静な性格ゆえに、すでにピンカートンがもう蝶々さんの元には戻ってこない、
ということを薄々感じ始めているスズキが、泣き崩れる中、”馬鹿ね、彼は絶対帰ってくるんだから!”
と蝶々さんが歌う”ある晴れた日に”はあまりに有名なアリア。
歌詞で歌われる、ピンカートンが日本に戻ってくるときの模様をひたすら描写した
”水平線に煙がたなびいて、白い船があらわれ、
祝砲が打たれて、、”云々という箇所は、
幕の後半で、実際にピンカートンの船が長崎港に入港するときの様子と巧みに対応しており、
このオペラのリピーターは、思わずこの後に訪れるシーンに思いを馳せ、倍の量の涙を流すのです。
また、真ん中の、”すぐにピンカートンを迎えにはいかないで、じっとじらすの”という歌詞とあわせて、
このピンカートンが長崎に戻ってくる光景を、何度となく頭の中で繰り返したであろう蝶々さんのいじらしさが泣けます。
そんな蝶々さんのもとを、シャープレスとゴローが訪問。
すわ!良い知らせか?と浮き足だつ蝶々さん。
しかし、シャープレスがやってきたのは、ピンカートンからの手紙の内容を蝶々さんに伝えるため。
辛い内容であることを予感しているシャープレスがなかなか手紙の件を切り出せないでいるなか、
蝶々さんを新しくヤマドリという男性(ヤマドリ氏、自らがすでに数々の女性と関係があるため、
蝶々さんの過去は気にならないらしい。)と引き合わせようとするゴロー。
しかし、そんなヤマドリを蝶々さんは冷たくあしらいます。
まさにピンカートンもそんな無関心さ、冷たさで蝶々さんを見ているであろうとは思いもしないように。
蝶々さんの視点では、ゴローはひどい男であるし、
確かに、これでまた手数料を一稼ぎ、という腹がゴローにもないわけではないのですが、
しかし、彼は一方で、アメリカ人ピンカートンに捨てられた蝶々さんに対し、
同じ日本人として憐れみを感じており、むしろその気持ちこそ、
このヤマドリ斡旋の直接かつ最大の動機であると私は思っています。
いや、ヤマドリもそんな事情を知りながら、この話にのってくれているわけで、
この場面を見るたびに、ついこの二人の日本人男性と、そして、シャープレスの
蝶々さんへの思いやりが心に染みる。
しかし、もちろん蝶々さんは、そんな彼らの思いやりが理解できるほど大人な女性ではないのであって、
悲劇への道をまっしぐらに進んで行くのです。
 とばっちりを受けるシャープレス~ピンカートンからの手紙
とばっちりを受けるシャープレス~ピンカートンからの手紙ついに手紙の件を切り出すきっかけを得たシャープレス。
ごく静かなオケの伴奏にのせて始まる、手紙の二重唱("
Legger con me volete questa lettera")は、涙腺崩壊必至の場面。
ここで注目は、この手紙におよんでなお、ピンカートンの野郎は、
直接に蝶々さんに話しかけるのではなく、あくまで、シャープレスに宛てた手紙になっている点です。
いやー、この台本、本当にうまいです。
この設定だけで、あいかわらずピンカートンが、自分で引き起こしたことの顛末すら、
自分で責任を持って片付けることのできない、赤ん坊のような男であることを十分伝えきっているのですから。
そして、とばっちりを受けるシャープレス。アンラッキーな人です。
この二重唱、シャープレスが手紙を読み上げ、蝶々さんが合いの手を入れる形になっているのですが、
実にせつない。
特に、”もう蝶々さんは、私のことなど覚えていないかもしれないが”という手紙の一節に、
蝶々さんが、”覚えていないですって?スズキ、お前からも言ってちょうだい!
もう僕のことを覚えていないかもしれない、だなんて!”
と答え、つい今まで抑えていた思いのたけがあふれ出してしまう箇所は、
旋律の美しさとあいまって、我々観客もつい胸が痛くなるような場面です。
手紙の中で、自分が再度長崎に入港することを伝えるピンカートン。
あまりの嬉しさに、蝶々さんは、この後に続く、シャープレスへの
”あなたから、適切なご配慮を頂き、彼女に心の準備をさせてほしいのです”
という言葉の真意を理解できません。
しかし、シャープレスは、さすがに大人ですから、いち早くその意味を理解し、
蝶々さんに、”もしこのまま彼がずっとあなたのもとに帰ってこなかったら、どうしますか?”という言葉で、
その手紙の本意を彼女に伝えようとします。
ここで初めて、蝶々さんは、今までゆるぎのなかった自分の心に、
黒い雲が垂れ込めてくるのを感じるわけです。オケがすでにそんな彼女の心の動きを描写していて見事ですが、
もちろん蝶々さん役のソプラノも、歌で彼女が感じたその不安を表現せねばなりません。
ついに”ヤマドリのプロポーズを受けては?”と駄目押しするシャープレス。
自尊心を傷つけられ、”帰ってください!”と言い放つ蝶々さんの様子に、
いかに彼女の気持ちを傷つけたかを悟って、愚かなことを言いました、と詫びるシャープレス。
この後の蝶々さんの、
Oh, mi fate tanto male, tanto male, tanto, tanto!
(ああ、あなたは本当にひどいことをされました。とても、とても!)
という言葉は、今やシャープレスという、ピンカートンおよびアメリカという世界への、
架け橋も今や失おうとしているのでは?という蝶々さんの不安と、
その向こうにある、ピンカートンを失うということ、および自らの死への予感が凝縮されている大事なフレーズです。
(一枚目の写真はレナータ・テバルディ、二枚目はマリア・カラス)
<後編 その2に続く>