
いよいよ15日の週は、ライブ・イン・HD(ライブ・ビューイング)でもちらりと紹介されていた、
ナショナル・カウンシル(映画に収められているものと年度が違うと思われますが、
ナショナル・カウンシルとは何ぞや?ということはこちらで少しご紹介しました。)の様子を収めた
映画『The Audition』のプレビュー、
パヴァロッティを偲んでメトで演奏されるヴェルディ・レクイエム、
(いずれも、レポをあげるつもりでおります。お楽しみに!)
そして、22日の月曜日はいよいよメトの2008-9年シーズンの開始、ということで、
このブログも本格始動モードに入りますが、その前に、夏休みの特別企画として、
何本か、メト以外のオペラハウスによるオペラ公演の映像を視聴する機会がありました。
視聴した場所は我が家。たまには愛犬と戯れつつ、こうしてリラックスしながらオペラを観るのもよいものです。
このブログを通じてお知り合いになった方から、映像を提供頂きました。お礼を申し上げます。
どのオペラハウスのものでも、どんな公演でも、こうして映像にふれることは、
大変興味深く、勉強になるので、どんな感想を持ったとしても、
見て損した!時間を無駄にした!と思うことはありません。
いつもの当ブログのモットー通り、思った通りを書き連ねることになりますが、
その点だけは強調させてください。では第一弾、行きましょう!
何本か頂いた録画映像の中から、やっぱり最初に選んでしまったのが『蝶々夫人』。
今までこのブログで何度も『蝶々夫人』は私の大好きな演目の一つであることを開陳して参りました。
お弁当の中に大好物の食べ物が入っていたら、まずそれに箸が伸びるタイプです。
これは2004年にミラノのアルチンボルディ劇場で、スカラ座のオケと合唱で行われた公演。
浅利慶太の演出、森英恵の衣装、照明や舞台美術にも日本人があたり、指揮はバルトレッティ。
蝶々夫人役を歌うのはニテスクというソプラノで、残念ながら私は一度も生で彼女の歌を聴いたことがないのですが、
この公演を聴く限り、冒頭でやや声の伸びがないというか、締め付けられているような音になっている個所、
また音が下がり気味になっている個所が見られますが、尻上がりによくなっていきます。
登場の場面での最後のオプショナルの高音は出さずじまい、
それ以外の個所でも特に一幕で、高音域で、やや音程を含め安定感を欠く場面がありましたが、
逆に低音域ではメゾのような深い響きがあり、
声の質そのものはこの役には悪くないものを持っていると思います。
少しぽちゃっとした体型ですが、この役はぎすぎすした声で歌われてもきついので、
もしぽちゃっとしていることでふくよかな声が出ているとするなら、それはそれでよい。
むしろ、歴代蝶々さんの中ではルックスも仕草も悪くありません。
一幕15歳、ニ幕目以降18歳であるはずの蝶々さんにしては、どちらも少し、
やや年齢がそれよりも上のような印象を歌唱が与えるのと、
最後の”私の坊や Tu, tu, Piccolo Iddio"では、オケよりも早く音符を畳んでしまっていたり、
少しスタミナ切れしたかな?と思わせるのは残念ですが、全体的には良い歌唱だと思います。
ピンカートンを歌うのは、ロベルト・アロニカ。
彼は生で何度か聴いたことがありますが、いつもことごとく期待を裏切られて来たので、
私の中では、ほとんど”存在しないテノール”化していましたが、
おやおや、この公演ではがんばっているではありませんか!
ほんの少しオケから走ってしまうくせがあるのを除いては。
しかし、あいかわらず、顔が四角い、、。メイクがさらにそれを助長しています。
シャープレスは、アガーケ。同情心ある、情け深いシャープレス、という、
最も多く見られるアプローチの仕方でこの役を歌っていました。
スズキはケシアン。表情が常に深刻でやや鬱陶しい感じがしますが、
深くていい声を持っていて、ニテスクとの声の相性がよいのはプラス。
蝶々夫人とスズキの二重唱の場面では、これは大きなボーナスです。
ゴローがものすごく歳をとっているのもおもしろい。海千山千な感じがよく出てます。
しかし、なんといってもこの公演の素晴らしいのはオケと合唱。
というか、ソリストよりもオケと合唱が主役のような感じすらするほどです。
ハミング・コーラスの合唱のそれは素晴らしいこと!!
そして、シャープレスが蝶々さんに”ピンカートンがこのまま帰って来なかったらどうしますか?”
と尋ねる個所や、大砲の音の後のオケの音は!!!すごい表現力です。
バルトレッティのような職人芸指揮者が今やほとんど不在なのは本当に残念なことです。
というわけで、演奏する側はなかなか頑張っているのですが、私、実はこの公演の足をひっぱっているのは
演出をはじめとする日本人チームではないか、、?と感じました。
もちろん、切り絵を思わせる背景とか、着物などのデザイン、微妙な色合いの照明、
またおそらく、現在、『蝶々夫人』のいろいろなプロダクションに
多用される(メトの2006年プレミアの演出もその一例)ハシリになったのではないかと
思われる黒子の使用、など、日本人スタッフならではの、
美しい場面、面白いアイディアがあるにはあるのですが、同じくらいに問題も多い。
まず、衣装。日本人の諸役はいいとして、このピンカートンの衣装はどうでしょう?!
軍服はJALのパイロットみたいだし、スカイブルーのジャケットに至っては、何と言っていいのやら、、。
私たちが、非日本人のデザインした蝶々さんの着物を見て”何か変”と思うのと同様に、
このピンカートンの衣装も”何か変”。
この演出では、基本的には日本”らしさ”を大事にしようとしているはずなのですが、
それなら、アメリカ”らしさ”も大事にしなくては、アンバランスです。
森英恵といえば、企業や学校の制服のデザインによく登用されていましたが、
何となく、このピンカートンの衣装も、その延長のような、、。
オペラの衣装デザインが、企業のための制服のデザインの延長ではあまりにも悲しい。
次に、これは演出家の演技付けの力量か、歌う歌手の演技力量(の不足)か、判断が難しいところですが、
現在のトレンドと比べると、この公演では、いかにも歌手が直立不動で立って歌っているシーンが多い。
まあ、数年前まではこれでも良かったのかも知れませんが、今や、オペラの公演も
HDに乗ったり、DVD化されたりする時代。
最近の、歌手がひっきりなしに歌って動いて、という舞台に比べると、
のどかというか、時代の流れを感じます。
さて、そんな中でいきなり飛び出すのが、一幕最後のピンカートンの舌なめずり。
あろうことか、蝶々さんを今や自分のものに!と盛り上がっているピンカートンが
愛の二重唱の途中で舌なめずりをするのです!!!!
ここの、このピンカートンをあまりにもの軽薄男に貶めたこの演出には私は大反対です。
この二重唱を聴いて、こんな舌なめずりが頭に浮かぶのか?浅利慶太という人は?
人間の感情の、簡単に白だの、黒だの、と簡単にラベルを貼れない複雑さ。
そのことが描かれているところに、オペラの、いえ、全てのアートフォームの素晴らしさがあるのでは?
もちろん、ピンカートンは、まさに蝶々さんとラブ!と盛り上がっていることは間違いなく、
よって、この二重唱がイタリアもののオペラの中でも一、二を争うエロティックな二重唱、
といわれる由縁なのですが、
エロティックはただの助平と同じではないでしょう。
この二重唱の音楽を聴けば、スケベ心を超えた何かがピンカートンの心の中にあったことははっきりしている。
先立つ場面で、シャープレスに”蝶々さんのことを愛しているのか?”と聞かれ、
”わからない”と答えたピンカートンの心情はそこにあるのです。
”愛している”とは即答しませんが、”もちろん遊びさ”とも即答しない。
その感情こそを、この二重唱では表現してほしいのです。
本当の愛ではないかも知れないけれど、スケベ心とも違う何か(恋でも、情欲でも、
何でもいいですが)があったはずなのです。
それから、この愛の二重唱で、舞台上、黒子がうろうろする、これも私には許せない。
黒子を使うアイディア自体は悪いこととは思いませんが、灯篭を持った黒子を、
この二重唱の途中で登場させるのはなぜなのか。
この二重唱でのピンカートンと蝶々夫人は、もう”二人だけの世界”状態なのに。
まるで、二人が愛し合っている途中の寝室に、他人が土足で入り込むような無粋さを感じるのは私だけではあるまい。
そう、公演で歌手が縁側や庭で歌っているからと言って、騙されてはいけない!
この二重唱は、さっきも言ったとおり、二人が愛し合っている様子を描写しているんです。
もちろん、世界のメジャーな歌劇場で具体的にそれを描出するわけにはいきませんが、
だからなおさらのこと、せめて、二人の世界を邪魔しない、ということだけは徹底してほしい。
つまり、二人以外の人間を舞台にのせない、ということを私は望みます。
しかし、これを実行に移してくれる演出家というのは実はとても少なく、
メトのプロダクションでも、黒子がうろうろしていましたっけ、、。
他にも、
1)二幕の、シャープレスと蝶々さんの会話のシーンで、縁側に座って話せばいいものを、
なぜだかはっぴを着た男が庭に椅子を準備したり、片付けたり。落ち着かない。
2)蝶々さんとスズキの花を撒くシーンでは、黒子が木になっていた。もじもじ君みたいでとても変。
3)蝶々さんがピンカートンを待つシーン。家全体が寝静まっているような印象を与えるのは変。
少なくとも蝶々さんは夜通し起きて彼の到着を待っている、その姿に観客は胸が引き裂かれる思いがするのに、
家がこんなに真っ暗では、まるで蝶々さんも寝てしまったかのようで、
ちっとも感動的でない。
などなど、数々の気になる点がありました。
ただ、その後、オケの演奏をバックに空が白み始める中、
障子に、影絵のように、芸者が踊る姿を映し出したのは、その後の不吉な運命を暗示しつつ、
観客にも退屈させない効果もあって、良いと思いました。
さて、蝶々さんが自害にのぞむため、白装束に変わるシーンは、
それまで着ていた着物から瞬時に変身!という、まるでコマ劇場を思わせる方法。
”名誉を持って生きれぬものは、名誉を持って死ぬべし”と、
蝶々さんが歌うシーンでは、ニテスクの声の表現力は良いのですが、演技力がいま一つ。
自害のシーンでは、扇子で刀を表現、さらにその扇子を広げた時に見える赤色が血を表わす、
という流れになっており、最後には大きな布が地面に広げられるのですが、
この一連の流れは少し凝り過ぎかな、という印象を持ちます。
歌唱陣、オケ、合唱が頑張っているだけに、もう少し演出が、
音楽と物語にそったものとなっていれば、もっともっといい公演になっていたのではないかな、と思わされました。
日本人スタッフが関わっているだけに、特に外人には(観客、オペラハウス関係者ともに)
アンタッチャブルといいますか、マイナス意見を言いにくい演出なのだと思います。
今だスカラ座ではこの演出が使われているようなので、、。
しかし、私にとっては、演出、美術、衣装に日本人が関わって、
全体がそれらしくあればいい、というものではないのだ、ということを確認させられる興味深い公演でした。
Adina Nitescu (Cio-Cio-san)
Roberto Aronica (Pinkerton)
Alexandru Agache (Pinkerton)
Elena Cassian (Suzuki)
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala
Conductor: Bruno Bartoletti
Production: Keita Asari
Costume: Hanae Mori
Performed at Teatro degli Arcimboldi di Milano
*** プッチーニ 蝶々夫人 Puccini Madama Butterfly ***
ナショナル・カウンシル(映画に収められているものと年度が違うと思われますが、
ナショナル・カウンシルとは何ぞや?ということはこちらで少しご紹介しました。)の様子を収めた
映画『The Audition』のプレビュー、
パヴァロッティを偲んでメトで演奏されるヴェルディ・レクイエム、
(いずれも、レポをあげるつもりでおります。お楽しみに!)
そして、22日の月曜日はいよいよメトの2008-9年シーズンの開始、ということで、
このブログも本格始動モードに入りますが、その前に、夏休みの特別企画として、
何本か、メト以外のオペラハウスによるオペラ公演の映像を視聴する機会がありました。
視聴した場所は我が家。たまには愛犬と戯れつつ、こうしてリラックスしながらオペラを観るのもよいものです。
このブログを通じてお知り合いになった方から、映像を提供頂きました。お礼を申し上げます。
どのオペラハウスのものでも、どんな公演でも、こうして映像にふれることは、
大変興味深く、勉強になるので、どんな感想を持ったとしても、
見て損した!時間を無駄にした!と思うことはありません。
いつもの当ブログのモットー通り、思った通りを書き連ねることになりますが、
その点だけは強調させてください。では第一弾、行きましょう!
何本か頂いた録画映像の中から、やっぱり最初に選んでしまったのが『蝶々夫人』。
今までこのブログで何度も『蝶々夫人』は私の大好きな演目の一つであることを開陳して参りました。
お弁当の中に大好物の食べ物が入っていたら、まずそれに箸が伸びるタイプです。
これは2004年にミラノのアルチンボルディ劇場で、スカラ座のオケと合唱で行われた公演。
浅利慶太の演出、森英恵の衣装、照明や舞台美術にも日本人があたり、指揮はバルトレッティ。
蝶々夫人役を歌うのはニテスクというソプラノで、残念ながら私は一度も生で彼女の歌を聴いたことがないのですが、
この公演を聴く限り、冒頭でやや声の伸びがないというか、締め付けられているような音になっている個所、
また音が下がり気味になっている個所が見られますが、尻上がりによくなっていきます。
登場の場面での最後のオプショナルの高音は出さずじまい、
それ以外の個所でも特に一幕で、高音域で、やや音程を含め安定感を欠く場面がありましたが、
逆に低音域ではメゾのような深い響きがあり、
声の質そのものはこの役には悪くないものを持っていると思います。
少しぽちゃっとした体型ですが、この役はぎすぎすした声で歌われてもきついので、
もしぽちゃっとしていることでふくよかな声が出ているとするなら、それはそれでよい。
むしろ、歴代蝶々さんの中ではルックスも仕草も悪くありません。
一幕15歳、ニ幕目以降18歳であるはずの蝶々さんにしては、どちらも少し、
やや年齢がそれよりも上のような印象を歌唱が与えるのと、
最後の”私の坊や Tu, tu, Piccolo Iddio"では、オケよりも早く音符を畳んでしまっていたり、
少しスタミナ切れしたかな?と思わせるのは残念ですが、全体的には良い歌唱だと思います。
ピンカートンを歌うのは、ロベルト・アロニカ。
彼は生で何度か聴いたことがありますが、いつもことごとく期待を裏切られて来たので、
私の中では、ほとんど”存在しないテノール”化していましたが、
おやおや、この公演ではがんばっているではありませんか!
ほんの少しオケから走ってしまうくせがあるのを除いては。
しかし、あいかわらず、顔が四角い、、。メイクがさらにそれを助長しています。
シャープレスは、アガーケ。同情心ある、情け深いシャープレス、という、
最も多く見られるアプローチの仕方でこの役を歌っていました。
スズキはケシアン。表情が常に深刻でやや鬱陶しい感じがしますが、
深くていい声を持っていて、ニテスクとの声の相性がよいのはプラス。
蝶々夫人とスズキの二重唱の場面では、これは大きなボーナスです。
ゴローがものすごく歳をとっているのもおもしろい。海千山千な感じがよく出てます。
しかし、なんといってもこの公演の素晴らしいのはオケと合唱。
というか、ソリストよりもオケと合唱が主役のような感じすらするほどです。
ハミング・コーラスの合唱のそれは素晴らしいこと!!
そして、シャープレスが蝶々さんに”ピンカートンがこのまま帰って来なかったらどうしますか?”
と尋ねる個所や、大砲の音の後のオケの音は!!!すごい表現力です。
バルトレッティのような職人芸指揮者が今やほとんど不在なのは本当に残念なことです。
というわけで、演奏する側はなかなか頑張っているのですが、私、実はこの公演の足をひっぱっているのは
演出をはじめとする日本人チームではないか、、?と感じました。
もちろん、切り絵を思わせる背景とか、着物などのデザイン、微妙な色合いの照明、
またおそらく、現在、『蝶々夫人』のいろいろなプロダクションに
多用される(メトの2006年プレミアの演出もその一例)ハシリになったのではないかと
思われる黒子の使用、など、日本人スタッフならではの、
美しい場面、面白いアイディアがあるにはあるのですが、同じくらいに問題も多い。
まず、衣装。日本人の諸役はいいとして、このピンカートンの衣装はどうでしょう?!
軍服はJALのパイロットみたいだし、スカイブルーのジャケットに至っては、何と言っていいのやら、、。
私たちが、非日本人のデザインした蝶々さんの着物を見て”何か変”と思うのと同様に、
このピンカートンの衣装も”何か変”。
この演出では、基本的には日本”らしさ”を大事にしようとしているはずなのですが、
それなら、アメリカ”らしさ”も大事にしなくては、アンバランスです。
森英恵といえば、企業や学校の制服のデザインによく登用されていましたが、
何となく、このピンカートンの衣装も、その延長のような、、。
オペラの衣装デザインが、企業のための制服のデザインの延長ではあまりにも悲しい。
次に、これは演出家の演技付けの力量か、歌う歌手の演技力量(の不足)か、判断が難しいところですが、
現在のトレンドと比べると、この公演では、いかにも歌手が直立不動で立って歌っているシーンが多い。
まあ、数年前まではこれでも良かったのかも知れませんが、今や、オペラの公演も
HDに乗ったり、DVD化されたりする時代。
最近の、歌手がひっきりなしに歌って動いて、という舞台に比べると、
のどかというか、時代の流れを感じます。
さて、そんな中でいきなり飛び出すのが、一幕最後のピンカートンの舌なめずり。
あろうことか、蝶々さんを今や自分のものに!と盛り上がっているピンカートンが
愛の二重唱の途中で舌なめずりをするのです!!!!
ここの、このピンカートンをあまりにもの軽薄男に貶めたこの演出には私は大反対です。
この二重唱を聴いて、こんな舌なめずりが頭に浮かぶのか?浅利慶太という人は?
人間の感情の、簡単に白だの、黒だの、と簡単にラベルを貼れない複雑さ。
そのことが描かれているところに、オペラの、いえ、全てのアートフォームの素晴らしさがあるのでは?
もちろん、ピンカートンは、まさに蝶々さんとラブ!と盛り上がっていることは間違いなく、
よって、この二重唱がイタリアもののオペラの中でも一、二を争うエロティックな二重唱、
といわれる由縁なのですが、
エロティックはただの助平と同じではないでしょう。
この二重唱の音楽を聴けば、スケベ心を超えた何かがピンカートンの心の中にあったことははっきりしている。
先立つ場面で、シャープレスに”蝶々さんのことを愛しているのか?”と聞かれ、
”わからない”と答えたピンカートンの心情はそこにあるのです。
”愛している”とは即答しませんが、”もちろん遊びさ”とも即答しない。
その感情こそを、この二重唱では表現してほしいのです。
本当の愛ではないかも知れないけれど、スケベ心とも違う何か(恋でも、情欲でも、
何でもいいですが)があったはずなのです。
それから、この愛の二重唱で、舞台上、黒子がうろうろする、これも私には許せない。
黒子を使うアイディア自体は悪いこととは思いませんが、灯篭を持った黒子を、
この二重唱の途中で登場させるのはなぜなのか。
この二重唱でのピンカートンと蝶々夫人は、もう”二人だけの世界”状態なのに。
まるで、二人が愛し合っている途中の寝室に、他人が土足で入り込むような無粋さを感じるのは私だけではあるまい。
そう、公演で歌手が縁側や庭で歌っているからと言って、騙されてはいけない!
この二重唱は、さっきも言ったとおり、二人が愛し合っている様子を描写しているんです。
もちろん、世界のメジャーな歌劇場で具体的にそれを描出するわけにはいきませんが、
だからなおさらのこと、せめて、二人の世界を邪魔しない、ということだけは徹底してほしい。
つまり、二人以外の人間を舞台にのせない、ということを私は望みます。
しかし、これを実行に移してくれる演出家というのは実はとても少なく、
メトのプロダクションでも、黒子がうろうろしていましたっけ、、。
他にも、
1)二幕の、シャープレスと蝶々さんの会話のシーンで、縁側に座って話せばいいものを、
なぜだかはっぴを着た男が庭に椅子を準備したり、片付けたり。落ち着かない。
2)蝶々さんとスズキの花を撒くシーンでは、黒子が木になっていた。もじもじ君みたいでとても変。
3)蝶々さんがピンカートンを待つシーン。家全体が寝静まっているような印象を与えるのは変。
少なくとも蝶々さんは夜通し起きて彼の到着を待っている、その姿に観客は胸が引き裂かれる思いがするのに、
家がこんなに真っ暗では、まるで蝶々さんも寝てしまったかのようで、
ちっとも感動的でない。
などなど、数々の気になる点がありました。
ただ、その後、オケの演奏をバックに空が白み始める中、
障子に、影絵のように、芸者が踊る姿を映し出したのは、その後の不吉な運命を暗示しつつ、
観客にも退屈させない効果もあって、良いと思いました。
さて、蝶々さんが自害にのぞむため、白装束に変わるシーンは、
それまで着ていた着物から瞬時に変身!という、まるでコマ劇場を思わせる方法。
”名誉を持って生きれぬものは、名誉を持って死ぬべし”と、
蝶々さんが歌うシーンでは、ニテスクの声の表現力は良いのですが、演技力がいま一つ。
自害のシーンでは、扇子で刀を表現、さらにその扇子を広げた時に見える赤色が血を表わす、
という流れになっており、最後には大きな布が地面に広げられるのですが、
この一連の流れは少し凝り過ぎかな、という印象を持ちます。
歌唱陣、オケ、合唱が頑張っているだけに、もう少し演出が、
音楽と物語にそったものとなっていれば、もっともっといい公演になっていたのではないかな、と思わされました。
日本人スタッフが関わっているだけに、特に外人には(観客、オペラハウス関係者ともに)
アンタッチャブルといいますか、マイナス意見を言いにくい演出なのだと思います。
今だスカラ座ではこの演出が使われているようなので、、。
しかし、私にとっては、演出、美術、衣装に日本人が関わって、
全体がそれらしくあればいい、というものではないのだ、ということを確認させられる興味深い公演でした。
Adina Nitescu (Cio-Cio-san)
Roberto Aronica (Pinkerton)
Alexandru Agache (Pinkerton)
Elena Cassian (Suzuki)
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala
Conductor: Bruno Bartoletti
Production: Keita Asari
Costume: Hanae Mori
Performed at Teatro degli Arcimboldi di Milano
*** プッチーニ 蝶々夫人 Puccini Madama Butterfly ***



















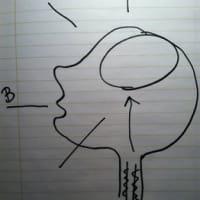
私は他と比べるものが無いので、純粋に号泣したのだけれど、色々な観点からの感想を読んで参考になりました。
メトの口裂けオンナのような、髪ざんばらの蝶々さんがとても映像的に怖かったので、こちらの蝶々さんはなかなかふっくらではありますが、チャーミングだと思いました。
その時は気付かなかったけれど、確かに昔のパイロットのような服装だわね、ピンカートン。
ゴローと大村昆がちょっとダブってしまったのだけれど、アガーケのシャープレスもケシアンのスズキもでしゃばっていなくていい塩梅で舞台の脇をつとめていたのではないかと、そんな印象を持ちました。
まだ他の映像も、そしてなんたることか生の舞台も見たことが無いので、来年はきっとどこかの蝶々さんの舞台を観たいものだわ。
少なくとも、怖くてもメトのHDでは上映されるから見られるはずだもの、更に予習に励みます。
私も、歌手、オケ、合唱はとても水準が高いと思いました。
実演ではなかなか全部が揃う、ということがないので、
それだけに、あのピンカートンの衣装と、
ややピントのずれた演出が残念無念!
メトのミンゲラ演出の舞台はやや微妙にエキセントリックなので、
>来年はきっとどこかの蝶々さんの舞台を観たい
なら、新国立劇場はどうかしら?
2009年の1月に公演があるみたいよ。
カリーネ・ババジャニアンって誰?って感じだけれども。
新国立劇場が開場したばかりの頃の『蝶々夫人』のプロダクションは、
以前このブログでも絶賛したとおり、本当にすばらしかったのだけど、
残念なことに新しいプロダクションにその後とってかわられてしまったようです。
あんな素晴らしい演出をお釈迦にするなんて、信じられない!
だけれど、新しくなったプロダクションも、結構評判が良いようなので、
もし時間があえばぜひ!
私もyolさん同様蝶々夫人は生舞台はおろか、映像でも最後まで見たのはこれが初めてだったので、結構感動しました。デッシーが本当に蝶々の扮装で登場するのは、歌を聴く以前に止めてしまってたし。
さすがに蝶々夫人を沢山ご覧になっていて、思いいれの強いMadokakipさんならではの視点をうかがって、
参考になりました。
初めての生舞台は新国立で観る予定です。
今まで蝶々夫人は避けてきましたので。
ところで、島田雅彦さんの「無限カノン三部作」を
ご存知ですか?蝶々さんとピンカートンの息子の
話から始まって、その息子、またその息子と現代まで
繋がっていくんですよ。
>デッシーが本当に蝶々の扮装で登場する
本当に?すごい(笑)。
デッシーは確かだいぶ前ですが、日本に来てこの役を歌ったことがありました。
その時はシンプルですが比較的まともな演出で、
白い着物を着て愛の二重唱を歌っていた記憶があります。
なのに、そのプロダクションでは蝶の羽を背負わされたりしているわけですか、、。
そんな演出にのって歌うデッシーもデッシーですが、
あまりに素っ頓狂で、怖いものみたさの気持ちもあります。
メトでは、今のミンゲラのプロダクションの前のプロダクションを
何度か観ていますが、それはもう地味なセットに演出で、
歌が良くなければ、おそろしく退屈になりかねない代物でした。
蝶々夫人といえば、この忠実再現型と、
シンプルにまとめたり、シンボリックなものを使用する型の大きく二つに分かれるような気がします。
今はどちらかというと、後者の方が多いような気がしますね。
(デッシーの蝶々の扮装も後者ですね。)
前者は一つ間違うとものすごく退屈な公演になりかねないところがおそろしいところです。
新国立劇場の『蝶々夫人』の第一号プロダクション(ご覧になるものと違う、一つ前のプロダクションです)は、
前者のカテゴリーですが、決して退屈にならず、
一つ一つのシーンすべてに、ああそうか!と納得させられました。
この作品は音楽が素晴らしいので、歌がよければ感動は得られますが、
この時の、演出と音楽がかみ合って、ジグゾーパズルのピースが次々はまっていくような感覚は忘れられません。
むしろ、歌唱の方があまり記憶がなく(悪かったという記憶もないのですが)、
今も、色々な演出を観るときに、この新国のプロダクションを思い出して比べてしまいます。
『無限カノン三部作』、
子供はアメリカに行ったはずなので、アメリカが舞台なんでしょうか?
新作で音楽もリブレットもすぐれた作品が出て来るといいのですが、、。
オペラのほうは(元すら見てないので)見てませんが、小説はなかなかおもしろかったです。
さっきコメントを入れたばかりなのに、もうお返事を頂いたということは、
もしやチャット状態ですね!
無限カノン情報、ありがとうございます。
小説、ぜひ読んでみようと思います!