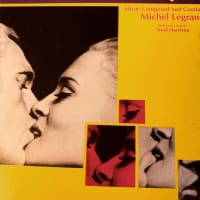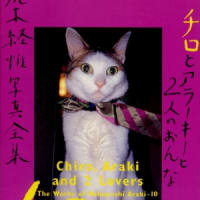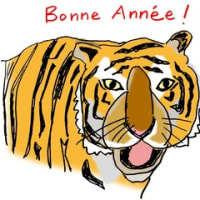8月16日
今日の音楽美学講座はウェインショーター作曲の「プラザリアル」、
最もドラマティックな最終楽章の分析。ここに至るまでじつに3ヶ月。
長くて途中やや間延び感を感じた事もあったけれど
複雑で壮大な曲だし、講師である菊地さんご自身の
ラテンコンセプトのバンド(ペペトルメントアスカラール)の
10月に発売されるアルバムで取り上げるというだけあって、
教える側の曲に対する情熱を感じられ、
講義に引き込まれたのだった。
今回、最も起伏に富んだこの魅力的な部分の分析に用いられた音源は
スタジオでミックスダウンほやほやの菊地さん自身のSAX演奏による
ラテンアプローチの「プラザリアル」で、幸運なことに
私たち生徒はいち早く発売前にこの曲を聴くことが出来た。
じつはオリジナル版であるウェザーリポートの「プラザリアル」には
楽曲の絶対的な美を感じながらも、少々とっつきにくい「怖さ」のようなものも
同時に感じていた。幾分子供っぽくも緻密な何か・・・狂気すらもあって
そういった全ては曲が持つ強い構造性に支えられ
独特な音楽美を成立させている。
これはフーガの技法とか音楽の捧げものなんかに感じる
バッハっぽさプラスモーツァルト的な(笑)破格的奔放さもある。
曲の美しさを感じながらなぜとっつきにくさを感じたのかは
菊池さんたちが演奏するペペトルメント…版を聴いて判明した。
たぶん、これは「POP」ということに関わっている。
ペペ・・・の演奏とアレンジも同様に美しいのだけれど
ラテン(ルンバ?)のリズムもあってか親しみと陽気さがあって
ダンスしたくなるような音楽になっている。そうだ、ウェザーリポートの
プラザリアルでは(5拍子とか7拍子も出てくる変拍子だし)
音楽に引き込まれてもダンスのことは思い出さなかった。
さて、今回の分析は、いつも以上に「精神分析」的なアナロジーに満ちた
魅力的な意味解釈で、たとえば「言い間違い」や「記憶の取り違え」などは、
それも含めて「本人の属性」なのだ、という言及は興味深かった。
繰り返し起こるような「間違い」の原因には
無意識的に刷り込まれた何らかの強い記憶が作用していて、
菊地さんは自分が学生時代に毎回聴き間違いをする
テンションコードについて触れて
たとえば初めて聴いて強烈に記憶に残ったある曲のフレーズの隠れた影響だとか
「4軒あるラーメン屋のうち、自然に足が向く或る1軒のラーメン屋」が
決定していく事の嗜好性についても(笑)触れられ
それと同様にその人が奏でたいと思い、なおかつそこに向かおうとする
「転調」感というのはあって、それは音楽家によって違うのだ、とする説は
興味深く面白かった。当然、私にもそれはある。
たまたま先日完成した去年の卒業制作曲への講評
(日記:「Lighten」への講評はこちら)を頂いたことと、
今年の講義の修了に向けた卒業制作となる次回作となる
曲の構想を練っていてそれは以前観た松浦寿夫氏の
展覧会の作品について初めて抱いたイメージと
あるアーティストへのオマージュ作品である
コンピレーションアルバムの或る曲を聴いて
2つのイメージが繋がり、輪郭を持ち始めたもので
(たとえば「抽象化された具象美」であるとか)
言葉を使わずに直接感情を動かすことに出来る音楽には、
こうした表現が可能で
とりわけ同じ言葉の中に表現の仕方によっては
別な意味が立ち上がるという概念が
私は好きなのだけど(理由はわからない…)
このことは転調の概念と、よく似ていると思う。
プラザリアルの最終楽章では
10回繰り返されるシンプルな主旋律に対して
コードが徐々に変わって行き、またもとに戻る、というかんじで
コードが変わるたびに主旋律の聴こえ方も変わり、意味合いも変わる。
そういう意味では、まさに私が好きな概念上の出来事が
この音楽の中では起きていたのだった。
<BODY>
<script type="text/javascript" src="http://www.research-artisan.com/userjs/?user_id=20060529000243138"></script><noscript>
</BODY>
今日の音楽美学講座はウェインショーター作曲の「プラザリアル」、
最もドラマティックな最終楽章の分析。ここに至るまでじつに3ヶ月。
長くて途中やや間延び感を感じた事もあったけれど
複雑で壮大な曲だし、講師である菊地さんご自身の
ラテンコンセプトのバンド(ペペトルメントアスカラール)の
10月に発売されるアルバムで取り上げるというだけあって、
教える側の曲に対する情熱を感じられ、
講義に引き込まれたのだった。
今回、最も起伏に富んだこの魅力的な部分の分析に用いられた音源は
スタジオでミックスダウンほやほやの菊地さん自身のSAX演奏による
ラテンアプローチの「プラザリアル」で、幸運なことに
私たち生徒はいち早く発売前にこの曲を聴くことが出来た。
じつはオリジナル版であるウェザーリポートの「プラザリアル」には
楽曲の絶対的な美を感じながらも、少々とっつきにくい「怖さ」のようなものも
同時に感じていた。幾分子供っぽくも緻密な何か・・・狂気すらもあって
そういった全ては曲が持つ強い構造性に支えられ
独特な音楽美を成立させている。
これはフーガの技法とか音楽の捧げものなんかに感じる
バッハっぽさプラスモーツァルト的な(笑)破格的奔放さもある。
曲の美しさを感じながらなぜとっつきにくさを感じたのかは
菊池さんたちが演奏するペペトルメント…版を聴いて判明した。
たぶん、これは「POP」ということに関わっている。
ペペ・・・の演奏とアレンジも同様に美しいのだけれど
ラテン(ルンバ?)のリズムもあってか親しみと陽気さがあって
ダンスしたくなるような音楽になっている。そうだ、ウェザーリポートの
プラザリアルでは(5拍子とか7拍子も出てくる変拍子だし)
音楽に引き込まれてもダンスのことは思い出さなかった。
さて、今回の分析は、いつも以上に「精神分析」的なアナロジーに満ちた
魅力的な意味解釈で、たとえば「言い間違い」や「記憶の取り違え」などは、
それも含めて「本人の属性」なのだ、という言及は興味深かった。
繰り返し起こるような「間違い」の原因には
無意識的に刷り込まれた何らかの強い記憶が作用していて、
菊地さんは自分が学生時代に毎回聴き間違いをする
テンションコードについて触れて
たとえば初めて聴いて強烈に記憶に残ったある曲のフレーズの隠れた影響だとか
「4軒あるラーメン屋のうち、自然に足が向く或る1軒のラーメン屋」が
決定していく事の嗜好性についても(笑)触れられ
それと同様にその人が奏でたいと思い、なおかつそこに向かおうとする
「転調」感というのはあって、それは音楽家によって違うのだ、とする説は
興味深く面白かった。当然、私にもそれはある。
たまたま先日完成した去年の卒業制作曲への講評
(日記:「Lighten」への講評はこちら)を頂いたことと、
今年の講義の修了に向けた卒業制作となる次回作となる
曲の構想を練っていてそれは以前観た松浦寿夫氏の
展覧会の作品について初めて抱いたイメージと
あるアーティストへのオマージュ作品である
コンピレーションアルバムの或る曲を聴いて
2つのイメージが繋がり、輪郭を持ち始めたもので
(たとえば「抽象化された具象美」であるとか)
言葉を使わずに直接感情を動かすことに出来る音楽には、
こうした表現が可能で
とりわけ同じ言葉の中に表現の仕方によっては
別な意味が立ち上がるという概念が
私は好きなのだけど(理由はわからない…)
このことは転調の概念と、よく似ていると思う。
プラザリアルの最終楽章では
10回繰り返されるシンプルな主旋律に対して
コードが徐々に変わって行き、またもとに戻る、というかんじで
コードが変わるたびに主旋律の聴こえ方も変わり、意味合いも変わる。
そういう意味では、まさに私が好きな概念上の出来事が
この音楽の中では起きていたのだった。
<BODY>
<script type="text/javascript" src="http://www.research-artisan.com/userjs/?user_id=20060529000243138"></script><noscript>
</BODY>