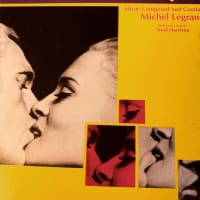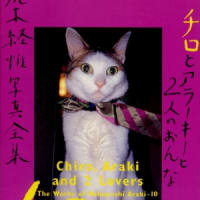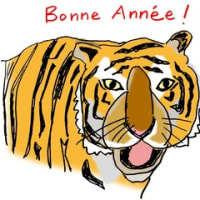12月8日(木曜日)
今日は4回目の楽理講座。
2週間に1度のこの講義と映画美学校。
会社や仕事でストレス感じてるつもりもないんだけど
仕事のあとにこの学校に来て、
顔見知りになった人々とちょっとだけ挨拶を交わしたり
音楽の話しをしたり
菊地さんの情熱的な楽理講義に集中し、
理論と感覚を照らし合わせたり
そんな事を繰り返しているうちに
ふと、自分がとてもリラックスしている事に気がついた。
水を得た魚とでも言うんだろうか。
やっぱりこの楽理講義は楽しい。
音楽の仕掛けがわかればわかるほどに。
で、講義の前、モードのスケールの練習を鍵盤でしながら
先日、中川五郎氏とライブで共演をした
同じクラスのミュージシャンK君と
彼が歌詞をつくる時のことを訊いたり
コーネリアスの2010(アルバム:FANTASMAに入ってる)や
レイハラカミ、矢野顕子、やはり良いよね、などなど
とても短い時間なのに話が盛り上がる。
現役で活動しているミュージシャンの感覚は
そうでなくて音楽をやっている人間とはやはり違う事を感じる。
音楽的な軸がしっかりしていて
物事を見極めていながら、外に開かれた何かと
音楽表現を生業としている人が持つ
感覚のブレの無さを感じる。
中川五郎氏の翻訳がとても好きなので
ここで繋がるなんて、と思いつつライブに行けなくて残念。
でもまた次回行こう、きっとそんな日が来るだろう。
音楽的共通感覚を他の人と共有出来る事は
とても幸せだ。言葉にする必要がない部分が多く、
属性などを越えた信頼感が生まれる。
私はこの楽理の講義を『勉強』とは特に思っていない。
幾分の集中力と理解力、そして想起力を必要とする
楽しい遊びだと思っている。
自分の中に眠っていた「知りたくて知らなかった事」を
紐解いているようで、今初めてというより
既にあった感覚や経験、記憶を参照したり駆使、総動員して
臨んでいる、というかんじ。だから殊更に楽しい。
考古学者のように時間を遡行し
行ったり来たり発掘したりの冒険をして楽しんでいる。
菊地さんは風邪を召していてマスク姿で時間通りに登場。
でも、講義に熱くなるあまり(苦しいのだと思う)
マスクを外して菌が一部、蔓延した模様(笑)
先週に引き続きモード2の概念を念入りに踏襲。
正直、初等科ではぴんときていない部分も多かったので
この高等科の懇切丁寧で復習的講義で改めて
認識しているだめな私。
講義の中で前々回の特別講義で高山さんが
「良い編曲をするには、上方倍音を聴く事が大切」
と言った言葉で気になっていた「上方倍音」の事が
また触れられた。しかしまだちゃんと解っていない。
前回宿題だったモードスケールを弾けるように、という事で
あれこれ練習していたのだけど
どうやら私が最も憶え易く弾き易いやり方というのは
講義で言われたホールトーンスケールでの乗り換えでも
スケールの丸暗記でもなく、
鍵盤で半音を押さえる場所を明確にする、という
単純な方法だった。どうやら私は論理よりも
鍵盤に対して視覚感覚的に弾いているようで
かつ音符を同時に数字に置き換えて認識するやり方が
良いらしい。もしかしてこれはクラシック的なんだろうか?
そんな発見もあったり、菊地さんの久々の
ハイテンションモードの講義という事もあって、
講義を終えて外に出てもあまり寒さを感じなかった(笑)
次回は、前回の楽理講義日記に書いた
「モーダル・メロディ」
「1コード/1モード」「コード&モード」
そして、いよいよモード概念の核心「コード/モード」
『総てのスケールがモードと等しくなる次元』について
学習して、来年からはいよいよ楽曲を具体的に聴いて
分析を始める。目白押しに楽しみ満載。体力と知力勝負だ。
風邪などひいていられない師走が始まった。
今日は4回目の楽理講座。
2週間に1度のこの講義と映画美学校。
会社や仕事でストレス感じてるつもりもないんだけど
仕事のあとにこの学校に来て、
顔見知りになった人々とちょっとだけ挨拶を交わしたり
音楽の話しをしたり
菊地さんの情熱的な楽理講義に集中し、
理論と感覚を照らし合わせたり
そんな事を繰り返しているうちに
ふと、自分がとてもリラックスしている事に気がついた。
水を得た魚とでも言うんだろうか。
やっぱりこの楽理講義は楽しい。
音楽の仕掛けがわかればわかるほどに。
で、講義の前、モードのスケールの練習を鍵盤でしながら
先日、中川五郎氏とライブで共演をした
同じクラスのミュージシャンK君と
彼が歌詞をつくる時のことを訊いたり
コーネリアスの2010(アルバム:FANTASMAに入ってる)や
レイハラカミ、矢野顕子、やはり良いよね、などなど
とても短い時間なのに話が盛り上がる。
現役で活動しているミュージシャンの感覚は
そうでなくて音楽をやっている人間とはやはり違う事を感じる。
音楽的な軸がしっかりしていて
物事を見極めていながら、外に開かれた何かと
音楽表現を生業としている人が持つ
感覚のブレの無さを感じる。
中川五郎氏の翻訳がとても好きなので
ここで繋がるなんて、と思いつつライブに行けなくて残念。
でもまた次回行こう、きっとそんな日が来るだろう。
音楽的共通感覚を他の人と共有出来る事は
とても幸せだ。言葉にする必要がない部分が多く、
属性などを越えた信頼感が生まれる。
私はこの楽理の講義を『勉強』とは特に思っていない。
幾分の集中力と理解力、そして想起力を必要とする
楽しい遊びだと思っている。
自分の中に眠っていた「知りたくて知らなかった事」を
紐解いているようで、今初めてというより
既にあった感覚や経験、記憶を参照したり駆使、総動員して
臨んでいる、というかんじ。だから殊更に楽しい。
考古学者のように時間を遡行し
行ったり来たり発掘したりの冒険をして楽しんでいる。
菊地さんは風邪を召していてマスク姿で時間通りに登場。
でも、講義に熱くなるあまり(苦しいのだと思う)
マスクを外して菌が一部、蔓延した模様(笑)
先週に引き続きモード2の概念を念入りに踏襲。
正直、初等科ではぴんときていない部分も多かったので
この高等科の懇切丁寧で復習的講義で改めて
認識しているだめな私。
講義の中で前々回の特別講義で高山さんが
「良い編曲をするには、上方倍音を聴く事が大切」
と言った言葉で気になっていた「上方倍音」の事が
また触れられた。しかしまだちゃんと解っていない。
前回宿題だったモードスケールを弾けるように、という事で
あれこれ練習していたのだけど
どうやら私が最も憶え易く弾き易いやり方というのは
講義で言われたホールトーンスケールでの乗り換えでも
スケールの丸暗記でもなく、
鍵盤で半音を押さえる場所を明確にする、という
単純な方法だった。どうやら私は論理よりも
鍵盤に対して視覚感覚的に弾いているようで
かつ音符を同時に数字に置き換えて認識するやり方が
良いらしい。もしかしてこれはクラシック的なんだろうか?
そんな発見もあったり、菊地さんの久々の
ハイテンションモードの講義という事もあって、
講義を終えて外に出てもあまり寒さを感じなかった(笑)
次回は、前回の楽理講義日記に書いた
「モーダル・メロディ」
「1コード/1モード」「コード&モード」
そして、いよいよモード概念の核心「コード/モード」
『総てのスケールがモードと等しくなる次元』について
学習して、来年からはいよいよ楽曲を具体的に聴いて
分析を始める。目白押しに楽しみ満載。体力と知力勝負だ。
風邪などひいていられない師走が始まった。