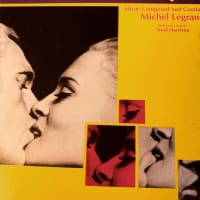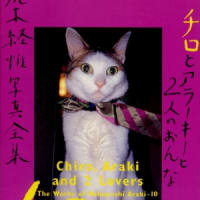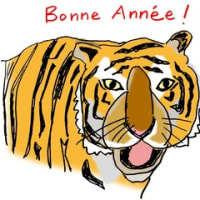2006年3月8日 第11回目 楽理高等科
引き続き、楽曲分析の講義。
前回は前々回に引き続き「カイリーミノーグ」
ジャニーズ(笑)「青春アミーゴ」とDANCE系POPSが続いたわけだけど
次回はアーティスティックな曲を、という予告どおり
アントニオカルロスジョビン。
何の曲かとワクワクしていたら、
私の中ではジョビンの曲で1、2位を争う程
好きな曲である「How Insensitive」(お馬鹿さん)
菊地さんが詞の「お馬鹿さん」ぶりについて(笑)説明を。
(確かこんなかんじ)
「恋人と別れたくらいで、
そんなに哀しむなんて、お馬鹿さんね」
この曲は10年程前、あるきっかけで
仲間とバンドをやる事になってその時に初めて
アドリブ練習用に演奏した曲で想い出深い。私はピアノで参加した。
これと争うほど好きな曲は去年の今頃の日記に何度か書いた
Children's game。
<参照用過去日記>
『Children's games/スケールの効用』
『サビはドレミファソラシド』
菊地さんが用意してくれたのは
StangetsとAstrudGilbeltと、ああ。これまた何て素敵、
坂本龍一ヴァージョン。
好みのアレンジはさらっとしたボーカルと共に
AstrudGilbelt版だったけれど
Stangetsのアレンジの、途中でリズムパート(ドラム)が
入って来る部分に身体が反応、とても良い。
坂本龍一の、この仕事を菊地さんは
エナジーフローより評価されて然るべきと
思っていらっしゃるようで、エナジーフローが
ピアノのインストゥルメンタルにもかかわらず
オリコン1位を取ったのは偉業だという事にも触れつつ
それを知らない高校生の生徒H君が「本当ですか!?」と
驚いていた様などを眺めつつ
坂本龍一の政治的な思想やスタンスにも触れ
(JAZZ HATEだという事にも・笑)
ブラジル生まれのボサノバとアメリカ生まれのジャズとの長年の
「どちらが先に生まれたか」論争に対する
世界のサカモトが取った姿勢は、ジャズ的なアプローチを排した
クラシカルなアレンジによるジョビンのボサノバで、
ついでにHow Insensitiveに劇的な転調のアレンジをしたのは
彼くらいだろう、と評価されていたのも印象的だった。
ここでふと、先日行った新宿ロフトの菊地さんがゲストで
参加されたパール兄弟と鈴木慶一のライヴのバックステージに
矢野顕子が来ていたことをうっかりサエキさんが言って、
矢野顕子と菊地さんのツーショットを思い浮かべ(笑)
心がさざ波立ったことを思い出した。考えてみたら
このお二人はジャズ繋がり。その後菊地さん御用達の
「青葉」を発見して、ここにあるんだ!と思って友人達と入ったら
菊地さんを発見(笑)して、嬉しくも美味しかった、、、青葉の料理。
そして、菊地さんはあの時カヒミカリィさんなしで一人で
「恋の面影」を唄うなんて、そしてSweetMemorieを唄うなんて
意外な展開に微笑しつつ、うっとりしたのだった(笑)
さて、講義録に戻ろう。
私は個人的にはCASAよりもA DAY in new york
(How Insensitiveもこちら)のほうが好きで、
このアルバムから選ぶならFalando de Amorが最も好きなんだけど
ジョビンのこのような哀しげな曲に感じる、
映画「黒いオルフェ」やブラジルの
強く明るい陽光の下にある黒く濃い影の明るさと暗さの、
強烈なコントラストを想い出していた。憂鬱と官能の国。
幾つかの印象的な分析内容と言述、その印象を復習&記録。
・ジョビンのこの曲を分析するにつれて現れて来る
『擬態』的な構造。
・似ているコード展開にもかかわらず
2度目に現れた時は違ったものに聴こえる
・マイナーダイアトニック使いのお手本
・クリシェ
・小節ごとに変わって行くモード、音列
(同じキー内でHM,NM,MNと展開)
・動く音
・動かない音
・ジョビン→トラウマ→森→エコロジスト的発想
分析していて、概観ではわからない
小宇宙的なものを感じた。
ざっと全体を観ては感じられないようなミクロの世界。
菊地さんは、私のそんな感覚を
「天津」(飲茶?)に喩えて(笑)分かり易く説明された。
以前から楽理分析を「精神分析」に喩えられていたけれど
たとえば数センチ大の小龍包を「おいしい!」と
一口で食べる人は世の中で大半だけど(笑)
楽理分析の作業は小さな天津を少しずつ食べて
中に何が入っているか
フカヒレだとかツバメの巣(笑)とか何とか
堪能して感じながら食べつつ
その作り方や原料を知って「天津職人」に
なれるような事(笑)と仰った。(面白過ぎます)
精神分析とは、初対面の人にも誤解することなしに
その人が何を言っても「この人はこういう人だ」という
分析と理解が出来る反面、特に感動することもなく
ある種の脱力感を抱きつつも尚、
その事に向かうようなもので
それを知らなかった時のように刺激的でもなく
特に楽しくもなく、といった状態ではあるけれど
「天津職人」になっておいしいものを作って
人に喜びを与えられる(笑)とでも言うようなかんじ。
途中で、ふと考えた。
バカラックもそうだけど、こういった優れた楽曲は
メロディーとコードとの、どちらが
作曲における推進力を持っているのだろう、と。
野暮な質問なのかもしれないけど…
たぶん、相互作用なのだろう。
ジョビンはピアノで作曲していた。
唄いながらやっていたかもしれないし
それにつれてコードも変化したのかもしれない。
それにしても、緻密な展開だった。
これを感覚的に出来るとしたら、
それは天才のなせる技なのかと思った。
次の分析する楽曲の予告があった。
ちらっと聴いた、そのジョビンの曲は出だしが3拍子で
聴いた事の無いものだった。とても複雑なメロディー、
不思議な哀愁と喜びが満ちていて叙情的な曲だった。
聴いた事のないジョビンの音楽。
そしてジョビンと思われるヘタウマで
味わいのあるヴォーカルを聴いて
何故か坂本龍一のヴォーカルを思い出した(笑)
うん、ちょっと似てるかも…(笑)
とても気になるこの曲(まだタイトル曖昧)
次回の講義が待ち遠しい。
<BODY>
<script type="text/javascript" src="http://www.research-artisan.com/userjs/?user_id=20060529000243138"></script><noscript>
</BODY>
引き続き、楽曲分析の講義。
前回は前々回に引き続き「カイリーミノーグ」
ジャニーズ(笑)「青春アミーゴ」とDANCE系POPSが続いたわけだけど
次回はアーティスティックな曲を、という予告どおり
アントニオカルロスジョビン。
何の曲かとワクワクしていたら、
私の中ではジョビンの曲で1、2位を争う程
好きな曲である「How Insensitive」(お馬鹿さん)
菊地さんが詞の「お馬鹿さん」ぶりについて(笑)説明を。
(確かこんなかんじ)
「恋人と別れたくらいで、
そんなに哀しむなんて、お馬鹿さんね」
この曲は10年程前、あるきっかけで
仲間とバンドをやる事になってその時に初めて
アドリブ練習用に演奏した曲で想い出深い。私はピアノで参加した。
これと争うほど好きな曲は去年の今頃の日記に何度か書いた
Children's game。
<参照用過去日記>
『Children's games/スケールの効用』
『サビはドレミファソラシド』
菊地さんが用意してくれたのは
StangetsとAstrudGilbeltと、ああ。これまた何て素敵、
坂本龍一ヴァージョン。
好みのアレンジはさらっとしたボーカルと共に
AstrudGilbelt版だったけれど
Stangetsのアレンジの、途中でリズムパート(ドラム)が
入って来る部分に身体が反応、とても良い。
坂本龍一の、この仕事を菊地さんは
エナジーフローより評価されて然るべきと
思っていらっしゃるようで、エナジーフローが
ピアノのインストゥルメンタルにもかかわらず
オリコン1位を取ったのは偉業だという事にも触れつつ
それを知らない高校生の生徒H君が「本当ですか!?」と
驚いていた様などを眺めつつ
坂本龍一の政治的な思想やスタンスにも触れ
(JAZZ HATEだという事にも・笑)
ブラジル生まれのボサノバとアメリカ生まれのジャズとの長年の
「どちらが先に生まれたか」論争に対する
世界のサカモトが取った姿勢は、ジャズ的なアプローチを排した
クラシカルなアレンジによるジョビンのボサノバで、
ついでにHow Insensitiveに劇的な転調のアレンジをしたのは
彼くらいだろう、と評価されていたのも印象的だった。
ここでふと、先日行った新宿ロフトの菊地さんがゲストで
参加されたパール兄弟と鈴木慶一のライヴのバックステージに
矢野顕子が来ていたことをうっかりサエキさんが言って、
矢野顕子と菊地さんのツーショットを思い浮かべ(笑)
心がさざ波立ったことを思い出した。考えてみたら
このお二人はジャズ繋がり。その後菊地さん御用達の
「青葉」を発見して、ここにあるんだ!と思って友人達と入ったら
菊地さんを発見(笑)して、嬉しくも美味しかった、、、青葉の料理。
そして、菊地さんはあの時カヒミカリィさんなしで一人で
「恋の面影」を唄うなんて、そしてSweetMemorieを唄うなんて
意外な展開に微笑しつつ、うっとりしたのだった(笑)
さて、講義録に戻ろう。
私は個人的にはCASAよりもA DAY in new york
(How Insensitiveもこちら)のほうが好きで、
このアルバムから選ぶならFalando de Amorが最も好きなんだけど
ジョビンのこのような哀しげな曲に感じる、
映画「黒いオルフェ」やブラジルの
強く明るい陽光の下にある黒く濃い影の明るさと暗さの、
強烈なコントラストを想い出していた。憂鬱と官能の国。
幾つかの印象的な分析内容と言述、その印象を復習&記録。
・ジョビンのこの曲を分析するにつれて現れて来る
『擬態』的な構造。
・似ているコード展開にもかかわらず
2度目に現れた時は違ったものに聴こえる
・マイナーダイアトニック使いのお手本
・クリシェ
・小節ごとに変わって行くモード、音列
(同じキー内でHM,NM,MNと展開)
・動く音
・動かない音
・ジョビン→トラウマ→森→エコロジスト的発想
分析していて、概観ではわからない
小宇宙的なものを感じた。
ざっと全体を観ては感じられないようなミクロの世界。
菊地さんは、私のそんな感覚を
「天津」(飲茶?)に喩えて(笑)分かり易く説明された。
以前から楽理分析を「精神分析」に喩えられていたけれど
たとえば数センチ大の小龍包を「おいしい!」と
一口で食べる人は世の中で大半だけど(笑)
楽理分析の作業は小さな天津を少しずつ食べて
中に何が入っているか
フカヒレだとかツバメの巣(笑)とか何とか
堪能して感じながら食べつつ
その作り方や原料を知って「天津職人」に
なれるような事(笑)と仰った。(面白過ぎます)
精神分析とは、初対面の人にも誤解することなしに
その人が何を言っても「この人はこういう人だ」という
分析と理解が出来る反面、特に感動することもなく
ある種の脱力感を抱きつつも尚、
その事に向かうようなもので
それを知らなかった時のように刺激的でもなく
特に楽しくもなく、といった状態ではあるけれど
「天津職人」になっておいしいものを作って
人に喜びを与えられる(笑)とでも言うようなかんじ。
途中で、ふと考えた。
バカラックもそうだけど、こういった優れた楽曲は
メロディーとコードとの、どちらが
作曲における推進力を持っているのだろう、と。
野暮な質問なのかもしれないけど…
たぶん、相互作用なのだろう。
ジョビンはピアノで作曲していた。
唄いながらやっていたかもしれないし
それにつれてコードも変化したのかもしれない。
それにしても、緻密な展開だった。
これを感覚的に出来るとしたら、
それは天才のなせる技なのかと思った。
次の分析する楽曲の予告があった。
ちらっと聴いた、そのジョビンの曲は出だしが3拍子で
聴いた事の無いものだった。とても複雑なメロディー、
不思議な哀愁と喜びが満ちていて叙情的な曲だった。
聴いた事のないジョビンの音楽。
そしてジョビンと思われるヘタウマで
味わいのあるヴォーカルを聴いて
何故か坂本龍一のヴォーカルを思い出した(笑)
うん、ちょっと似てるかも…(笑)
とても気になるこの曲(まだタイトル曖昧)
次回の講義が待ち遠しい。
<BODY>
<script type="text/javascript" src="http://www.research-artisan.com/userjs/?user_id=20060529000243138"></script><noscript>
</BODY>