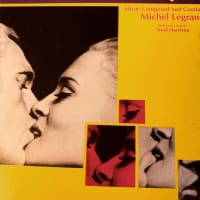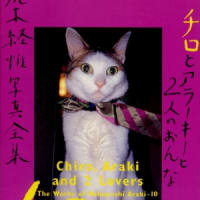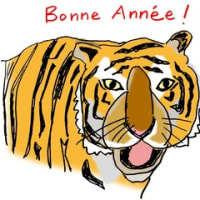「都市というのは、上辺だけの約束事と、何の保証も無い情報だけに
がんじがらめに成っている空間である。
いつどこで何をするか、誰と会うか。都市民にとっては、
既に決まっている事であり、こんな人生は無いのも同じ空虚である。
今や都市民にとって真実のコミュニュケーションとは
間違い電話だけなのだ。だから自分は電話番号を聞かれた時に、
積極的に間違った電話番号を教えるのである」
、、、というのは故・寺山修司氏の言葉で
それを日記で引用されたのは菊池成孔氏です。
この引用に、そしてこの言葉にぐっときたので書き留めることにしましょう。
先日書いた講義録日記で触れたけれど
精神分析的に「言い間違い」とか「記憶違い」なんかは
すべてその人の属性と言える、、、とした言及が
この出来事に表れているのだけど
この場合は明らかにわざと具体的に店の名前と
おいてあるメニューを言い間違えて、ファンの人々と
真のコミュニケーションを試みた(?)菊池さんの
過去の日記についてと、それに対するファンの皆さんの
楽しい突っ込みがあって菊池さんという人は
月に数回、ご本人を目の当たりにしている私にとっても
改めてチャーミングな人だな~と、思う。
今日は、そんな菊池さんによる特別講義de
お題は「ポリリズム」
専門的な内容に触れる前に感じたあれこれ。
今回の講義は通常の特別講義の枠外でもうけられたもので
現在初等科に通う数名の有志の生徒さんたちが原動力となって
講義に至ったものだ。旋律に対する講義の要望はあっても
律動(リズム)に対するものは(特に日本では)要望がない…と
菊池さんは言っていて、でもこの講義を聴いて(去年に続いて2度目)
彼が何故ポリリズムと、そして「ダンス」にこだわっているのか
ず~っと気になっていたのだけど
そのことに納得し、今回、よくわかったのだった。
それは(たぶん)こんな思想が背景にあったのだったと思う。
(私の主観も存分に入ってはいますが、とりあえず書きます)
その前に「ポリリズム」の概念について
ちょっとだけ触れませふ。
「ポリリズム」とは
アフリカの音楽に顕著だそうで、
複数のリズムが重層的に重なり合い
2つ以上のリズムが対立して絡みあうリズム。
ポリフォニー(多旋律←私はこの概念と音楽を
とても愛しているのだけど)と同様
それぞれに自立した異なるリズムが
同時に鳴っているリズム、、、というかんじ。
たとえば(これは説明してもリズム感覚などの
身体感覚を必要とすることなので言葉では難しいことを前提に)
「4」拍子のリズムを3~9迄のリズムで
等分したり等積する…という概念。
といってピンとくる人とこない人がいるのは当然だけど
ここからが面白いところ。
ちなみに私は何度か日記に書いているけれど
ドラムもやっていたことがあって(うまくはない)
乳児の頃に「ポンポポポン」のっ、「ポンポンッ!」と
お箸で茶碗を叩いた当時家業の寿司屋の板前だった
(元自衛隊のトランぺッター)Mさんという人
(現在は伊丹で中華料理を営んでいる)の膝の上で
1歳に満たない私はそのとおりに箸で叩いた、という
伝説が残っていて(笑)両親に何度か聴かされた。
そういえば私にはなぜかいつも4拍子を
3拍子に置き換えてカウントする癖があった。
その癖については以前「リズム」という日記を書いたのだけど
時々面倒なくらいにつきまとい
時にはバスや車に乗っていて電信柱から次の電信柱まで
4拍子をカウントしたりそれを3で分割したり、という
幾分偏執的な作業は自然なことになっていて
とりあえずリズム(ビート)とダンスとハーモニーが大好きで
それが何故なのか理由はよくわからず
今日まで生きていたわけですが、、、(笑)
私がポリフォニーの概念と音楽にひかれるのと
ポリリズムのそれが同じかどうかはわからないけれど
菊池さんは「ポリリズム」を
ある種の「社会参加」的な概念にたとえていて興味深い。
鳴っているリズムだけを聴いて
そのリズムだけに従って、受動的なダンスをするよりも
鳴っていないリズムを自分で感じて
それを自らが発することは、心身に
とても健全な行為なのだ、、、と、説いていらっしゃる。
私の場合は頭の中でそこにないリズムを鳴らす癖は
常にあって、ダンスすることもそれと同様で、
確かに魅力的なビートを感じながら
自分から発するビートを体に刻んで踊れば
自然にポジティブになれる、しかも心身ともに。
いっぽう、私にとって多声音楽(多旋律)である
「ポリフォニー」の概念は
どこかその音楽性に「理想的な社会」という要素を感じていて
それは「それぞれが全く違って独立した美を持っていて
互いは時に絡み合って近づき、時には離れてバラバラになり
それでも双方の違いは多旋律の
美しい音楽となって調和に向かう」、、、などという
楽園的な(笑)社会のイメージと
重ね合わせているんだけど、、、
ドラマーである外山明氏の講義を2回受講したのと
菊池さんのポリリズム講義を去年受けた経験が早速
リズムを理解するうえで有意になっていると感じる。
これは体で感じたうえで理論化するがよい。
そして月曜日は28日は2度目のポリリズム講義。
理解を深めるために出たいと思っていたのだけど
明日は東京を二日ほど離れてしまうので
出席出来ないのが何より残念、、、
生徒のニーズに応えるべく菊池さんは
普段と違うハイテンションだった。
しかも、今日の菊池さんのヅラは、ばっちりキマっていた。
フサフサと風になびく少年のようで
かなりイケてる。
ポリリズムの講義メソッドへの理解と共に
今宵の朗報は菊池さんの私塾である
「ペンギン大学」のこと。
ご本人から説明があって発覚したことなのだけど
なんとなんと、我々美学校生徒は
ペンギン式のエスカレーターで自動入学が可能な今期からは
「POPS部門」をもうけるそうな!!!ワ~イ!うれしいな♪
(もう何度も日記に書いているけれど)
コアなジャズに未だとっつき難さを感じる
ドミナントモーションから離れられない私のような嗜好性を
もった人間には本当に、これは朗報。
私には、どちらの概念も必要なのだ。たぶん。
<BODY>
<script type="text/javascript" src="http://www.research-artisan.com/userjs/?user_id=20060529000243138"></script><noscript>
</BODY>
がんじがらめに成っている空間である。
いつどこで何をするか、誰と会うか。都市民にとっては、
既に決まっている事であり、こんな人生は無いのも同じ空虚である。
今や都市民にとって真実のコミュニュケーションとは
間違い電話だけなのだ。だから自分は電話番号を聞かれた時に、
積極的に間違った電話番号を教えるのである」
、、、というのは故・寺山修司氏の言葉で
それを日記で引用されたのは菊池成孔氏です。
この引用に、そしてこの言葉にぐっときたので書き留めることにしましょう。
先日書いた講義録日記で触れたけれど
精神分析的に「言い間違い」とか「記憶違い」なんかは
すべてその人の属性と言える、、、とした言及が
この出来事に表れているのだけど
この場合は明らかにわざと具体的に店の名前と
おいてあるメニューを言い間違えて、ファンの人々と
真のコミュニケーションを試みた(?)菊池さんの
過去の日記についてと、それに対するファンの皆さんの
楽しい突っ込みがあって菊池さんという人は
月に数回、ご本人を目の当たりにしている私にとっても
改めてチャーミングな人だな~と、思う。
今日は、そんな菊池さんによる特別講義de
お題は「ポリリズム」
専門的な内容に触れる前に感じたあれこれ。
今回の講義は通常の特別講義の枠外でもうけられたもので
現在初等科に通う数名の有志の生徒さんたちが原動力となって
講義に至ったものだ。旋律に対する講義の要望はあっても
律動(リズム)に対するものは(特に日本では)要望がない…と
菊池さんは言っていて、でもこの講義を聴いて(去年に続いて2度目)
彼が何故ポリリズムと、そして「ダンス」にこだわっているのか
ず~っと気になっていたのだけど
そのことに納得し、今回、よくわかったのだった。
それは(たぶん)こんな思想が背景にあったのだったと思う。
(私の主観も存分に入ってはいますが、とりあえず書きます)
その前に「ポリリズム」の概念について
ちょっとだけ触れませふ。
「ポリリズム」とは
アフリカの音楽に顕著だそうで、
複数のリズムが重層的に重なり合い
2つ以上のリズムが対立して絡みあうリズム。
ポリフォニー(多旋律←私はこの概念と音楽を
とても愛しているのだけど)と同様
それぞれに自立した異なるリズムが
同時に鳴っているリズム、、、というかんじ。
たとえば(これは説明してもリズム感覚などの
身体感覚を必要とすることなので言葉では難しいことを前提に)
「4」拍子のリズムを3~9迄のリズムで
等分したり等積する…という概念。
といってピンとくる人とこない人がいるのは当然だけど
ここからが面白いところ。
ちなみに私は何度か日記に書いているけれど
ドラムもやっていたことがあって(うまくはない)
乳児の頃に「ポンポポポン」のっ、「ポンポンッ!」と
お箸で茶碗を叩いた当時家業の寿司屋の板前だった
(元自衛隊のトランぺッター)Mさんという人
(現在は伊丹で中華料理を営んでいる)の膝の上で
1歳に満たない私はそのとおりに箸で叩いた、という
伝説が残っていて(笑)両親に何度か聴かされた。
そういえば私にはなぜかいつも4拍子を
3拍子に置き換えてカウントする癖があった。
その癖については以前「リズム」という日記を書いたのだけど
時々面倒なくらいにつきまとい
時にはバスや車に乗っていて電信柱から次の電信柱まで
4拍子をカウントしたりそれを3で分割したり、という
幾分偏執的な作業は自然なことになっていて
とりあえずリズム(ビート)とダンスとハーモニーが大好きで
それが何故なのか理由はよくわからず
今日まで生きていたわけですが、、、(笑)
私がポリフォニーの概念と音楽にひかれるのと
ポリリズムのそれが同じかどうかはわからないけれど
菊池さんは「ポリリズム」を
ある種の「社会参加」的な概念にたとえていて興味深い。
鳴っているリズムだけを聴いて
そのリズムだけに従って、受動的なダンスをするよりも
鳴っていないリズムを自分で感じて
それを自らが発することは、心身に
とても健全な行為なのだ、、、と、説いていらっしゃる。
私の場合は頭の中でそこにないリズムを鳴らす癖は
常にあって、ダンスすることもそれと同様で、
確かに魅力的なビートを感じながら
自分から発するビートを体に刻んで踊れば
自然にポジティブになれる、しかも心身ともに。
いっぽう、私にとって多声音楽(多旋律)である
「ポリフォニー」の概念は
どこかその音楽性に「理想的な社会」という要素を感じていて
それは「それぞれが全く違って独立した美を持っていて
互いは時に絡み合って近づき、時には離れてバラバラになり
それでも双方の違いは多旋律の
美しい音楽となって調和に向かう」、、、などという
楽園的な(笑)社会のイメージと
重ね合わせているんだけど、、、
ドラマーである外山明氏の講義を2回受講したのと
菊池さんのポリリズム講義を去年受けた経験が早速
リズムを理解するうえで有意になっていると感じる。
これは体で感じたうえで理論化するがよい。
そして月曜日は28日は2度目のポリリズム講義。
理解を深めるために出たいと思っていたのだけど
明日は東京を二日ほど離れてしまうので
出席出来ないのが何より残念、、、
生徒のニーズに応えるべく菊池さんは
普段と違うハイテンションだった。
しかも、今日の菊池さんのヅラは、ばっちりキマっていた。
フサフサと風になびく少年のようで
かなりイケてる。
ポリリズムの講義メソッドへの理解と共に
今宵の朗報は菊池さんの私塾である
「ペンギン大学」のこと。
ご本人から説明があって発覚したことなのだけど
なんとなんと、我々美学校生徒は
ペンギン式のエスカレーターで自動入学が可能な今期からは
「POPS部門」をもうけるそうな!!!ワ~イ!うれしいな♪
(もう何度も日記に書いているけれど)
コアなジャズに未だとっつき難さを感じる
ドミナントモーションから離れられない私のような嗜好性を
もった人間には本当に、これは朗報。
私には、どちらの概念も必要なのだ。たぶん。
<BODY>
<script type="text/javascript" src="http://www.research-artisan.com/userjs/?user_id=20060529000243138"></script><noscript>
</BODY>