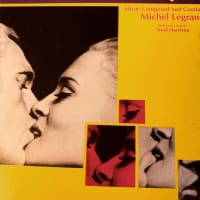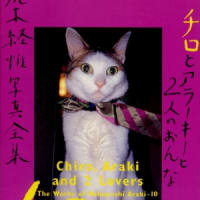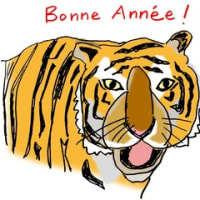2006年3月26日
今日はピアノレッスン@桜咲く春の谷中
4月末のピアノの催しに向けて、練習曲は
メンデルスゾーン 無言歌 第1番『甘い想い出』
レッスンに行く坂の途中にある桜

不思議なほど、幾ら弾いても弾き飽きない曲なので
何故なのだろうと思っていたら教師がそんな私の疑問を
演奏によっていとも簡単に説明された、、、
『これは、コラールなんです』
…え、、、!?どういう事?
『メンデルスゾーンは無言歌で、コラールの和音を
分散させたんですね(=垂直な音の響き<縦>を
水平<横>に捉えなおしたということ)
これをバッハのコラールのように
和音で弾いてみましょう』そう言って弾いた彼の演奏は、
違う側面から解釈された、重厚な
メンデルスゾーンの無言歌だった。
その後に、師はマタイ受難曲に繰り返し表れる
フレーズを弾いてくれた。数百年前の宗教曲とは
思えない程ポピュラリティがあって
鳥肌が立つほど美しい演奏とフレーズ。
つまり無言歌はメンデルスゾーンによる軽めの
『バッハのコラールのポップ解釈』なのだと、
解釈することにした。(笑)
ポップなマタイ受難曲的インストゥルメンタル、
と言っても良いだろう。何せ20歳にして
作品完成100年後にマタイ受難曲を編曲し自ら
指揮し初演をした早熟の天才メンデルスゾーンだったのだから
でも、そういった解釈によって楽しく、
曲が生き生きと魅力に溢れて
表現にもそれが生きて来るから面白いものだ。
彼は今回のレッスンの最後のほうで言った。
『マズルカのような舞曲的なリズムは今後
音楽的表現においてレッスンは不可欠ですが、
演奏会まで残り1ヶ月となった今は、あなたが好きな
バッハのコラールの性質を持ったポリフォニックなこの曲は
むしろ優れた演奏への早道でしょう』と
師は何故私がこの曲に惹かれるのか、お見通しだった。
(そういえば私が前回このピアノの催しに初めて参加した時
弾いたのはバッハのコラールをコルトーがピアノにアレンジした
「アリオーソ」だった)
今回のレッスンではテクニカルなことを詳細に教わり、
しかも、そのことが、これまで自分で分析しつつ
統合し切れなかった幾つかの物事と共に
ほぼ完璧に心身ともに理解出来た。それは、
どこか不自由で、手首から下を拘束されたような
私の右手の演奏が自由にダンスし始めたようなかんじ。
(楽しい事に『ネコが獲物を狙う手』で、
右手の理想的な動きを師は表現したのだった・笑)
この曲をただ弾くのは(読譜も含め)難しいということはないけれど
音楽的に美しく弾くのは、とても難しい。何故かというと
・3声(2本の手で3本の手を使うような演奏をする)
・ほぼ曲の全体に16分音符(とても早い音)の4連符が
左手と右手に渡って伴奏として常に存在していて
・メロディーは、ほとんど右手の薬指と小指のみで
表現しなくてはいけない
・指の運びだけでもあまり簡単ではない上に
・左手のベースと伴奏、さらに右手の中指~親指で
左手のような伴奏をしたうえで
・右手の薬指と小指は主旋律を弾く
ということになると、ともすると
バラバラで騒々しい演奏に成りかねない。
じつは私の演奏は、今日迄ずっとそうだった。
何だかとても慌てた演奏だったのだ。
「3倍くらい遅く弾いてごらんなさい」と言われて
やってみたら、これが速く弾くよりも思いのほか難しい。
遅く弾く事によって、手の漫然とした運動で
(勢いや惰性で)弾くことと
曲の構造や和音、前後の繋がりを理解し
解釈しながら弾くのとは大きな違いがある、と彼は言って
そのことをやっと理解することが出来たのだった。
帰宅して4時半から9時前まで珍しく
長い時間弾いたのだけど、途中で
自分で自分ではないような(笑)演奏だった、
手が勝手に弾いているようで
聴こえ方も響きも弾き方もまるで変わっていた。
手と鍵盤がこれまでと違うもののように(笑)軽くて自由になった。
何度か3倍遅く弾いて、その後に本番の速さで弾いて
もう少し速く弾いて、また遅く弾いて…という練習は
難しいけれど、表現の幅が驚く程広がって、変わっていく。
ここから、幾分自由になった私の演奏は
今後どう変わって行くのか楽しみに思える
本日のレッスンだった。
こんな事ってあるのだなと、これまでの
3年間のレッスンを思うと感慨深い。
この状態を良い風に維持していこう。
さて、レッスンが終わるとあまり優秀ではない
私の頭も幾分ピアノを弾くと働いているのか
必ず甘いものが食べたくなっていつも
谷中で老舗の甘味処に行くのだけれど
今回向かった場所は違うところで、
隠れた蕎麦の名店で、これまで一度も入れたことのない
(売り切れると閉店してしまう)店だった。
ふと店の前に行くと『蕎麦あります』の看板に
誘われる様に店内に入ると、蕎麦と木の香り(檜だろうか?)と
清浄な空気の静謐な店内ではイタリアのルネサンス音楽や
ギターで奏でられる古いバロックがかかっていた
何とも不思議な空間。
ごつごつとして手触りの良い急須とゆのみで
お茶が出される。
座敷に通されたので正座してせいろを注文。
とろりとしたお茶が何とも美味。
お膳に置いてある色々なものに興味津々。
妙に可愛らしい猫の置物があって、これは
お店の人を呼ぶベルだった。ニャー!

大根おろしと細く千切りされたねぎと
幾分甘めの蕎麦つゆと一緒に頂く
細打ちの蕎麦は上品な逸品でした。
いつも幸せ感じる春の谷中にて

<BODY>
<script type="text/javascript" src="http://www.research-artisan.com/userjs/?user_id=20060529000243138"></script><noscript>
</BODY>
今日はピアノレッスン@桜咲く春の谷中
4月末のピアノの催しに向けて、練習曲は
メンデルスゾーン 無言歌 第1番『甘い想い出』
レッスンに行く坂の途中にある桜

不思議なほど、幾ら弾いても弾き飽きない曲なので
何故なのだろうと思っていたら教師がそんな私の疑問を
演奏によっていとも簡単に説明された、、、
『これは、コラールなんです』
…え、、、!?どういう事?
『メンデルスゾーンは無言歌で、コラールの和音を
分散させたんですね(=垂直な音の響き<縦>を
水平<横>に捉えなおしたということ)
これをバッハのコラールのように
和音で弾いてみましょう』そう言って弾いた彼の演奏は、
違う側面から解釈された、重厚な
メンデルスゾーンの無言歌だった。
その後に、師はマタイ受難曲に繰り返し表れる
フレーズを弾いてくれた。数百年前の宗教曲とは
思えない程ポピュラリティがあって
鳥肌が立つほど美しい演奏とフレーズ。
つまり無言歌はメンデルスゾーンによる軽めの
『バッハのコラールのポップ解釈』なのだと、
解釈することにした。(笑)
ポップなマタイ受難曲的インストゥルメンタル、
と言っても良いだろう。何せ20歳にして
作品完成100年後にマタイ受難曲を編曲し自ら
指揮し初演をした早熟の天才メンデルスゾーンだったのだから
でも、そういった解釈によって楽しく、
曲が生き生きと魅力に溢れて
表現にもそれが生きて来るから面白いものだ。
彼は今回のレッスンの最後のほうで言った。
『マズルカのような舞曲的なリズムは今後
音楽的表現においてレッスンは不可欠ですが、
演奏会まで残り1ヶ月となった今は、あなたが好きな
バッハのコラールの性質を持ったポリフォニックなこの曲は
むしろ優れた演奏への早道でしょう』と
師は何故私がこの曲に惹かれるのか、お見通しだった。
(そういえば私が前回このピアノの催しに初めて参加した時
弾いたのはバッハのコラールをコルトーがピアノにアレンジした
「アリオーソ」だった)
今回のレッスンではテクニカルなことを詳細に教わり、
しかも、そのことが、これまで自分で分析しつつ
統合し切れなかった幾つかの物事と共に
ほぼ完璧に心身ともに理解出来た。それは、
どこか不自由で、手首から下を拘束されたような
私の右手の演奏が自由にダンスし始めたようなかんじ。
(楽しい事に『ネコが獲物を狙う手』で、
右手の理想的な動きを師は表現したのだった・笑)
この曲をただ弾くのは(読譜も含め)難しいということはないけれど
音楽的に美しく弾くのは、とても難しい。何故かというと
・3声(2本の手で3本の手を使うような演奏をする)
・ほぼ曲の全体に16分音符(とても早い音)の4連符が
左手と右手に渡って伴奏として常に存在していて
・メロディーは、ほとんど右手の薬指と小指のみで
表現しなくてはいけない
・指の運びだけでもあまり簡単ではない上に
・左手のベースと伴奏、さらに右手の中指~親指で
左手のような伴奏をしたうえで
・右手の薬指と小指は主旋律を弾く
ということになると、ともすると
バラバラで騒々しい演奏に成りかねない。
じつは私の演奏は、今日迄ずっとそうだった。
何だかとても慌てた演奏だったのだ。
「3倍くらい遅く弾いてごらんなさい」と言われて
やってみたら、これが速く弾くよりも思いのほか難しい。
遅く弾く事によって、手の漫然とした運動で
(勢いや惰性で)弾くことと
曲の構造や和音、前後の繋がりを理解し
解釈しながら弾くのとは大きな違いがある、と彼は言って
そのことをやっと理解することが出来たのだった。
帰宅して4時半から9時前まで珍しく
長い時間弾いたのだけど、途中で
自分で自分ではないような(笑)演奏だった、
手が勝手に弾いているようで
聴こえ方も響きも弾き方もまるで変わっていた。
手と鍵盤がこれまでと違うもののように(笑)軽くて自由になった。
何度か3倍遅く弾いて、その後に本番の速さで弾いて
もう少し速く弾いて、また遅く弾いて…という練習は
難しいけれど、表現の幅が驚く程広がって、変わっていく。
ここから、幾分自由になった私の演奏は
今後どう変わって行くのか楽しみに思える
本日のレッスンだった。
こんな事ってあるのだなと、これまでの
3年間のレッスンを思うと感慨深い。
この状態を良い風に維持していこう。
さて、レッスンが終わるとあまり優秀ではない
私の頭も幾分ピアノを弾くと働いているのか
必ず甘いものが食べたくなっていつも
谷中で老舗の甘味処に行くのだけれど
今回向かった場所は違うところで、
隠れた蕎麦の名店で、これまで一度も入れたことのない
(売り切れると閉店してしまう)店だった。
ふと店の前に行くと『蕎麦あります』の看板に
誘われる様に店内に入ると、蕎麦と木の香り(檜だろうか?)と
清浄な空気の静謐な店内ではイタリアのルネサンス音楽や
ギターで奏でられる古いバロックがかかっていた
何とも不思議な空間。
ごつごつとして手触りの良い急須とゆのみで
お茶が出される。
座敷に通されたので正座してせいろを注文。
とろりとしたお茶が何とも美味。
お膳に置いてある色々なものに興味津々。
妙に可愛らしい猫の置物があって、これは
お店の人を呼ぶベルだった。ニャー!

大根おろしと細く千切りされたねぎと
幾分甘めの蕎麦つゆと一緒に頂く
細打ちの蕎麦は上品な逸品でした。
いつも幸せ感じる春の谷中にて

<BODY>
<script type="text/javascript" src="http://www.research-artisan.com/userjs/?user_id=20060529000243138"></script><noscript>
</BODY>