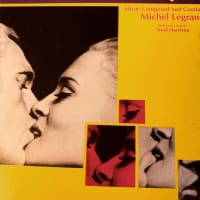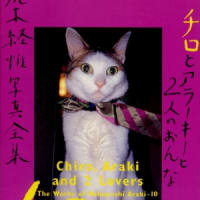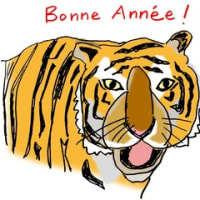黄味がかった白の程良く着古された(皮革素材?)
ヨレッとしたコートを着て菊地さんが
いつの間にかフワリと入室。
2006年1月10日 音楽美学講座 楽理高等科
第7回目の今日は、いよいよ架橋である楽曲分析。
待ちに待っていた瞬間。
新年の挨拶をして講義がスタート。
楽曲分析に入るにあたって分析対象の
曲の選び方について説明される。
基本的に菊地さんが何曲か相応しいものを選曲して
それに対して多数決で決めるという方法をとることに。
選ばれるのは1曲。
いつの場合でもそうだけど、全員一致で
良いという曲を分析するのは難しく
(そりゃそう、だって世代も属性もバラバラなのだから)
なるべくポピュラーかつ名曲を、という事で
菊地さんは何を選ばれたのだろうと興味津々でいた。
全部で3曲用意されてるよう。
これです、と菊地さんがCDをセットして曲が流れた。
思わず顔がほころんで直後に泣きたい気分になる(笑)
1曲目「雨にぬれても」バートバカラック
去年初等科の最後の講義で分析した「恋の面影」同様
映画の存在と共に稀有な出会いの記憶と重なる曲。
バカラックのこれらの曲は
無彩色だった寒い冬の時期に出会い
春の暖かさを予感させるように私の生活に色彩をもたらした。
菊池さんが以前日記に書いていたような「喪失と獲得」
(=「憂鬱と官能」)は私をそれまでよりも一層強く
音楽に向かわせた。その結果、今学んでいる
作曲家のピアノ教師と岸野雄一氏が立ち上げ、菊地成孔氏が教える
この「憂鬱と官能を教えた学校」こと映画美学校の
音楽美学講座に辿り着いた。そしてこの経験が今後
喪失につながるのか獲得につながるのか未だわからない。
そんな事を思い起こしながら
私はこれまで彼岸として見ていた場所に
今居るのだなと実感しつつ
2曲目:世界は愛を求めている (バートバカラック)
3曲目:I'm not in love(10cc)
私にとってはこの3曲が選ばれたのは小さな偶然の奇跡。
名曲であるだけでなく、何れも特別な思い入れのある曲で
聴けば、それぞれに対してある物事や鮮烈な感情が
今でも明確に思い起こされるのだ。
しかし時間の都合上I'm not in loveは少々複雑だと言う事で
(以前少しだけコードを取ってみた時に
もしかしたらこの曲は「モード」を使ってる部分が
あるのかなと直観的に感じたことがあった)
多数決によって選ばれたのは
優れて強いポピュラリティと共感性を持つ「雨にぬれても」
「世界は愛を求めている」とは僅差だった。
こんなに思い入れのある好きな曲を
音楽美学講座で分析出来ることはとてもラッキーな事だ。
新春早々、素敵な予感に包まれる(笑)
初等科の時から噂には聴いていたバカラックの
作曲の「作法」のようなもの。
印象は強いポピュラリティを持ちながら
冷徹なまでに静謐で緻密、かつミニマルなものだった。
そういえば映画のインタビューでバカラックは
監督であるジョージ・ロイ・ヒルと共に
バッハの音楽を敬愛していると言っていた事を思い出す。
そしてそれを観ていた私はバカラックの文字には
「bach」が入ってる、と話した事も同時に思い出していた。
大いに盛り上がった今年最初の音楽美学講座は
今週に入ってずっと寝不足でかつ仕事もピークを迎え
気を緩めればへとへとな状態なのにも関わらず
最後迄、気が緩まずに音楽的悦楽を堪能する講義だった。
帰り際に久々にハイテンションで
ふと気がつけばやめたはずの煙草を吸っていた菊地さんは
いつものチャーミングな様子で
楽しげにモロッコへの取材の旅について語り
彼の話を傍で聴きたいと思う生徒達と
灰黄色の煙草の煙にぐるっと囲まれていた。
バルトが定宿にしていた怪しい場所の事や(笑)
ジミヘンが泊まった13号という部屋に
宿泊して気分が悪くなった話とか
回教徒の女性の目力の美しさやら
回教徒の男性の欲求不満度の高さや(笑)
どんなに罵倒しあい喧嘩していても
コーランが鳴れば皆が床にひれ伏す滑稽な様など
短い時間に魅力的な会話がなされ
今日の講義は幕を下ろした。
講義の時より身近な菊地先生と目線が合うと
何故か嬉しくなる。講義を通してこうして時々
近くに居るだけで素敵と思える…のは良いのだけど
考えてみたら菊地さんと講義以外で会話したのは
全て何故か食べ物のことだった、ほんの数回(苦笑)
少し日焼けした様子で無精髭を蓄え
元気だけどどこか枯れたような(笑)
素敵な中年的魅力(でも青年)の気配を漂わせていた。
菊地さんは講義の冒頭に「楽曲分析は精神分析のようなもので
(自分の嗜好性を知るという意味で)
自分を分析する事のようでもあります」と仰った。
私も好きな物事を知りすぎる事は悦びであると同時に
何らかを喪失するかもしれない
切ない行為でもあると考えていた。
楽曲を事細かに楽理によって論理分析し
理解した後のその曲は、まるでただの現象として在るようで
これまでのように新鮮に聴こえなくなります、という事だった。
ただ、好きな音楽を楽しみ快楽的に沢山聴きたいと思うのであれば
いますぐこの学校を退学した方が良いくらいだと。
そしてその事を恋愛に喩えて
ミステリアスに思っていた相手をすっかり知ってしまえば
何とも思わなくなるようなかんじ、と表現された。
「雨にぬれても」は私のiPodShuffleにも入っていたので
聴きながら帰った。
理論によって分析し、これまでよりも色々な事を知り
深い理解をした曲だけれど、聴こえて来たのは
これまでよりもずっと魅力的な「雨にぬれても」だった。
楽曲分析をしていて自分が音楽の表象性と共に
音楽にある本質そのものを必然としていた事を
再認識出来た今年最初の講義だった。
<BODY>
<script type="text/javascript" src="http://www.research-artisan.com/userjs/?user_id=20060529000243138"></script><noscript>
</BODY>
ヨレッとしたコートを着て菊地さんが
いつの間にかフワリと入室。
2006年1月10日 音楽美学講座 楽理高等科
第7回目の今日は、いよいよ架橋である楽曲分析。
待ちに待っていた瞬間。
新年の挨拶をして講義がスタート。
楽曲分析に入るにあたって分析対象の
曲の選び方について説明される。
基本的に菊地さんが何曲か相応しいものを選曲して
それに対して多数決で決めるという方法をとることに。
選ばれるのは1曲。
いつの場合でもそうだけど、全員一致で
良いという曲を分析するのは難しく
(そりゃそう、だって世代も属性もバラバラなのだから)
なるべくポピュラーかつ名曲を、という事で
菊地さんは何を選ばれたのだろうと興味津々でいた。
全部で3曲用意されてるよう。
これです、と菊地さんがCDをセットして曲が流れた。
思わず顔がほころんで直後に泣きたい気分になる(笑)
1曲目「雨にぬれても」バートバカラック
去年初等科の最後の講義で分析した「恋の面影」同様
映画の存在と共に稀有な出会いの記憶と重なる曲。
バカラックのこれらの曲は
無彩色だった寒い冬の時期に出会い
春の暖かさを予感させるように私の生活に色彩をもたらした。
菊池さんが以前日記に書いていたような「喪失と獲得」
(=「憂鬱と官能」)は私をそれまでよりも一層強く
音楽に向かわせた。その結果、今学んでいる
作曲家のピアノ教師と岸野雄一氏が立ち上げ、菊地成孔氏が教える
この「憂鬱と官能を教えた学校」こと映画美学校の
音楽美学講座に辿り着いた。そしてこの経験が今後
喪失につながるのか獲得につながるのか未だわからない。
そんな事を思い起こしながら
私はこれまで彼岸として見ていた場所に
今居るのだなと実感しつつ
2曲目:世界は愛を求めている (バートバカラック)
3曲目:I'm not in love(10cc)
私にとってはこの3曲が選ばれたのは小さな偶然の奇跡。
名曲であるだけでなく、何れも特別な思い入れのある曲で
聴けば、それぞれに対してある物事や鮮烈な感情が
今でも明確に思い起こされるのだ。
しかし時間の都合上I'm not in loveは少々複雑だと言う事で
(以前少しだけコードを取ってみた時に
もしかしたらこの曲は「モード」を使ってる部分が
あるのかなと直観的に感じたことがあった)
多数決によって選ばれたのは
優れて強いポピュラリティと共感性を持つ「雨にぬれても」
「世界は愛を求めている」とは僅差だった。
こんなに思い入れのある好きな曲を
音楽美学講座で分析出来ることはとてもラッキーな事だ。
新春早々、素敵な予感に包まれる(笑)
初等科の時から噂には聴いていたバカラックの
作曲の「作法」のようなもの。
印象は強いポピュラリティを持ちながら
冷徹なまでに静謐で緻密、かつミニマルなものだった。
そういえば映画のインタビューでバカラックは
監督であるジョージ・ロイ・ヒルと共に
バッハの音楽を敬愛していると言っていた事を思い出す。
そしてそれを観ていた私はバカラックの文字には
「bach」が入ってる、と話した事も同時に思い出していた。
大いに盛り上がった今年最初の音楽美学講座は
今週に入ってずっと寝不足でかつ仕事もピークを迎え
気を緩めればへとへとな状態なのにも関わらず
最後迄、気が緩まずに音楽的悦楽を堪能する講義だった。
帰り際に久々にハイテンションで
ふと気がつけばやめたはずの煙草を吸っていた菊地さんは
いつものチャーミングな様子で
楽しげにモロッコへの取材の旅について語り
彼の話を傍で聴きたいと思う生徒達と
灰黄色の煙草の煙にぐるっと囲まれていた。
バルトが定宿にしていた怪しい場所の事や(笑)
ジミヘンが泊まった13号という部屋に
宿泊して気分が悪くなった話とか
回教徒の女性の目力の美しさやら
回教徒の男性の欲求不満度の高さや(笑)
どんなに罵倒しあい喧嘩していても
コーランが鳴れば皆が床にひれ伏す滑稽な様など
短い時間に魅力的な会話がなされ
今日の講義は幕を下ろした。
講義の時より身近な菊地先生と目線が合うと
何故か嬉しくなる。講義を通してこうして時々
近くに居るだけで素敵と思える…のは良いのだけど
考えてみたら菊地さんと講義以外で会話したのは
全て何故か食べ物のことだった、ほんの数回(苦笑)
少し日焼けした様子で無精髭を蓄え
元気だけどどこか枯れたような(笑)
素敵な中年的魅力(でも青年)の気配を漂わせていた。
菊地さんは講義の冒頭に「楽曲分析は精神分析のようなもので
(自分の嗜好性を知るという意味で)
自分を分析する事のようでもあります」と仰った。
私も好きな物事を知りすぎる事は悦びであると同時に
何らかを喪失するかもしれない
切ない行為でもあると考えていた。
楽曲を事細かに楽理によって論理分析し
理解した後のその曲は、まるでただの現象として在るようで
これまでのように新鮮に聴こえなくなります、という事だった。
ただ、好きな音楽を楽しみ快楽的に沢山聴きたいと思うのであれば
いますぐこの学校を退学した方が良いくらいだと。
そしてその事を恋愛に喩えて
ミステリアスに思っていた相手をすっかり知ってしまえば
何とも思わなくなるようなかんじ、と表現された。
「雨にぬれても」は私のiPodShuffleにも入っていたので
聴きながら帰った。
理論によって分析し、これまでよりも色々な事を知り
深い理解をした曲だけれど、聴こえて来たのは
これまでよりもずっと魅力的な「雨にぬれても」だった。
楽曲分析をしていて自分が音楽の表象性と共に
音楽にある本質そのものを必然としていた事を
再認識出来た今年最初の講義だった。
<BODY>
<script type="text/javascript" src="http://www.research-artisan.com/userjs/?user_id=20060529000243138"></script><noscript>
</BODY>