政治におけるアイディアを重視する文献でほぼ必ず引用・参照されているMark Blyth, Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century (Cambridge University Press, 2002)をやっと読むことができました。

「Great Transformations」というタイトルは、もちろんKarl Polanyiを意識したものです。
ただし、本書全体がポランニーさんの学説について書かれているわけではありません。
ポランニーさんの『大転換』は本書のモチーフとして使われているだけです。
著者は冒頭においてポランニーさんの「double movement」という概念を紹介した上で、それは次のような欠陥があると指摘します。
すなわち、ポランニーさんは「double movement」を一方通行のプロセスとして描いてしまっているけれど、実は市場の埋め込みと脱埋め込みは現在もまだ続いている(p.4)。
20世紀には2つの大きな転換(1920~30年代及び1970~80年代)が起きており、本書において著者はその両者を整合的に説明しようと試みています。
(なので、「Great Transformation」(『大転換』の原題は、The Great Transformation)ではなく、「Great Transformations」という複数形のタイトルが付けられています。)
2つの大転換を説明するために著者が注目するのが、「アイディア」の役割です。
人々の利益(interest)ももちろん大事なのだけど、何がその人の利益であるかは実はそんなに明らかではない(p.27ff)。
本書が注目する大転換が起こったときのように「ナイトの不確実性」(Knightian uncertainty)が社会経済を覆っているときにおいてはなおさら、どうすることが利益になるのかがよく分からなくなる。
その人の利益は何らかのものによって定義されなくてはいけなくて、ここにおいてアイディアが重要になってきます。
アイディアはナイトの不確実性の状況下において、現状がなぜそうなっているかを診断し、その診断によってどんなアウトカムが可能か、どのアウトカムが望ましいのかを定義します。
アイディアをこのようにとらえることによって、合理的選択論者のようにアイディアを残余(auxiliary)の説明変数として扱うのではなく、もっと積極的な役割を果たすものと位置付けることが可能になる。
本書における仮説は次の5つです(pp.34-42)。
仮説1:経済危機の時代において、アイディアがその危機の原因と処方箋を提供することにより不確実性を減少させる。
仮説2:不確実性が減少した後、アイディアは様々な主体の共通の枠組みとなることで集合行為や連合形成を可能にする。
仮説3:既存の制度を脱正統化する際において、アイディアが武器として使われる。
仮説4:アイディアは既存の制度に取って代われるべき新しい制度の青写真となる。
仮説5:制度構築の後、アイディアは制度の安定性をもたらす。
ちなみに、本書の表紙の絵は上記の2つ目の仮説を表現したものと言えます。
描かれているのは、裕福で恰幅の良い資本家と貧しい労働者。
彼らの利益は普通に考えると異なっているはずなのに、なぜか2人は腕を組んで歩いている。
このような連合を可能にするものこそがアイディアだという意味が、この絵に含意されています。
これら仮説の実証はアメリカ合衆国とスウェーデンのそれぞれの大転換を詳細に描くことによって行われています。
このケースの選択は、most different case strategyであるということ及び、これがcrucial case study(最もその状況が起こりやすそうなケースと最も起こりにくそうなケースをペアにすることによって説明能力を高め得る)であるということによって正当化されています(p.11ff)。
それぞれのケースについて著者は丁寧にそのプロセスを叙述してくれているのですが、いろんな場所で「あるアイディアに基づく政策が失敗したという事実だけではその思考の型を覆すのに十分でない」ことが強調され、「旧来のアイディアに取って代わるアイディア」の存在と「そのアイディアを支持する連合を形成する動き」の重要性が主張されていることが特に印象的でした。
おそらく本書の最も重要な貢献は、アイディアが大きな役割を果たすのが「いつ」(When)で、それはどういう理由によるかを示したことなんだと思います。
ある状況がナイトの不確実性の状況かどうかというのは後付けじゃないのかとか、そもそも「平時」は存在するのか(政治を見ていると、常に何らかの大きな課題がある気がする。)とか疑問もあるけど、アイディアが活躍する条件を著者は我々読者に見事に示している。
でも、「なぜあのアイディアではなくてこのアイディアだったのか」はやっぱり十分に明らかではないように思われる。
もちろん、あらかじめ、どのアイディアが勝利するかを予想することは不可能だとは思うけれど、今後の研究は「どういう」(What)アイディアがどういう条件で影響力を持ちやすいのかという方向で行われていくのかなあと漠然と思いました。
そういう意味で、それぞれの国の政治制度とアイディアの関係(coordinative discourseとcommunicative discourse)を分析したVivien Schmidtさんの研究(2002)などと組み合わされる必要があるし、また、政策変化には課題の認識とその課題を解決できそうな政策アイディア、その政策アイディアを推進できる都合の良い政治的状況の3つがすべて揃っていないといけないと主張するJohn W. Kingdonの研究(Agendas, Alternatives, and Public Policies)等の再度の読み直しも実り多いかもしれません。
(投稿者:Ren)

「Great Transformations」というタイトルは、もちろんKarl Polanyiを意識したものです。
ただし、本書全体がポランニーさんの学説について書かれているわけではありません。
ポランニーさんの『大転換』は本書のモチーフとして使われているだけです。
著者は冒頭においてポランニーさんの「double movement」という概念を紹介した上で、それは次のような欠陥があると指摘します。
すなわち、ポランニーさんは「double movement」を一方通行のプロセスとして描いてしまっているけれど、実は市場の埋め込みと脱埋め込みは現在もまだ続いている(p.4)。
20世紀には2つの大きな転換(1920~30年代及び1970~80年代)が起きており、本書において著者はその両者を整合的に説明しようと試みています。
(なので、「Great Transformation」(『大転換』の原題は、The Great Transformation)ではなく、「Great Transformations」という複数形のタイトルが付けられています。)
2つの大転換を説明するために著者が注目するのが、「アイディア」の役割です。
人々の利益(interest)ももちろん大事なのだけど、何がその人の利益であるかは実はそんなに明らかではない(p.27ff)。
本書が注目する大転換が起こったときのように「ナイトの不確実性」(Knightian uncertainty)が社会経済を覆っているときにおいてはなおさら、どうすることが利益になるのかがよく分からなくなる。
その人の利益は何らかのものによって定義されなくてはいけなくて、ここにおいてアイディアが重要になってきます。
アイディアはナイトの不確実性の状況下において、現状がなぜそうなっているかを診断し、その診断によってどんなアウトカムが可能か、どのアウトカムが望ましいのかを定義します。
アイディアをこのようにとらえることによって、合理的選択論者のようにアイディアを残余(auxiliary)の説明変数として扱うのではなく、もっと積極的な役割を果たすものと位置付けることが可能になる。
本書における仮説は次の5つです(pp.34-42)。
仮説1:経済危機の時代において、アイディアがその危機の原因と処方箋を提供することにより不確実性を減少させる。
仮説2:不確実性が減少した後、アイディアは様々な主体の共通の枠組みとなることで集合行為や連合形成を可能にする。
仮説3:既存の制度を脱正統化する際において、アイディアが武器として使われる。
仮説4:アイディアは既存の制度に取って代われるべき新しい制度の青写真となる。
仮説5:制度構築の後、アイディアは制度の安定性をもたらす。
ちなみに、本書の表紙の絵は上記の2つ目の仮説を表現したものと言えます。
描かれているのは、裕福で恰幅の良い資本家と貧しい労働者。
彼らの利益は普通に考えると異なっているはずなのに、なぜか2人は腕を組んで歩いている。
このような連合を可能にするものこそがアイディアだという意味が、この絵に含意されています。
これら仮説の実証はアメリカ合衆国とスウェーデンのそれぞれの大転換を詳細に描くことによって行われています。
このケースの選択は、most different case strategyであるということ及び、これがcrucial case study(最もその状況が起こりやすそうなケースと最も起こりにくそうなケースをペアにすることによって説明能力を高め得る)であるということによって正当化されています(p.11ff)。
それぞれのケースについて著者は丁寧にそのプロセスを叙述してくれているのですが、いろんな場所で「あるアイディアに基づく政策が失敗したという事実だけではその思考の型を覆すのに十分でない」ことが強調され、「旧来のアイディアに取って代わるアイディア」の存在と「そのアイディアを支持する連合を形成する動き」の重要性が主張されていることが特に印象的でした。
おそらく本書の最も重要な貢献は、アイディアが大きな役割を果たすのが「いつ」(When)で、それはどういう理由によるかを示したことなんだと思います。
ある状況がナイトの不確実性の状況かどうかというのは後付けじゃないのかとか、そもそも「平時」は存在するのか(政治を見ていると、常に何らかの大きな課題がある気がする。)とか疑問もあるけど、アイディアが活躍する条件を著者は我々読者に見事に示している。
でも、「なぜあのアイディアではなくてこのアイディアだったのか」はやっぱり十分に明らかではないように思われる。
もちろん、あらかじめ、どのアイディアが勝利するかを予想することは不可能だとは思うけれど、今後の研究は「どういう」(What)アイディアがどういう条件で影響力を持ちやすいのかという方向で行われていくのかなあと漠然と思いました。
そういう意味で、それぞれの国の政治制度とアイディアの関係(coordinative discourseとcommunicative discourse)を分析したVivien Schmidtさんの研究(2002)などと組み合わされる必要があるし、また、政策変化には課題の認識とその課題を解決できそうな政策アイディア、その政策アイディアを推進できる都合の良い政治的状況の3つがすべて揃っていないといけないと主張するJohn W. Kingdonの研究(Agendas, Alternatives, and Public Policies)等の再度の読み直しも実り多いかもしれません。
(投稿者:Ren)










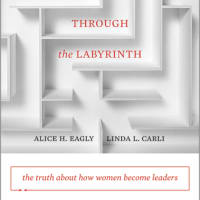









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます